
【ひとりの時間を、ひとりじめ。】最初の1ページから最後の1ページまで、めくれば、誰もが自由になれるから。

好きな
世界を
好きなだけ
楽しもう
わくわく
するままに
想像の
広がるままに
さて
いつもの
時間に
「無限」
に
「形」
が変わる
「トルネコ」的
な
「本屋ダンジョン」
に
突入!
本屋さんの
「本棚」
それは
「宝箱」
でもあるし
気を付けていないと・・・
「ミミック」
だったりもする(^^;
この本が
気になる人は・・・
これも
気になるだろう・・・
そんな
「推理」
をベースにして
書店員さん
が
「順番」
に
並べていたり
するので
「コントロール」
されないように・・・
要注意
です!
「制限時間内」
に
「最高の本」
を
見つけなければ
俺
の
負け(は嫌だ)
■背表紙
↓
■カバー
↓
■目次
↓
■キーワード
の
順に
気になった
本
を
巡回
してみる
やっぱり
本屋さんに
来ないと
こんなに
いろんな
ジャンルの本
を
手に取らない
ことから
本屋さん
には
日常的
に
行った方が
いいなと
思う
ネット
だけだと
こんなに
いろんな中
から
選ぶって
ことはないんで
分母
を
広げる意味
でも
本屋さん
っていうのを
絶対
に
使った方が
いいなと
本屋さん
が
あるっていうのは
本当
に
社会の財産
だと思うし
公共資本
でもあり
コモンズ
知らない本
との
出会いこそ
本屋さん
ならではだなって
思うし
基本
気になった本
を
全部
買う派
なんですが
今回は
書店員さん
の
セレクション
を
堪能
していて
出会った
この8冊を
セレクト!
■新しい心の科学と哲学の始まり
「心の哲学史」村田純一/渡辺恒夫(編)

心についての問題意識はプラトン・アリストテレスなどの古代哲学から連綿と続いているが、一般向け書籍で述べられる心理学史では、近代に始まる
「科学的心理学」
から述べられることが多い。
たとえば
「19世紀後半に科学としての心理学が内観から始まり、20世紀になると、それを否定したワトソンの行動主義が隆盛をきわめ、やがて認知革命に至った」
と。
しかし、それは、心理学史の或る一面の流れであって、哲学と心理学が分岐する前の19世紀後半を凝視するならば、それとは異なり、現代まで展開していくもう一つの心理学史が見えてくる。
本書では、1874年という年に刊行された二つの書物
『経験的立場からの心理学』(ブレンターノ)
と
『生理学的心理学綱要』(ヴント)
を起点とし、新しい心の科学と哲学の始まりと見なした。
それに対して、ブレンターノから哲学を学んだフッサールは、心の哲学としての心理学として独自の現象学を展開し、志向性・身体性・世界内存在など、心のあり方を解明する上で重要な役割を果たす諸概念を開発した。
実際現在では、それらの諸概念は、新たに展開し始めた、認知科学や神経科学の知見を理解するうえでも重要な役割を演じるようになっている。
本書では、このような心理学と心の哲学のいわば隠れた歴史の流れを、内観、発達心理学、脳科学、方法論論争など多様な側面から明らかにすることによって、心の哲学の歴史を展望している。
■人工知能研究の「現在地」と「方向性」
「人工知能と哲学と四つの問い」人工知能学会(監修)三宅陽一郎/清田陽司/大内孝子(共編)

本書は、人工知能学会誌『人工知能』の連載記事:レクチャーシリーズ「AI哲学マップ」および関連記事を再編集し、書籍化したもの。
レクチャーシリーズ「AI哲学マップ」は、人文系(主に哲学)の研究者と人工知能分野の研究者の対談から、相互の知見を共有し集積した先に、
「人工知能のフロンティアを描き出す」
ことを目的として企画された。
本書では、記事・対談の内容から浮かび上がった下記四つの問いを提示し、これらを軸に対談内容を理解することで、人工知能研究の
「現在地」
と
「方向性」
を明らかにし、学問としての発展に示唆を与えてくれる。
問い1 人工知能にとってコミュニケーションとは何か
問い2 人工知能にとって意識とは何か
問い3 人工知能にとって社会とは何か
問い4 人工知能にとって実世界とは何か
記事再編にあたり、人工知能を専門としない多くの方々にもわかりやすく読めるよう、技術解説の補足や挿絵の追加など、内容理解の助けとなる工夫を凝らしてくれた親切本。
■なぜその短歌はすごいのか?
「すごい短歌部」木下龍也(著)

入部希望殺到の好評連載、「群像短歌部」待望の単行本化。
木下さんが極めてプラグマティックに短歌の核を探る。
これには読者もなるほど、すごい!と頷くばかり。
テーマは
「群れ」
「虫」
「ヘビロテ」
「ガム」
「ふわふわ」
など、ちょっと、一筋罠では行かなそうなものばかりだ。
けれど、難しく考える必要はない。
はりきって部室のドアを叩いてみましょう。
短歌部発足にあたって。
1.テーマを決めて短歌を募集。僕もみなさんと同じテーマで短歌をつくります。
2.採用歌のなにが「すごい」のかを言語化します。
3.僕の短歌の発想→推敲→完成までを詳細に記録します。
4.選者として、プレーヤーとして、腕を磨きながら投稿の場を楽しみます。
あなたの短歌に胸を撃ち抜かれる準備はできている。
人気歌人の思考回路を明かし、投稿者と腕を磨きあう。
「シャンシャンを一目見ようと並んだが 残った記憶はルンルンなヒト」松本悠
「常設展「車窓」において作品はまばたきのたび入れ替えられる」田中颯人
「スピッツが歌っていない感情を私が感じるはずがないだろ」山田桃子
「きみがくれた変なグミさえ好きになった危ない 今を忘れたくない」つき子
「空耳に父のハモニカ聴きながら 群れを離れて生きてもいいか」猫葉
■人類の起源以来最長の歴史をもつ大陸の哲学
「アフリカ哲学全史」(ちくま新書)河野哲也(著)

アフリカ哲学は、北アフリカのイスラム文化に基づく哲学、サハラ以南地域の哲学、アフリカ大陸の外で発展したアフリカーナ哲学に分けられ、アフリカーナ哲学はカリブ海の島々で発展した哲学も含む。
本書は、日本初のアフリカ哲学の入門書として、サハラ以南のアフリカ、カリブ海諸国で展開された哲学、アフリカ大陸での哲学に影響を及ぼしたアメリカやヨーロッパでのアフリカ人の哲学を解説。
これまでの哲学を相対化し、複数の世界に共通する人間の思考のあり方を解明する試み。
■たった一つの世界しかない
「黒人理性批判」(講談社選書メチエ)アシル・ムベンベ(著)宇野邦一(訳)
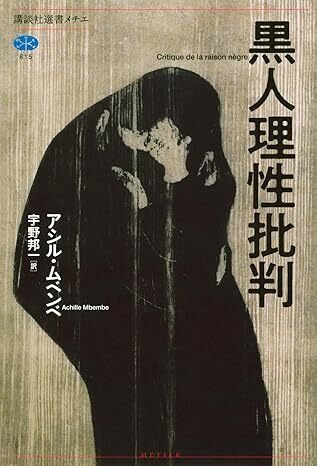
「黒人」の歴史は、奴隷制や植民地の過去と切り離すことができない。
1957年にカメルーンに生まれ、フランスやアメリカで学んだアシル・ムベンベ(Achille Mbembe)は、主著となる本書(2013年)を「世界が黒人になること」と題された「序」から始めた。
それは、奴隷制や植民地が特定の人種に限られたものではないこと、そして、すでに、過去のものとなった事態ではないことを、冒頭で宣言することを意味している。
新たな奴隷制や植民地、そして、人種差別は、形を変えて席捲しうるし、現にしている。
それを可能にする構造が、今の世界にはある、ということにほかならない。
だからこそ、不幸や苦痛、弾圧や収奪の歴史だった
「黒人」
の歴史を知り、共有しなければならない。
そのとき
「黒人」
には、新たな意味が与えられる。
著者は言う。
「途上にある者、旅に出ようとしている者、断絶と異質性を経験する者の形象として、「黒人」を新たに想像しなければならない。
しかし、この行路と大移動の経験が意味をもつためには、アフリカに本質的な役割を与えなければならない。
この経験は私たちをアフリカに回帰させ、または少なくともアフリカというこの世界の分身を通じて方向転換しなければならない」
アフリカから到来する何か、
「黒人」
から到来する何かにこそ、悲惨にあふれ、いや増すことを予感するしかない現在の世界を普遍的に、そして原理的に転換する可能性はある。
歴史的事実を踏まえつつその意味を明らかにした本書は、エドゥアール・グリッサンの言葉を借りるなら〈全-世界〉に向けられる希望の書である。
■この海の下で我々は手を取り合う
「私が諸島である カリブ海思想入門」中村達(著)
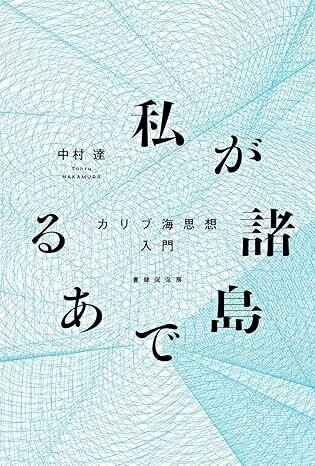
「web侃づめ」の大好評連載が大幅増補され、ついに書籍化!
カリブ海思想研究の俊英による待望のデビュー作。
リブ海思想について、新たな見取り図をえがく初の本格的な入門書。
西洋列強による植民地支配の結果、カリブ海の島々は英語圏、フランス語圏、スペイン語圏、オランダ語圏と複数の言語圏に分かれてしまった。
それらの国々をそれぞれ孤立したものとしてではなく、諸島として見るということ。
カリブ海をひとつの世界として認識し、その独自の思想を体系化する画期的著作。
これからのカリブ海思想研究のためのリーディングリストを付す。
「私が目指すのは、「カリブ海思想には独自の歴史がある」ということをお見せすることだ」(中村達)
■身体のない自己というものを考えることはできるだろうか?
「生きられた〈私〉をもとめて 身体・意識・他者」(心の科学のための哲学入門)田中彰吾(著)

意識は,脳の活動から生じるのではないのか?
ミニマル・セルフの成立にとって他者は不必要か?
現象学的な立場から、アイデンティティを
「私が私であること」
と理解し、根源的な場面まで遡ってその根拠を考える。
ラバーハンド・イリュージョン、離人症、ブレイン・マシン・インタフェース、心の理論など、心の科学がもたらした多様な知見を織り交ぜ、時には、読者の常識を揺さぶりながら、
「自己とは何か」
をめぐる思考実験の旅へと誘う。
■日本語の文体の特質と多様性を小説家の文例を挙げながら具体的に分かり易く説く
「日本語文体論」(岩波現代文庫)中村明(著)

本書は、1992年の岩波市民セミナーの五回講座をもとにした
岩波セミナーブックス『日本語の文体―文芸作品の表現をめぐって』
を、大幅に加筆して、タイトルも新たにしたもの。
「I 文体の発見」は、全章の序章にあたる。
文体論を論じる前に、文体論の素材となる文章自体の多様性(文語と口語,…書き手の年齢,職業,…)を小説家の文例を挙げながら分類・例示して説明。
「II 文体研究の展望」では、日本での文体論研究史を整理、総括している。
文体論研究の問題点は、
「多様な方法論が試みられ、分析手段の有効性が論議されないまま多彩な研究成果が発表されてきた」
ことにある。
波多野完治、小林英夫、時枝誠記らの
「文体」
の定義をめぐる原理論、方法論、分類法をめぐる様々な論をまとめることで、
「文体論」
の輪郭を明らかにすることが試みられている。
「III 文体論の構想」では、I、IIを踏まえたうえで、著者の独自の文体論が、展開されている。
著者は、
「文体」
を基本的には、以下のように定義している。
「文体とは、表現主体によって開かれた文章が、受容主体の参加によって展開する過程で、異質性としての印象・効果をはたす時に、その動力となった作品形成上の言語的な性格の統合である。」
この定義の特色は、文体を作者側からの一方的な静的な存在と見ずに、作者と読者の間で実現する動的現象と捉えることにある。
読者が参加し働きかける過程で、文体が姿を現す。
著者は、自説の検証を抽象論にならないように、具体的な作家の文例を一つ一つ読者に示しながら分かり易く説いている。
文例には、漱石、鷗外、芥川、横光利一、川端康成、井伏鱒二、井上ひさしを始め、近代・現代の名文が引かれ、的確な、ユーモアを込めた達意の文で論じられている。
「IV 文体分析のモデル」は、IIIまでの文体の理論を踏まえた上で、文体分析の方法、手順が示される。
「V 作品の文体」では、漱石の「坊っちゃん」を取上げて、発話、対話の表現分析から、生き生きとした語り口、豊富な言葉の連想を呼び起こす文体の秘密に迫る。
「VI 作家の文体」では、井伏鱒二の文体を通して、笑いの表現の諸相を具体的な文章を挙げながら分析している。
「文体論」の研究を推進させてきた著者による、文、文章、文体に関心のある読者にとって必読の一冊であり、
波多野完治さんの
「文章心理学入門」(新潮文庫)波多野完治(著)
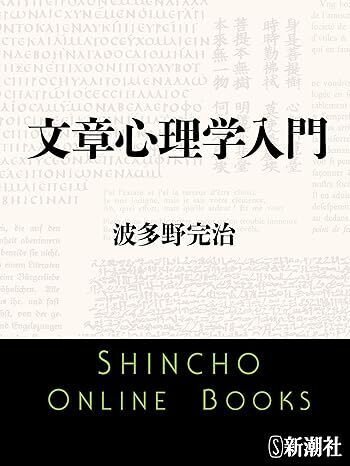
や
安本美典さんの
「文章心理学入門」安本美典(著)

が紹介されていた。
