
【じっくりと耕す】教養とは心を耕すこと

映画『愛を耕すひと』本予告
「教養」
は、英語で、
”culture”
ですが、
「耕す」
という意味もあります。
よく耕された土地が、栄養を吸い込むように。
人も、可能な限り、
「柔軟な心」
で、
「考えることのできる人」
になれるように、
「想像力の旅」
に、出てみませんか?
背中を押してくれる言葉。
「人」
より、
「本」
からもらえたりすることも、あるから、ね(^^)
■「今、ラジオ全盛期。」冨山雄一(著)

本書では、オールナイトニッポンの成功を支えた、3つの戦略が挙げられています。
これにより、長期間かけて、リスナーとの関係を育む姿勢が、強調されています。
1.素の良さを生かすこと
ラジオは、見栄を張らず、ありのままの自己を表現できるメディアです。
この自然体が、リスナーとの深い結びつきを生み出しています。
2.関係性を耕すこと
パーソナリティとリスナーの関係は特殊で、見えない絆が育まれています。
この親しみ感が、リスナーを惹きつけて離さない、要因の一つです。
3.じっくりと待つこと
ラジオは、短期的な結果を求めるのではなく、長期的に、リスナーとの関係を築くことを、重視しています。
「ラジオは1クール10年」という言葉に象徴されるように、時間をかけた、信頼の構築が、重要なのです。
これらの戦略によって、ラジオは、幅広い支持を得ることができたのです。
■「栽培植物と農耕の起源」(岩波新書)中尾佐助(著)(岩波新書)

「「文化」というと、すぐ芸術、美術、文学や、学術といったものをアタマに思いうかべる人が多い。
農作物や農業などは″文化圏″の外の存在として認識される。
しかし文化という外国語のもとは、英語で「カルチャー」、ドイツ語で「クルツール」の訳語である。
この語のもとの意味は、いうまでもなく「耕す」という意味のことばである。
地を耕し作物を育てること、これが文化の原義である。」
本書は、こんな書き出しで始まります。
■「プロの条件」藤尾秀昭(著)
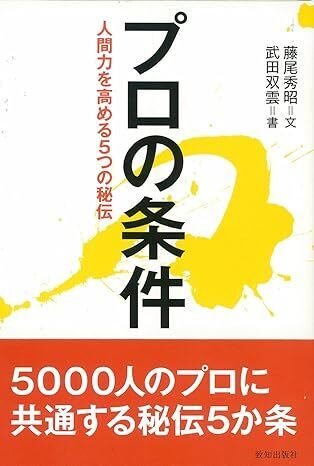
「心をひらかずに固く閉ざしている人に、人生はひらかない。
「ひらく」には、開拓する、耕す、という意味もある。
いかに上質な土壌もコンクリートのように固まっていては、よき種を蒔いても実リを得ることはできない。
心をひらき、心を耕す・・・人生をひらく第一の鍵である。」
■「中島らも その日の天使」(人生のエッセイ)中島らも(著)

「死んでしまったジム・モスリンの、なんの詞だったのかは忘れてしまったのだが、そこに”The day’s divinity, the day’s angel”という言葉が出てくる。
英語に堪能でないので、おぼろげなのだが、ぼくはこういう風に受けとめている。
「その日の神性、その日の天使」
大笑いされるような誤訳であっても、別にかまいはしない。
一人の人間の一日には、必ず一人、憂鬱を笑い飛ばし、絶望の淵で微笑む「その日の天使」がついている。
その天使は、日によって様々な容姿をもって現れる。
少女であったり、子供であったり、酔っ払いであったり、警察官であったり、生まれて直ぐに死んでしまった、子犬であったり。
心・技・体ともに絶好調の時は、これらの天使は、人には見えないようだ。
逆に、絶望的な気分におちている時には、この天使が一日に一人だけさしつかわされていることに、よく気づく。
こんな事がないだろうか。
暗い気持ちになって、冗談でも"今自殺したら"などと考えている時に、とんでもない友人から電話がかかってくる。
あるいは、ふと開いた画集かなにかの一葉によって救われるような事が。」
