
ポケポケの「モンスターボール」の効果は革命的だった
こんばんは!みなさんポケポケやっていますか!

私は毎日、フリーザーexを使ってカスミで泣かせたり泣かされたりしています。

ところで、下のカードを見てください。
もう持っているよ!という人も多いかもしれません。

まあ、何の変哲もないカードですね。
ただ、本編のゲームをしている人からすると、一つ違和感があるのではないでしょうか。
「ほのおのうず」ってそんなパワー系のワザだっけ?
150という威力は魅力的ですが、エネルギーを2個トラッシュするというのは、かなり大きなデメリットです。
ゲームでの「ほのおのうず」の効果は以下の通りです。
・威力35
・命中率85
・4~5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間ゴーストタイプではない相手は逃げたり交代できない。
パワー!というタイプというよりは、テクニカルな技ですね。
今の環境では、カイリューが電磁波羽休めで粘りながら使ってくるイメージです。
例えば、「オーバーヒート」という技があります。
・威力130
・命中率90
・攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。
威力が高い代わりにデメリットあり。
大きな威力の代わりにエネルギーをトラッシュするというカードの効果にも噛み合っているように感じます。
威力が高い技でいえば「だいもんじ」などもあります。
どうして、テクニカル系である筈の「ほのおのうず」がデメリットまであるパワー系のワザに設定されているのか。
これの背景には、ポケモンカード28年の歴史にある、一つの「ルール」が大きくかかわってきます。
その「ルール」に触れる前に、簡単にポケモンカードの歴史に触れたいと思います。
ポケカの歴史(ポケモンのわざ編)
ポケモンカードは1996年10月に発売されました。
これは、ポケモンという存在が世界に初めて生み出されたゲーム本編「赤・緑」が発売された1996年2月からたったの8か月後の話です。

ここから、本編と同様にポケカは歴史を重ね、現在も続いております。
ポケカの魅力の一つとして、ゲームの要素を上手くカードに落とし込んでいる、というところがあります。
例えば、色違いポケモンという要素は「ひかるポケモン」として実装されています。


例えば、剣盾での「ダイマックス」は「Vmax」として実装されています。


このようにゲーム本編の内容をカードに落とし込むこと、ともう一つ大きな特徴として、「28年間の中での一貫性が非常に強いこと」が挙げられます。
そして、これはポケポケにも受け継がれている精神です。
まずは、ポケポケのフリーザーを見てみてください。

続いて、ポケカでのカードを何枚かご覧ください。




ここまで見れば察しの良い方ならお気づきのことでしょう。
「ふぶき」の効果、全て一緒では?
「相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ」
偶然にしてはあまりにも揃いすぎています。
これは、「ふぶき」限定なのか?と聞かれますと、その逆です。
ポケモンカードでは、全てのワザが基本的に性能が統一されているのです。
例えば、「ひのこ」に注目してください。



すべてエネルギーをトラッシュする効果になっていますね。
ポケポケでもこれは統一されています。
どうして、ここまで技の統一にこだわっているのか。
これは、上記の「ゲームをカードに落とし込んでいる」というところに関係していると考えられています。
ゲームでは、ポケモンによって性能は異なるものの、わざの性能は誰が覚えたところで変わるものではありません。
ヒトカゲの「ひのこ」もアチャモの「ひのこ」も性能は変わらない筈なのです。
ポケカはその世界観を守るため、「一度設定したワザ効果を変えない」ということを基本的に貫き通しています。
これを踏まえれば「ほのおのうず」の謎も明らかになります。

このカードが収録されたのは、ポケモンカードはじめてのパック。
つまり1996年10月のことです。
「ほのおのうず」は、この時に「エネルギーをはがすデメリットのあるパワーワザ」として設定されました。
そのために2024年現在でも、「ほのおのうず」は、「エネルギーをはがすデメリットのあるパワーワザ」として貫き通されているのです。
じゃあさあ!初めから「ほのおのうず」はテクニカルな効果にすればよかったんじゃねえの!という意見もあるかもしれません。私もそう思います。
ただこれには、当時のポケモンのメディアミックスの問題がありました。
ゲーム発売から八か月でカード発売という話があったと思います。
考えてみてください。
間に合うわけがないですよね?
ルール設定から、イラストから、フレーバーテキストから、ゲームバランスの調整、販売の方法、少しかんがえるだけでとても間に合うわけがありません。
実はこれには裏があり、ゲーム発売前からカードの開発は始まっていたそうです。
少し話はずれますが、漫画なども執筆が始まっていたそうです。
コロコロコミックで連載している「ポケットモンスター」というギャグ漫画。
通称ギエピーでは、設定資料もままならなかったために、初期はかなり怪しい表現が多くあります。


ポケモンカードは、これに比べると資料がそろっていたかもしれませんが、完璧なものではなかったという情報もあります。
「ほのおのうず」がテクニカルなワザであるという資料は、果たしてあったのでしょうか。
かなり怪しいように思います。
名前からすると大技のように感じるのも不思議ではありません。
当時の開発者はそのように判断したのでしょう。
こうして生まれた初期のリザードンの「ほのおのうず」の影響が28年たった今でも響いているわけです。
他のワザでも「おにび」という相手をやけどにする技が普通の攻撃技になっていたり、「10まんボルト」が全エネルギートラッシュの大技になっていたりと、ゲーム側からすると違和感のある設定のワザは沢山あるので、是非探してみてください。
ちなみに「フリーズドライ」という技はカード発祥で、ゲームに逆輸入された珍しい技です。

ゲームでは「氷わざだけど、水タイプには弱点扱いで攻撃できる」というユニークな技になっていますが、カードでは「まひにする」という効果。
これも当然引き継がれています。

技の統一も面白くはあるのですが、こういったところで「水タイプには+20」のような効果にならないことは、少し寂しくも感じます。
ポケカの歴史(トレーナーズ編)

それでは、グッズとサポート、つまりトレーナーズ系のカードには一貫性があるのかどうか。
これに触れるには、また少しポケカの歴史に触れる必要があります。
ポケカは1998年に発売され、その後現在まで続いていますが、その長い歴史を大きく分けると、以下の三つに分けられると思います。(これは私が勝手に言っているだけです)
①旧裏時代(1998年~2001年)
②新裏~DP時代(2001年~2010年)
③BW以降(2010年~)
DPはダイヤモンド・パール、BWはブラック・ホワイトを指しています。
それぞれ、ゲームでは以下のように対応しています。
①赤緑、金銀の前半
②金銀の後半、RS、DP
③BW以降
それぞれ簡単に説明します。
①旧裏時代(1998年~2001年)
まず①の旧裏時代というのは、そのままの意味で、今とは裏面が異なっている時代のことです。
これはグローバル化が進んだ2001年に、世界中のポケカの裏面を統一するために刷新されることになります。

旧裏時代を一言でいえば、「バランスの悪い大味のゲーム」と言わざるを得ません。
旧裏時代を象徴するカードに「オーキドはかせ」があります。

手札を全て捨てるというデメリットの代わりに7枚ドローという破格の効果。
遊戯王ではデッキから2枚ドローできる「強欲な壺」が、強すぎるために禁止となっていることを考えると、カードゲーム全体から見ても異常な効果であることが伺えます。

更に当時は「サポート」という括りがなく、「オーキドはかせ」をデッキに入れられる4枚全て1ターンで使用することもできました。
これだけでも60枚デッキの内、28枚を手札に持ってくることができたのです。
ちなみに当時は「オーキドはかせ」はそれほど強いカードでは無かったそうです。
このレベルのカードが、「それほど強いわけではない」という評価を下されるほどに、旧裏時代は大味でバランスが悪いゲームであったと言えます。(だからこそのファンもいるのですが)
②新裏~DP時代(2001年~2010年)
そのあと、②新裏に入る際に、多くのカードが調整をされることになりました。
「オーキドはかせ」も「オーキドはかせの研究」として、生まれ変わります。

手札をトラッシュするというデメリットこそ無くなったものの、単純に引ける枚数が7枚から5枚に減りました。
現在まで続く「サポーターは1ターンに1枚」というルールも追加されました。
更にこの時代には他にドローカードが非常に少なく、このレベルでも4枚入れることが必須だったそうです。
旧裏時代が「インフレ」の時代だとしたら、調整された新裏は「デフレ」の時代になりました。
他のカードも軒並み効果が弱くなり、よく言えばうまく調整されている、悪く言えば薄味のゲームになりました。
そして、これは、その後10年ほど続いていきました。
そして、BWに入って事態が急変します。
③BW以降(2010年~)

「オーキドはかせ」が帰ってきたぞ!?!?!?!?
BW、すなわちブラック・ホワイトは「クリアまで新ポケモンしか出ない」という革命的な作品であり、悪の組織が「ポケモンを人々が支配するのは良くないのでは?」と説得してくる、かなりダークで大人向きの雰囲気を持っています。
「大地を広げたいからグラードン捕まえるで!」というおバカ集団を相手していた時とはわけが違うのです。
そんな作品をカードに落とし込むにあたって、カードゲーム側にも多くの革命が行われました。
その一つが、上にもある「原点回帰」です。
旧裏時代は大味ではあったが、あれはあれで愉快だった。
だからこそ、それを現代に蘇らせよう、としてBWのポケカはそれまでではあり得なかったほど強いトレーナーカードが大量に作成されます。
例えば、「相手のポケモンを入れ替える」効果のカードが3つの時代でどのように変わったか、見てみてください。



ご覧の通り、ポケカは①インフレ②デフレ③原点回帰という流れを踏んできました。
尚、③以降、強すぎるカードは弱体化などもあったものの、基本的には現在まで効果が引き継がれています。
この②、③の変化はかなり大きく、ポケカの「一貫性を大事にする」ことよりも優先されました。
例えば、「マスターボール」というカードは①と③で同じカード名でありながら、効果が変更されています。


③にあたって、「デッキに1枚しか入れられない」代わりに「どんなポケモンも1枚持ってこれる」というテキストに変更されました。
マスターボールの特別感も上手く表現されています。
「スーパーボール」もこの時に効果が変更されました。
他にも名前が同じまま、効果が変更されたカードは幾つもあると思います。
それでは、いよいよ本題です。
ポケポケの「モンスターボール」革命
ポケカにおける「モンスターボール」とは何なのか。
①②③のそれぞれの「モンスターボール」をご覧ください。



そう、ご覧の通りです。
「モンスターボール」は28年間、一度も効果が変わったことがないカードなのです。
コインによって、捕まったり捕まらなかったり、でも運が良かったらどんなポケモンでも捕まえられる、というゲームでの性能を表現しています。
それでは、ポケポケではどういった効果か。

おい!!!!効果が違うじゃねえか!!!!!
ランダムという要素はあれど、モンスターボールに「たねポケモン」という言葉が結びついたことは、これまでに一度もなかったことです。
「たねポケモン」を持ってくるボールは、現代ではネストボールが担っている役割です。

「ネストボール」はゲームでは「弱いポケモンを捕まえやすい」という効果のため、それを「たねポケモン」として表現されています。
何が起こっているのでしょうか。
これには幾つかの要因があると考えています。
まず、「モンスターボール」というカードの効果が弱かったこと。
ガチデッキで使われたことは長い歴史の中でも殆ど無いはずです。
ポケポケからはじめるカジュアル層に対して、「モンスターボール」という知っているアイテムが弱いというのはネガティブに感じます。
続いて、「デッキから選ぶ」というシステムを最初から付けたくなかったのではないかという推測。
デッキから1枚選ぶというのは選択肢も多く、カジュアルに楽しむにはゲームを複雑にしすぎてしまいます。
そして、テキストを変更しても「モンスターボールっぽさ」は残るということ。
もともとはランダム性を表現したテキストですが、「弱いポケモンなら捕まえやすい」というところに注目すれば「たねポケモンを持ってこれる」効果も違和感がありません。
結局どれが真因かは分かりませんが、明らかなことは「意図的にモンスターボールの効果を変更している」ということです。
ポケカでは「一貫性」を非常に重視していることは、既にわかっていただけたかと思います。
二度の大幅な変革はあれど、これほど長い年月において、むしろそれだけしか変革が行われてこなかったとも言えます。
それでも、モンスターボールの効果には大きなメスが入れられました。
実はこれだけではありません。
ナツメの効果は、悪の組織のボスが持つ効果でした。


悪の組織のボスの強引さ、力強さを表現しているのだと思いますが、ナツメの超能力で入れ替えているのも納得感があります。
「博士の研究」は「博士の研究」というよりも、ライバルが持つ効果に近いです。


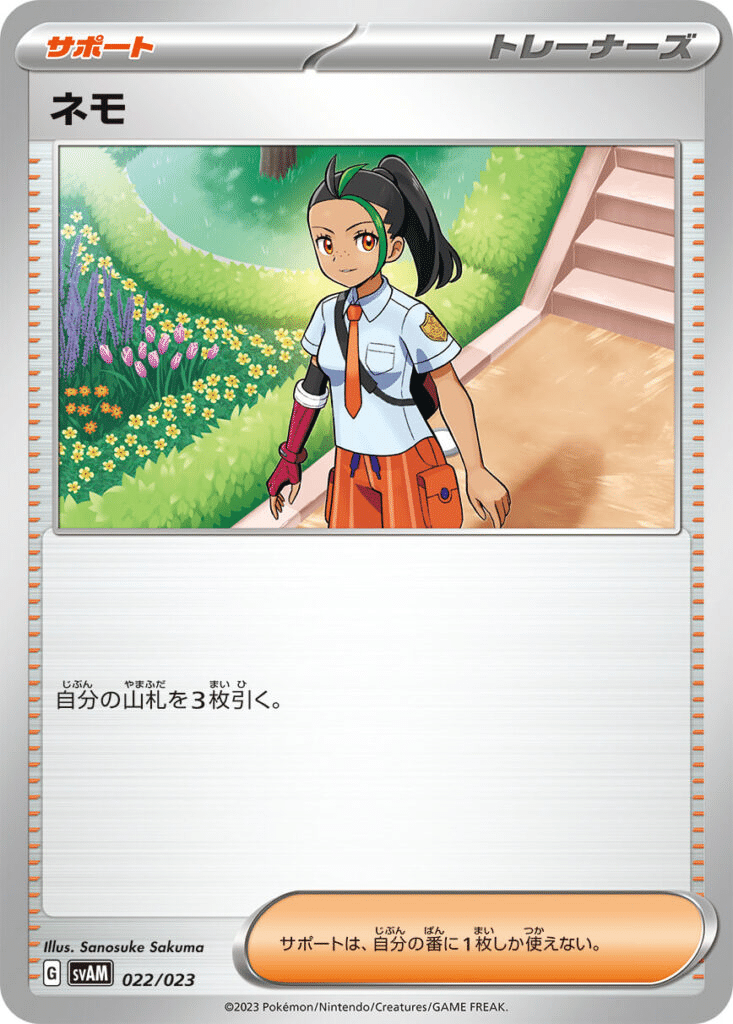
ポケカから入ると違和感がありますが、なんで博士がトラッシュ効果と結びついているのかと聞かれると、それはそれで困ります。
ポケポケのトレーナーズの効果は、どれも違和感のあるものはないように思います。
また、運要素が強く、カジュアルに楽しむことができるように調整されています。
カジュアル層にはじめて触ってもらっても楽しんでもらえること、それがポケポケにおいて、「一貫性」よりも重視された結果なのではないでしょうか。
これが、ポケポケにおいて発生した「モンスターボール」革命です。
この後、ポケポケは果たしてどのようになるのでしょうか。
「ハイパーボール」や「ふしぎなアメ」といった、長い間効果が変わらずにずっと使われ続けているグッズもまだまだ残っています。
「ポケモンのどうぐ」や「スタジアム」など、実装されていないジャンルのカードもあります。
恐らく上記が実装されても、今のカードそのままというわけではないでしょう。ゲームの雰囲気を壊さないまま全く違う効果になることもあるでしょう。
「一貫性」という言ってしまえば「プライド」よりも、「面白さ」を優先したポケポケが今後どのように発展していくのか。
とても楽しみです。
