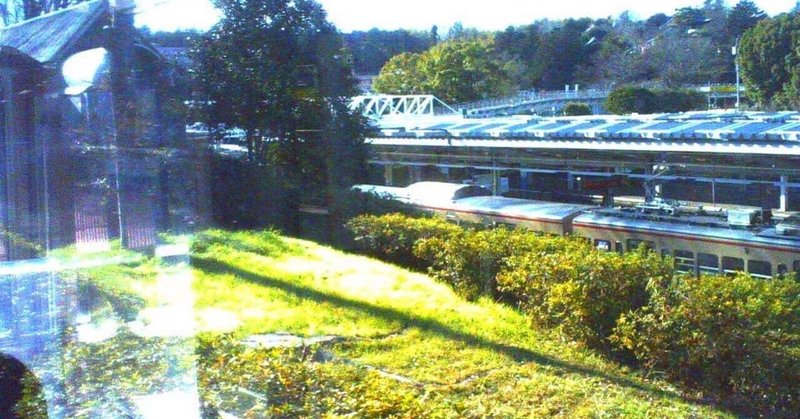#jpop
バンドブームの話 モテとGSと若年と社会
映画『Shall We ダンス?』を観て下心から始まる本気について思いをはせていたらバンドブームについて調べ始めてしまいました。色々聴いてしまって収集がつきません。若年人口とブームの関係はあると思います。GS、ビートルズ、イカ天
春に聴きたいキャンディーズ『微笑がえし』
春は前も後ろも見通す季節。グループの歩みをひとつの楽曲のなかで描き、振り返る。房型というかマトリョーシカ的というか。幅があるけど重心はずばり真ん中をとらえたサウンド。微笑は含み深く、広く、啓示に富んでいる。
井上陽水『クレイジーラブ』異端と愛の幅
溌剌としていながら聴く者に対してトリモチのような粘性を発揮する歌声とは対照的に、井上陽水の歌詞の世界はときにドライでがらんどう。死んだ魚のまなざしで刺す無常の様相が鋭い。愛も幸福もさまざまで、日常こそ異端への道。
never young beach『あまり行かない喫茶店で』 刹那の匂い、大衆の記憶。
ある時代、ある社会で強く匂った様式、文化。当時の人はたぶん「匂っていた」のに無意識だ。時や場所を離れてみるとその個性が際立つ。奇抜や独創は、調和や普遍の裏返しであるのを思う。
チューリップ『神様に感謝をしなければ』 雨の多面性、忘れる愛
「忘れる」は「気にしないで済むようになった」というか「受け入れることができた」というか。「忘れた何か」への認知は生きている。せつなくて祈りにも似た曲の響きの正体なのだと思う。好きな歌である。
ダ・カーポが歌った『宗谷岬』 夏を望むアンテナ
最北端の地理・アンテナ状の地形は恩恵も災禍も含め万事への高い感性を秘めて思える。ハマナスの開花や流氷の時期とは。「夏を望む歌」は言い過ぎか? 私も自分の目で幅をもって観察してみたい。あと、味噌ラーメンたべたい。
星野源『ドラえもん』 扉の先へ誘う道標
『ドラえもん』の主題にまなざしを向け、必要十分以上の心血を一つ一つその適切さを確かめながら注いでいった丁寧さ、遊び心と誠心誠意が結実している。エンディングのキメを聴き終えて心の中で拍手をした。ライトファンの私に刺さる。
WAになっておどろう 〜イレ アイエ〜 魂の響き合い AGHARTA、V6
V6で知っていた曲。おしゃまんべって由利徹さんのギャグだったのですね。大滝さん作品のオシャマンベ・キャッツを思い出したら、角松さんもはっぴいえんどをやはり通っていらっしゃる。
松崎しげる『地平を駈ける獅子を見た』 私のプロ野球原体験
歌い出しからハイトーン、松崎しげるの心技活きる作詞は阿久悠、作曲は小林亜星。心身のコントロール、パフォーマンスの最大化への挑戦は音楽も野球もまるで一緒。球団は街の一部でプロ野球に疎い私の一部。ウォウ。
プログラミング(打ち込み)に思うこと 〜私の生演奏びいきとYOASOBIの『群青』〜
ボカロ曲を連聴していくと、沼にはまるのを感じます。打ち込みは音像が安定しやすく、ストレスフリーなのかもしれません。平らな音像と生の歌唱やギターを組み合わせた表現の台頭を思います。
山本リンダの歌声 渡り歩く人柄
肉食のケモノ。かまってくる相手をほんろうする幼児。おしゃれな夜の街をうろつく遊び人。山本リンダを、いろんな人がらが通り抜け、交差し、横切っていきます。いろんな人の中にいる人が入れ替わりつつあらわれる。歌手はイタコです。
泉谷しげる『黒いカバン』事実のナナメ上の漫談
実話でしょうか。自分もおまわりさんに止められた経験を思い出します。ライブ演奏される機会も多いようで、だんだんパフォーマンスが過激に。漫画『ハコヅメ』であっち目線を知ると喜劇として俯瞰しやすくなります。
平山みき『希望の旅』不安と全能 長短の平行調
パッとBメロで開ける視界。平行長調へ。徐々にもとのFmにうつろいます。筒美京平さんのサウンドはファッショナブルでエキゾチック。メロディは万人にフィットする美人。コード進行はドラマティック。歌詞の展開を映した妙です。