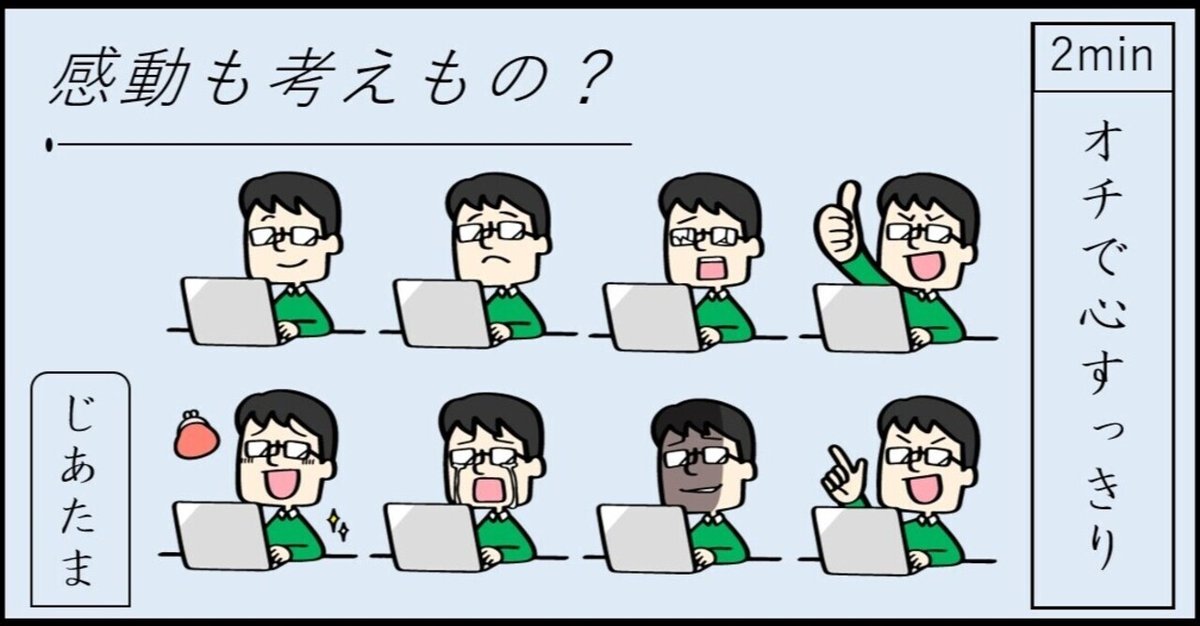
「だよなあ。いくらボケ始めた頑固じいさんだとしても、かつての巨匠だろ?」
ベストセラー作家でもある建築家にデザインされたオフィス街で、現代アートの展覧会が開かれている。展示会場には、三色のベタ塗りで描かれた図形の集合体や、浮遊する大理石が並ぶ。
壁に飾られた2m四方の絵を眺める家族。
「ママ、この絵、なんだかすごく好き。」
絵を見ながらそうつぶやいた娘は返事がないことにムスッとし、母親の袖を引っ張った。
「あ、○○ちゃん。ごめんね、ちょっとママ、すごく悲しくなっちゃって。」
母親は目の前にある濃紺基調の世界に、あと一歩で帰ってこれなくなるほど深く引き込まれ、鼻水をすすりながらようやく返事をした。
そんな『感情の揺れ動き』が、あらゆる作品の前で起こっていた。ある作品の前では床に血が垂れるほど強く唇を噛むものがいて、また別の作品の前では、思わず肩でリズムを取り出すものもいた。
ただ、鑑賞者が全くの無表情でいる作品が、一つだけあった。
「なあ、あれは流石にやり過ぎじゃないか?」
展覧会の端っこで、黒スーツを着こみワイヤレスイヤホンを付けた男二人が会話している。
「だよなあ。いくらボケ始めた頑固じいさんだとしても、かつての巨匠だろ?」
アルバイトのボディーガードたちは、『テクノロジーの参入』を拒んだベテラン作家に対する、運営の当てつけ行為について話していた。
数年前からアート鑑賞者には、特製のメガネをかけ、こめかみには薄いシールを貼ることが推奨された。視線の動きと脳波を調べることで、作品のクオリティを数値化する流れが始まったのだ。
しかしそんな風潮に耐えられなかった巨匠は、結果、あらゆる展示会の運営に嫌われた。
彼は今回、長い年月かけてようやく生み出した新作の展示を依頼していた。しかし今、場内の彼のスペースには、何も入ってない額縁だけが飾られている。
足を止めて額縁を眺める来客者たちは、やはり全くの無表情だ。
「過去最高の集客だったな。」
「ああ、データも最大量だから、きっと次回の作品はもっとすごいことになるぜ。」
展示会場の裏にある一室で、データアナリストたちは早速今回の分析を開始する。
「ん?おい!あの額縁のやつ、異常に満足度が高いぞ。」
「そんなバカなw。さっき俺がちらっと会場を回った時は、額縁の前にいる人はみんな死んだ顔してたぞ?」
そう言いつつも、アナリストは部屋の隅から段ボールを引っ張ってくる。惰性で集め続けていたアナログのアンケートだ。
「そこにはなんて書いてあるんだ?」
『ここ数年の間、一切止まることなく動き続けていた心が、久しぶりに休まった気がしました。』
