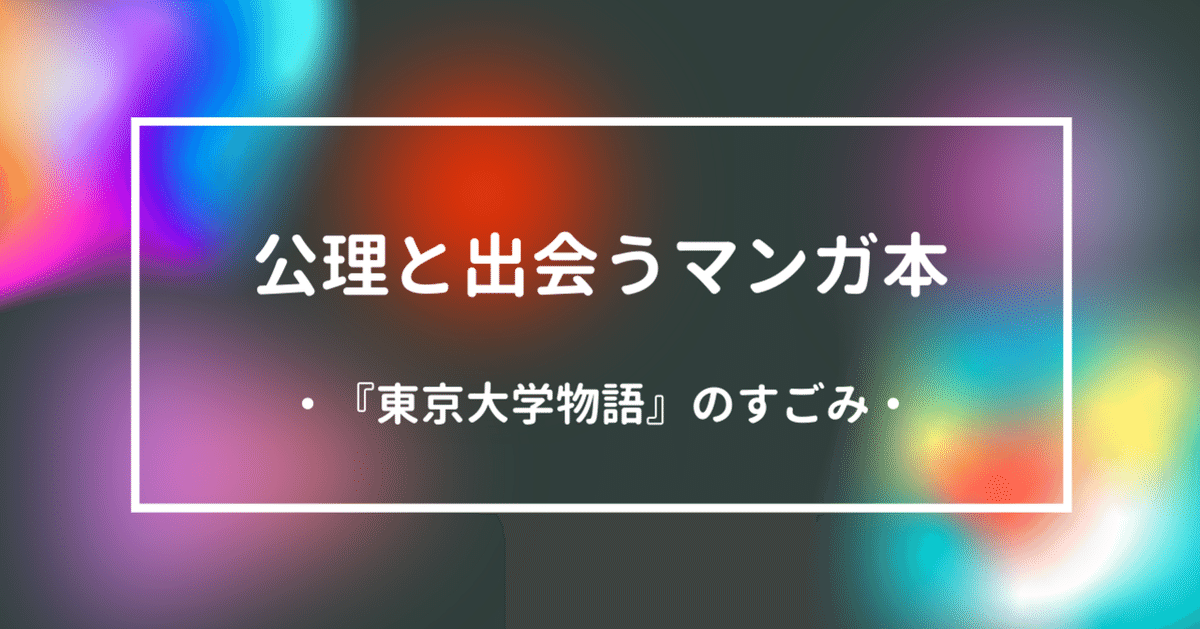
『東京大学物語』の凄み/「公理」との偶然な出会い
『東京大学物語』は連載終了後20年を経た2021年現在でもTwitterなどで盛んに言及される傑作マンガです。
様々な角度から語られる作品ですが、本noteでは特に「公理」との関わりに触れようと思います。なお『東京大学物語』で公理に関わる話は「●第365回●創造」で、下記の電子書籍に含まれます。単行本巻数は不明ですが、恐らく最終34巻掲載分でしょう。
公理について
公理(こうり)とは、最も基本的な仮定・前提のこと。
論理学者や数学者、数学教師、数学科の学生など論理や数学に深く関わるのでなければ、普段の生活で公理について考えたり思いをはせたりすることはまずありません。
しかし、公理に全く無関係に生きることはできません。毎日毎時、誰しもがなんらかの公理から導かれるルールに従って生活しています。それにも関わらず公理についてほとんど考えないのは、ルールに関して盲目になりがちな人間の思考の癖があるのではないかと考えていますが、それはまた別の話。
『東京大学物語』では、主人公の男(村上直樹)・女(水野遥)が東京大学へ入学後、色々あってありすぎたのち一時的に地元の函館へ戻り、出身高校の数学教師(矢野先生)と再会するシーンで「公理」が登場します。
東京大学と公理(第365回「創造」)
やや長くなりますが、以下、矢野先生・水野遥・村上直樹の会話を引用。
ーーー
矢野先生「水野…どうだ東大は?」
水野遥「えへ…今行ってないんです。」
矢野「そうか。やはりな…」
水野「やはり…な?
まいったナーー矢野先生には…お見通しだったのかーー」
矢野「ふ…自分で考えることは(原文ママ)始めてしまった人間は、組織の枠から、はみ出てしまうものだからな。
組織や、社会には、その組織を形成する核となる思想…言ってみれば常識や道徳や規範やモラルや法といった、その世界の公理がある。
知らず知らずのうちに、人はその世界の公理を不変の真理と思い…その公理から導かれる種々の定理にのっとって行動してしまう。
しかし…自分で考え始めた人間、自分で公理をつくり、自分の世界をつくってしまった人間は、人々が真理と思っている公理を真理と思わないし、たかだか一つのモノの見方でしかないと思う。結果、その組織からはみ出すしかなくなる。」
水野「でも先生、人はもともと、そんな公理なんて持たないで生まれてくるのに…どうしてそう思ってしまうのでしょう。」
矢野「社会は、まやかしの教育というものによって、社会の公理をあたかも真理のように見せてしまうし…世の中をこう見ろと教えこむのだ。」
村上直樹「矢野先生、やっぱりオレは東大を頂点とする教育機関にマインドコントロールされているんですか?遥ちゃんは、はっきりマインドコントロールされていないってわかるけど…」
矢野「試金石は簡単だ。自らが考え、楽しみ、感動し…数学をするか、テストでいい点を取るために人の考えたパターンをおぼえこむ訓練の、数学をするか…
数学は、世界をどう見るかだ。今まであった見方ではない。新しい見方・公理をつくることが数学なのだ。
しかし、しょせんすべて…頭の中の出来事…現実ではない。どんなに科学が発達したとて…人間は現実の真理になど到達できないのだ。」
村上「そうか、オレにとって東大に入ることが真理だと思っていた。東大の思想の受け売りをより正確にテストで答えるのが得意だった。
今だって…試験をつくる人間のお気に入りの答えを書くことを訓練している。独創性などない…」
ーーー
引用ここまで。
東京大学には日本の実質的なルールメイカーたる官僚を多数輩出する官僚養成機関という側面があります。最も基本的なルールとしての公理に対してどのような態度をとるか、公理をどのように扱うかという話題は東京大学の学生にとって非常に親和性があります。
矢野先生は「数学の取り組み方によって、自分自身が公理や真理をどう捉えているかが分かる」という高校数学課程を超越した大事な教えを、元生徒の東大生たちに伝えています。
引用部分だけで伝えることは不可能ですが、第一話からここに至るまでの過程を共に過ごした読者ならばこの会話の深みや、村上の納得に対する納得感を十二分に楽しむことができるはず。
科学と公理
さて、なぜ本noteでこの箇所を採り上げたかと言えば、僕自身が公理に深い関心があるためです。
特に科学と公理の関係性については、強い興味を抱いています。
数学教師である矢野先生は数学と公理について多くを語るものの、科学と公理についてはほとんど語りません。
しかし、しょせんすべて…頭の中の出来事…現実ではない。どんなに科学が発達したとて…人間は現実の真理になど到達できないのだ。
もし質問ができるなら聞いてみたい。
「科学の公理は何ですか?」と。
公理とプラセボ効果
なぜ科学の公理について聞いてみたいかと言えば、それがプラセボ効果に関わると信じているから。
「素朴プラセボ効果論」に替えて、「公理的プラセボ効果論」の必要性をひしひしと感じるため。
…。
…。
…という誰かの夢のお話。
