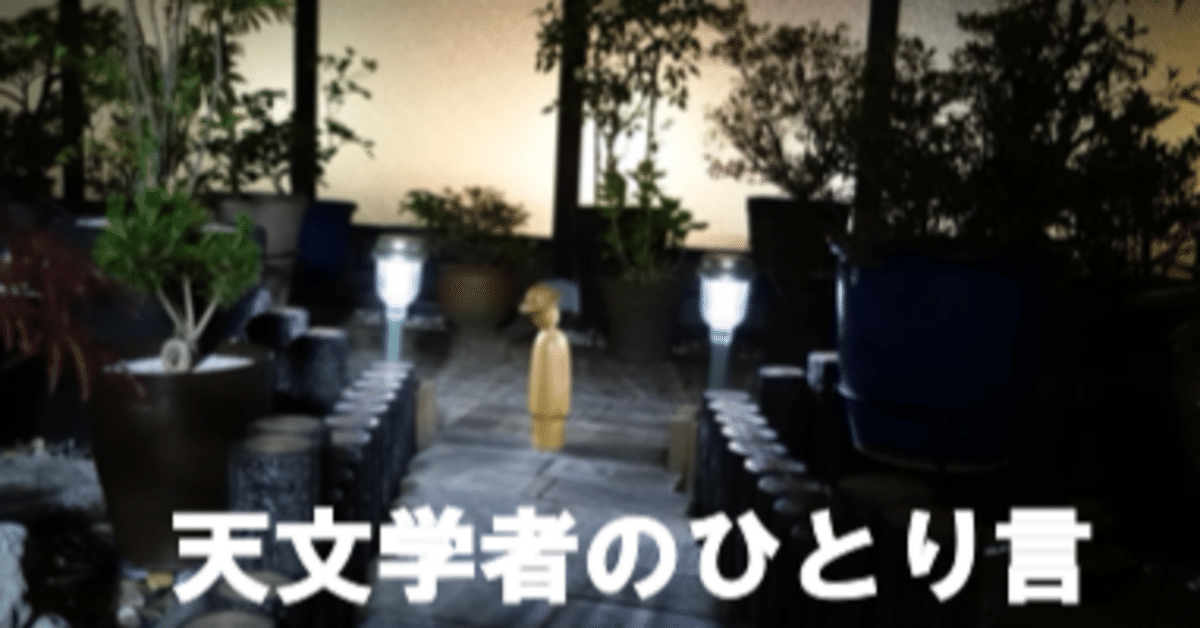
天文学者のひとり言(16)積読じゃなかった、単なる本の山だった
積読、再訪
前回のnoteで我が家の積読状態を紹介した(図1)。

ところが、冷静になって考えると、紹介した我が家の積読状態は積読ではないことに気がついた。なぜなら、積読で積まれる本は未読本なのだ。その意味では、我が家の場合、ドイツで言うところの「本の山」に近い。
ここで、「積読」の定義を確認しよう。WIKIPEDIAには次のように説明されている。
積読、積ん読、つんどくは、入手した書籍を読むことなく自宅で積んだままにしている状態を意味する言葉である
日本人の癖
江戸時代にはすでに読書のスタイルとして「朗読」、「黙読」、「積置」の三種類があるとされていたそうだ。ここで「積置」は「積み置き」のことで、本を読まずに積んで置くこと、つまり積読を意味する。なんと、日本では積読は江戸時代からの慣わしのひとつだったのだ。
「積読」と言う言葉は明治時代からあったようだ。考案者としては経済学者の田尻 稲次郎(たじり いなじろう、1850-1923)や和田垣謙三(わだがきけんぞう、1860-1919)など、諸説あるようだ。二人とも、経済学者であることが面白い。たしかに、文系の研究者のオフィスは本だらけのことが多い。
古典社の『書物語辞典』
古典社が1936年に出版した『書物語辞典』には「積読」と言う項目がある(図2、図3)。昭和の時代になると、それなりに積読という言葉は市民権を得ていたのだろう。令和の現在ではnoteの人気キーワード(ハッシュタグ)のひとつになっている。
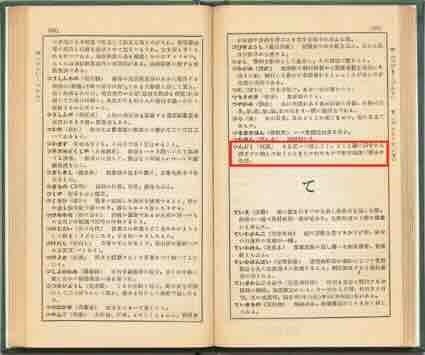

最近の辞書ではどう説明されているのだろう? 気になったので、手元にある『広辞苑 第7版』(岩波書店、2018年)を見てた。すると、次の説明があった。
つんどく 積ん読 (「つんでおく」とドク(読)とをかけた洒落) 書物を読まずに積んで置くこと。
(註:「つんどく」は、正しくは「積読」ではなく「積ん読」のようだが、現実には「積読」の方が頻繁に用いられている。)
『広辞苑』では、明らかに『書物語辞典』の説明を引用している。
読まずに積む
「積読」で積まれている本は未読。まだ読まれていない本、未読本なのだ。実は、私はこのことに注意を払っていなかった。単に「本が積まれている状態」を「積読」だと勘違いしていたのだ。
読んでから積む
図1の写真を見ると、たくさんの本が積まれている。これらすべての本が未読かというと、そうではない。実のところ半分以上の本は既読だ。つまり、定義上、「積読」になっている本は、見えている本の半分以下でしかないのだ。こういう状態をなんと呼べばいいのだろうか? やはり、ドイツに倣って、単に「本の山」と言う方が良いのかもしれない。
「棚読」という言葉はあるのか?
では、本棚にきちんと並べられている本は、何と呼べばいいのだろう? 本棚に並んでいるから「棚読」か?
まさかこんな言葉はあるまいと思っていたら、あの偉大な著述家の松岡正剛氏(1944-2024)が既に使っていた。
ただし、「棚読」は、本を読むのではない。何と、本棚を読むのだ。これには合点がいく。本は背表紙で私たちに語りかけてくれるからだ。
じゃあ「本読(ほんどく)」か?
さて、困った。本棚に並んでいる本は何と呼べばいいのだろう? 「本棚」のうち、「棚」は使われたので、残るは「本」だ。じゃあ、「本読(ほんどく)」? これを「積読」に対抗する言葉だとすれば、本棚に並んでいる本は、すべて既読本じゃないとダメだ。ところが、我が家の本棚を見ると、多くは既読本だが、未読本も並んでいる。買ってきた本を読まないうちに本棚の空いている場所に入れてしまうことがあるからだ。
サラどく パラどく チョイどく
ところで、既読と言っても、いろいろある。熟読した本もあれば、少しだけ読んだ本など、「前書き」と「目次」だけ見て、おさらばした本。うーん、これは本当に困った。
例えば、次のようなケースもある。
サラッと眺めただけの本 → サラどく
パラっとめくっただけの本 → パラどく
一部だけ読んだ本 → チョイどく
こんなふうに名付けることもできそうだ。まあ、こんなに細かく分けても、しょうがないかもしれないが。
以上をまとめると、表1のようになる。

本と付き合う方法は思ったより多様だ。しかし、それでいいように思う。
未読本もいずれは既読本になる。そして、本棚にきちんと並べられる日が来ることを願って。
