
3-1-2 爆跳の3要素 ー素因と対策ー
前前回から炭火初心者向けに「備長炭の爆跳」について解説をしています。
じつは備長炭は「跳ねる部位」が決まっています。
これを知らないでがむしゃらに爆跳対策をしても、ムダな苦労するだけです。
爆跳の素因について絶対に知っておかなければいけないこととは、
『備長炭は堅い部分が跳ねる』
たったこれだけです。
備長炭のうち「どの部分が特に堅いのか」を理解して対策すれば、着火時のハネはなくせます!
今回は備長炭のうちハネの原因となる「特に堅い部分」について写真を見ながら解説していきます。
ぜひ明日の着火作業で、備長炭をよく観察してみてください!
こんな経験や悩みのある方に読んでほしい
・爆跳については、運だとあきらめていた
・対策をしようにも、見当もつかない
・跳ねるから、二度と備長炭は使いたくない
今回お伝えしたいこと
・備長炭は爆跳する部分が決まっている
・堅い部分から着火させるのはやめよう
・「爆跳の原因は炭の品質不良」は誤解
こんなことが書いてあります
・爆跳の原因が炭の物性による場合について
・備長炭のうち爆跳する部位を写真で解説
・素因は3パターンしかない
【大原則】備長炭は「固い部分」から着火させてはいけない!
「備長炭は全体的に堅いでしょ!」と言われそうですが、その中でも特に堅い部分がハネの原因になります。
素因の代表的な『堅い部分』というのがこの3パターン、
①「芯」
②「節」
③「とがった部分」
では順番に、備長炭のうち「堅い部分」について写真で確認してみたいと思います。
そのまえに、ちょっと復習。
爆跳の3要素
備長炭は3つの要素がそろったときに爆跳します。その3要素は、①主因、②素因、③誘因に分類することができます。
※今回はその3要素のうち、②素因についての解説です。


それでは本題です。
①備長炭は「芯」から着火させてはいけない

木の中で堅い部分は、木の「芯」の部分です。
木全体を支えている部分なので、芯が堅いのは想像つきやすいですよね。
製炭の際、堅い木の芯の部分は柔らかい周辺部分よりも熱が入りやすいです。
そのため堅く締まりすぎてハネやすくなります。
とくにガス火の燃焼温度は非常に高いので、本来備長炭の着火には向きません。
ガス火に対してこの芯の部分が接しないようにしてみてください。火種が下なら、芯はなるべく上の方に位置するようにしてください。
②備長炭は「節」から着火させてはいけない

木の「節(フシ)」も、木の芯と同じように原木(製炭前)の段階から堅い部分です。
木の断面を見たことある方はわかると思いますが、節や節の周辺は木の繊維が入り組んでいます。
また、葉がついた長くて重い木の枝を支えている部分なので、非常に堅いです。
この部分もやはり製炭の際に、ほかの柔らかい部分よりも熱が入りやすいです。
そのため堅く締まりすぎてハネやすくなります。
この部分も「芯」と同様、ここから火種の熱が入らないようにしてみてください。
③備長炭は「とがった部分」から着火させてはいけない

これは断面が「丸」のタイプの備長炭ではなく、断面が「扇型」のタイプの備長炭に多いです。
原木の中でも比較的太めの部分を縦に割って製炭するわけですが、割ったときに「とがった部分」が3辺できてしまいます。
この「とがった部分」は製炭時に「面」の部分よりも熱が入りやすく、堅く焼き締まりがちです。
この部分も前の2つの部分と同様、ここから着火の熱が入ることを避けてください。
この代表的な堅い3点から着火させてしまうと跳ねやすくなります。
ただ,「できるだけ」という話なので、しょうがない場合は「とにかく弱火で根気強く」時間をかけて着火してください。
「備長炭はこの①芯、②節、③突起の3点から着火させないこと」に注意するだけで、爆跳のほとんどを防ぐことができます。
___Q. 結局、備長炭のどの部分から着火させていけばいいのでしょうか?

A. できるだけ、丸くなっていて節のない「原木の外周」部分から着火させてください。
___Q. 短い備長炭の場合どこから着火させればいいのでしょうか?
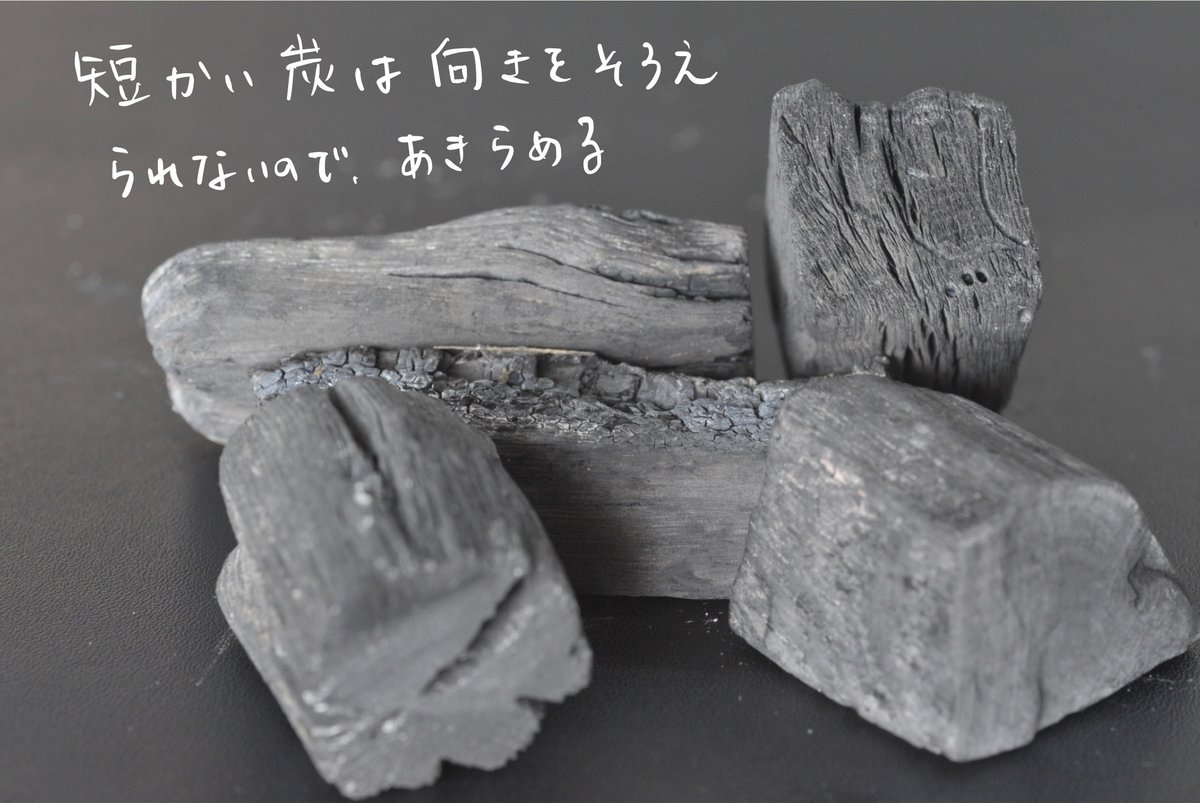
A. 短い場合は向きをそろえることができないので、あきらめます。特に弱火にする必要がありますが、長い炭よりは着火は早いです。
今回のまとめ
✓ ガス火は備長炭の着火には強すぎる
✓ 炭は炭で着火させるのが理想的
✓ 芯、節、突起以外から着火させよう
よかったら前回、前前回の記事もぜひ!
今回の参考文献
①『伝熱工学』JSMEテキストシリーズ 日本機械学会
②『伝熱概論』甲藤好郎 株式会社養賢堂版
③『熱学入門』藤原邦男・兵頭俊夫 東京大学出版会
④『熱輻射論講義』マックス・プランク 岩波文庫
⑤『おいしさをつくる「熱」の科学』 佐藤秀美 柴田書店
⑥『爆跳性木炭について』高橋憲三 国立国会図書館デジタルコレクション
Writer:
ホンダタロウ/炭火研究家 @HIROBIN
ふだんは備長木炭の生産→流通→消費のうち、
「流通」を担っています。
世界の伝統文化、アート、JAZZが好きです。
Instagram:@hirobin___taro.honda___
twitter:@sumibinogakkou

