
没ネタの記:月岡芳年の箱庭への異常な愛情
これまでARTISTIANで何回か浮世絵師・月岡芳年の箱庭趣味について触れてきました。
箱庭制作に駆り出され、完成したらしたで早朝から箱庭の手入れを任される芳年の弟子たちの嘆き・・・はては箱庭を借金のカタに取り上げられたことなどを紹介してきました。
今回はあまりにマニアックかつ長い引用になることから簡単な紹介にとどめていた、『やまと新聞』に掲載された月岡芳年の箱庭についてご紹介します(絵でも描ければ、箱庭を再現した絵をつけたいところですが・・・)。記事のタイトルにした通り、並々ならぬ箱庭へのこだわりを感じさせます。
当時の新聞で紹介された月岡芳年の箱庭
引用記事の冒頭は以下の通り(以下、引用部の変体仮名や旧字体はすべて新字体に直し、適宜読点を入れています)。
芳年翁 手製の箱庭
先頃の新聞にも(先月廿三日頃)芳年翁が箱庭の事を記したるが翁は其後ふたゝび製造て復た十六基の箱庭に丹精を顕はさる
芳年の十六基の箱庭紹介のはじまりはじまり。
山王祭
其第一は山王祭、是は昔し山王の祭礼に一台の鉾を牽出し牛ヶ淵の景色を見せ豆の如き陶器製の人形が整列して(其人数五十三粒)練行体裁うるわしくも可愛らしき状態にて耳を傾むけて聞ときは囃の音きやりの声も聞ゆるが如くに思われ珠のほか上出来なり(其陶器師は浦野繁)。
浦野繁は尾形乾山の子孫の養子となり、六代目乾山を自称した陶工・浦野乾哉のこと。晩年にはバーナード・リーチに教えたこともあったとか。ご参考までに尾形月耕が描いた山王祭をリンクしておきます。
田家の苗代
其第二は田家の苗代にて是は何処と見せたるにあらず。只ある田家の苗代を造りたる物にして牛を牽く野翁が無心にあり葎(引用者注:生い茂ったつる草のこと)に閉られたる農家が静あり。其他苗代の蒼々たる体これも我耳を傾むくる時は鳴子の音かわずの声が遠く近く聞ゆるの想像あらしめ天然の雅致そなわりて就中嬉しう出来たり。
縄手の懸茶屋
第三は縄手の懸茶屋、是は東海道大津の宿の尽処にして懸茶屋の妙なるは云ふに及ばず近く来る小原女の尻の振かた遠く立つ農人の鍬柄杖いづれも真に迫りて奇なれど就中て懸茶屋に人物を置ずにあり肥溜の中に茶殻を入れて有なぞは実に人をして其処に在らしむるの感じを起させ熟く聴かば軽尻馬の嘶なく声の聞ゆるかと思想れて頗ぶる閑気に甚はだ妙なり。
閑林の茶亭
第四は閑林の茶亭なるが是は京桶の左官湯山音次郎が丹精に成たる茶亭を軸とし其他の構へ到らざる隈もなく痒きところに手の届くとは此辺と想はれ是も観る人をして松風を聞せ思ひ邪しま無らしむるの趣きありて其妙なる例ふるか物なし(後は次号に)
湯山音次郎はたびたび芳年の逸話に登場する左官で、半ば内弟子のように芳年の家に寝泊まりしていたようです。
深更の原野
(前号のあと)第五は深更の原野、是れは遠山を軸として其の麓より何処まで連なりたるや際限もなき宏原の中に深更いまぞ丑三ツとも思ふ頃ほひ両頭の狼獣くさむらの中より出没して秋天片月の影に咆え宿を取後れたる旅人もがなど、求食をれる趣むきを備へ、信濃あるひは甲斐辺りの原野と見えて頗ぶる凄く殊に其狼獣は象牙彫刻師を以て有名なる美術家島村俊明翁が丹精に成りたる物ゆえ一段と凄気を装たり。
島村俊明は、16歳の若さで回向院の欄間を手がけて有名になった彫刻家で、のちに牙彫家となり高村光雲・石川光明とともに彫刻の三傑と称された人物です。そんな人物に趣味の箱庭のために狼を彫らせる芳年の徹底ぶりに驚かされます。
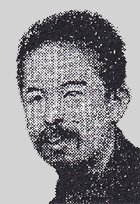
円月の井
執筆した記者が紙面が足りないことに気付いたのか、このあたりから説明が足早になってきます。
第六は円月の井、是れは一ツの拮撑を見せたるものにて古色あつて甚はだ雅なり。
鈴ヶ森
第七は鈴ヶ森、是れは昔しの鈴ヶ森刑場の処ろを顕はし例の供養塔を建て傍はらに梟首台と捨札を建て笹薮を見せたるなど至れり尽せりと云ふの外なし。
安部川の渡頭
第八は安部川の渡頭、是れは東海道安部川の渡しにして同じく昔しの状態を模し川越連台を見せたるなど人をして転た懐旧の情を興さしむるの妙あり。
膳所の城
第九は膳所の城にして戸田一西(引用者注:初代膳所藩藩主)の往古を思はせ、
芝浦の景色
第十は芝浦の景色を見せ人の心を爽快ならしめ、
穴稲荷
第十一は穴の稲荷を造れり。是れは上野の稲荷の奥にて穴を臨みて両三狐が出没する体、青苔なめらかにして頗ぶる雅致あり。
積善の水
第十二は積善の水、是れは昨今その跡を絶ちたるが彼の流れ灌頂を見せたる物にて産女なぞが迷ひ居る如くに思はれ、
唐崎の松
第十三は唐崎の松、是には明智左馬之助が馬轡を把つて佇立をり遠近の景色その度に適ふて丹精いたらざる隈もなく、
本能寺の変の後、追い詰められた明智左馬之助が琵琶湖を馬とともに「湖水渡り」したという伝承を元にした箱庭のようです。芳年の師匠である歌川国芳が描いたこんな左馬之助が箱庭になっていたのかもしれません。

庭園の飼猿
第十四は庭園の飼猿、園の内に猿猴を飼養する体にして狙公が朝四暮三の餌を俟ち孤吟長嘯して山を思ふの姿を見せ、
こちらは四字熟語「朝三暮四(目先にこだわって結果は同じであることに気づかないこと)」の語源となった中国春秋時代の宋の狙公にまつわる話から。狙公が飼っていた猿にトチの実を朝に3つ晩に4つ与えると言うと猿が怒り出し、朝に4つ晩に3つ与えると言ったら喜んだという故事をあらわしています。
今戸の朝烟り
第十五は今戸の朝烟り、是れは即ち今戸の朝烟りを見せたる物にて瓦を焼く竈の塩梅むかふ河岸を遠見に顕はし其真景を写し得て妙なるが此一箱は主人翁が例のお箱物に縁あるに因りたるならん罪ふかし〱。
「例のお箱物」「罪ふかし」とは何のことを指しているのでしょうか?今戸に芳年の馴染みの芸者がいたのでしょうか?気になるところです。
古橋の修繕
第十六は古橋の修繕、さて此の古橋の修繕なるが是等は真に絶妙にして其の結構いはん方なし。先づ或る村の朽果たる板橋を造り橋の前後に跨ぎを設けて之れに「ふしん」と云ふ小さき札を下げ傍はらに仮橋を渡し橋の袂には左も有るべしと思はるゝ大老杉あり。其杉に標縄を纏ひ豆の如き絵馬を懸け白布の幟四五本たてゝ之を大杉大明神と崇めたる容体と云ひ其ほか惣て不思議に奇にして実に妙なりと云ふに止まり憖じひ評せざる方よろしからんとの衆議なり、惣じて益々精巧を極め愛弄に余り有る物にして世の同好の人一見を請はゞ記者が評言の真なるを知る事あるべし
これだけ記者にほめられたら、借金取りが芳年の箱庭を借金のカタに持って行ったのもうなづけます。改めて芳年の箱庭について触れた記事はこちらから。
