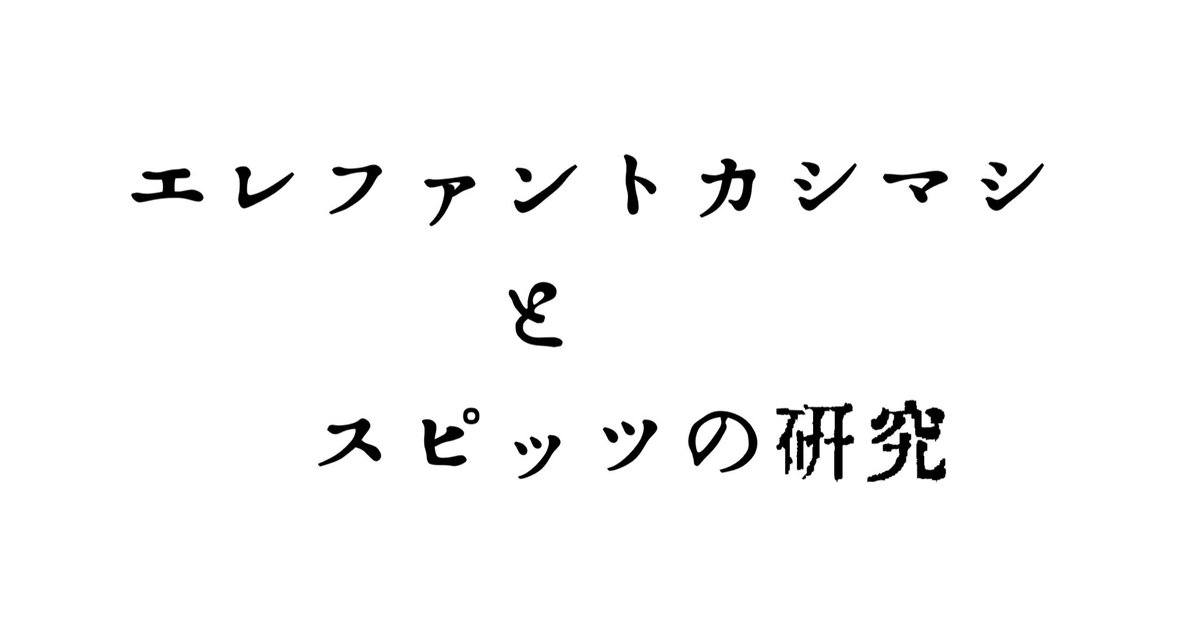
「エレファントカシマシ とスピッツの研究」 (第五回)
神に近づけなくなった詩人、苦行の始まり『巡礼行』
ドイツの近代詩を作り上げた詩人ゲオルゲ、彼は何を目指していたのだろうか。
いったいにゲオルゲは、自覚的に態度を重んずる人である。詩文はむろん、つたえられる彼の諸種の写真像や生活態度もそれを裏書きする。無節度と独創性を混同することをドイツ的弱点とし、「ドイツ人がドイツ的な挙措(die Deutsche Geste)を獲得することは十の領土を攻め取るより重要」だというのである。
(中略)
ドイツ人のためにその点で若い彼がなしうる最高のことは、詩語においてそれを達成することである。それゆえ、詩語の獲得・革新の彼の事業を、その根本動機を強調していうなら、それはその時代のドイツ文化に形式意志をあたえんための象徴的行為だといえる。
(「ゲオルゲとリルケの研究」昭和35年11月10日 第一刷発行 手塚富雄著 株式会社岩波書店 P122)
詩人ゲオルゲが感じたドイツ的弱点の克服のために「ドイツ的な挙措(die Deutsche Geste)」の獲得ということを彼は詩で目指したとなれば、日本的弱点の克服のために「日本的な挙措」の獲得ということをロックで目指したのはロックバンドエレファントカシマシ の宮本浩次氏と言えはしないか。
浮き草のような 自由の幻想
勘違いして楽しんで
浮き沈みのない平らな人生を 開き直ってやってる
何かやりたくても 何があるのか
考え込むのはまっぴら お天とう様もわらってる
みんなと同じ楽しい人生
(『浮き草』:エレファントカシマシ アルバム『エレファントカシマシ 』収録)
ゲオルゲの結社した芸術サークル、ゲオルゲ・クライスの会員、ゲオルゲの一番弟子と目されていたフリードリヒ・グンドルフは師ゲオルゲの詩業について、
言語と詩とは、個人が自己の根源的な魂の力以外になんらの外力も借りないで、世界を根底から変えることへの地盤となるものだとし、物質的な世界にあっては「言語こそ精神の最奥のとりで(、、、[傍点])であり、人間の内部における神の究極の避難所である」といっている。
(「ゲオルゲとリルケの研究」昭和35年11月10日 第一刷発行 手塚富雄著 株式会社岩波書店 P122)
手塚先生はこれを受けて、ゲオルゲという詩人について、
言語をエレメントとしてゲオルゲは戦ったのであり、その戦いは、そのエレメントを越えて時代と世界に交渉すべき動勢をもっていた。しかも、「芸術は社会との断絶」をいうこの詩人にとっては、その動勢はいよいよ彼をして、その固有のエレメントに力を集中させることになったのである。
(「ゲオルゲとリルケの研究」昭和35年11月10日 第一刷発行 手塚富雄著 株式会社岩波書店 P122)
これは、フランスのパリで出会った詩人マラルメのアティテュードに影響されたものではなかろうか。「芸術は社会との断絶」という思念は、ゲオルゲのみならず、鮮烈なデビューを果たしたロックンロールバンド、エレファントカシマシ にもこれ以後、その固有のロックへの集中が色濃く表れ始める。
言語をエレメントとして戦ったゲオルゲ、彼は詩集『讃歌』の中の「聖なる訪れ」で、世間を突き離して「待ち」「成熟した」己の中の詩語の目覚めにより、彼の元に降臨した聖なる女神(詩の神様ミューズか)と同等の立場で触れ合った(第三回 参照)。
その女神はさらにゲオルゲに話しかける。だがあくまでもそれはゲオルゲが自分の精神世界で作り出した女神であり、それでもって外の時代や世界へ詩人として影響を与えられる程のエレメントとはなりきれていない。
汝は王者の態度をもっていやしい女たちには汝の肉体をこばみ、みずからも嘆息しながらそれを断念しているが、われ(ミューズ)はわれにたいする冷やかな崇敬を喜ぶものではない。汝は高き圏からの癒やしの飲物を求めて、いたずらに手を揉みあわしていなければならなかった。おお、われは、それをみずからなんじにさずけえんために、人の胎より生まれた身であればよかったのに。汝は専横なものとしてわれを招くもよし、哀願してわれを招くもよし(Herr oder flehend mögest du mich laden)。いずれのばあいもわが顔の紅に二色はない。われは汝を練絹の波に沐浴させ、深紅のいろの上に喜びをもって汝に応じよう、云々。
(中略)
卑俗をこばんで高い圏に参じようとしながら、ミューズの口を仮託して言わせるこの情熱的結合への願いは、くりかえし現われるゲオルゲ固有の問題である。もしこの結合が完全に実現されれば、彼は彼の願う詩人性を確立しうると予感するのであろう。そして今の彼は、その実現の可能性を積極的に信じ、「抗がう鉄筆をはこび」ながら、詩人としての歩みを進めようとしている段階にある。
(中略)
「盛夏」(Hochsommer)では、ヴェニスの貴顕淑女のエレガントな社交ぶりを華麗なことばを駆使して写しているが、描写以上には出ない。ゲオルゲの真骨頂はそういう点にはなくて、その優雅さを空虚と断じ、
喜々としたつどいのむなしさ
そは暗鬱な行為の海と反目する、
痴愚ならぬ弛緩は、ただ沐浴のときにのみ
まことの恩寵。
ときめつけるところにある。生硬ではあるが、こういう句には若いゲオルゲの本来の意気ごみがのぞいている。しかしそれなら、なぜそのむなしいものを美しい言葉をつくして描くのか、その矛盾感が作の性格をにごすのである。詩作の態度が一貫していないのである。
(「ゲオルゲとリルケの研究」昭和35年11月10日 第一刷発行 手塚富雄著 株式会社岩波書店 P191〜193)
さてそれで詩集『巡礼行』(Pilgerfahrten, 1891)のすがたを明らかにするために、これを次の詩集『アルガーバル』(Algabal)との関連において見ると、これはまったくそれへ至る過渡的性格のものであることがわかる。あるいはこう言ってもいい。『巡礼行』の結論として生み出されたのが、さしあたりこの『アルガーバル』なのであるが、それは積極的に巡礼行によって何物かが見いだされたからではなく、その反対に何物も見いだされぬことが確認されて、あの『アルガーバル』の意識的な主我的世界に移ることになったのである。そして生命のリズムからいえば、「やわらかい苔のしとねで眠りを欲する」という感情が投影しているこの巡礼行の段階は、全体的には下降沈静の様相をしめしている。詩としても物足りないものが多い。そして次の『アルガーバル』では、詩人はその消極的結果を自覚し、いわばギリギリのところへ押しつめられた者として、強烈なエネルギーをふりしぼることになるのである。
(「ゲオルゲとリルケの研究」昭和35年11月10日 第一刷発行 手塚富雄著 株式会社岩波書店 P195)
「やわらかい苔のしとねで眠りを欲する」というのは詩人としての目覚めを告げる詩集『讃歌』の最終の詩に登場するフレーズである。詩集『巡礼行』の段階において高い圏に参じようとするあからさまな意気込みは息をひそめる。
手塚先生のゲオルゲ評に触れて、私は痛快なデビューアルバムを放ってから後のエレファントカシマシ が続け様にリリースした『エレファントカシマシⅡ』、『浮世の夢』がさしあたり、詩人ゲオルゲにとっての詩集『巡礼行』から『アルガーバル』へと向かう道筋に当たるものではなかろうかと思っているのである。
ゲオルゲのアティテュードを思いながら「初期エレファントカシマシ 三部作」と云われる時期についてまた改めて見ていきたい。
つづく
