
明治ゆるふわストヲリイ◆ザンギリ頭誕生編
2018年10月23日…つい先月の事ですがこの日、日本は明治150年を迎えました。
さて、明治時代と聞いて有名な言葉「ザンギリ頭を叩いてみれば文明開化の音がする」とは誰しも学校の授業で聞いたような聞いていないような、そんな言葉かと思われます。

今回の明治ゆるふわストヲリイは明治時代のザンギリ頭をはじめとした明治初期の散髪のお話です。
●ザンギリ頭は命がけ
むかしむかし、江戸時代での日本男子は額から頭のてっぺんまでを剃りあげてその上に髷(まげ)が結ってあるという、大河ドラマなどでも馴染み深いあの髪型をしていました。
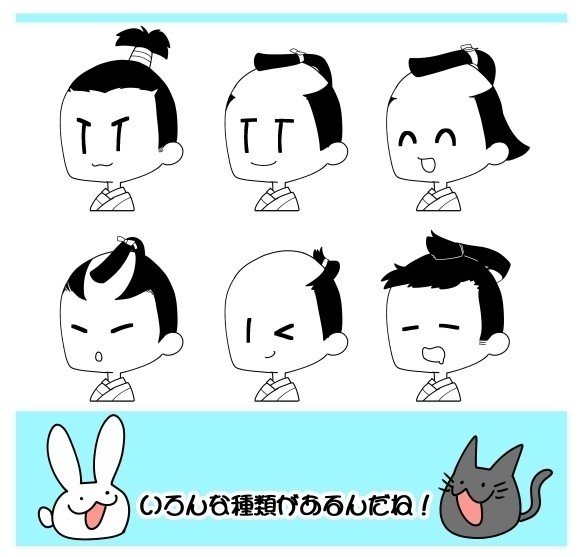
当時このヘアスタイルは当たり前の習俗で、右も左も日本男子はデコから頭まで毛を剃って髷を結っていたのです。ところが江戸幕府も終わりがけ…つまり幕末の頃になるとこの髷文化のせいで困ってしまう人達がでてきました。それは欧米留学生たち。
彼らは、欧米へ行った際にはその髷を軽蔑されてしまうので外出する時には帽子を目深にかぶって髷を隠していた程でした。髷なんて止めればいいじゃん?とも考えられますが、やめたくてもやめられない事情があったのです。
当時、幕府が留学生に散髪を禁止していたという事もあるのですが、それよりももっとヤバイ…最悪命に係わる理由がありました。
それは攘夷派の浪人による襲撃です。

1864年(イヤナムシって覚え…なくてもいいよ)、エグザイルにいそうな顔立ちの佐久間象山(さくましょうざん)が攘夷派によって暗殺されたという血なまぐさい事件がおきます。
佐久間さんは海外の技術を積極的に取り入れて日本を強くしよう!という考えのもと活動していましたが、攘夷派の中でも特別血の気の多い浪士に

とされてしまいました。物騒ですね。
こんな事があったものですからうっかり髷をおとして西洋ヘアーになんてなったら大変です。留学生たちも海外から日本に帰ってきた際に最悪死にます。誰でも自分の命は最高に可愛いので、こんな事で殺されては堪ったもんじゃありません。
とはいえ、留学生たちの中にはさっさと髷を止めて髪をおろしザンギリ頭にした人々もいました。な、なんてリスキーな事を…とも思いますが、日本に帰ったときには付け髷をして帰国したとの事。おいそれと髷を止められない時代だったようですね。
●日本人、髷スタイル止めるってよ
さて、明治時代に入って日本の政治形態は徳川から新政府へ移行しました。
新政府は1871年(明治4年)に「散髪脱刀令」を出します。この法令は「髷を止めてもいいよ~やりたい人は引き続き髷ってていいよ~」というものです。
最初は慣れ親しんだ髷を止めるのに抵抗があった人々。すぐにはその髷を手放しません。
しかし散髪は従来の髷に比べて清潔であり、新しいものが好きなニュージェネレーションたちは進んで散髪するようになります。また1873年(明治6年)には天皇も散髪を行い、官吏を中心にどんどん散髪する人が増えて行きました。
明治4年の新聞雑誌にはあの言葉の全文が紹介されています。

「ザンギリ頭をたたいて見れば、文明開化の音がする」という言葉は当時流行ったユーモアだったのです。
このようにして、男性たちの間では散髪がどんどん増えていくことになりました。
●散髪が引き起こすあれやこれ
1872年(明治5年)3月の名古屋新聞には東京府下の住人の八分が散髪と書いてあり、その頃にはかなり散髪も普及している事が伺えます。髷を止めると帽子が被れるようになった為か洋品店では一時、帽子が売り切れてしまったという話も。
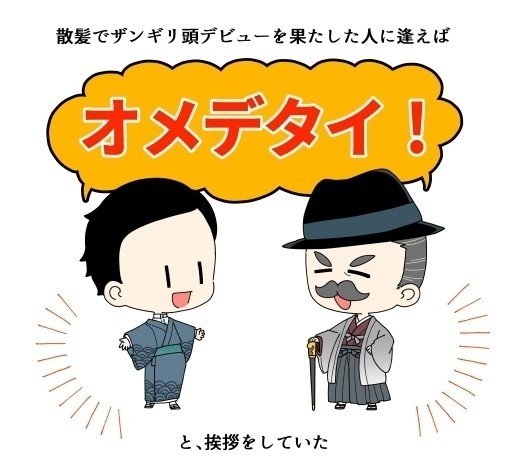
東京や大阪、京都といった都市部ではどんどん断髪デビューが果たされていく一方、地方ではまだまだ全体がそのような雰囲気ではないようで婿養子に貰われた青年が断髪者であった為、それを妻が嫌がって結局離縁になったり、友達に誘われて断髪デビューを果たすもまたもとの髷に戻ったり、髷を切られて訴訟した人もあった程でした。
●散髪文化、その先に…
このように、明治時代初期は老いも若きも都市も地方も断髪によって騒がれていました。200年以上続いた習慣を止めるというのはやはり大事に違いありません。さてこの断髪現象、実は男性たちだけはありません。
そう、女性にも断髪者があらわれていたのです!!

その話はまた次回…。
◆参考文献◆「新聞資料明治話題事典(小野秀雄・著)/東京堂出版」「幕末明治風俗逸話事典(紀田順一郎・著)/東京堂出版」
いいなと思ったら応援しよう!

