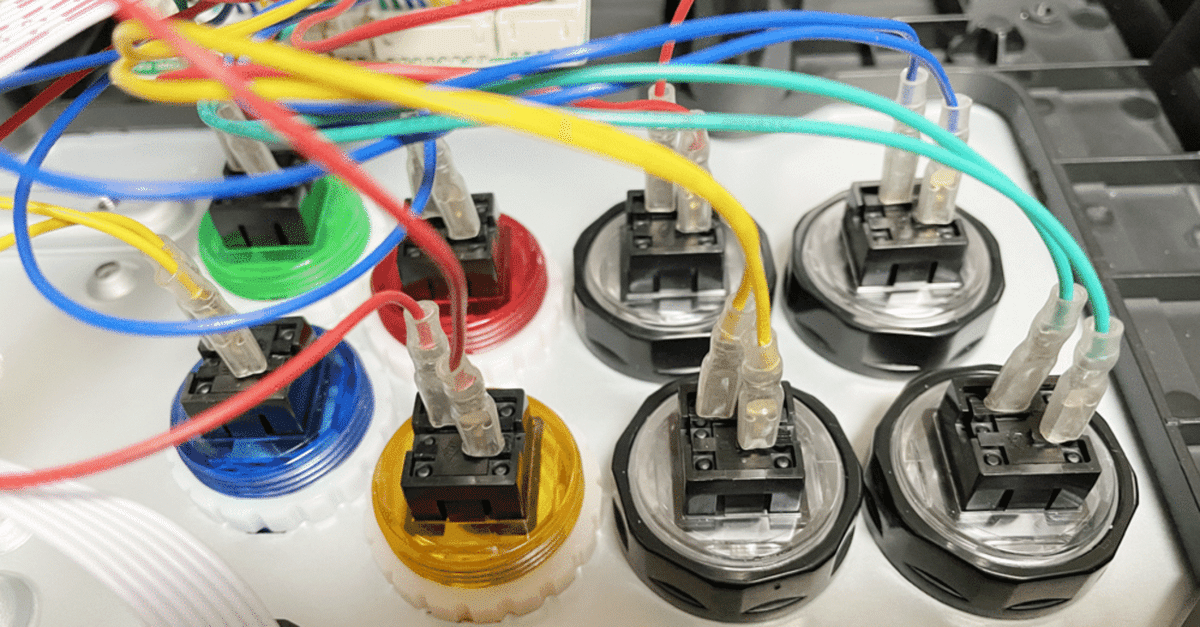
トランジスタアンプを作って実体配線図に迷った1年間
雑誌の記事でアンプを作ったが鳴らない。配線間違いかと思い、何回も何回も点検たが、間違い箇所が分からない
10代の頃にトランジスタアンプも作ったことがあります(これは中古の基板を買った話ではありません)。昔は、弱電関係が好きな青少年を「ラジオ少年」と呼んだようですが、私もその一人で、ラジオやオーディオ、アマチュア無線の記事が載った雑誌を、毎月楽しみにしていました。
もちろん真空管アンプの記事もありましたが、トランジスタアンプに比べて部品代が数倍したので、買えなかったのです。その当時の記事に載っていた真空管アンプのデザインや構成が、今、私が持っている6L6系中華真空管アンプに似ているので、懐かしい気分もしています。
脱線しましたが、話しをトランジスタアンプに戻します。
それも5W+5W程度のアンプでした。本当は真空管アンプのように金属シャーシーに組むのですが、加工道具も含めて高いので、無理を承知で、べニア板で作った箱に入れました。
キットではないので部品を一括で買う事は出来ません。部品店に行き、一つ一つ集めました。(失礼ながら)キットで一括で部品が手に入ってもあまり嬉しくないのに、部品店で一つ一つ集めるのは苦にならないどころか、楽しい時間なのはなぜでしょう。
そうやって集めた部品で作りました。
ところが、完成しても音が出ないのです。
配線間違いかと思って、何回も、何回も点検しましたが、間違い箇所が分かりません。
普通は1~2日で見つかるものですが、どうしても分からないのです。疲れ果て、とうとう、あきらめてしまいました。この時の落胆はとても大きいものです。
1年後に似たような記事が掲載された。実体配線図を注意深く見比べてみたら、一か所配線が変わっていた
それから、一年たちました。
すると、似たような製作記事がまた掲載されたのです。
古い雑誌と見比べてみましたが、やはり同じ製作記事です。こんな事もあるんだと思って、実体配線図を注意深く見比べてみましたら、一か所配線が変わっていたのです。素人の私は回路図ではなく実体配線図を見て作ります。現代ではほとんどが写真なので誤記は無いはずですが、昔は手書きが多かったので、まれにあったようです(後から気づきました)。
「あっ!」と思って、押し入れから引っ張り出し、アンプを修理してみました。
そうしたら、
音が出たのです。
この時の喜びを、何と表現したら良いのでしょう。
でも、出版社も間違いが分かった段階で、もっと早く訂正のお知らせを載せなかったのでしょうか。いや、きっとそうしていたのでしょう。私が見落としたに違いありません。毎月立ち読みしても、毎月買うとは限りませんでしたから。同類の本は2~3種類あり、立ち読みして、どれか一冊だけを買っていたのです。
でも、やっと完成したそのアンプを使う期間は、長くありませんでした。
やがて、就職すると、すぐに給料でオーディオを揃え始め、手に入れた一流メーカーの評判の良いトランジスタプリメインアンプと比較試聴して、自作トランジスタアンプは引退することになりました。
そんなに高いものではありません。オンキョーの「インテグラA-755」という、グリーンメタリックのボディが美しい普及品のアンプです。しかし、ラジカセとミニコンポほどに、自作品とは音に違いがありました。自作はゆるい音がしていたのに、インテグラは締まったハイファイで、私にとっては未体験ゾーンでした。
私はオーディオショップで「音がカタイ」と愚痴をこぼしました。店員さんは困り顔で、「これ以上柔らかい音だと真空管アンプしか・・・」と言いました。私にはすぐに買い替える金も決意もなかったですが。
やがて「インテグラA-755」の音にも慣れると、今度は自作アンプの「ゆるい」音がローファイに思えてきました。それで捨てたのです。家も狭いし、余分なものは廃棄するのがわが家のスタイルでした。
今思えばゆるい音には「ゆるい」という長所があるので、自作アンプも取っておけばよかったですが。
(「小記事の備忘録」オーディオの話題 2022.10.15の加筆再掲 )
( 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
更新されたときは「今週までのパレット」でお知らせします。)
