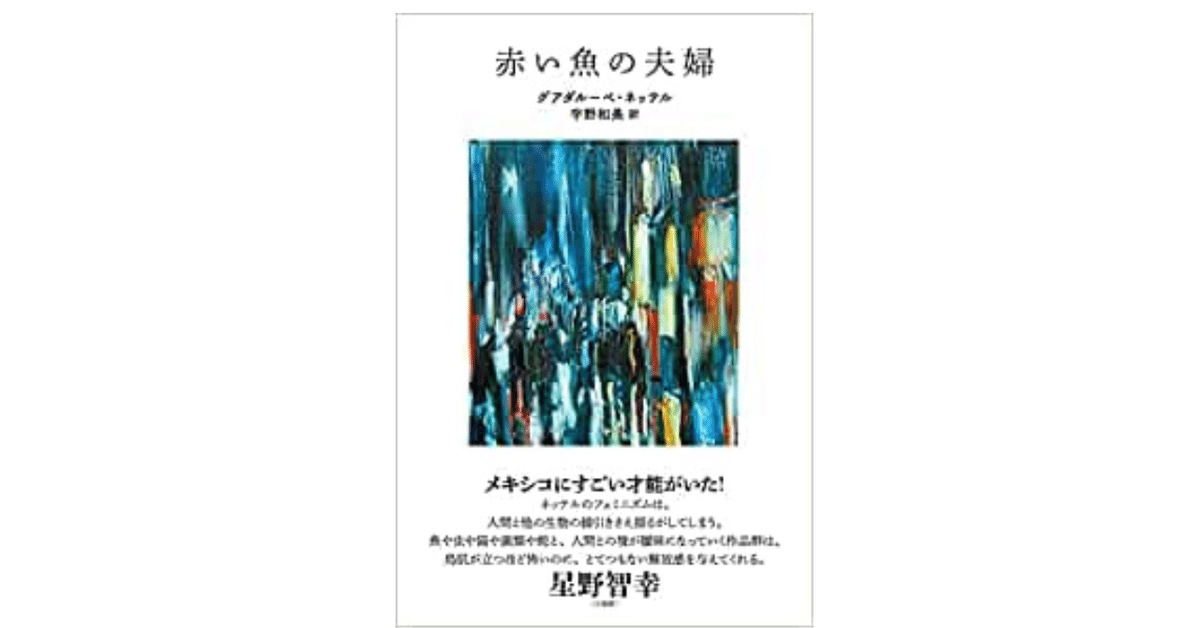
動物化していく人間の作品
『赤い魚の夫婦』グアダルーペ・ネッテル , (翻訳)宇野和美
第3回リベラ・デル・ドゥエロ国際短編小説賞受賞。
メキシコの作家が贈る人間とペットにまつわるちょっと不思議な物語。
初めての子の出産を迎えるパリの夫婦と真っ赤な観賞魚ベタ、メキシコシティの閑静な住宅街の伯母の家に預けられた少年とゴキブリ、飼っている牝猫と時を同じくして妊娠する女子学生、不倫関係に陥った二人のバイオリニストと菌類、パリ在住の中国生まれの劇作家と蛇……。
メキシコシティ、パリ、コペンハーゲンを舞台に、夫婦、親になること、社会格差、妊娠、浮気などをめぐる登場人物たちの微細な心の揺れや、理性や意識の鎧の下にある密やかな部分が、人間とともにいる生き物を介してあぶりだされる。
「赤い魚の夫婦」「ゴミ箱の中の戦争」「牝猫」「菌類」「北京の蛇」の5編を収録。
2014年にはエラルデ文学賞を受賞するなど国際的に高い評価を受け、海外では毎年のように「今年のベスト10」に取り上げられる実力派作家グアダルーペ・ネッテルの傑作短編集、待望の日本語訳。
メキシコの女性作家。生物に感応していくマジック・リアリズム的な短編。性病という病原菌もあるけど。菌が愛おしくなるのは移された相手との関係性を愛おしく思うという倒錯的な愛の姿なんだが、もともと母親の爪の菌に感応してしまうというのがあった。関係性の小説。こじらせ女子ということか?女子だけではなかった。ゴキブリに感応してしまう少年もいた。飼い猫と共感覚していくというのは経験することがあるかもしれない。ちょっと自分の記憶と重なった。猫が自分の死に場所を決めるというような。
「赤い魚の夫婦」
表題の「赤い魚」とは闘魚といわれるベタのこと。オスは繁殖期になるとヒレをひらひらさせて求愛行動に出る。ただ雌との相性の問題で行き過ぎる求愛行動はしばしば攻撃的になりメスを傷つける。夫婦間の微妙なすれ違いをベタを飼うことでシンクロさせていくのだが、語り手夫婦の場合は、大きな争いの元になっているのは子供を巡ってだった。
そこがベタとは違い求愛期間が終わった後での問題なので、そこはベタとは異なるがただこの語り手の場合は相性ということを問題にしているようだった。ベタのペアは無作為に選ばれて、そしてメスは怯えて逃げ惑う。水槽を大きくしても結果的にはペアの相性の問題でそこに閉じ込められていれば自ずと不幸な結果は目に見えてくる。
そしてメスの死のあとに代わりに、再びオスのベタを買ってきたことだ。それはメスを痛めつけたオスの見せしめのために元気の良いオスを買ってきたのだ。このへんはよくわからん。ただそのうちに先住のオスも死んで新しいオスだけが残り顧みられることなく忘れされていく。そのベタの名前が「オブローモフ」。ロシアのゴンチャロフの作品の主人公で無気力な貴族の若者は「オブローモフ」主義と言われた。
「ゴミ箱の中の戦争」
離婚する両親の喧嘩が絶えない家から叔母の広い家に預けられた少年の作品。両親は芸術家タイプで叔母の家は近代のブルジョア家庭というような。個室を与えられているのだが、従兄弟たちに虐められるので食事は別にするという。女中が年取った婆さんと住んでいるのだが、その婆さんが巫女的な人で一匹のゴキブリを正しく殺さなかったので仲間を集めて復讐に来るという話。ゴキブリ対策をしているうちにゴキブリに愛着を持ってしまう。自分もゴキブリのようだと感じてしまうのだ。民話的な話が少年の中で感応していくマジック・リアリズム的作品。面白い。母親が迎いに来るかと思ったら精神病院(アル中か)に入院するということも重要だ。
両親の関係性が精神に影響を与えている。
「牝猫」
金持ちの学生なのだがルームシェアーを探したりしているのだが、猫を書い始めて、友達よりも猫中心の生活になっていく。大学の教師と関係を持って妊娠(アニー・エルノー原作映画『あのこと』)と同じようなことだと思ったが、彼女は流産させてしまうのだ。猫もその頃妊娠して子猫を産むのだが、飼い主との関係を察知して逃げていく。アラン・ポーの『黒猫』のようなミステリーになるかと思ったが、上手く猫が逃げて行った。
「菌類」
これはちょっとグロテスクな倒錯的な短編。母が水虫なのか酷い皮膚病で病原菌を見てそだった語り手(音楽家の女性)は病原菌に愛着も持ってしまう。
不倫関係の末に性病に感染するのだが、その病原菌は彼の一部なんだと思って愛着を持つ。そしてどんどん病気がひどくなっていくという短編。このへんになると病んでいる小説だった。
「北京の蛇」
父親が中国系で中国に行ったときに浮気しておかしくなって戻ってくる。部屋を仏塔的にし、その部屋で毒蛇を飼っているのだが、それは中国で毒蛇女に噛まれたからというような短編。違う世界に取り憑かれるのは、生き物も愛も一緒だみたいな。倒錯的な話が好きな人は好きになる作家かもしれないが一般受けはしないだろう。
