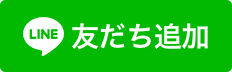三世代家族と子供の学力の不思議:後編【未来を見通す力】
<参考記事>三世代家族と子供の学力の不思議
前編【幸福度の関係】
中編【“姥捨山”の昔話から】
先の行方が見えにくい現代社会を生き抜くために、「未来を見通す力」こそ、新しい学力の定義とも言えますが、自分の祖父母の世代から学びを得ることが、なぜ、こうした力の育成につながるのでしょう?
「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ」
これは、ビスマルクによる格言です。
世の中には、、、
「まずは自分でやってみないと、分からない。」
「今までの自分の実体験とフィットしないから、判断できない。」
などと言って、全ての基準を自分の実感ベースに落とし込んで考えるタイプの人がいます。
たしかに、自分の実体験の中にはたくさんの学びがあります。
ですが、得られる学びの拠り所を、自らの実感や経験のみに固執しすぎてしまうと、視野の狭い表面的な見解しか持てなくなる可能性があるということは、ビスマルクの格言が示唆するとおり、気をつけるべきではないでしょうか。
私は、そのような視野の狭さから脱却できる環境が、三世代家族にあるのだと思います。

たしかに、祖父母の世代と子供の世代には、優に半世紀の開きがあります。祖父母を通じて、自分が生きている時系列を超えた社会の流れを感じることは、自分一人の経験だけでは掴むことのできない歴史の潮流を理解することに通じます。
そして、そうした歴史観から生まれる学びの中には、未来に残すべき教訓や知見が必ずあります。
これは、単に自身の経験のみで得られる学習とは全く違う性質のものです。
私は、経験から得られる学びも歴史から得られる学びも、両方をバランスよく伸ばすことが重要だと考えます。
特に、AO・推薦入試は、その受験をきっかけに、まだ見ぬ将来や未来について、自分なりのビジョンを描いていくことが必然です。
そのためにも、歴史観を持つことで得られる「未来を見通す力」の育成を、まずは、自分の最も身近なファミリーである祖父母からスタートすることは、非常に効果的だと思うのです。

とはいえ、核家族世帯の親と子が、世代を超えた強い繋がりを自分たちの暮らしの中に取り入れるには、どのようにしたら良いのでしょうか?
いざという時に頼れる人間関係について、「遠くの親戚より近くの他人」という言葉で表すことがあります。
疎遠になってしまっている血縁よりも、日常で信頼関係を形成している、すぐ近くにいる他人の方が、よほど当てになるということです。
私は、こうした、何らかの損得や利害関係に依拠しない、新しい信頼関係を、AO・推薦を受験する中高生たちが、どんどんと形成している事例をたくさん見てきました。
自分が知りたい専門分野の一線級の方々にメールやSNSなどでアポイントを取って、すぐに会いに行き、大人ではとても入り込めないような場所まで案内してもらうなど、AO・推薦入試をきっかけに、親よりも上の世代のプロフェッショナルたちとの信頼の絆を、着々と築いている事例は枚挙に暇がありません。
このような世代を超えた人脈を築けるのは、やはり、10代の特権でしょう。

大人のような、実社会での仕事や立場などによるしがらみがないからこそ生まれる信頼関係なのだと思います。
今は、インターネットのおかげで、距離的なハンデが差にならない時代です。また、コロナ禍によって、いよいよ教育の中にもオンラインによるテクノロジーが一気に入り込んでいます。
そうしたネットワークを上手に活用できれば、これまでは、なかなか難しかった若い世代と年配世代による交流も、さらに可能になるでしょう。
AO・推薦入試をきっかけに、損得勘定ありきではない、擬似的な家族のような多世代交流がより盛んになれば、それはとても素敵なことだと思います。
次回からのテーマは、
「誰も知らない“オンライン面接試験”のリアル」です。
お楽しみに。
<公式LINE>
青木唯有【AO・推薦合格は親子軸で決まる】
ライブ配信などの情報などもお伝えしています!
<青木唯有 Facebook>
AO・推薦入試オンラインサロンでの情報などもお伝えします!