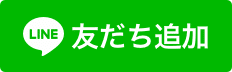親子軸を定めるメンタリング術:中編【上智大学に出願した高校生の実話】
今回の記事では、上智大学外国語学部ロシア語学科の公募制推薦入試に挑戦した、ある男子高校生のエピソードから、メンタリングの考え方について深めていきたいと思います。
彼が、ロシア語に興味を持ったきっかけは、本当にちょっとしたことです。
当時、世間で流行っていたロシアのスパイ映画を観たとき、ロシア語が醸し出す発音に何故だかとても惹かれたそうです。
その後、動画サイトなどで自分なりにロシア語について調べるようになりました。
【悩む本人を前に、母が起こした行動】
ところが、本人は、特に流暢なロシア語が話せるわけではありません。友人や先輩から、「外国語学部の名門である上智のロシア語学科は、ロシア語ペラペラの帰国子女が有利らしい」というまことしやかな情報も入ってきます。
推薦入試の面接の日が近づくごとに、「自分にはやっぱり難しすぎる挑戦だったのではないか」と急激に自信を失っていくようになります。

「自分の志望校の設定は、やっぱり安易だったのではないか?」
「ロシア語学科を志望するのには、ふさわしい自分ではないのではないか?」
迷っている本人の様子を目の当たりにしたお母様も、ロシアについて詳しいわけでもありませんし、行ったことすらありません。
「我が子に対してどのように助言をすればよいのか?」
「親として自分にできることは何だろうか・・・?」
悩んだ末に、お母様が、とった行動があります。
それは、毎日、ロシア料理を作ること。
サッカー部だったその高校生は、秋まで部活動と受験を両立させなければなりませんでした。
学校で授業を受け、放課後は部活、その後塾に通って帰宅する・・・
そんな受験生活を送る我が子のために、毎日のようにせっせとロシア料理を作りました。

ボルシチ、ピロシキ、ビーフストロガノフ・・・・
そうした食事をきっかけに、ロシアについてもあれやこれやと家族の中で毎日のように対話が生まれるようになります。
何よりも、母親が作るロシア料理を食べ、その愛情を感じた本人の気持ちが、とても前向きなものに変化したのでしょう。
【面接当日の本人は、果たして・・・?】
面接当日、彼の前の受験生は、やっぱりロシア語ペラペラの帰国子女だったそうで、部屋からは面接官とロシア語で会話する声が漏れてきたそうです。
ですが、彼は、
「自分は自分。帰国子女だからとか、言語が話せるからという理由で志望したわけではない。自分の心からのロシアへの関心を伝えよう。憧れの志望校の教授に、自分の思いを直接伝えられる場に感謝しよう。」
と、気持ちが乱されることなく面接に臨みました。
結果、見事に合格しました。
もちろんこの高校生は、塾で専門にAO・推薦入試の指導を受けていましたし、それなりの準備もしっかりと行っていました。
ただし、その前提として、保護者の方のメンターとしてのバックアップが、本人の自尊心を高め、「自立」を促すことに大きく貢献したことは、間違いありません。
実は、私がこのエピソードを聞いたのは、この受験生が合格した後だったのですが、この事実を知った時に、「なるほど」と思いました。
思い当たる節があったのです。
(後編につづく)
<公式LINE>
青木唯有【AO・推薦合格は親子軸で決まる】
AO・推薦の最新情報についての動画などを発信しています!
<青木唯有 Facebook>
AO・推薦に関心のある保護者の方向けのLIVE配信なども行う予定です!