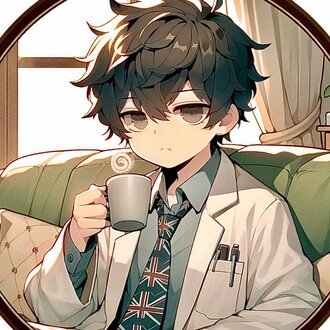右心房をあらためて勉強してみる
おそらく心臓内の中でもっとも複雑でわかりにくい構造をしているのが右心房です。
1 上大静脈、下大静脈、冠状静脈洞からの血液が入り、右心室へ送る
2 心房中隔の一部に卵円窩(卵円孔)が存在する
3 Eustachian弁、Thebesian弁などの遺残弁が残りうる
4 洞房結節、房室結節などの刺激伝導系が存在する
単純に心不全管理ということであれば1だけでいいです。
しかし、心房中隔欠損症や卵円孔開存に関しては2, 3の知識が必要となり、
さらに不整脈、電気生理、アブレーションといったことに携わるには4の知識も必要になってきます。

ということで上記が右心房・右心室の大まかな構造です。
立体的なイラストの描写が困難なのでわかりにくいかもしれませんが、ピンクが心臓の内面、肌色が心臓の外面です。
右心房・右心室の全面の壁を取っ払って中身が見えている状態と思ってください。右心耳をぺらっと上にめくっています。
このうち、先天性心疾患を理解する上で必要なのは
卵円窩、Eustachian弁、Thebesian弁です。その他、Todaro索、コッホの三角など知っているとより理解が深まります。
卵円窩とEustachian弁
イラストがわかりにくくて恐縮ですが、Eustachian弁というのは下大静脈内に胎児の頃に存在している弁で、出生とともに退縮します。

これは母親からの酸素が豊富な血液を下大静脈から効率よく全身へ運ぶために、右室ではなく、直接、卵円窩を通じて左心房へと流すために存在している弁です。
したがってEustachian弁が遺残していると下大静脈の血流は三尖弁へと向かうのではなく、方向的に卵円窩へと向かいます。
以前こちらで少しお話しましたが、卵円孔は左房から右房への圧の圧排により閉鎖が促される構造をしています。
したがって下大静脈の血流がそのまま卵円窩へ向かう血流が残存してしまうと、卵円孔がそのまま開存してしまう確率が高くなります。
心エコーでEustachian弁遺残を認めた際に卵円孔開存の可能性を考慮しなければいけないというのはこういう事情です。
次に、Thebesian弁というのは冠状静脈洞の出口に存在する弁で、右房内の血流が逆流しないように存在しています。
一方、イラストでは示していませんが、Chiari 網というのが右房内で認められることがあります。これは右心房内に存在する線維性の網状構造で、胎児発生の過程で静脈洞弁の一部(主に右)が残存したものと考えられています。
心エコーだと網のようなものがモヤモヤと動いて見えるものです。
Chiari Networkの形成に関するまとめ
左静脈洞弁は、胎生15週ごろに心房中隔と癒合して消失する。
右静脈洞弁同様に上部は消失するが、下部は下大静脈弁(Eustachian弁)や冠状静脈洞弁(Thebesian弁)として残存する。
右静脈洞弁の下部が完全に退縮せず、広範に遺残した場合、この構造が網状となってChiari 網として確認される。
最後にコッホ(Koch)の三角について

これは三尖弁(中隔尖)の付着部、冠状静脈洞、Todaro索の間に囲まれた三角形の領域のことを指します。この中に房室結節など刺激伝導系に重要な組織が含まれていることから特別な名称が付けられているわけです。
急にTodaro索というのが出てきてよくわからないと思いますが、これは膜性中隔とEustachian弁を結んだところにある索条の繊維性組織です。
この隆起によりさらに下大静脈の血液が三尖弁の方向への血流を防ぎ、卵円窩に向かうようになっていると考えられています。
膜性中隔:緑の点線の領域
心内膜床から隆起してできる部分。ヒス束が通る。
心房内は心房中隔、心室内は心室中隔を形成する。
この領域の異常を認める房室中隔欠損などでは
そしてKochの三角は三角というわりに別に三角ではありません。またイラストではわからないですが意外と広い領域です。
とまだまだ語り足りないことばかりですが、いったん解剖学的なまとめは異常にしておきます。
いいなと思ったら応援しよう!