
Qastの価値の本質は「人との繋がり」 - Qastの便益を高めるPdMが目指すもの -
シリーズB資金調達記念 any的アドベントカレンダー🎄本日は第11弾!テーマは「anyのPdMチーム」です。
今回の記事の担当者
👤 前田 貴章(呼び名:前ちゃん):any社員(2023年4月入社)、PdMマネージャー
座談会参加者
👤 樽川 翔太(呼び名:たるちゃん):any社員(2020年4月入社)、:PdM / カスタマーサクセス
anyのPdMポジションができるまで
anyでPdM(プロダクトマネージャー)を担当している前田です。簡単ですが自己紹介をしたいと思います。
キャリアとしてはマーケティングリサーチ会社で法人営業やマネジメントを15年ほどしており、その後職種を変え、同業界でソリューション開発や新規サービスの開発をしておりました。直近だと企業のAI活用の全プロセスを支援するスタートアップ企業、株式会社ABEJAで、お客さまのニーズに合わせてAIを活用するPM(プロジェクトマネージャー)を担当。anyには2023年4月からPdM未経験で入社しました。
自分が入社する約3か月前にPdMがチームとして誕生しました。当時は代表の吉田がプロダクトオーナーとして開発をリードしていましたが、チームとして動いていく必要性があるということで、これまでCSとして働いてきてQastやその顧客の解像度の高い樽川がPdMに兼務という形でコンバートされました。当時の資料を見てみると、代表の吉田がメンバーを募りながら、バリュープロポジション策定やアジャイルなどの施策を試行錯誤しながら進めていたことがわかります。

PdMチームの役割とやってきたこと
PdMの役割は多岐にわたります。


開発組織との連携
アジャイル開発をしながら日々のアウトプットを意識したり、お客さまの理解やユースケースの解像度を上げるための会議(通称そもそも会)を行っています。CSやセールスサイドとの連携
同等の会議を実施しコミニケーションやアウトプットの齟齬が無いように運営をしています。
具体的な例ですが、CSと「育☆会(いくせいかい)」という定例会議を実施しており、お客さまの事をより深く理解してこれ以上ないレベルで解像度を高めながら、Qastの機能やCSのありかたを考える会があります。
その中のQast利用者の導線やためたナレッジをどう活用したいかのユースケースを話す回で、そこにAIがあれば何がさらに改善できるかなどを議論していました。
またナレッジを検索する段階でもその企業での社歴や情報感度により検索体験も変わってくる、ペインが違うなどの議論になり、社内での情報格差をなくし、ナレッジを探せない人がたどり着くためには、AIをどのように掛け合わせるかのが良いかを整理していきました。ユースケースとAIの得意な領域をマリアージュするような形で爆誕した機能が、こましりchat(自然言語でAIと会話するように検索ができる)でした。
開発前からプロトタイプやfigmaでのデザイン整理、PRD(プロダクト要求仕様書)、コンセプト整理などをしつつ、場合によってはコンセプトの段階でパートナーのユーザー様にフィードバックをもらいながら議論を進めることで、よりスピーディに要件整理や細かい機能の優先順位付けなどの意思決定をすることができました。

議論する内容はかなりまじめで濃い内容です笑
anyのPdMチームは前段でも述べたようにお客さまと接点を多く持つことも意識をしています。お客さまへの機能ヒアリングや展示会に来場いただいたお客さまから生の声を収集し、ユースケースへの解像度を上げ、吸い上げた情報をもとに機能開発、改善に生かすことを心がけています。
お客さま⇒CSやセールス⇒開発という流れの中で常に有機的に動くことで、Qastの便益を高めていくことを推進するチームを目指しています。
直近ではより意思疎通を早くするためにEM(エンジニアリングマネージャー)の柳川がオーナーとなり他部門に向けてプロダクトチーム(エンジニア、デザイン、PdMのワンチーム)の成果や進捗を共有する、ALL Product MTGも毎週行われています。
全社員が参加必須となるので、プロダクトチームのプレゼンス向上や他部門との相互理解に繋がっています。
PdMがハブになりながら、プロダクトチームがビジネスサイドと同じ目線で事業を作れる文化や、パワーバランスが偏らないような仕組みを整えているので、本質的なプロダクト開発ができる環境になっていると自負しています。
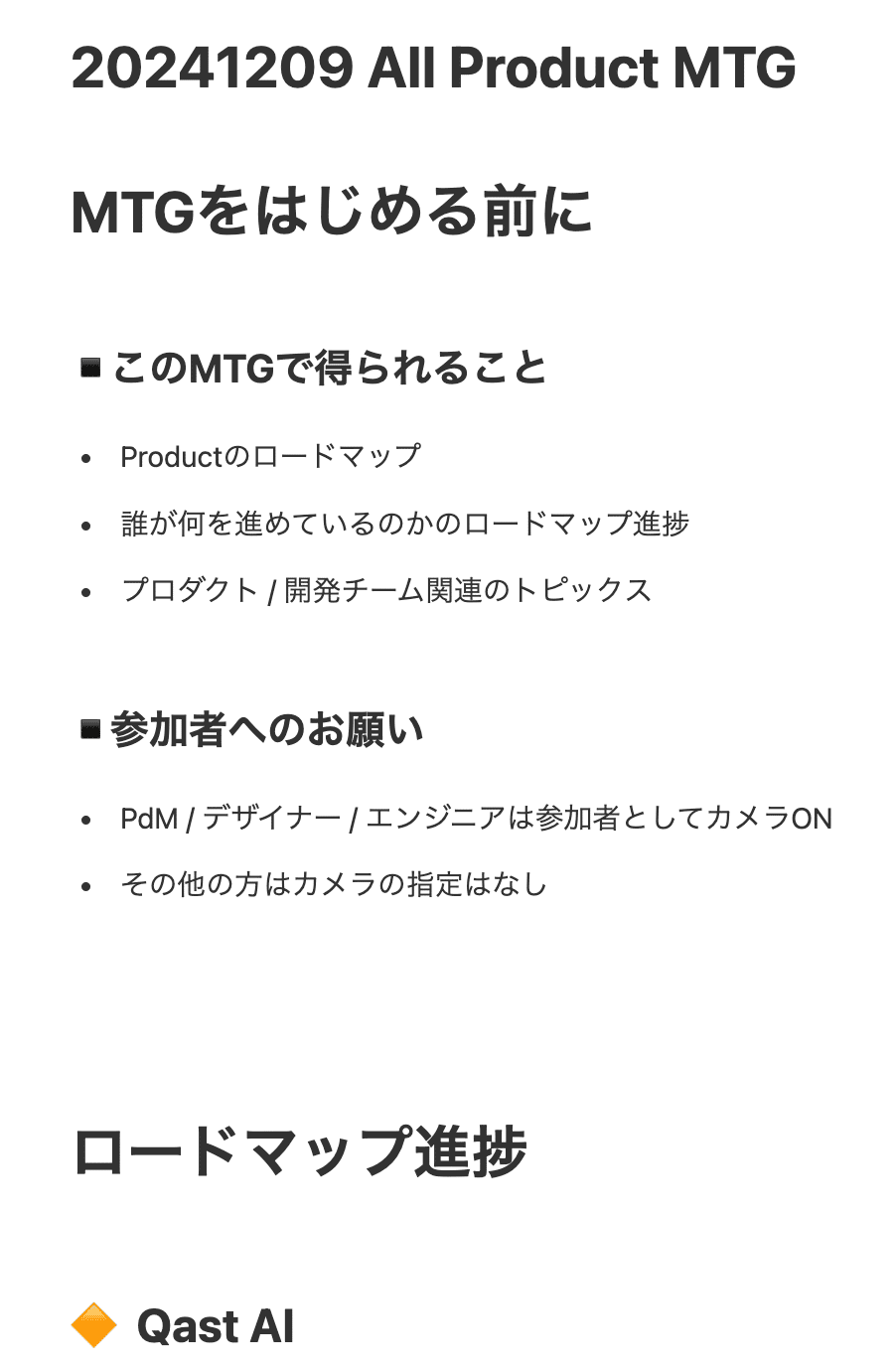
any(Qast)のPdMの難しいところ、そしてやりがい
ナレッジマネジメントを推進するという点だけにフォーカスすると、anyが提供しているSaaSのナレッジプラットフォームQastを利用することでデータの蓄積、検索、利活用などをある程度容易に行うことができます。
ただ本質的には、組織に属している方がナレッジマネジメントの必要性を感じ、能動的に且つ継続的に行動することで本当の意味での情報共有の文化が醸成されていくと考えています。組織に浸透していく過程で、組織毎、ユースケース(お客さま、推進者、管理者)による使い方などニーズは多様です。その中で汎用性がある機能、お客さまにとって本当に便益につながる機能などを模索しながら、時にはパートナーとしてご協力いただきながら開発をしています。
そういった時間軸とユースケースの変数が多い中で、優先順位を決めながら開発をすることはやりがいでもあり、難しいところでもあると感じています。
ナレッジマネジメントというと少し仰々しいのですが、日々の業務の中で自分が行っていることを共有し、そこのフィードバックや資料の補完をもらいながら、自分の業務を少しでもより質も高めながらアウトプットをしていくサイクルは、皆さんが当たり前のようにやっていると思います。
その個人の業務サイクルが、個人から組織、組織から会社、会社間どうしでの繋がりに広がっていき、そこからイノベーションや企業文化を変えることができる。そういった未来を想像し、その一助となるサービスを提供できると考えると自ずとワクワクしてきませんか??
日々の活動をちょっと意識したり、いつもより少しアイデアをだしていくことは個人では力が弱いかもしれません。ただそのちょっとしたことを組織全体、会社全体で継続的に取り組むことができれば指数関数的により質の高い業務に生まれ変わることができると考えております。
ちょっとした努力が質の高い業務に生まれ変わり、かつチームとして連携、貢献できるそんな世界観を本気で実現してみたいと思っています。
上記記事を書きながら、今後PdMチームを大きくしていく中で、せっかくなので共にPdMとして取り組んでいる樽ちゃんとこの1年を振り返ってみました。

ナレッジマネジメントの未来を共に創造する──PdM対談
Q:1年を振り返って、PdMチームとしてどのような変化がありましたか?
前田:
元々はワンチームでの体制・運用でしたが、Qastの中でAI機能の開発をするチーム(こましりchatやファイルtoナレッジ)、新機能開発(大規模なエディターのリニューアル)、シン・カイゼン(お客さまの要望やバグ対応など)、ミライ基盤(リファクタやーアップデート)の4チーム体制を敷いて連携を取りながら進めるようになりました。
樽川:
取り組みとしては、お客さまからのニーズが如実にあったAIの機能開発がQastの進化にとってとても大きかったと思います。Qastには暗黙知を表出化する為の機能(KnowWhoやユーザータグ、QAなど)がありますが、そもそもの形式知(テキスト化された情報やナレッジ)を蓄積する、検索する、など人が担保するとどうしても工数がかかってしまうところをAIが補助するような機能が求められていました。

Q:AI機能の導入によって、お客さまの行動に変化はありましたか?
樽川:
データの蓄積と検索性が向上したことで、Qast自体の使い勝手の向上を求める声や、具体的な機能要望をいただく機会が増えました。これは、お客さまがQastをより深く活用していただけるようになってきたからだと考えています。
前田:
シン・カイゼンチーム(お客さまの要望やバグ対応など)の役割も重要でしたね。
樽川:
そうですね。シン・カイゼンチームでは、お客さまからいただいた機能要望をそのまま実装するのではなく、「お客さまの真のニーズは何か?」「機能ではなく運用や体制で見直せることはないか?」「他のお客さまからの要望との整合性は取れているか?」といった点を多角的に検討し、短いスパンで意思決定を行うサイクルを確立できていたと考えています。
前田:
改めて整理するとAI機能の実装と既存機能の改善による便益がお客さまに伝わって、それを下支えするシンプルなUIやお客さま体験を提案できたことでより誰もが使いやすいプロダクトになった1年だったと感じます。
Q:今後の「Qast」の開発において、どのような点に注力していきますか?
前田:
Qastの進化の方向性を検討する上で、ユーザーインタビューで得られた知見は非常に貴重でした。樽ちゃん、そのあたりについてはどうですか?
樽川:
そうですね。Qastの継続利用を促す要因を探るため、既存のお客さまへのインタビューを実施したのですが、その結果、スタンプやコメント機能によるリアクションが、お客さまの投稿意欲向上に繋がっていることが分かりました。他者からのリアクションやコメントを通して嬉しい気持ちが満たされたり、新たな人間関係が生まれたりするといった効果は、今後も注目していきたいです。
前田:
やっぱり継続して使用していく中で、投稿を続けていくとなるとどうしても一定負荷はかかってくるけれど、それでも長く使っていくことで、情報共有をして、人とうまく繋がっていくといった人間の本質的な部分に関わっててくることがとてもよく分かりました。AI機能の追加で便利になっていくということはもちろん大事ですが、生身の人間同士の交流で大切なこととか、そこにももっと取り組んでいきたいですね。
樽川:
AIはあくまでもツールです。Qastの本質的な価値は、「人との繋がり」そして「人の役に立つ」という点にあると考えています。ナレッジマネジメントは、チーム全体で取り組むべき課題です。AIを上手に利用しながら、機能的でありつつも本質である人のつながりを重視したプロダクトを目指していければいいなと思っています。
前田:
まさにanyのコンパス(会社の指針)にも合致する考えでいいなと思っています。柔軟な思考で「本質的なプロダクトとは何か?」を問い続け、機能性と人間的な温かさの両立を実現していきたいですね。
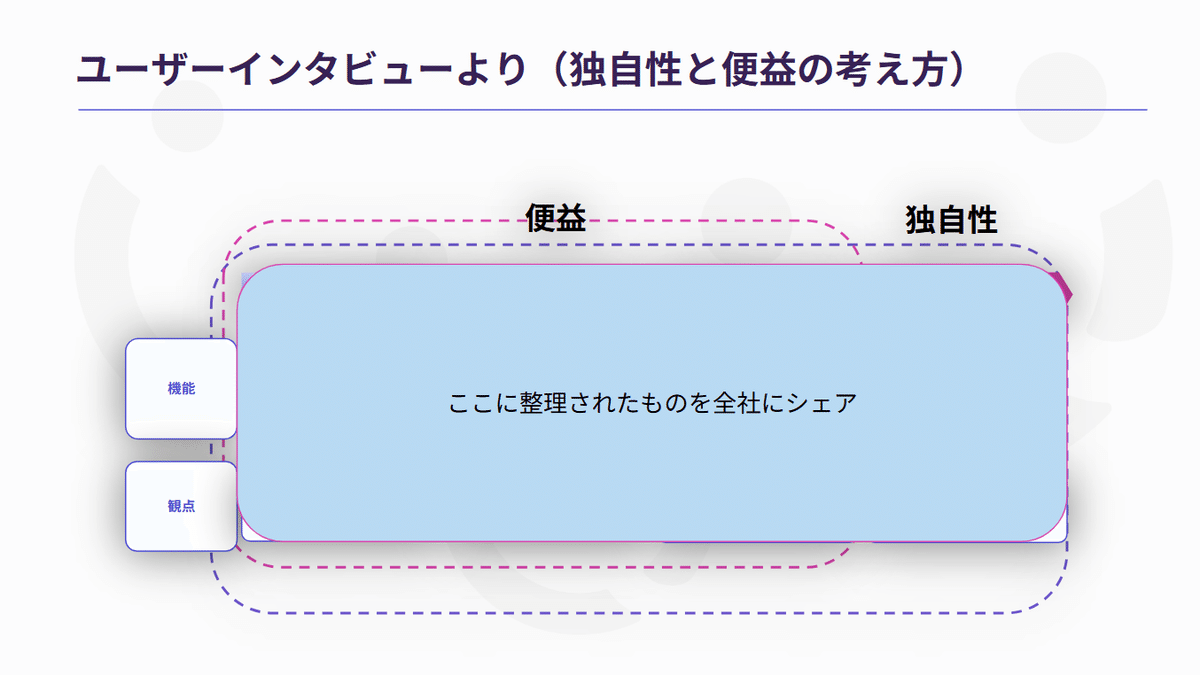
Q:未来を見据えて、これから築きたいチーム像を聞かせてください
樽川:
自分はCS出身ということもあり、その時に得たお客さまの解像度を生かして機能を軸に課題解決に導いていく、という役割を任されていると考えています。なので、もし今後チーム内にエンジニアリングやコンピューターサイエンスの経験のある方が入ってくだされば、技術的課題に対する適切な問い立てやアイディアが出てくると思うので、さらに提供できるソリューションの幅が広がる気がしています。
前田:
なるほど。自分もバックグラウンドはプロジェクトマネジメントの経験が長いので、各ラインの全体最適やアサイン、PJの進行が得意なのでチームとして新しい気づきや知見がある人と連携できるといいね。開発以外にもデザインやCSなど多様な職種の人との連携は新しいアイデアをチームとして考えていきたいなと思います。
樽川:
anyのPdMチームはとてもフラットな関係性なので、過去のご自身の業務で自走しながら人を巻き込んでコトを進めた経験がある方とご一緒したいですね。
前田:同感です。そして、その過程でどのような失敗を経験し、どのように乗り越えてきたのか、その経験から何を学んだのかについても、興味があります。AI技術は進化が速く、常に新しいチャレンジが求められます。失敗を恐れず、そこから学びを得て成長できる力は、PdMにとって不可欠な気がします。
今後Qastを起点にしつつ、セカンドプロダクトへのアイデアもある中で、ナレッジマネジメントへの興味、anyというチームの場を使ってそれを実践してみたい方と是非ご一緒できればと思っています!
イベントのお知らせ
Archetype Ventures福井さんと代表吉田の対談(収録)を12月18日に配信します。投資家目線でのanyの魅力や将来性について、客観的な立場から語っていただいてます。社員とはまた違う角度からanyのことを知っていただける機会ですので、ぜひご覧いただけると幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
anyでは共に事業を推進する仲間を募集中
候補者の方々にとって、これからは個人としても組織としても新しいチャレンジをしながら事業フェーズをダイナミックに変えていけるステージに突入していきます。最高のチームと、最高の仕事がしたい方のご応募お待ちしております。
現在募集中のポジションはこちらですが、それ以外のポジションも近い将来募集させていただく可能性は十分にあるので、ご興味を持っていただいた方はまずは一度お話しましょう!
