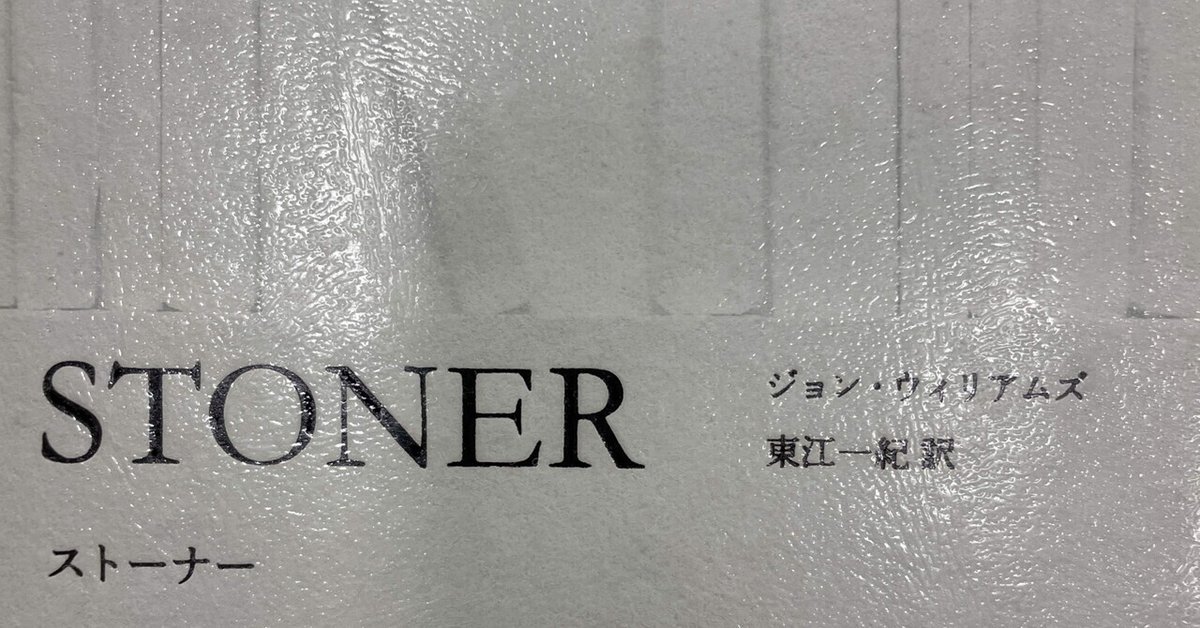
それぞれの生 『ストーナー』
ジョン・ウィリアムズの『ストーナー』という小説を読んでいる。ストーナーという男の人生を淡々と描写している本だが、読んでいるとアイツの人生は華やかで楽しそうだな、それに比べて自分は、などと他人と比べたり羨ましがったりすることがバカバカしくなり、ちゃんと自身の生活を見つめながら生きるのがいいんだという気分にさせてくれる稀有な小説だ。話に派手な起伏や情熱的な会話シーンや意外な展開などはなく、若きストーナーが親のいいつけで大学で農学を勉強しているとき英文学の講義に魅了されて英文学専攻に転向し、そのまま講師から助教授になり、いろいろなライフイベントや人間関係を経て歳を取り病死するまでが淡々と書かれている。
彼の経歴は大学在籍の研究者としてさほどインパクトがあるものではなく、同僚から「先生には長く勤めていただいて……」と社交辞令を受けたきり忘れ去られる地味な存在であったことが冒頭に語られる。家族や友人や同僚たちとの関係にしても熱く魂を交わし合うような場面はなく、どこかうまくかみ合わなくて、何かの拍子にちょっと互いの深いところに触れたと思ったらまた遠ざかってしまうようなところが味わい深くて良い。
特に印象に残っているくだりがある。ストーナーの狷介不羈な恩師が亡くなり埋葬されるとき彼だけが涙を流すのだが、自分が泣いている理由が敬愛する人との別れがさびしいからなのか、自らの青春と履歴の一部をうしなうことへの惜しさからなのか自分でも分からないという箇所。恩師の死を受け新しい英文科主任として外部からやってきたローマックスは才気煥発な辛辣さと明るさを備えており、そこに嘗て戦死した学生時代の友人の面影をみたストーナーは彼と親しく話をしてみたいと思い用事のついでに夕食に誘ってみるのだが、同僚には一線をひいた対応をすると決めているらしいローマックスから丁寧ではあるがそっけない断り方をされ、それ以上接近の手立てを思いつけず立ち尽くしてしまう箇所。青年時代は率直さと熱意をもって相手に接近し友情を成立させるということができたが、年取ったいまは(たぶん30代か40代?)もうそういうことができないと思い悲しくなってしまうストーナーなのだが、そこに胸を打たれた。こういう細かな場面で立ち止まって情景や心理を深掘りするので、話全体に陰影と奥行きが感じられて読者の感興を刺激するのではないかと思う。生きていて派手な出来事に見舞われることは誰もができるわけではないが、ふとした折に立ち止まって自分の心持ちや状況を色んな角度から眺め人生に陰影を与えることはできる。なんとなく自分の人生をそれなりにつくりあげる自信と温かさが湧いてくる。
