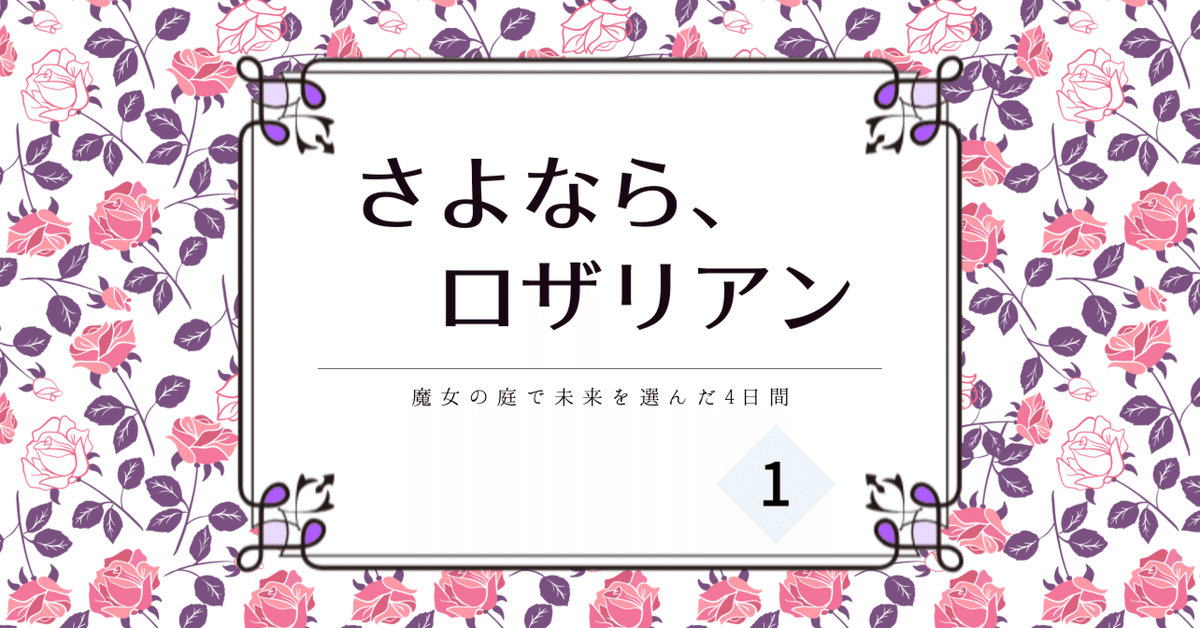
【小説】さよなら、ロザリアン(1)
医大での一年目を留年寸前の成績で終えた荻野翔は、親の勧めで一年休学して勉強をやり直すことにした。だが、その計画は早々に行き詰まってしまう。なぜ勉強が進まないのか思い悩む翔は、旧友との食事も楽しむことができない。
そんな折、翔は偶然子供時代に通った英語教室の講師、野澤英理衣に再会する。英理衣は自宅の庭に見事なローズガーデンを持ち、『マダム・ロザリアン』と呼ばれるちょっとした有名人だった。
翔は絵里衣に誘われ、現状に行き詰まっている自分の突破口を探してオープンガーデンの手伝いを引き受ける。そして、ある時英理衣が自分はかつて魔術を勉強した魔女だったと告げてから、翔の世界は急速に動き始めるのだった。
『打ち込めるものさえあれば、なんとかなる』
荻野翔はそう信じていた。その言葉を心の真ん中に看板のように掲げていれば、どんなことも乗り切れるはずだと。
しかし、医大での最初の一年が終わったときには、その看板は色褪せ、錆びつき、すっかり見る影もなくなっていた。
履修した科目は必修科目こそ『可』が取れたが、選択科目はほぼ全滅。その必修科目だって、臨床心理学と哲学の点数があと一点足りなかったら危うく単位を落とすところだった。
『なんとか乗り切った』のではなく、『すんでのところで留年を免れた』。そうとしか言いようがない成績だった。
その成績はすぐに両親の知るところとなった。翔の通う大学は成績表を保護者にも郵送しているからだ。
春休みに入ってすぐ、翔は一人暮らしをしている大学近くのアパートから家族会議のため実家に呼び戻された。
実際のところは、母から「春休みに入ったし、一度家に帰ってこない?」とメッセージが届いただけだ。けれど、久しぶりに帰る実家には成績表と、それを隅から隅まで何回も見たであろう両親がいる。そこで自分に何が待っているのかは想像に難くない。
いっそ、「成績のことで話があります」みたいにストレートに言ってくれればよかったのに。成績には一切触れずに「帰ってこない?」だなんて軽い感じで言ってくるのが怖い。
翔は「うん。それじゃあ今週末に帰るよ」と調子を合わせて返信しながら、深い溜息を吐いた。
それから数日後、意を決して翔は実家に帰った。
リビングに入ると、テーブルの上に広げられた成績表を前に、それをじっと見つめる父と、その父を隣に座って心配そうに見つめる母がいた。
帰ってくるまでの間、電車の中で想像していた光景そのものだった。
「ただいま」
人生で五本の指に入るくらいの気まずい挨拶だった。頭の中はこれから始まるであろう話でいっぱいだ。
これからこの結果を怒鳴られるのか、それともここに至ってしまった経緯を問い詰められるのか。どっちにしろ、何をどこからどう説明しようか。
だが、両親の反応は翔が考えていたそのどちらでもなかった。
「翔」
父は成績表から顔を上げて息子のことを頭から足元まで見ると、何かを確認するように隣の母をちらりと見た。それを見た母が何も言わずに頷くと、自分もそれに頷き返してから、改めて息子の目を見てこう言った。
「一度休学して、態勢を整えてみたらどうだ。勉強をやり直してもいいし、自分が本当にやりたいことを探してもいい。この一年で選ぶんだ」
休学。これは予想外だった。
方法は何であれ、大学で勉強を続ける前提で話があるのだと思っていた。二年生になったらもっと勉強を頑張れだとか、大学と並行して医学部生向けの予備校に通えだとか、そういう話をされるものだと。
それなのに出てきたのは「休学」、つまり「自主的な留年」だ。そんなことを親から提案されるなんて。
翔は動揺して両親の顔を交互に見た。その様子を見て、母が口を開いた。
「大学生の休学なんて、そんなに珍しいことじゃないでしょう。お金のことは心配しなくても平気だから。けれどもし……」
「そうだね」
翔は早口で話し続ける母の言葉を遮った。
頭の中には「態勢を立て直す」「やり直す」「やりたいこと」「休学」「自主的留年」……さまざまな言葉がぐるぐると渦巻いている。けれども、答えはもう出ていた。
この成績が授業にも出ないで遊んでばかりいた結果だったら、まだ自分でも考えようがあったかもしれない。
けれど、そうではない。この一年、医学部生として翔は勉強に打ち込んだ。休まず授業に出て、レポートも提出したし、テストも受けた。なのに、自分でもびっくりするくらい何もわからなかった。
読んだはずの教科書の文字も、聞いたはずの教授の話も、何も残っていなかったのだ。
どれだけ必死に勉強しても、網で水を掬っているみたいに、知識がすり抜けていってしまう。ずっとそんな感じがしていた。
打ち込んでいたはずの勉強がどうにもならなかった今、翔は自分がどうしたらいいのか正直わからなかった。
けれど、そんな時の対処法は決まっている。自分で考えないのが一番だ。親が提案してくれたプランに乗っておけばいい。
そう、医大を受験することにしたあの時のように。
「申し訳ないけれど、休学させてください」
翔は両親に頭を下げた。
また打ち込めるものを探そう。見つからなかったら、きっとまた見つけてもらえるはずだ。
こうして、何の見通しもないまま翔の休学は決まった。春もまだ遠い、二月の真ん中のことだった。
第二話
第三話
第四話
第五話
第六話
第七話(終)
いいなと思ったら応援しよう!

