
大人への路(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 17)
※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。
大人への路
おたまから文だ!
熊千代本人は、珠子からくれと言われてから、雨あられのように手紙を書き送っていたが、本人からほとんど返事がない。あれは無精で、と父親の光秀までが少し気の毒そうな顔をして言う。そうなると、使いの者の口から聞こえる、喜んで読んでいただとか、心待ちにしていただとか、あれこれと気を使っているだけなのではないかと、熊千代は多少疑心暗鬼になっていた。
その、滅多にくれぬ手紙を!
すごい勢いで屋敷にすっとんでいき、ぶるぶる震える手で開いた。心なしかよいにおいがする。
前の手紙に熊千代は書き添えた。信忠さまは、今も松姫さまにひそかに文を送っている、贈り物もしているようだと、その話が珠子の琴線に触れたようだった。
──もし私が敵方の娘になっても、そなたは文をくれますか?
少しだけ考え込む。そんなもしはありえない。
あるのは今だけだ。
珠子は、おれと、おれの手紙を嫌っていない。それどころか、敵であってもと言うてくれておる。そんな珠子は!もうすぐおれの!おれの妻になる!おれの!
手紙を手に、うれしさのあまりひっくり返ってゴロゴロ転がりながら縁側まで転がり出てふと上を見上げる。空と木々と破風の間から、蒲生氏郷の困惑した顔が見下ろしていた。
上から下から一瞬、お互いを凝視した。熊千代は手に持って広げたままの文をあわてて押し伏せた。
「大丈夫、大丈夫。何も見ておらぬ」
「忠三郎!貴様、何しに来た!」
「それよ、元服されたならばこれからは、そなたのことを与一郎どのとお呼びせねばならぬであろうが」
本人は不覚にもちょっと嬉しそうな顔をしたが、すぐに渋面を作ってそっぽを向いた。忠三郎めはいつも仰々しくわざとらしい言い方をして、これはからかいに来たのだ!
「ゆえに、これはちと本人の顔を見て練習せねばなるまいと思うて参った」
「いらぬ!」
「はて、与一郎どのには、なにかお邪魔なことでもござったかな?」
「余計な世話だ!」
右近が後ろから顔を出してなだめた。
「それくらいになされ」
もうあちこちで既に与一郎どのと呼びならわされはじめていたが、懐に隠した文からは、懐かしい声が聞こえた気がした。
──熊千代!
珠子は、許嫁からの文を広げながら、与一郎どの?与一郎どの……と口の中でつぶやき、試すように舌の上で転がした。
そばにはお聡の文もある。家内の采配から家々との交際まで、姉は全てが完璧に見える。ほっと息をついて文を押しやる。
わたしはお聡姉上のようにはとても出来そうにない。熊千代と暮らすのに不安などないが、兄弟姉妹も多いと聞く。細川家の人々になじめるだろうか。それに、父上はどうなるのだろう。どなたがお世話申し上げるのか。このおたまがいなくなったならば……。
「おたま」
部屋の外から父の声がかかった。珠子が目をやると、見覚えのない女性を連れて立っている。
ちらりと見ただけでも非常に美しい女性であることがわかった。
まさか、父上の側室か?ついに?
どきんと胸が鳴ったが不安は湧いてこない。ふっと匂うようなよい香りが立ち込めて、締め付けられる懐かしさに泣きたくなった。
父は上座に入ってゆっくり座り、女性も入って平服している。
「たまも何かと大変であろうから、側近くに召し使うよう、侍女頭として今から入ってもらおうと思うておる。嫁入り先にも、一緒に行くことになろうから、今から、お前も慣れておくとよい」
では、側室ではなかったのだ。
「小侍従とお呼びくださいませ」
伏せていた顔をまともに上げてにこやかに微笑んだ相手の顔をみて、珠子は息が一瞬、止まった。
──姉上!
年齢から背格好まで、何もかもが長姉のお岸に生き写しなほどよく似た容貌だった。
胸がどきどきして顔が赤くなり、子供のように飛んで行って抱きつきたい衝動にかられて珠子はじっと耐えた。
荒木の家で姉は痩せてやつれてしまったと聞く。だが今、この目の前にいるのは珠子の記憶の中の姉そのものだった。若く輝かしく柔らかで、どことなく雅な気配がする。
侍女もしげしげと見比べて、驚いたような表情を浮かべる。
「何と、お二人はよう似ておられますな」
「まさか!」
小侍従は笑った。
「かようなお可愛らしいかたに、少しでも似ておると言って頂けて嬉しゅうございまする」
姉よりもはっきりと物を言い、瞳が輝いている。
同じと思ってはならぬ。姉上とは別人なのだから。姉上にも、この者にも悪い。
そう自分に言い聞かせながらも、弟たち相手に姉ぶっていた珠子が、彼女をちらちら伺いながらまるで幼子のような顔をしていた。
◇
「去年は抜群の働きであった」
天正六年(1578)の正月、年賀の挨拶を受けて信長は機嫌よく熊千代を褒めた。
「長らく信忠の小姓としてきたが、元服までわずかではあるが、この安土の城でわが小姓として仕えるがよい。」
「まことにございますか?」
と言ったきり、熊千代は言葉が出ない。
建てられたばかりの聳え立つ壮麗な城、信長の威光を示す場所で、側近くに仕えることを許される。感極まっている様子に、去年の大騒ぎの記憶も新しい諸将はやれやれとため息をついた。
信忠に岐阜を家督と共に譲ったのち、ついに安土城は諸将にお披露目となった。記念すべき茶会が開かれ、明智には天下の名物、八角釜が下賜され、茶会を開く名誉が他の諸将に先駆けて許された。
信長は常々から、少年を成年となす適齢期は十八前後であると主張している。万見仙千代も津田坊も同じく元服は常よりも遅かった。熊千代は本人が熱望しているため齢十五の元服が許されたが、この安土において最後の前髪姿を愛(め)でたいらしい。おかげであれは実は上様の隠し子であったのではないかとまことしやかな噂まで流れる始末だった。
藤孝は何ともいえない顔で苦笑いをしている。
昨年の十一月に正親町天皇は信長を従二位・右大臣にさせ、一月にはさらに正二位に昇叙させている。右府さまと呼ばれるようになった信長は機嫌がよい。
「あの文武両道の細川どのが、まぁこの御嫡男には相当に手を焼いておられる。弟君の方が素直でありますからな、扱いやすいじゃろうな?」
秀吉が剽軽に軽口を叩くと
「それよ」
信長は扇子でひざを叩いて指した。
「育てづらいと申すのはな、親の器を超えておるのよ」
いやいやいや、実態を知らぬから!好き放題を言いおって。
ゲッソリしている藤孝に、奇妙に嫌味な調子で荒木村重が一声上げる。
「おい、大したものだな」
その後に続けて口の中で言った一言が、甲高い声で響き耳についた。
「胡麻擂りも一流とは」
◇
「小侍従、教えて欲しいのです。奥方の役割というものを。みなの面倒をみなければならないのでしょう」
侍女たちはみな顔を見合わせたが、小侍従ははっきりと言った。
「奥の家中帳をお持ちしてくださいませ」
寄り添って、教える。
「ほれ、これがわたくしの名前です。皆の名と家の名が書いてあります。録はここに」
言いながら珠子の横顔を見て、小侍従はほれぼれと目を細める。
「しばらくはお姑さまがなさるでしょう。少しずつでよろしいのですよ。あまり差し出がましくては嫌われまする。家督をお譲りされる時に引き継ぎなされるでしょう。まずは身の回りのお世話をする者からお覚えなさいませ」
家中帳をのぞきながら、珠子は考え深げに言う。
「皆、婚礼の話ばかりする。わたしはそのあとのことが知りたいの。乳母に聞いても、嫁いでみねばわからぬとか、こちらの方がえらいだとか、でも父上は昔は細川さまに仕えていたのでしょう?嫁入り道具の数などどうでもよい。どうなるのか、どうしたらよいのかが知りたいの」
小侍従も周囲のひそひそ話は耳にしていた。
こんなに恵まれた容姿を持ちながらお気の毒に、お可哀相。どんな良縁も望めたろうに。
乱暴者の小僧が右府様に強請って無理に決められたのですわ。細川の父上さまは殿に遠慮をし、気の毒がって再三お断りしたのに、上様が押し通されたとか。ごね得とはまさにこのことですわ。
お岸さまがあんなことになり、お聡さまはさすがにしっかりなさっておりまするが、三女のお珠さまが……。
こうして目の前に姫君を見れば、無理もないものと思わぬこともないが、噂をふりきって、小侍従はにこやかに答えた。
「実はわたくしは既に細川家に参上仕りました」
「まことに?では麝香さまにもお会いしたのか」
「ご挨拶がてら、こまごまとした取り決めをいたし、そのほかのこともお聞きしてまいりましたよ。色々とね、動く目になる者がいりまする」
珠子の顔がぱっと輝いて、少しすりよる気配を見せた。
◇
熊千代が安土城での小姓づとめを始めて早々、去年小姓に入っていた森家の三兄弟がそろってお辞儀をし、大きい忠興に憧憬の眼差しを向けて寄ってきた。
「なんだなんだ。おれの方が後輩だぞ」
笑顔で言うと、年長の乱丸が真剣な顔で言う。
「上様が、熊千代どのに学べ、手本にせよと言われました!」
若年の子供たちに囲まれて照れながら応対する。いつの間にか自分も後輩の指導する方に回っていた。
「戦の話を聞かせてくださいませ!」
「茶の湯の作法を知りとうございます!」
「いかがして左様な優なる(格好いい)仕立てをされまするか!」
珠子に相応しくあろうという心、また生まれ持っての美意識から、黒系統の地に鮮やかな色をひとさし刺す、独特な仕立てを好んで用いている。派手な安土城の中でも目立ち、評判になっていた。信長に気に入られているのも多分にこの外見上の理由がある。
「最初に小姓として入った頃は、心配した親父からたくさんの細かい指示を書いた手紙が次から次へと来たものだ。日向守どのからも来たぞ。余計なことは言わん。短い消息と、こうだ。『(織田の)分限帳を見るべし。控えは取るな。記憶しろ』」
「頭で……」
乱丸は真剣な顔をしている。
「小姓が共通で使える文庫(図書館)がある。貴重ゆえ貸出係がきっちりつけて管理しているぞ」
相手をしている所にどたどたと誰かが入って来る。それほど大きくない小兵であると何気なく見て、熊千代はぎょっとした。三兄弟の兄、森長可だった。
「兄上!兄上!」
弟たちはてんでにまとわりつく。
気性が荒いなどというものではない。殿中だろうと禁じられた場であろうと、見境なくいつどこで刀を抜くかわからない。(藤孝には熊千代は長可と同じ類であるとみなされていた)さすがに緊張したが、ここで臆している様子を見せてなるものかと、きっと平静を装ってお辞儀をする。
いきなり大声で恫喝するような声が降ってきた。
「上様に恥ずかしくないように仕えとるか!」
はい!はい!と口々に答えるところを見ると、彼らは慣れているらしい。長可はにわかに熊千代の方に向き直った。
熊千代の姿勢をじろじろとながめ、手の内にある茶器と設えを眺め、うなるように言う。
「ふん!見事な」
長可はこれでなかなかの茶の湯の名手であり、茶器の真贋も造詣が深い。
いきなりガシッと手を捕まれ揺さぶられて戸惑いを隠せない。
「細川の!弟を仕込んでやってくれ。恥ずかしゅうないようにな。頼んだぞ」
首が勢いで前に後ろにとふれたのを、勝手に応と捉えたらしく、鬼武蔵は目をカッと見開き恐ろしげな顔をくしゃくしゃにして笑った。父の亡くなった後に親代わりとなっている長可の兄らしい一面を見た気がした。弟たちに鬼のような顔でどなり散らしている自分をふとかえりみる。
弟たちを振り返り、笑いながら長可は言う。
「この細川の小僧の親父はなあ、塚原卜伝に太刀を習い免許皆伝を受けとる。斬りかかろうにもすきのなさは天下一よ」
さきほどの兄弟愛への感心はどこへやら、長可は親父を切ってやろうと思ったことがあるのだろうかと熊千代は寒気がした。
◇
「お城でございますが、狭いですね」
小侍従はあっさりと言った。隠しても仕方がない。
「というてもこの坂本のお城があまりにも美々しく壮麗なのでございます。これより優れたるは、右府さまの安土のお城ぐらいのものでございましょう。右府さまさえ、この城のあまりの美しさを見てご機嫌を損じたと言われておるぐらいでございます」
珠子は熱心に体を乗り出して聞いている。
「勝竜寺は平城なれど、活気がありまする。何事も上下の隔てなく、率直に正直にものを言う雰囲気があり、細川の殿様の度量でございますね。当代一の学者でいらっしゃる。これは大切なことにて、一見、和気藹々としておるように見えても各々が心底を隠すようになりますと、疑心暗鬼を生じて争いが起きまする」
「麝香さまは?今まで会うても、何もいやなことはない。でもねえ、みなそうは言うても、姑というものは、わけもなく嫁がきらいなものだと申すのです」
「麝香さまは、わけもなく意地悪をなさるような方ではありませぬ」
小侍従はいかにも陰口じみた言に逆らうよう、いささか強い口調で言った。
「それは大変な女丈夫でいらっしゃる。自分用の鎧ももっておいでで、自ら戦へ向かう準備が常に出来ておりまする。武芸の稽古を欠かさず、城の女たちにも義務づけておいでです。殿様もとてもかなわぬとか」
語りながらも、おおよそ、城の女たちが気の毒がったり、威張っておれなどと吹き込んでおるのは、この大変な女丈夫への愚痴が下々の女たちを通じて届いているのであろうと、小侍従には察せられた。
確かに実際に暮らしてみねばわからないが、この嫁と姑は仲良しとはいかずとも、合わぬということはないだろうという予感がした。
麝香は考え方が理路整然としてはっきりしている。よいか悪いかの判断は自分で決め、根拠のないしきたりに無暗にこだわる質でもない。
「確かに細川のお家は、明智の殿に比べれば貧しゅうございます。さて姫さまはどうなさりたい?」
小侍従は話題を変えて質問を投げかけた。
「小さなお城が大きゅうなるよう盛り立てなさる?若殿は右府さまの大のお気に入りでございます。奥方同士のお付き合いも大事になりまする」
珠子は少し考えた。
熊千代は逸る気性、大きくなりたいと口癖のように言っておる。
わたしはどうか。
口先だけの人づきあいは慣れぬし苦手だ。奥方同士の交流や、安土で勤めるなど、考えるだけでもいやな気持がする。
そもそもえらくなれば幸せなのか。安泰なのか。小さな浪宅暮らしのときがいちばん幸せで好きであったような気もするし、かといって今が不幸せというわけでもない。
これは珠子にとっての問題ではなく、こだわるのは熊千代の方であろう。それが一因として自分のせいでもあるということは、珠子にはわからなかったが、よく考えたすえにこう答えた。
「わたしは戦うならば熊千代どののお役には立てると思うの。したが奥方同士のお付き合いなどそれほどうまくは出来まい。盛り立つか否かは結局、時の運なれば、どうなろうとも如何様にもおれるように、気構えを備えるべしと心得まする」
まだ十五の年頃ならば、結婚を目の前にして夫婦生活や衣装や暮らしぶり、親戚付き合いのことを気にするものなのに、娘らしからぬ老成した答えに小侍従は驚きもし、大人ぶった口調を愛しいと思った。
誰にも気付かれない程度わずかに眉が曇り、それから小侍従はまた花のように微笑んだ。
◇
三月、熊千代を連れて丹波攻めの準備をしている明智の軍を訪れた藤孝は、声高な秀吉の声を耳にして周囲を見渡した。
「よいか小一郎!明智どのにようあれこれと習うんじゃぞ!」
今日は秀長どのをお連れか。
丹波黒井城を攻めるのに、多忙の秀吉のかわりに秀長が参加するのだと聞いている。あの様子だと、十兵衛の近くであれこれ経験させようと秀吉自らが弟を押し込んできたようだ。
秀吉は旧幕臣の連中とも仲がよい。荒木、藤孝とうまくやっている。
頭の回転が速いのと同時に口もよくまわる秀吉は、ガチャガチャとうるさい奴とみられている。秀吉の弟の秀長は、育ちの悪さは兄と似たようなものだが、秀吉よりももの柔らかで人当たりがよい。
熊千代は今や父とはまったく違う目で明智の軍勢を眺めていた。
光秀と共に何度か従軍するうちに、その緻密さ、細部までゆきとどいた秩序に感心した。礼節をわきまえ、厳しくするべきところは処断する。上様が、父ではなく明智どのを取り立てた理由が、残念ながら自分にもわかる、と思った。
だが心は?
明智軍を明智と妻木の一族で率いてはいるが、譜代の郎党がいない。また整然たる秩序を尊ぶだけに、命も共にと切り崩し突っ込んでいく、そんな覚悟の気迫は足りないように思えた。戦の現場においては大切なことだ。
光秀は坂本城の内部にいて、牢人らしき男と話をしていた。
積極的に人材を登用しようとしている明智家のこと、それ自体は不思議ではなかったが、熊千代は目を見張った。
大きい!痩せてはいるが、座っていてさえ見上げるほどの背の高さだ。どこかで見たような気がする。首をかしげて考え、思い当たった。
「日向守どの、あれは……」
そっと手で合図をされた。
「ちょうど良かった。ご紹介しておこう。こちらは藤堂高虎と申す」
大男は頭を下げた。
「磯野殿のもとに仕えておったのだ」
光秀は短く言う。
それで藤孝も熊千代も、事情は察した。
お聡の夫、七兵衛信澄は磯野員昌の養子に入っていたが、磯野は二月になって突如として高野山へ入り、所領はすべて信澄が継ぐこととなった。北畠に続き、お家の乗っ取りが行われた余波なのだ。
「お聡が、仕官の口を探してやってくれと手紙をよこしました」
◇
「奥方さま、お聡さま!」
「どうしたのです」
高虎の妹が、涙をいっぱいにためていた。これも兄に劣らず大柄な体格の娘だ。それがおろおろして手紙を握りしめている。
「兄が、放逐された兄が……三河あたりでウロウロして、店でお餅を盗んだとのこと」
「まあ!」
信澄は信長の名に従い、家督を譲るよう磯野の義父にはっきりと言った。
──納得を求めているのではない。できないのもわかっている。しかし、自分はあなたを北畠の二の舞にはしたくない。どうしても聞き分けてもらわねばならぬ。
憤然として去った磯野は、命を取られることは免れた。
今回のことは、父上も裏で動き、関わっているに違いない。お聡は去年見た信澄の高虎への冷たい態度と照らし合わせて空恐ろしい心地がした。だって、もう新しい城を築き、その縄張りは父上がするという話まで既についておる。さすが信澄どのと明智どの、乗っ取りも鮮やかな手腕と言われている。
磯野付の将である藤堂は、そもそもがあまり信澄との関係もよくなかったこともあり、あっさりと放逐されてしまった。
「店主が気の毒がって饅頭を食わせてくれたので、何とか一命をとりとめたと書いてよこしました。仕送りをしても食べるだけで精一杯なのでございます」
「あの体では、さほど持ちますまい」
お聡は気の毒に思いながら、周囲の女たちが笑いをこらえているのに少し腹を立てた。他人事だと思って!
「書状を書くゆえ、明智陣営へ行くようにお言いなさい。あとこれは路銀のたしにしなされ。父上はきっと何とかしてくれまする」
「奥方さま!ありがとうござります。恩に着まする」
藤堂の妹は大きな体を伏せて涙を流した。信澄殿もよい将をもったいないことだがこればかりは相性ゆえ仕方がない。
命は助かったといえど、磯野殿の恨みも深かろうとお聡は憂慮した。これ以上の憎しみを集めぬように、尻拭いはわたしがせねばならぬことだ。
◇
磯野の妻子の面倒はお聡が見ていると信澄からも聞いていたが、さらに失職した家臣たちの世話までするとは、さすが日向守どのの娘らしいと熊千代は考えた。
光秀は藤堂に言う。
「御仁は槍も見事に使う。武勇は疑うべくもないが、何かもうひとつ得手を身に付けられるとよろしかろう。築城技術は如何か。どこに行っても必ず重宝されるであろう」
「ご指南頂ければ、誠にありがたき幸せに存じまする」
高虎は深く頭を下げた。
坂本の石工集団、穴太衆は光秀の引き立てと後援によって、今やどこの武将たちからも引っ張りだこになっていた。熊千代も築城については光秀について詳しく習い、石工たちにも顔を通してもらっている。
「とはいえ、信澄どのご勘気は激しい様子。これで奉公構(再仕官不許可証)でも出されては気の毒だ。羽柴秀長どのにお引き合わせしよう。ちょうどこちらに来ておられる」
信澄は今、石山本願寺攻めで忙しい。光秀はそっと熊千代にささやいた。
「ここであの者を見たことを、信澄どのには内密にしていてもらいたい」
四月、丹波の黒井城攻めで藤堂高虎は黒井城と八上城の間にある大山城を攻め、武功を立てて面目を施した。
このとき共に軍を率いていた羽柴秀長に仕官が決まり、この騒動は事なきを得て何とか落ち着き、お聡も報告に満足をした。
この何気ない小さな出来事が、いずれ明智の家に大きく関わって来ようとは、この時誰も思いはしなかった。
◇
藤孝は秀吉と立ち話をしている。熊千代は明智のそばを離れず、いつまでももじもじしていた。
「どうされた」
十兵衛のいたわるような顔には不審な表情が浮かんでいて、いっそう言葉はつまり、頬は赤くなってへどもどしてしまった。
「あのう、た、た……珠子どのは……」
やっと飲み込んで、これだけ言えた。
「息災でいられますか」
十兵衛はじっと黙っている。沈黙が怖くてなかなか顔を上げられなかった。ここに到って何するものぞと意を決して見上げると、静かな笑顔があった。
「ならば、ご自分でお訊ねあればよい」
「えっ!?で、でも……」
婚礼前には逢えぬしきたりではなかろうか。
「かまわぬ。おいでなされ」
久しぶりの明智家の奥屋敷だった。琵琶湖に張り出した美しい坂本城の桟橋が見渡せる渡り廊下を過ぎると、はじけるような笑い声が聞えてきた。
熊千代はすべてを忘れて立ち尽くしていた。
二年でこれほどまでに変わるものか。
すっかり背は伸びて体つきも大人に近づいた。十五歳の少女は、ぼんやりと想像で頭の仲で作り上げ、何度も何度も思い描いていたよりも、はるかに輝いていた。美しかった。誰であろうと、比べ物にならない。
横に見慣れない新しい侍女がいて、いっそう華やかさを増している。
華奢ではあっても、微塵も柔弱さのない顔立ちにしっかりした立ち居振る舞い、誇らしさで胸が高鳴る。陶然としながらも、その頬の柔らかさの中に熊千代は、かつての幼い面影をはっきりと認めた。
女たちがはしゃいでいるのは、嫁入りの話題だったと見え、まだ子供らしい侍女が声高に叫んだ。
「お珠さまはお嫁に行きなさるのよ」
途端に珠子はぱっと桜色に頬を染めた。
何一つ屈託のない、はじける笑顔だ。心より嬉しいと思ってくれている。おれを待っていてくれている。
熊千代は足を止めた。
「話さなくてよろしいのか」
「十分です」
くるっと踵を返し、挨拶も忘れて飛び出していく背中を明智十兵衛は見守った。
六月、信長が烏帽子親となって前髪をおろし、ここに熊千代は正式に成人となって、名も細川与一郎忠興と改めた。
第十七話 終わり
画像(加筆あり・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。









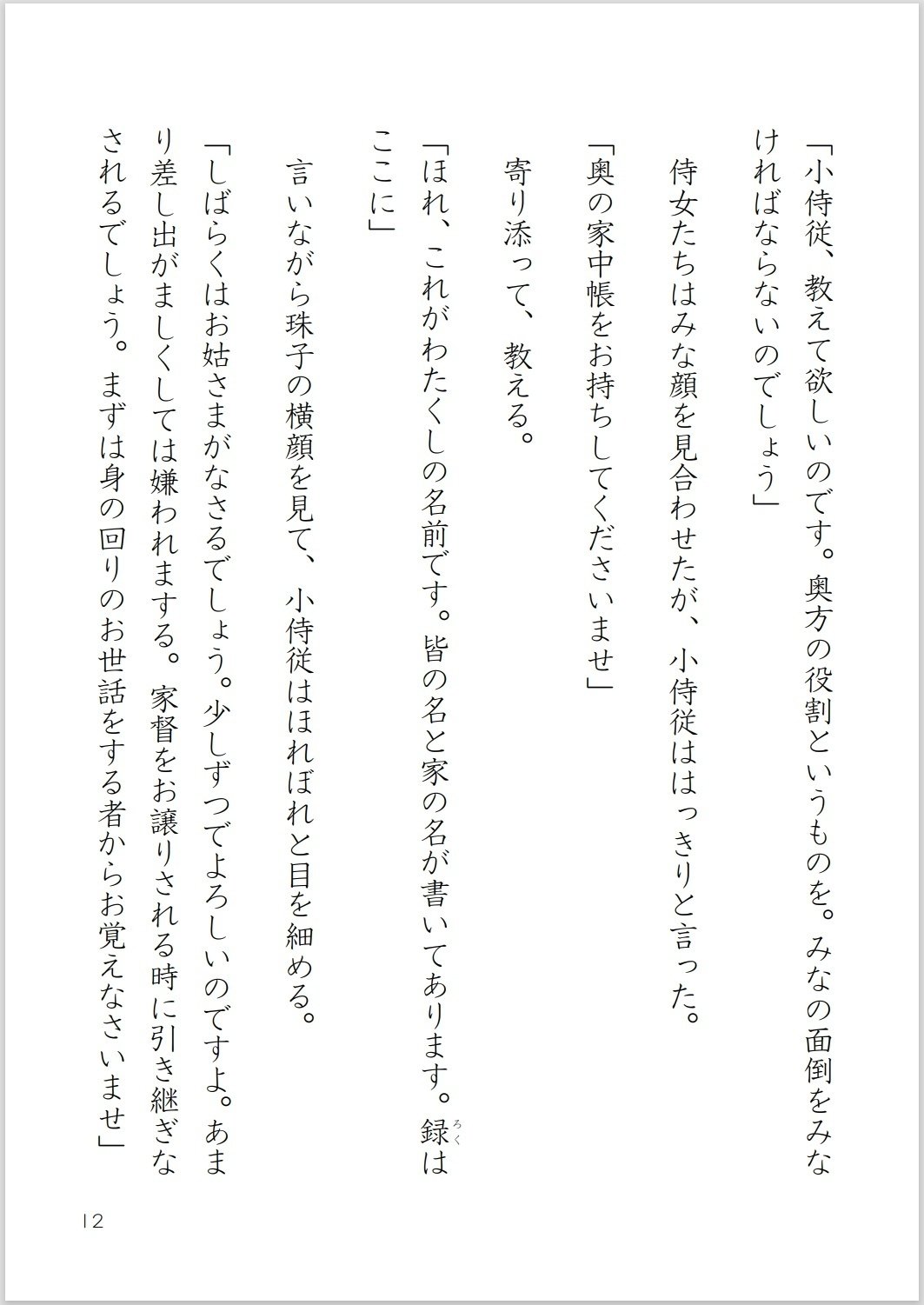




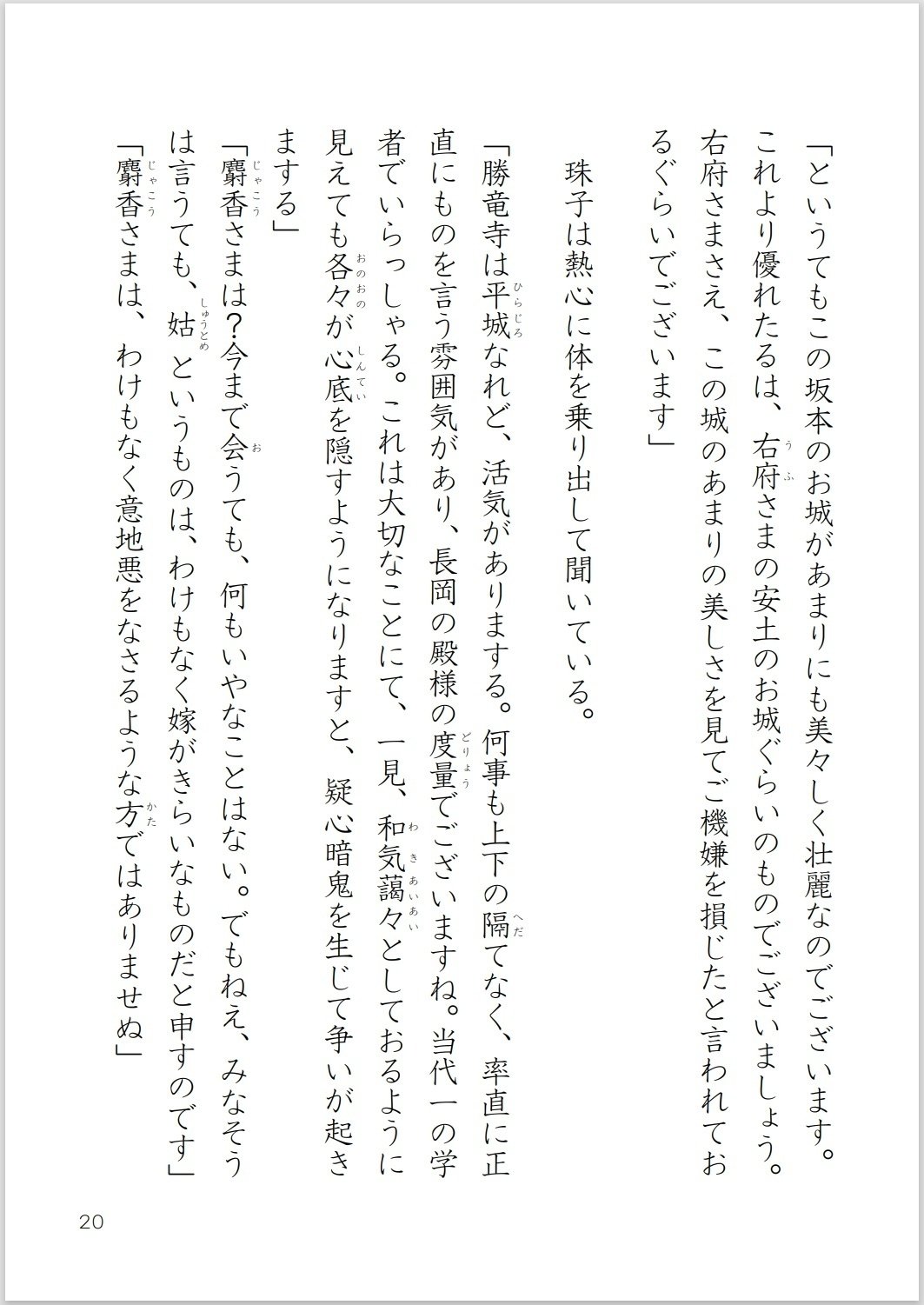













画像。本型。見開き版。
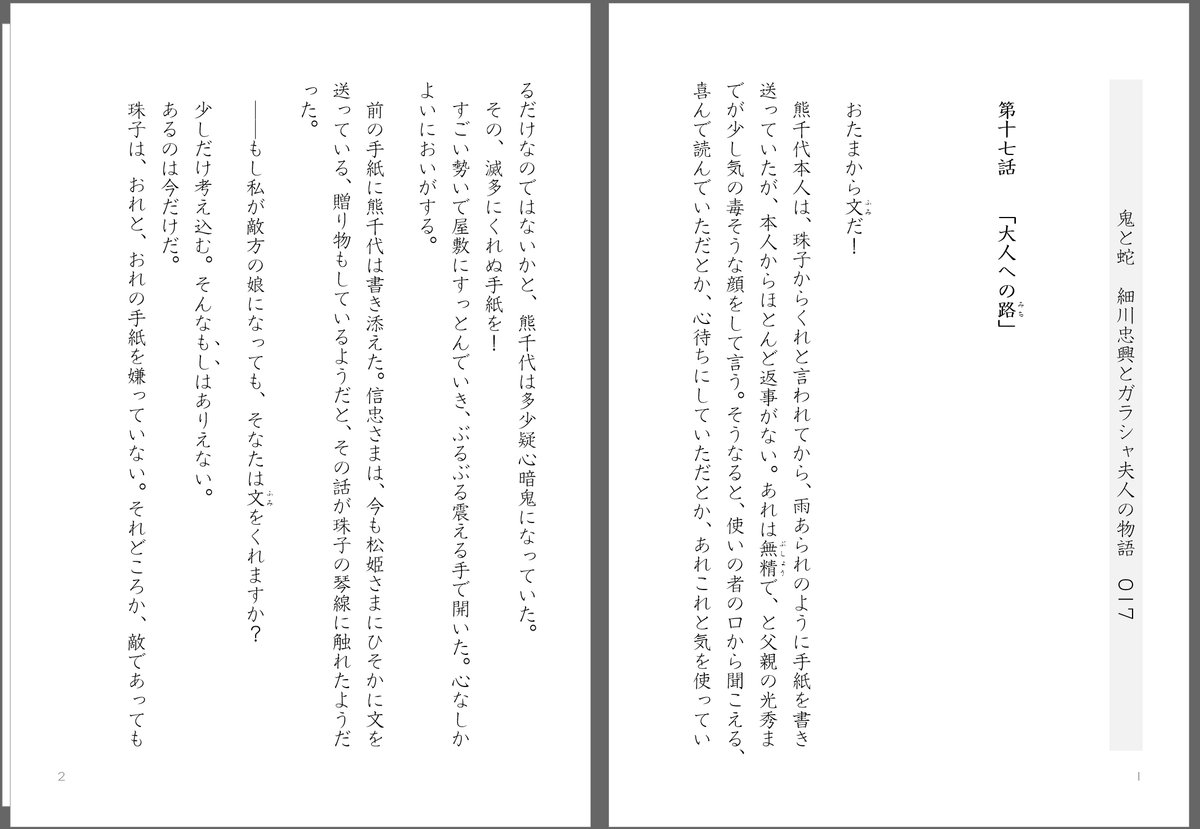













いいなと思ったら応援しよう!

