明智三姉妹(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 7)
※画像では、「ルビつき・縦書き」をお読み頂けます。
明智三姉妹
鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 007
第七話 「明智三姉妹」
熊千代の小姓暮らしが始まった。
寺の坊主に交じって過ごした日々の経験が役立った。早朝のお勤め、掃除、不寝番も楽々とこなす。日中の鍛錬は誰よりも熱心に猛烈に励んでいた。
公家の間で育った将軍の御供衆の子など、坊ちゃん育ちで何ほどのことが出来ようものかとみる者たちの目を驚かせるほどだった。
「熊千代、また書状が来たぞ」
先輩の小姓づてに箱が手渡される。
「毎日すごい量だな。心配しすぎだろう」
「おやじはいつもこの調子なのだ。もううんざりだ」
小姓部屋の書類が、普段の三倍ほど増えている。
「細川殿の送ってくる注釈つきの説明は誰よりもわかりやすい。熊千代、あとで読ませてくれ」
「それはもう終わったからお前にやる!」
熊千代は振り向きもせずに叫んだ。机に向かって身をかがめ、すごい速さで筆を走らせている。熊千代ははじめて、猛勉強に励んでいた。
出来が悪いと言われ、素直で聡明な弟と常に比べられていたせいでわからなかったが、小姓たちの中でも勉強熱心な者に負けないほどの知識も武芸も既に身に付いている。そんなことにも、熊千代は気づかないままだ。
小姓が交代で行う、不寝番の時間が熊千代は一番好きだった。
一人になると月を見上げては、岐阜城に来る途中で眺めた琵琶湖の湖水のゆらめきを思い、あの少女の面影を追う。
能の謡本を暗記して、ひそかに胸のうちで諳じた。
千早ぶる、神も願いのある故に
あの伊吹山の向こうには琵琶湖が広がっている。どこまでも続く水面に隔てられた対岸には、明智十兵衛の水城、坂本城があるのだ。そこにあの子がいる。珠子という名のあの少女が。庭の池に映る月の面に影が宿るように見え、あれほど拒否をした古今の和歌の一つ二つ、思い出さないこともない。
熊千代は心を奮い立たせた。
いつか明智殿に堂々と、珠子どのをもらいたいと申し込むのだ。
「はよう、はよう武勲を立てとうござる」
津田坊に言うと、こちらはふん、と鼻で笑われた。
「これから、大戦争がはじまる。われらの勝利は疑いなしだ」
信玄死去は驚天動地の混乱をもたらし、世界は音を立てて流れ始めた。
織田の激流が、雪崩をうって京を中心に日本を包む。
◇
小姓は交代で家に戻ることが許されている。
勝竜寺城に戻るなり、父が、「案内をしたのが津田坊殿と聞いて、終わったと思った」とか、「切り捨てられて首で戻ってくると思った」などと言っているのを聞いて、熊千代ははじめて、津田坊が小さな信長と言ってもいいほどの苛烈でむら気な性格で恐れられていることを知った。
驚いたのは、渡り廊下でぶつかったすさんだ顔の感じの悪い少年が、三七殿と呼ばれる信長の三男であったことだ。
あれが、信長さまのお子なのか!
小姓部屋では、食事になり、また夜になると噂話で賑やかになる。嫌でも声は聞こえてきた。
「三介どのが次男、三七どのが三男となっているが、お二人はほぼ同時に別々の側室腹から生まれた。言上に及ぶとき、三介どのの母御の侍女が邪魔をいたして、順番が逆になった。一時期、側室同士で大変な争いになったのだ」
「噂にすぎぬ!余計な口はつぐむがよいぞ」
信忠の同腹の弟は三介と呼ばれる、鈍重な顔の少年で、言葉も聞こえているのかいないのかよくわからない。
「あの年でもう養子にやられて敵の娘を嫁に取らされる、荒れたくもなろう」
「津田坊殿など、曰く付きの甥なのに上様のおぼえもめでたく、あれほど近いおそばで忠勤を励んでいるのにな」
三介(信雄)の母は生駒氏。
三七(信孝)の母は坂氏。
それぞれ、北畠氏、神戸氏と縁組、養子になっている。養子と言うものの、お家の乗っ取りと同じだ。
津田坊のことは、勝竜寺城へ帰ったとき、米田是政に聞いていた。
「津田坊どのは、誅せられた上様の弟君の嫡男であられます」
津田坊の父は信長の実の弟だ。織田信行(信勝)は謀反をとがめられ、実の兄である信長に殺された。幼かった子どもたちは柴田勝家に預けられ、育てられた。
信忠さまはともかく、おれにはお坊どのの方が、三介だの三七などよりもずっと立派に見える、と熊千代はひそかに考えた。
側室たちの争いはともかく、わからないことがある。
熊千代は津田坊に直接に聞いた。
「信忠さまの母上は生駒氏とのこと、明智殿の御従妹さま、あのかたはどなたなのですか?」
津田坊はちょっと黙った。
「信忠さまのご生母、生駒吉乃どのは、三年ほど前に亡くなられた。あのかたは、殿の以前のご正室。嫡男の信忠さまを養子にされて立派に育て上げられた。お名前は帰蝶さまと言う」
「以前?」
「美濃とのいくさのとき、子もできぬ敵のおなごがと、自ら正室の座を退くと仰せになった。だが上様はずっと大事にしておられるのだ。継室を置くこともせず、奥向きの側室たちも、あえてこの方を越えて前に出たりはせぬ」
熊千代にこの話はまださっぱりわからなかったが、口調に力がこもっていることから、あの婦人をきっと津田坊も慕っているのだなと推測した。
「みな、帰蝶さまのことはそっとしてあまり口にしないのだ。近親もおらず、今はいわば、明智どのが後見だ」
◇
岐阜城は華やかな先勝の空気に包まれていた。
二カ月もの遠征軍ののち、ついに朝倉義景を一乗谷で、浅井長政を小谷で討ち果たした。
岐阜城には祝いの挨拶に大名たちが次々と訪れる。そんな信長と信忠のもとに、堂々とした十七歳の若武者が入って来た。
「忠三郎か」
信長の顔は目に見えてほころんだ。
「大勝利、重ねておめでとうござりまする。朝倉攻めならず、浅井攻めもご一緒しとうござりました」
入ってきたのは蒲生忠三郎氏郷、器量を愛でられ、信長の娘を与えられてからは織田の一門ともみなされる立場となり、信忠とは義兄弟にあたる。
「これからは、一刻も早く畿内を落ち着かせたいものよ」
「まずまず、お市の方さまがご無事で、まことにようございました。ただいま、お冬がご挨拶に伺っておりまする」
氏郷の妻、冬姫は信長の娘、お市の方の姪にあたる。
蒲生氏郷は、多少、気分にむらのある津田坊や、嫋やかな貴公子然とした信忠と比べ、若いのにはるかに大人で、すでに老成すら感じさせる威厳があった。
冷静で有能、だがひとたび戦に出れば、誰よりも前に突出して馳せ下る。信長の評価は高い。
信長はちらっと嫡男の顔を見るが、本人は相変わらず物静かにしているだけだ。この調子で初陣はどうなるのかと思ったが、信忠は思いのほか朝倉攻めの激戦の中でもしっかりとした様子を見せ、重臣たちの評価も良かった。
縁談は遅々として進まないが。
「忠三郎、聞いているかもしれぬが今、面白い坊主が小姓にひとり入っておるのだ。信忠、あの元気な小僧はどうしている」
「いささか短気な所はございますが、素直に勤めておりまする。朝倉攻めに入る前に、岩成友通の討ち死にをその目で見届けたそうで、本人の語りを皆で聞き申しました」
「三好三人衆の岩成でございますな。淀城の戦にてございますか」
氏郷も面をただした。
◇
信長が大軍を率いて浅井・朝倉攻めへ向かったのが八月八日。
その六日前の八月二日に、将軍義昭に呼応して淀古城に立てこもっていた岩成友通は討ち死にをした。
熊千代はどうしても戦に出たいと言い張り、(藤孝の不快をよそに)信長に許されてついて来ていた。
是政の父、米田宗堅の肩に乗り、鹿角の兜の角にしがみ付いて首を伸ばして戦の様子を見物する。ぶかぶかのかぶとの下の目は燃えるように輝き、うなりを上げる矢の音にも、鎧のきしみ、鬨の声に怯みもしない。一層、気分は高揚しているようだった。
きらきら光る目のしわの多いにぎやかな小男が采配を取っている。常に誰かにしゃべりかけ、腰は低い。次々に命令を下し、ひっきりなしにご注進が入る。
「岩成友通は音に聞こえた剛の者、手は打ってあるものの、最後まで油断をするな!」
熊千代を見つけると鋭く手をかざして見下ろし、陽気に叫んだ。
「うむ、お子か!細川殿の!よしよし、こりゃ大したもんじゃ!」
あっという間に通り過ぎ、あちこちに鼻を突っ込んでは声高に檄を飛ばし、軽口を叩いてはまた命令を下している。
「秀吉め、調子にのりおって。いい気にさせるな」
米田宗賢が低い声で言う。
「手を打ってあるとは何だ?」
「内部に話をつけ、裏切りをさせたのでございます。でもなくば、岩成ほどの者がそうやすやすとやられるものか」
宗賢は、どちらの味方なのかわからないような言い方をした。
「こうなれば、何としても我が方の手で討ち取りたいものだ!」
是政の父、宗賢は息子よりも激しい気性で、藤孝と共につらい浪人時代を乗り越えてきている。藤孝との絆は深く、熊千代とも性があった。
熊千代は食い入るように城のお堀端付近を凝視していた。小さ目の小手をつけてもらった手がさっと上がる。
「あそこにおる」
「若は目が早い」
米田宗賢は熊千代の尻をゆすり上げて、自分も目を凝らした。
橋の上で誰かが刀を合わせるというよりは、ほぼ組み打ちに近い状態でもみ合っているのが見えた。
わあっと周囲が湧いた。
「あれは下津権内だ。殿の手の者にございますぞ、若!」
「岩成でござりまする!討ち取れ下津!行け!行けーっ!」
「落ちた!落ちたぞ!」
水音がして騒然となったあとにしばらく、静寂が包んだ。
皆、首を伸ばして見守る。注進の声も途絶えた。
大きな波紋が堀の水を揺らし、顔の水気を片手でぬぐって先に浮かび上がって来たのは下津の方だった。水を口から盛大に吹き出しながら、刀を握った片手を上げた。
静けさの中、ここだけは敵も味方も手を止めて堀を見下ろしている。勝敗が決定され、流れが決まる瞬間だ。
赤茶色の、泥のような鈍い色の水の塊ともに、ゆらりと堀の水表に背中を向けて上がってきた人影がある。
功を上げた下津権内の、顔から水をぬぐい咳をしながらの名乗りなど、かき消すような大歓声に淀城は包まれた。
米田宗賢がつぶやいた。
「殿はついに義輝さまのかたきを討たれた」
熊千代は、きらきら光る眼でじっと前を見つめている。だが藤孝はもうそこにはいなかった。周囲が死体に群がり、首を落とす所から背を向けてその場を立ち去った。顔には出さないが、胸は苦々しさでいっぱいだ。
本圀寺で義昭の命を狙った岩成が最期に義昭に味方をする。信長にだけは与すまじとの昔ながらに機内に勢力を張っていた三好三人衆の気概が、今はこうして信長に頭を下げている藤孝には苦しかった。
外では、秀吉が采配する甲高いてきぱきとした声がここまで聞こえてくる。よし、それはこちらに、残りは残党狩りへ向かえ、首は洗い清めよ、信長さまのもとへ送るでな。
十兵衛がいつの間にかそばに立っていた。
近江からわずかな手勢とともに駆けつけてくれたのだ。
「一徹な武将。見事な御最期でござった」
「何が見事なものか。死は、死だ!誰も変わりはない」
義昭を担いだ時には、何としてもこの足利の血を絶やすまいぞと、三好三人衆への復讐に燃えていたが、今やむなしさしか浮かばない。
十兵衛はつぶやいた。
「歌連歌 ぬるきものぞと言ふひとの 梓弓矢を取りたるもなし」
三好長慶の詠んだ歌だった。
かつて行われた連歌の会で、朗々とした声で詠み上げていた。静かな屋敷、蝉の声、岩成が首をわずかにひねって次の句を考えようとしている姿が昨日のことのように浮かびあがった。
句を考えていると前の句を詠んだ者の心も流れ込んでくる。次々に読み上げられる一連の詩が、不思議な一体感を持って場を包み、ゆるやかな流れがうねりとなって大きく流れるのだ。
藤孝は一瞬、戦を忘れた。
松永久秀の強い髭面の下の唇が微笑んでいるのが見えた。御簾越しに見事な庭園の白い砂が岩が微動だにせず、草木だけを風が揺らしていた。
声も歌も風と同じに通り過ぎるのかと思えば、記憶にこうしてはっきりと残り、また歌は文字として書き残され残っていく。
二人はしばらく黙って座っていた。
「十兵衛、歌は残る。歌には、時も利害も恨みも越えて、人の心を繋ぐ力があるのではないか」
十兵衛は、微笑んだ。
「あると存じます。時すらも超える力が」
◇
届いた岩成友通の首に、信長は比類なき働きの者であったと、着ていた胴衣をかけた。
秀吉は信長に伝えていた。
──何しろ三好三人衆の中核である岩成の最期、細川殿はさすがに万感あるとみえ、上機嫌の熊千代殿にはいささか御不快の様子でございましたな。
信長はうっすら唇をひきしめて思い出していた。
あのおやじ、挨拶の時は苦虫を噛み潰したような横目で息子を睨みおったなあ。
文武両道にすぐれ、教養を種に大名たちとの交流も人一番旺盛である藤孝だが、信長から見れば背中に過去の亡霊をひきずっている。
だが熊千代はまるで毛色が違い、そしてまだ幼い。父親と不仲となれば、十分に信長の意を汲む郎党となれる余地がある気がした。
信忠が、のどかに口を添えた。
「そういえば、熊千代には不思議な才がありまする。武芸も熱心でよくこなしますが、特に茶器、花入を運ばせて据えるとき、熊千代が担当した時と、他の者がしたのとでは、気配がまったく違いまする」
信長は興味をそそられた。
「置き方、見せ方、配置の具合が絶妙にて、これほど違うものかと驚き入りました」
蒲生氏郷は、そんな親子の会話にじっと目を開き、耳を傾けていた。
◇
氏郷は、小姓の夜番控の間に襖を隔てた隣の部屋で静かに目をつぶり、微動だにせず黙然と背筋を伸ばして座っていた。
小姓部屋が懐かしゅう存じます。今宵はわたくしも夜の番を務めとう存じます。
そう言って、静かにここに座ってからは気配を消し微動だにしない。
彼はこの若さでこの体勢を一晩保つことができる。朋輩からは、あまりの優等生ぶりと自他共への厳しさに、これでは息もつけぬ、迷惑なと陰口を囁かれることもあった。
夜番をする小姓たちは、交代で次の者を起こしに来る。ここは仮眠を取るための場所なのだが、若者たちのことでもあり、最初は神妙にしているがそのうち小さな会話から始まって、噂話に花が咲く。
「戻ってこられたお市さまには三人も娘がいるそうな。奥が急に賑やかになったとか」
「お市さまが美人だからなあ。その娘が三人か!」
埒もないことを。
氏郷は顔を動かしもせず、その話を聞いている。この自制心、とても十七歳とは思われない。
「美人と言えばだ」
誰か一人が声を低めて物々し気にささやいた。
「明智どのの三姉妹を知っておるか?」
「一番上は確か荒木に嫁いでおるよな?」
「ああ、あれは美人だった!村次どのがお目見えのときに、得意満面で連れてきておった」
「二女も三女も、たいそうな美人ぞろいの女たちだそうな。中でも三女は、信忠さまの側室候補に上がっている程だと言う」
「まだ幼かろう?十ぐらいだぞ?」
「その年で評判になるぐらいたいした麗質だそうな。顔を見た者が阿呆のように口を開けてしまうそうだ」
氏郷もそこは若者であり、さすがにわずかに興味を引かれた。たしなめに入るかと思っていた腰を落としてまた黙然と座り続ける。
「だが村次殿は奥方とあまりうまくいっていないそうだ」
「そりゃそうだ。婚約者がおったのに、明智どのが約定を破って荒木に嫁ってしまったのだから」
蒲生氏郷は、妻の冬姫を通じて、その縁談が荒木からの申し出であったこと、明智十兵衛が断りきれなかったこと、腹心の明智左馬之助との縁を残念がっていたのも知っている。
「明智の城づとめの者に聞くと、三女の美貌は魔と見粉う如きものと言っていたぞ!」
「兄上によると、京都奉行の頃までは、たまさか見ることもできたのだが、坂本城に入ってからは、まったく外に出なくなったらしい。何やら公家の娘もかくやという、英才教育をほどこしておるらしい」
「奧付きの美人たちのどれに似ている?」
小姓部屋は盛り上がってきており、だんだん声が大きくなっていた。
氏郷もさすがに腰を上げることにした。
「どれも大人だからな。わずか十の女と比べるのはどうか」
「やはり見て見ねばわからぬぞ!」
「いや美女とは言ってもだ。やはり添うてみねばわかるまい?」
氏郷がゆっくりと襖に指をかけた時、部屋の中の様子が変わった。
◇
「おい!」
細く開いた襖の影から見えたが、ひとりが声を上げ、丸く盛り上がった夜着の塊を揺すった。仮眠用の寝具だ。小姓たちがぐるりと周囲を囲んでいた。
ただならぬ気配に、氏郷が音もなくあけた隙間には誰も気づかない。
「熊千代、どうした?熊千代!」
丸い塊の中から、何かがひゅーひゅーと音を立てている。まるで冬枯れの枝の間を風が通り過ぎるような響きだ。
「いかん、喉が」
「歯を食いしばってがたがた震えて……こ、これは?瘧か?卒倒か!?」
「いったい何故?突然どうした!」
小姓部屋は突然の大騒ぎになった。
氏郷は襖を音を立てて閉じ、そっと指を唇にさした。
「蒲生さま!」
「落ち着け。医師を呼べ。騒ぐなと伝えよ」
医師が呼びにやられ、氏郷は夜着をそっとめくってのぞいた。小柄な少年が、唇まで白くなって額に脂汗を浮かべている。すっかり過呼吸になっていた。
「話はできるか?」
すると、食いしばって蒼白になった唇から、きれぎれに言葉が漏れてきた。
「だ、い、じ……ない」
「口はきけるとみゆる」
氏郷が少年の額に手を当てようとすると、乱暴に振り払われた。唇は真っ白だが、指は熱く燃えるようだ。
「やはり熱があるのではないか」
「さわるな!」
小姓の一人が困ったように口をはさんだ。
「そいつはとにかく、えらく気の荒い奴で」
「大事ない!何ともない!い、医者などいらぬ、人を呼んだりするな!」
氏郷は夜着を顔にかけてしまった。息を吸いすぎないようにとの配慮だ。
「これだけ口が回るようならば、そこまで大事はなかろう」
「蒲生さま!」
「こちらに床を敷けばよい」
氏郷は落ち着いて自らてきぱきと床を敷きなおし、熊千代をふいと持ち上げて持って行ってしまった。熊千代本人も口をさしはさむ暇がない。
「わたしが見ている。お前たちはお勤めに励むがよい。夜番の次の交代が来たぞ」
蒲生は、音もなく襖を閉めた。
残った小姓たちはあきれて顔を見合わせる。一体何が起きたのかさっぱりわからない。
「蒲生さま、すごい威厳だな」
「したが、一体……?何がどうしたのだ?」
「まだあの年にはおなごの話など刺激が強すぎたのではないか」
「たいした話などしていないではないか!」
襖の向こうから、声がした。
「噂話はそこまでにしておけよ」
◇
布団の下で、熊千代は震えていた。
側室!縁付き!結婚!
明智の三女とは、珠子ではないか。白い腕、柔い頬、あの神の化身とも言うべき、あの娘。おれの瑞兆の白蛇だ。あの、あの、娘が……。信忠さまの、そ、そ……。
気が狂いそうな悶えをこらえるために、熊千代は汗臭い夜着の袖をぎゅうっと噛みしめ、ほとんど食い破いてしまい、中の綿がはみ出てきた。
がばっと起き上がる。そしてまたがばっと夜着を頭からかぶった。
ぎりぎりと音が聞こえるほど歯ぎしりをした。
何としても阻止せねばならぬ。何をしてもだ!どんな手を使ってでも!
もう少し落ち着いた性質の者であれば、信長、信忠の名前を聞けば、無力にあきらめ、苦い現実にうちひしがれたかもしれないが、熊千代はそんな性ではなかった。恐ろしいほどの粘り強さで目的を実現するために邁進する。
とはいえ、何らかのうまい考えが浮かぶわけでもなかったので、とりあえず駄目元で父に直談判しようと決意した。
そしてまた夜着をはねとばし、げんこつで枕を殴ったので、枕元に届いて置かれていた薬湯を入れた茶碗が空中に飛び上がって着地した。
「取られてたまるものか。珠子どのは誰にも渡しはせぬ、絶対に!絶対にだ!」
そのとき、背後から咳払いが聞こえて、熊千代はぎょっとして振り向いた。
◇
熊千代は動揺して、思わず刀を探して腰に手をやっていた。
脇差を探し、懐を探っていると、相手がスッと指さしたのでそちらを見ると、どちらも寝具の横にきちんと丁寧に置かれている。
まだ動揺の冷めやらぬまま、熊千代は相手に詰問した。
「お前いま、何か聞いたか!?おれは何か……なにか言ったか?」
人影は、若いが元服もすませた年長者のようだったが、熊千代のその乱暴な物言いにも動じることはなく、怒りもしなかった。穏やかに答える。
「今ここに来たばかりだ」
「おれは、おれは!」
「そう興奮するものではない。具合が悪いのであろう?」
「悪くなどないっ!」
血まみれの懐紙が鼻から飛び出して膝におち、熊千代はびっくりした。
うわっ。
相手はいつの間にかそばに寄っており、有無を言わさぬてきぱきとした仕草で頭を上げさせられた。文句のつけようのない鮮やかな手際で、熊千代は新たな懐紙を鼻につめられ、夜着をかけられて寝かせられてしまった。
熊千代は疑い深そうにじろじろと相手を見た。
ずいぶん落ち着いているし元服もしているようだが、服装も質素でまだ若く、年配の小姓たちと年齢もほとんど変わりなく見える。
こんな所にいるのが、まさか大名の子息とは思われなかったので、熊千代は勝手に、中間の下っ端なのだろうと決めてしまった。
「おまえは……?夜番か何かの者か……?」
「忠三郎と申す」
すまして名乗った彼は、疑り深そうな熊千代の視線に付け加えた。
「わたしは近江の出でな」
「そ、そうか。おれは」
「細川熊千代どの」
近江の出ならば、尾張周辺の譜代の家来ではないのだろう。外様の立場は自分とおなじ、急に心安くなるとともに、生粋の京生まれの彼は、田舎者だと若干、侮った。たとえ育ったのが京の裏町であろうとも、いや、だからこそ、都生まれ都育ちの自負は彼の骨の髄まで染み込んでいる。
この男は若いくせにもみあげを生やし、まだうっすらとなのに髭まで蓄えている。何より、この若さで奇妙な落ち着きっぷりが気に入らない。
熊千代は、ひそかに思う。
おれは、長じてもぜったいにひげは生やさんぞ!
「わたしが小姓をしていたのは、つい数年前までのことでな。今日は懐かしくて、夜番をお願いさせてお許しをいただいた」
先輩か。
熊千代はまたがばっと起き上がり、鼻の懐紙はふたたび吹き飛んだ。
「ならば、上様のお好みはどんなか知っておるか。おぼえめでたくなるにはどうしたらいいか」
奇妙に落ち着いた年長者は、すまして答えた。
「ご機嫌を取り結びたい者は少なからず……」
「ちがう!」
熊千代は激昂して、相手はいよいよ落ち着いている。
「そういうわけではない。だが知りたい。上様のお役に立ちたい、そして、じ……じ、事情がある」
「上様のお好みは、なろうとしてなれるわけではないのだし、真似をしてもつまらぬよ?」
うんざりした様子も見せず、彼は辛抱強く鼻血のついた懐紙を再び拾って、また新しい懐紙を熊千代の鼻に突っ込んだ。それから腕を組んで空をみたのだが、その仕草がまた熊千代には一段とえらそうに見えた。
聞く耳持たずとばかり、熊千代は性急に口をはさんだ。
「何か具体的な、すぐに出来る、そのう、芸のようなものはないのか?」
「そんなものあるわけなかろう」
「おれは連歌は苦手だ。文字をこねくりまわすのはきらいだし、性に合わぬ。武芸の勝負仕合は終わったばかりだ。それにぜったい負けぬ自負はあるが、悔しいがおれは……このとおり、小さい。気持ちは負けぬでも、剛力の者に及ばぬこともある」
「猛将はすべからく小柄なもの、体の大きさに関係はない」
相手は慰めるように諭したが、熊千代のあまりの熱心さに、しばし考えた。
「おまえは茶はたしなむか?」
「の、信忠さまのもとで少し」
「上様はことのほか、茶器がお好きだ」
熊千代は、先ほどこぶしで殴ったときに、空中に飛び上がって着地した湯呑を見た。貴重な茶器は常に白木の箱に入れられ、絹布に包まれ大切にしまわれている。
先日、選んだ花入れを信忠に褒められたことを思い出した。
「茶器か!よ、よし!」
「高名な細川どのならば、父上にいくらでも指南してもらえように」
「いやだめんどくさい。明智どのにでも聞く」
頭が一杯になっている熊千代は、良い所を見せようとしている当の明智本人に知らず知らず頼っているのに気づかなかった。
ふむ、と口を咎らせてひざに肘をつき、相手はもみあげの顎に手を当てて、熊千代を上から下まで見渡した。
「お前はどうやらまだまだ若輩者のようだから、忠告をしておいてやろう」
むっとして熊千代が眉を上げると、彼は顔を引き締めていた。
「おれたち外様出身の者はな、特に気をつけねばならぬ」
「何?」
「周りは、すべて敵だ!」
そのとき、この素朴な年長者の顔が細く鋭くなり、瞳孔が開いて真っ黒なやみがのぞいた。
彼には二つの顔があるようで、能のひとつの面が落ちて背後に別の面が現れたように、その黒い猛々しさは、今までに見た誰とも違ってもっと厳しく、もっと硬質な深い暗さを湛えていた。
「わたしは、濃姫さまのもとに出入りできたので美濃の衆に可愛がってもらえた。今宵のおまえはわたしが相手だった。それは運だ。だがよいか、外様はいつでもどこでも、脚を引っ張られる。皆、お目に留まろうとしのぎを削っておるのだから、少しでも隙を見せると命取りになるぞ」
おのれの甘さを指摘されて力みのあまり、熊千代はまた顔をゆでだこのように真っ赤にして、口から泡を吹きそうになりながら怒鳴った。
「い、言われずとも!言われずとも……!」
「まあまあまあ、お前は少し落ち着けよ。薬湯を飲んで、もうちょっと休むがよい」
◇
いつの間にか朝になっていた。
あの年長者の姿はどこにもなく、熊千代は自分が夢を見たのではないかと疑った。
医師の僧侶がやってきて、薬を差し出すのに、殺気立っている熊千代はかんしゃくが破裂してしまった。
燃えるような目でにらみつけられた僧は困惑この上ない。完全なとばっちりだ。
「大事ない!」
「薬湯をお飲みなされ」
「余計なお世話だ!」
「気が立っておられる。飲めば落ち着かれるのだが」
これまで、熊千代にとって、明智珠子は美しい夢か幻の一幕にすぎなかった。ただ、あの頬に一瞬だけ触れた指の感触だけがすべてであり、大事にとっておいたあの実の種だけが守り袋の中にある。
だが、彼女も世間の中に生きている生身の人間で、少女は女でありその先に好悪はいざしらず、遅かれ早かれだれかに属することになるのだということを、この直情的な少年はわかりすぎりるほどはっきりと、唐突に理解した。
◇
勝竜寺城に帰った熊千代は、一も二もなく、さっそく父に率直に切り出してみた。
「おれの嫁には、明智の女をもらいたい」
それなりに礼儀作法を学んだことを示すため、やっと「です」と付け加えてみたものの、一喝されて何をばかなの一言ですべて終わった。
「どうせ若衆同士のくだらぬ噂でも聞いて思い付いたのであろう。ろくに勉強もしないくせに早うに色気づきおって。よいか、二度と口にするな。明智殿に失礼なことがあってはならぬぞ!」
おまけに、こんなことまで付け加える。
「あちらはお前などより、もっといい縁を探していることであろうよ」
熊千代は気が気ではない。ひとりで勝手に確信した。
きっと、話はすすんでおるのだ!
みじめに気が狂いそうになる。
夜も落ち着かれず、あっちにゴロゴロ、こっちにゴロゴロと転がって、うるさいぞ!新入り!と怒鳴られた。
幸をもたらすあの子、あんなにも美しいあの子を欲しいとおれが思うなら、きっとあの子を見た誰もがそう思うに違いない。
まして、あれほど仲良うやりとりされている松姫さまの間に側室として入るなど、信忠さまのためにも良いはずがない。全てが不幸だ。
一刻も早く、早く手を打たなければ!
考えるのだ、考えろ。
熊千代は必死にさまざまな小姓の噂話や会話を思い出した。
明智の長女は、明智の甥と約束していたのに荒木に嫁いだ。
荒木の息子は上機嫌だったらしいが、気の毒な左馬之助は、恨み一つ口に出さぬが、それから、誰とも結婚していない。どんな縁談もすべてことわっている。
明智どのの口約束はだめだ!
親もだめ、明智どのもだめ、ならばやはり信長さまに直接お願いするしかない。
第七話 終わり
(ここで第二話「熊千代の奇妙な願い」に戻るとループする)
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。





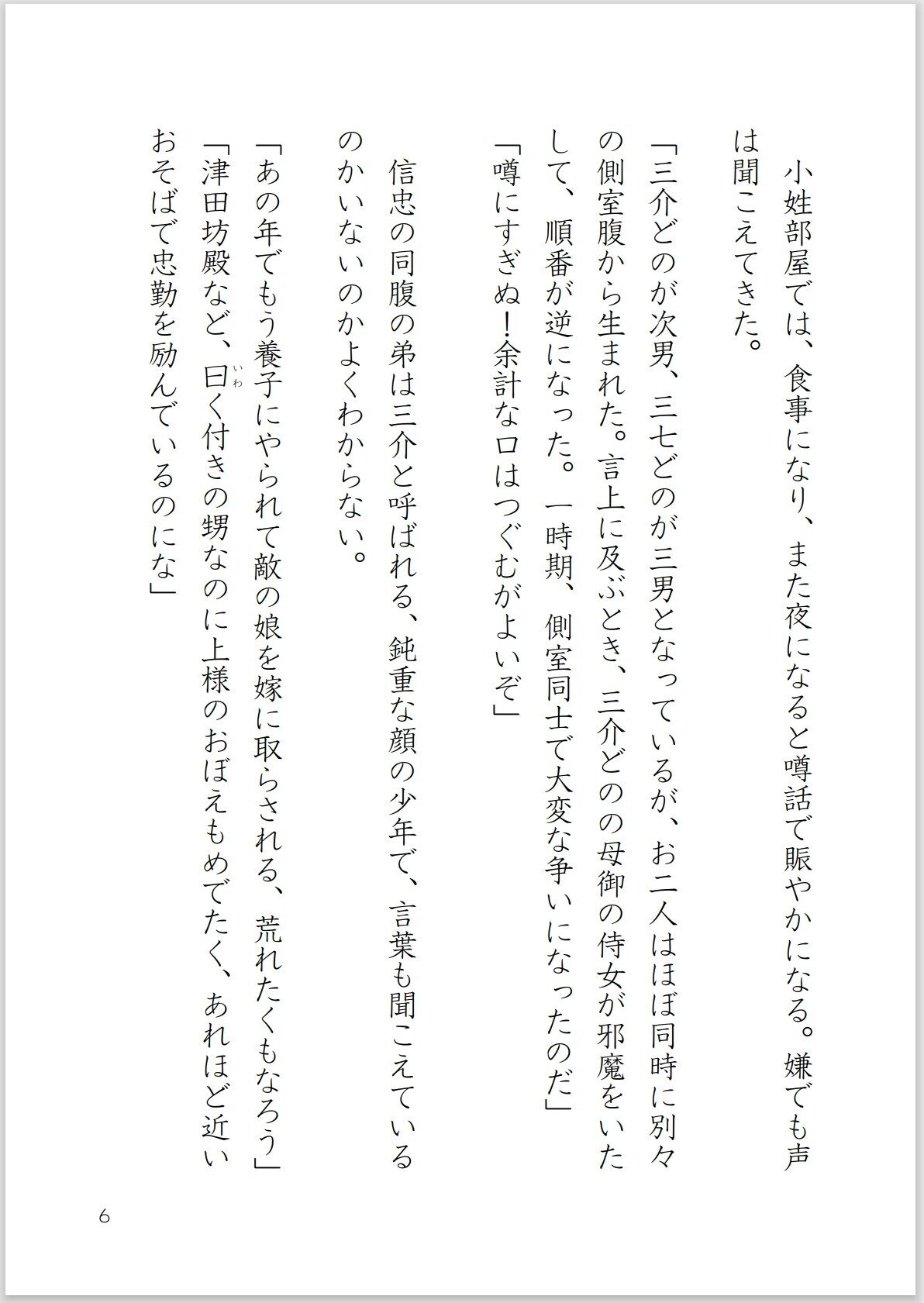





































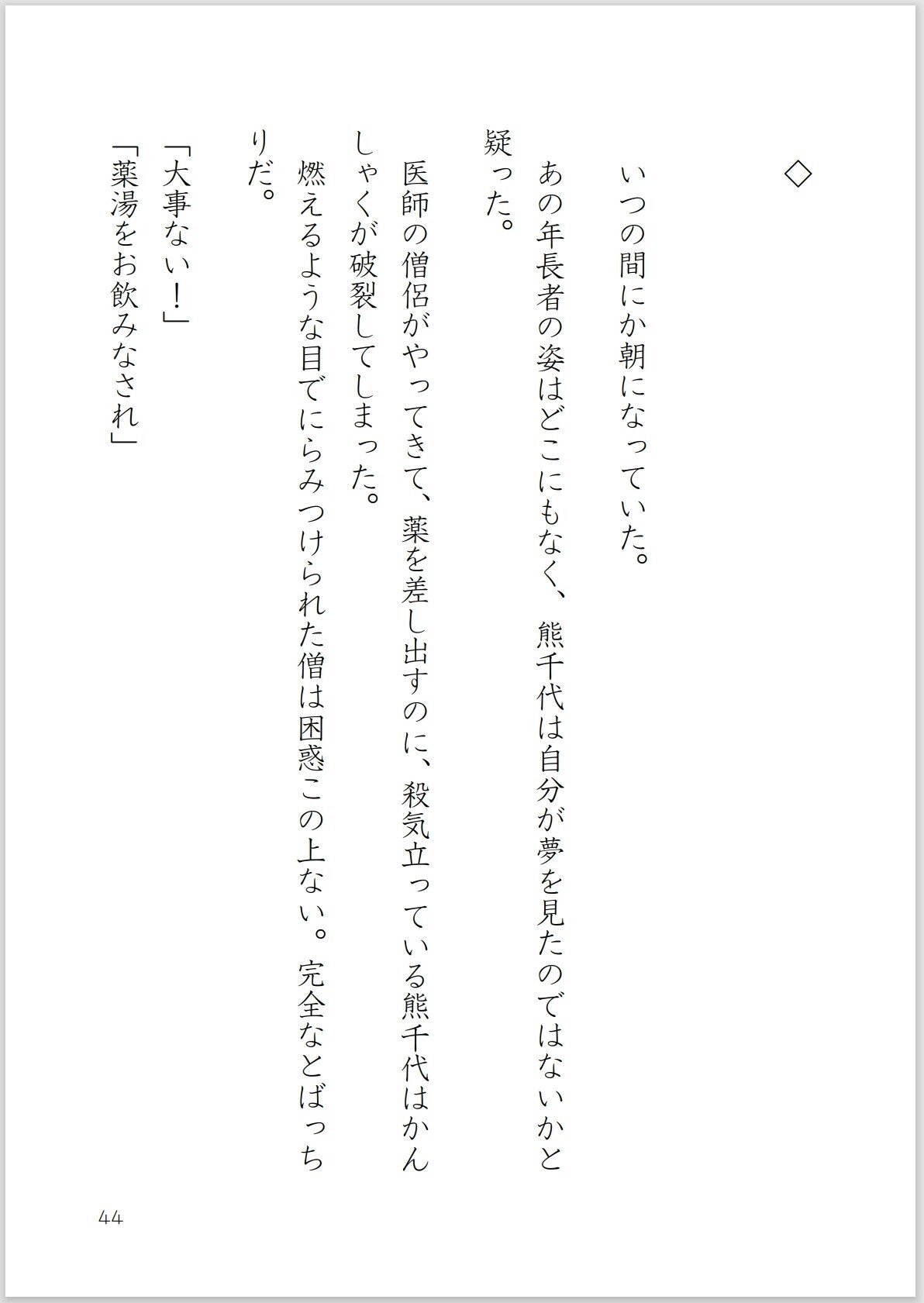




画像。本型。見開き版。
ちょっとテストで、見開き版を載せてみました。























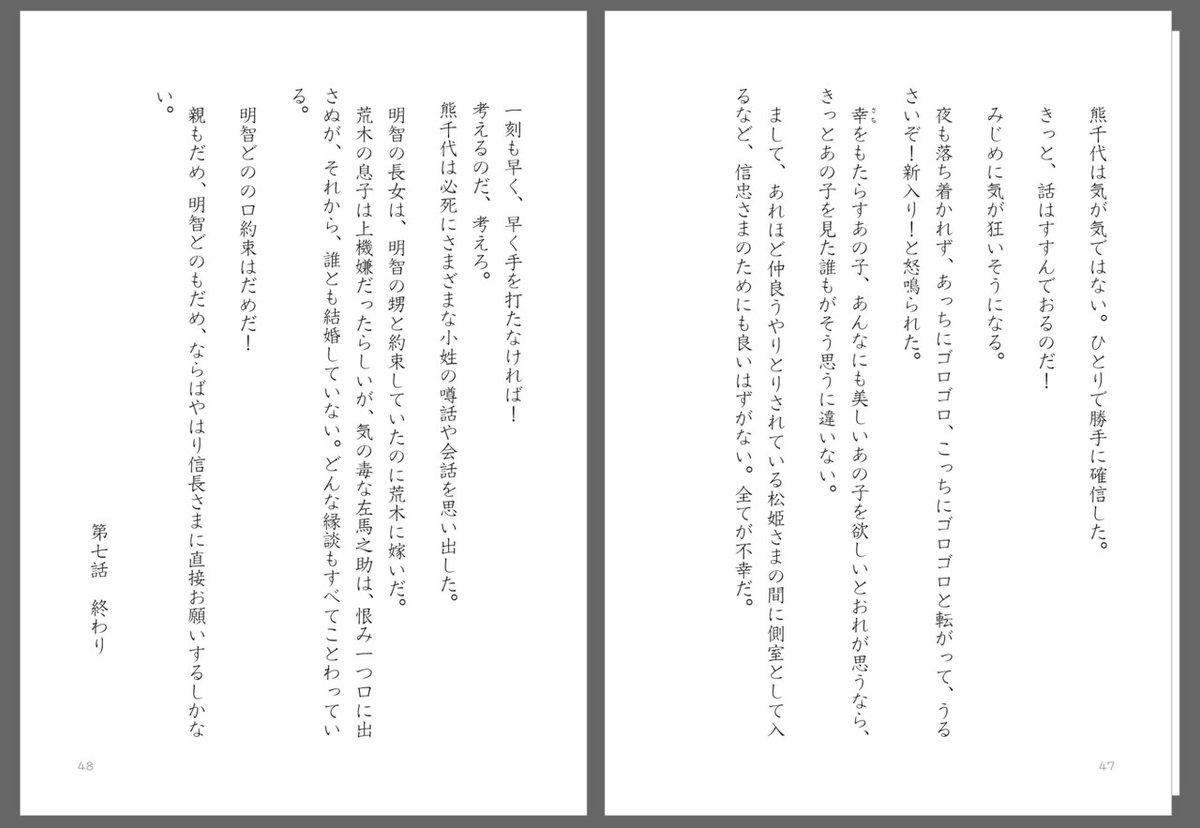
児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
