
藤孝、困る(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 3)
※縦書き画像をお読み頂けます。
藤孝、困る
「明智殿なら、良いではありませぬか。あなたは何がご不満か?」
「何がよいものか」
腐った饅頭を飲みこんだような顔で苦り切っている藤孝は、何の拘りもない妻の麝香に逆に驚いた。
何とも不可解な縁談だった。
帰ろうとする藤孝を追って使者が追い付き、二度、三度と催促があった。なぜここまで食い下がるのだろう。丹波・丹後の平定のために連携を固めよとの上意なのかもしれないが、他に優先すべき縁談はいくつもある。
藤孝は、家老の林佐渡守にこの話を固辞しつつも探った。
「十兵衛殿にてはこのこと、既にお話はついているのでございますか」
「いや、明智殿には上様みずから申し上ぐるとの仰せであった。明智はよもや断わるまいとのお言葉、それを細川殿がそのような……」
もしや十兵衛が信長さまに頼んだのではと思ったのだが、そのような気配もなさそうだ。考え併せてみれば、いまさら与力の立場の自分と縁組する利得が明智の方にない。
あるとすれば、いつも十兵衛が羨ましがっている部屋いっぱいに積み上げられた武道・文道問わぬあれやこれやの免状の数と、細川の一門に連なる家柄のよさぐらいだった。
藤孝は考える。
あとでとってつけたように『津田坊殿』の縁談もあると言っていたのも不自然だ。雰囲気からすると、どうも熊千代の話ありきで、津田坊のことは従の話であるらしい。ちょうど年頃の二女の話があとで、三女の話が先であるというのはおかしくはないか。
『津田坊殿』とは、信長の甥、それもただの甥ではない。信長が自ら粛清した弟、織田信行(信勝)の嫡男だった。
助命されて柴田勝家に育てられたという、曰くつきの子供なのだが、どうやらこの甥、信長にとっては次男三男、はては嫡男の信忠よりも肌に合うらしい。
信長次男の三介(信雄)と、三男の三七(信孝)は、四年も前に北畠と神戸に養子にやられ、それぞれの娘と縁組も決まっている。なのにこの甥の津田坊だけは、信長はいつまでもぐずぐずと側に置いていた。
はっきりした気性で武勇にもすぐれていれば、小姓として些事万端もそつなくこなす。藤孝から見ても三介、三七と比べると出来が頭一つぬきんでていた。
信長の嫡男、奇妙丸(信忠)と同じ年で十七になる。仲がよい。とうに元服もすませ、相手も見繕うべき頃のはずだ。
ここで思考は結局、同じ所に戻ってくる。
なぜ?
なぜ、この年まで縁が定まらなかった津田坊殿と共に、まだ岐阜に昇殿して数ヶ月の熊千代が、たかだか十の年で縁談が内定せねばならぬのだ?
解せぬ。
藤孝の疑心暗鬼はつのるばかりだ。
◇
藤孝がもうひとつ恐れていたのは、彼の妻、麝香の意向だった。
この嫁は、奥向きを支配している上に、藤孝をも完全に支配している。
藤孝は亡き将軍、義輝に若い頃から仕え、各地を転々として三好長慶と戦い続けて来た。比叡山の庇護を求めて坂本へ、さらに朽木城へと逃れ、近くには沼田氏の熊川城があった。元気で生き生きした少女だった沼田の娘に魅せられた藤孝は義輝の許可を得て婚約をしたが、転戦につぐ転戦で随分麝香を待たせてしまった。
やっと結婚でき、熊千代が生まれてすぐに永禄の変があり、藤孝がずっと仕えてきた足利義輝はついに殺された。弟、覚慶(足利義昭)を担いでの逃避行では、灯火の油すら変えぬほど困窮をしたこともある。苦労をさせた妻に頭が上がらない所は、十兵衛と変わりないのだが、十兵衛の妻、煕子とはまるで正反対で、この麝香の内助の功とは、ぐずぐずと悩む藤孝を叱り飛ばし、耳を捻り上げ、薙刀を持ってきて振り回す所にある。
今も、帰るなり熊千代と大喧嘩をしている麝香のことだ。
あんな小僧に嫁などもってのほか、馬鹿かあなたは、などと言われるのが恐ろしく、事と場合によってはもう一度お断わりせねばと思っていた。
それが思わぬ好印象だ。
つい元気を得て藤孝は、弱音と本音を吐いてしまった。
「理由はまったく見当もつかぬが、一つ残念と思うのはな、熊千代のやつ、妙に信長様のお気に召したであろうが?」
「はあ。それで?」
「それで(無論もっと大きゅうなってからの話ではあるが)、わしもどこかで淡~い期待を抱いておった。ほれ、蒲生の息子は幼少の人質でありながら気に入られ、見所があるとて信長様の娘御を頂いたではないか」
天を仰いで藤孝は嘆息した。
「短い夢であった」
麝香は心底あきれはてた顔をした。
「阿呆か。もらうならば、信長様の娘御とて、明智殿の娘御とて、そのあたりを歩いておろう娘とて、すべて同じでござりましょう。遅かれ早かれ、熊千代の気性に付き合うこととなりまする」
「それは、それよ……」
「気を使い、顔色を伺わねばならぬような信長様の娘なんぞより、気心の知れた煕子どのの娘御ならばよほどましじゃ。あなたは明智殿に見栄を張りすぎる。向こうは偉うなったとはいえ、こちらには常に礼儀を尽くしておるというのに」
「言われんでも、わかっておるわい!別に十兵衛とわしの仲だけならば問題はない。だがなあ……あれが関わってくるとなあ……」
「やかましいわ、グチグチ、グチグチと!」
ついに麝香はそのあたりにあった箒をつかみ取り、薙刀のごとく振り上げて藤孝は奧屋敷から追い出されてしまった。
「どうせ嫁なぞ先の話、どうなるかなどわからぬわ!あなたはすぐにあれこれ考えたり、詮索したり、誰かの動向を探りよる。そんな暇があるならもっとあれに親として因果を言い含めなされ!それから一つでもいいから部屋をもうちょっと片付けなされ!」
何という恐ろしい嫁ぞ。
胸をさすりながら、表屋敷に戻ってきた藤孝は、米田や松井が怪訝な顔をしているのを見て、面をあらため、咳払いを一つする。
すぐに真面目で思慮深く、頼もしいという、普段の武将の顔に戻った。
◇
明智十兵衛には、信長は直接に呼んで話をした。
こちらには二つ、縁組を申し伝える。
というのも、明智の長女は荒木村重の息子、村次に嫁いでいるのだが、まだ二女はどこにも嫁していない。熊千代だけに唐突に三女を目合わせるというのはいかにも不自然だ。
話をするとすれば、二女を先に片付けてしまわねばならない。それも三女が家柄はともかく格下への降嫁となるため、良い縁であることが重要だった。
「津田坊に二女、細川の熊千代に三女を目合わせよ」
多少の驚きはあったものの、こちらはごく普通に聞いて真面目に受け答えをした。
「どちらのご縁も、わたくしにとって何の不足もございませぬ。特に、津田の御坊様にわが娘とは、これはまことにありがたき縁と存じまする」
「うむ、そうか。細川の方はどうだ?」
今は、明智の力は藤孝をはるかに凌ぐ。しかも、藤孝がわずか十で無上のたおや女と称した、それほどの器量の娘とあらば不満も出るのではないかと信長は思った。しかし、十兵衛の表情に何の陰りもない。
「かねてより思うておりましたが、熊千代君は実に将来有望な御子でございます」
素直だなと見たが、その言葉を放った後の、いささか拍子抜けしたような呆けた顔に、信長は意地悪く問うてみる。
「何ぞ他に嫁入りの当てでもあったのか」
器量は眉唾にても、随分な英才教育を施している様子だ。これはかなりよい所への嫁入り先を探しているのではないか。そんな噂があったことも聞いた。それはあの熊千代も気が気ではなるまい。
しかし戻ってきたのは真面目な答えだ。
「お珠は幼いながらも良い話し相手になります故、父として愛憐の情、耐え難く、いらぬ親心とお笑い下され」
信長は苦笑する。
これはまた自分の息子に対して、短気だ乱暴だ嫁はいらぬ、などと情のないことを言う藤孝とは真逆の反応だった。明智十兵衛は、少し考えるようだったが、笑みを浮かべた。
「しかし上様、だからこそ親しうしておる細川殿に嫁入りできるは、私にとっては喜ばしき仕儀にございます。上様のご配慮、この十兵衛はありがたく承りとう存じます」
信長の中には、厳しい苛烈な処断を下す信長と、家臣の妻に到るまで気遣いを見せる信長がいて、後者は気取らない人間の顔を正直に見せるこの十兵衛光秀が好きだった。
さらに身も蓋もないことだが、若干丸めでごつごつした外見の藤孝に比べ、光秀はすらっとした痩身に色白で切れ長の眼差しは涼やか、四十六の年になりいくぶん髪は薄くなってきているが、目に入る姿が気持ちが良い。
従妹である帰蝶も皆、明智の家柄は美人揃いであったと思い出す。
もっと若い頃なればどれほどだったろうか、年上なが残念なことなどと、若干不謹慎な事を考えながら、信長は聞いた。
「熊千代とその娘は、日頃から仲良うしておるのか?」
明智十兵衛は首を傾げた。
「はて。私はともかく、娘が熊千代どのに会うた事があったでござろうか」
しかしそんなことを言いながらも十兵衛は、信長の口調からさすがに何となく事情を察したようだった。
抜け目ない十兵衛のことだ。藤孝に漏らすようなことはするまいと信長は見る。
「よし、事は決まった」
信長は扇を閉じて掌に打つ。
そして体を前に傾けると、打って変わった威圧を含んだ低い声で囁いた。
「これからおぬしらには、丹波に向こうてもらわねばならぬ。やれるか?十兵衛。あそこは難所だぞ」
信長は、明智十兵衛光秀が、すうっと頭を水のように上げて居直り、痩身をのびやかに起こすのを見た。それは、ぬるぬるとしながら神秘的で、どこか爬虫類のような妖しげな気配を纏っている。
気を取られる間に周囲はふと暗くなり、岐阜城のにぎやかな気配が消え、あたりは静まり返った。
静かな声が、空間に響き渡った。
「わたくしは、この我が身を信長さまの剣と変じて、ただ打ち払うのみでございます」
変わった。
軟らかかったからだが急に硬質となり、白く鈍く痩身が光りながら、天へと突きあげる。輝く刃か、これは神のお告げか。それとも、この男自身が何かしらの妖物なのか。
信長が我に返ってみれば、目の前には従順で柔らかな笑顔を浮かべる、いつもの礼儀正しい十兵衛が座っている。
席を立ちながら、信長は心のうちにつぶやいた。
まことにあれがおる限り、我は勝てる。
どんな戦にも必ず勝てる。
◇
あの時、明智十兵衛は藤孝に言った。
──もうこの流れは変えられませぬ。このままでは幕府に連なる者共は皆殺しになろう。
藤孝は麝香に追い出されて、言われるままに書架の部屋へ入った。ここは書架の部屋とは名ばかりで、ありとあらゆる芸事の指南書、古書、古今の底本、中国から取り寄せた選書、歴史書、経典までが、屋根まで積みあがっている。藤孝はやれやれとその真ん中に座った。
ここが落ち着くのだ。
──したが、兄を見捨てることになる。
──三淵さまは決してご同意はなされぬでしょう。
それは、誠のことだ。
ここまでか、とあの時の藤孝は思った。
幕府を守ろうと奉公衆たちは力を併せて、ここまで踏ん張ってきた。だが、時流は既に見えている。
そして藤孝は争いを逃れた旧幕臣たちをまとめ、信長お気に入りの明智の陰に隠れて、出過ぎぬよう働きすぎぬよう、だが戦うならば決死の覚悟で存在を見せて戦うように、細心の注意を払っている。
ちらりと疑いがきざす。
まさか、わしは一族郎党もろとも明智家中に取り込まれるのか?
今、十兵衛が家臣集めに苦慮しているのは知っていた。
譜代の家臣を多く持たぬ小武将の悲しさ、同じような無名の立場から抜擢された羽柴秀吉も、必死で人材登用をはかっている。
実力があれば家臣が主君になり、落ちぶれれば名家と言えども吸収されるのが当世の習いだ。現に、幕府の奉公衆であった仲間たちはいま、家老職となって藤孝に仕える立場となっている。ともに義昭をかつぎだした米田宗堅もそうなら、若い松井康之は藤孝よりもずっとよい家柄だった。
今、明智の勢いに飲み込まれれば、旧幕臣がそっくりそのまま光秀の配下となる。
腹を分け合い、心の底まで知り合う仲と言えど、越えてはならぬ一線がある。
十兵衛光秀に対して独立を保ちうる力があると見たからこそ、米田も松井も付いて来てくれているのだ。立場は薄氷のようなものでありながら、これを強固にしようと藤孝は慎重に足掻いていた。
陽が落ち、寒くなってきて、藤孝はぶるっと体を震わせた。だが、どんなに寒くなろうとも、この書架の部屋では決して藤孝は火を焚かない。
あれこれと思い悩んだ藤孝だったが、最終的にこの家の独立を保ちたいという心を十兵衛がわかっていないはずはないと思い直す。
「あなたは死んではならぬ方ですぞ」
明智十兵衛光秀は不思議な男で、荒れ屋で寺子屋の教師をしていた時にも、暗がりで彼の周囲だけがぼんやりと明るく見えるようだった。
「与一郎様が守るべきは、命だけではござらぬ」
「して他には」
「目に見えぬものではございませんか」
指をさしたわけでもないのに、藤孝はふと振り向いて背後を見ていた。
「茶器、絵画は目にも見えましょうが、目には見えぬが守らねばならない無数の価値がこの世にはありましょう」
「無形なる知財か」
信長以上に多分に現実的な性の持ち主である藤孝は、容易に神秘の気配に流されはしなかったが、心を大きく動かされたのは事実だった。
十兵衛と出会い、これらの書について夢中になって語り合った日々、主に死に遅れて思い惑うた日々、何とか義昭と信長の仲を取り持とうと奔走した日々の中で、藤孝の慰めであり支えであったこれらの文化財の山が、次第に息をつき、語りかけてくるのを感じた。
わしは公方さま(義昭)と、古書のたぐい、多くの知識を天秤にかけたかもしれぬ。
それでも、あの対信長の戦いを起こされたのが亡き義輝さまであったならば、共に死ぬのを喜びと思うたであろうに。物事には潮流がある。だが、兄を捨て、義昭さまを捨てるにはもう一つ理由が必要であり、十兵衛は彼の心中に触れてそっと背中を押して来た。
十兵衛はわしの運命は守人であると言う。
旧幕臣たちもそれぞれ、美しい足利幕府のありし日の記憶と血脈を抱えている。この堆い古書の山と、彼らの命や記憶は同じものだと十兵衛は言い、わしはその言葉に呼応して熱くなるのを感じた。
したが、心残りは……。
藤孝はまた、大きくため息をついた。
彼の跡継ぎは、これらに一片の興味も持たぬ暴れ者の熊千代だ。
落ち着かない彼に正座をして書を読ませようとするのは、麝香がどれだけ箒を振り回しても容易ではない。馬の耳に念仏と思いながらも、いやいや、門前の小僧習わぬ経を読むとも言うではないか。環境が大事なのだと自分に言い聞かせ、騙し騙しここまでやってきたが、熊千代の教育に関して藤孝はほとんど絶望しかけていた。
況や古書の類など、藤孝が死にでもすれば、あ奴はあっという間にすべて塵の山として捨てようとするのではあるまいか。
十兵衛の言ってくれた通り、わしは守人だとしても、とてもあやつがその役目を継いでくれるとは思えない。
せっかく助け出したこれらの貴重な古書の山も、結局は水の泡となるのではあるまいか。
「ああ、松井のようなが、我が子であったらなあ」
コトンと音がして、藤孝ははっと振り向いた。ちらっと覗いてすぐに消えた、しっぽのように見える刀の鐺(おしり)は、確かに熊千代に違いない。
第三話 終わり
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。







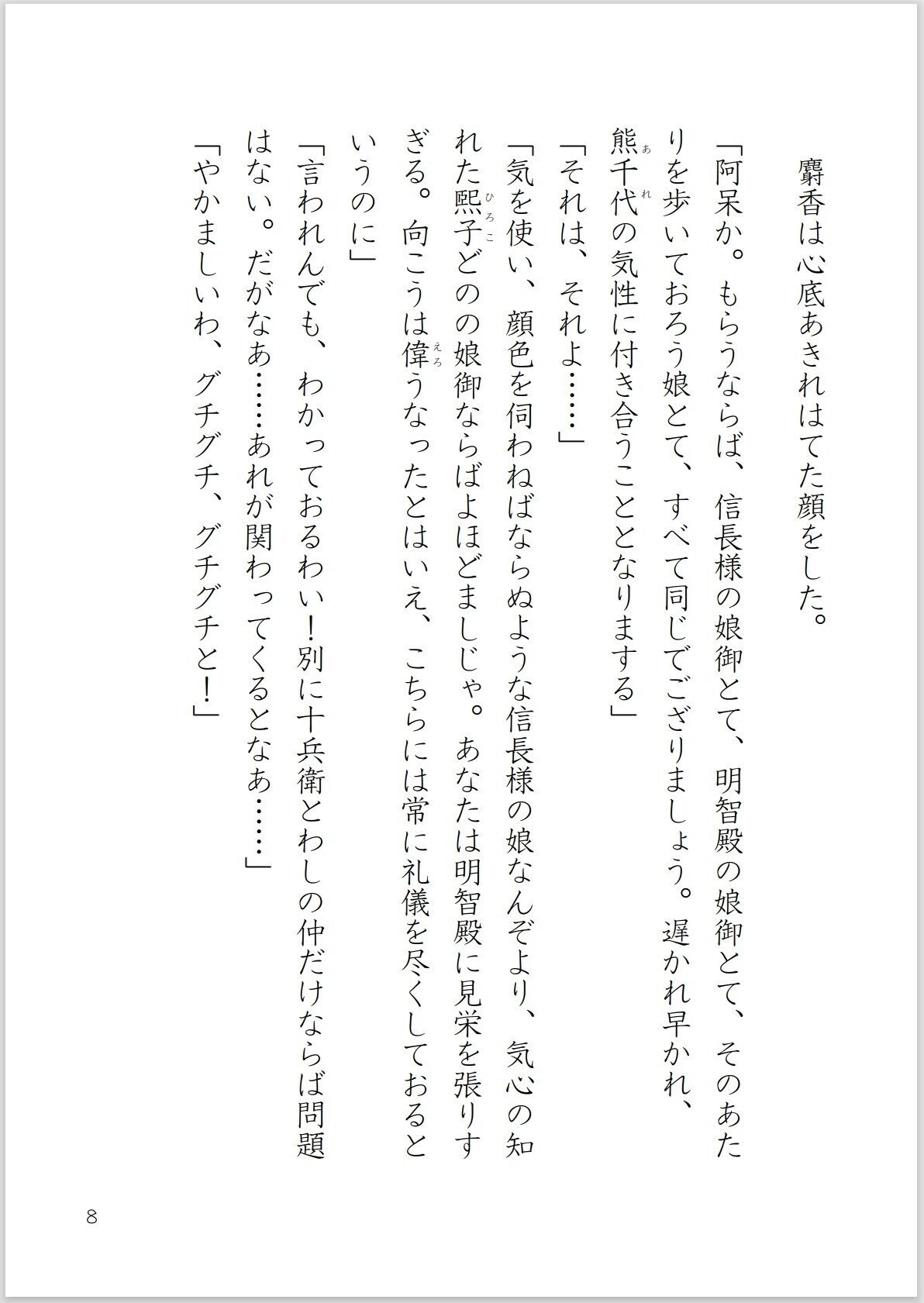





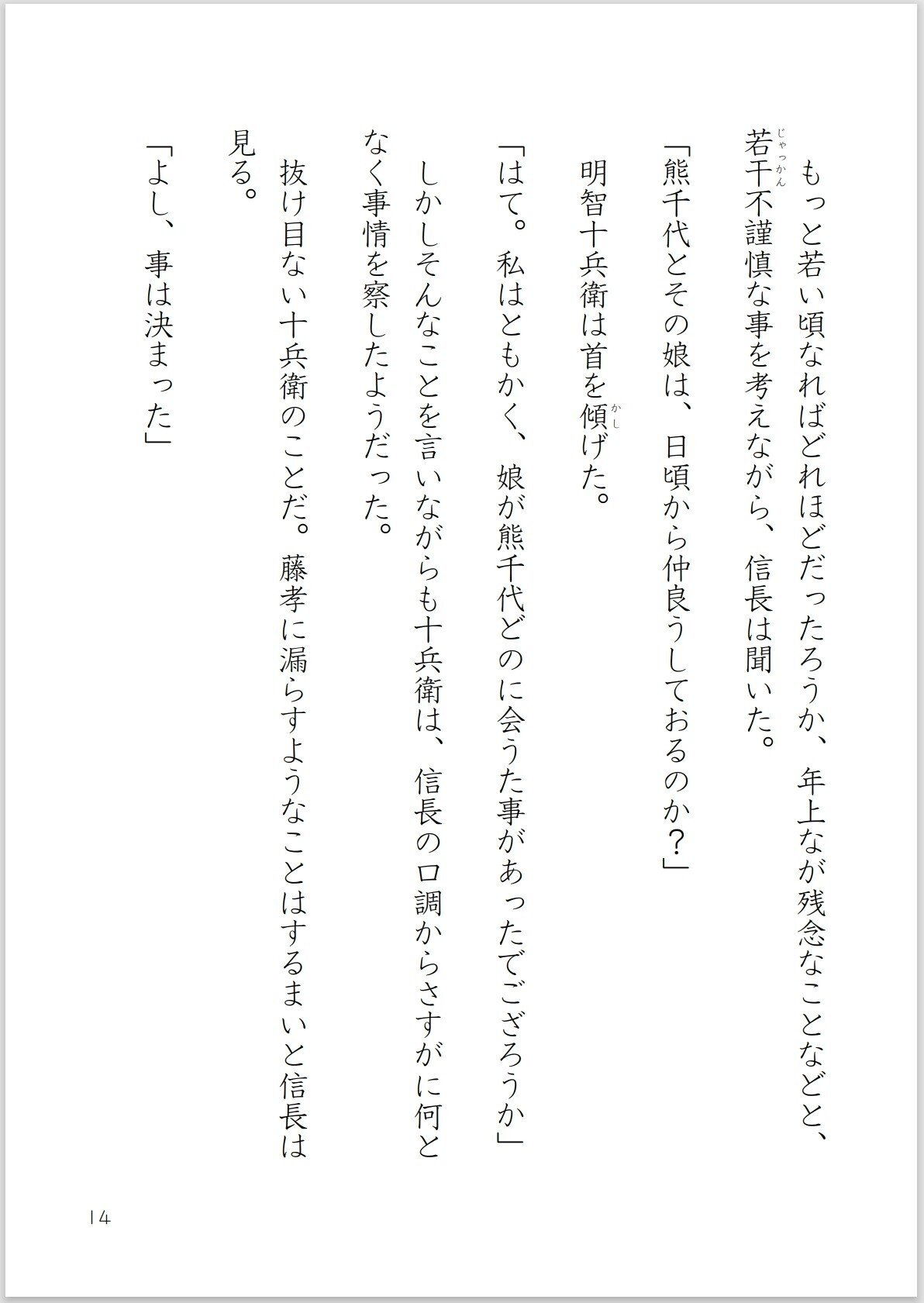



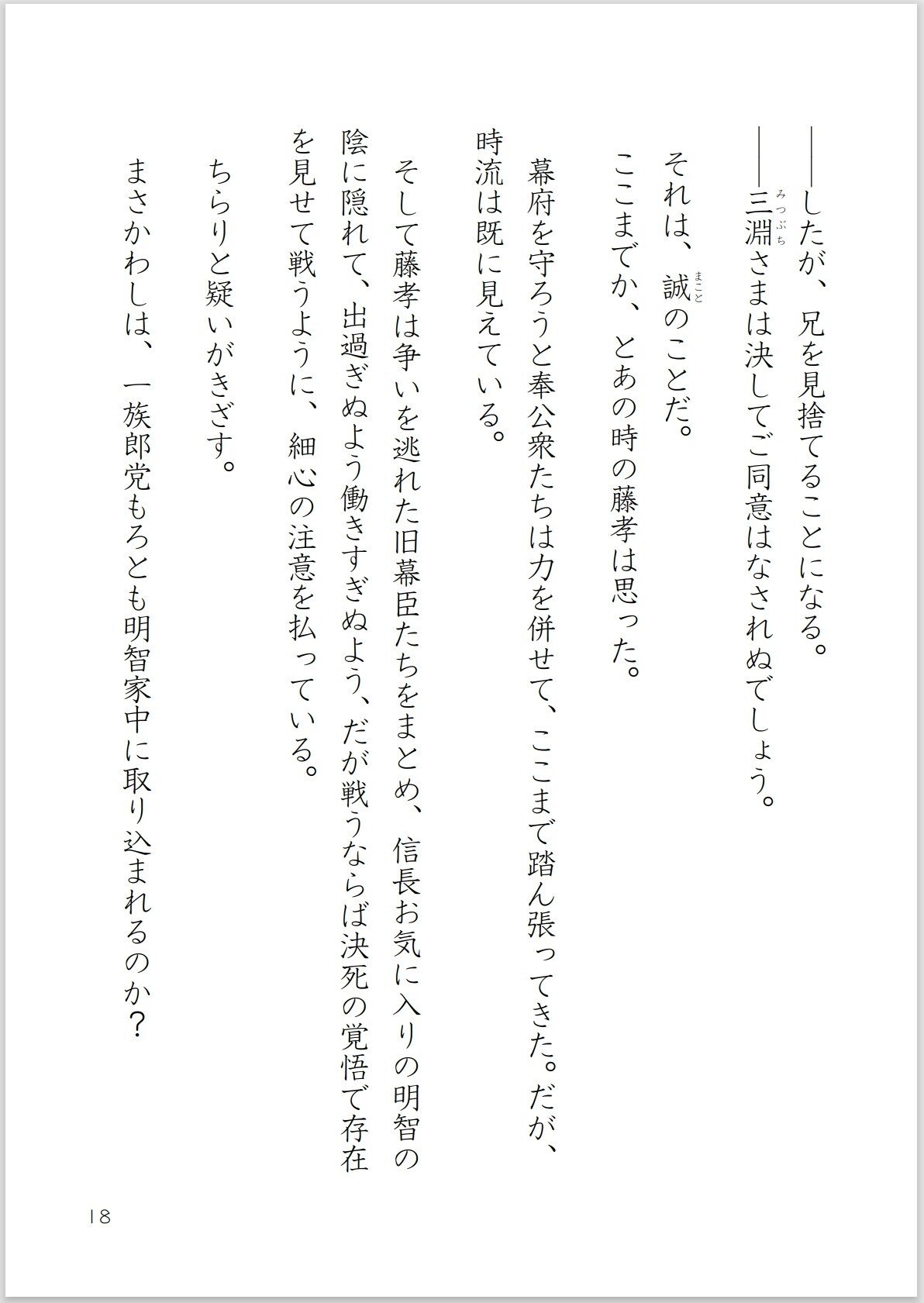






児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
