
篝火(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 19)
※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。
篝火
その日、長岡の城下町の大きな街道沿いには、よい匂いのする薪を置いた篝火が並んだ。夕闇が落ちる頃、次々に火が点され、ひとつひとつに蛾が群れてちらちら揺れる。
城の中で珠子を待つ忠興は、緊張で今にも爆発しそうだったが、ただ珠子に恥ずかしくない婿であるためにとその一念だけを胸に耐えている。まるで戦の前だ。
小声で父と米田宗堅が話しているのが聞える。
「輿は三挺とのことですな」
「まあそんなものだろう」
戦費を多く割く必要があるこの時代において、武家の婚礼支度としてごく一般的ではあるが、今の明智家の財力なら派手にしようと思えば出来るはずだ。実際、支度金はかなりのものであるのに、十兵衛は押しつけがましさを与えぬよう、こちらの懐具合に気を使ったのだと藤孝は考えた。そして明智家の影に隠れ保護のもとにある現状を思って少ししぶい顔をした。
神経過敏で全身耳のようになってしまっている忠興は、その会話を漏れ聞いてふと不安になる。
この婚礼の部屋一つ取っても父母が必死になってそろえ、忠興本人も口出しをして恐ろしく細かい部分まであれこれと整えたが、やはり壮麗な坂本とは比べ物にならない。珠子がどう思うかより、忠興自身がいやだった。何としても戦果を挙げ、なおいっそうの働きをもって家を盛り立てねばならぬ!
家を盛り立てるとは領地を広げることであり、要はどこに攻め入り、誰の首級を挙げて土地を奪おうかという話になる。血走った眼で忠興が物騒なことを考えているとき、誰かの声が叫んだ。
「は、花嫁がお着きじゃ!」
そこからはぼうっとしてしまい、何も考えられなくなった。
「えろう早くはないか?受け渡しはどうなった?首尾よく行ったか?」
藤孝が立ち上がって縁側まで出て聞くと、使いは古田左介という小者だったが、息を切らし汗をふきながら今度は正確に喚いた。
「三井寺のあたりまでお着きじゃ!」
「なんじゃまだぜんぜん途中ではないか」
腰を半ば上げかけた藤孝は苦笑して、ぬか喜びでさぞがっかりしたであろうと息子を振り返った。米田宗堅とふたり、顔を覗き込む。
「白目をむいとる」
「この調子で今日は最後までもつのか?」
◇
──これからそなたは、新たな生活に入らなければならぬ。
輿の中で揺れながら、珠子は婚礼前の控えの間で、父の訓戒を受けた時のことを一つ一つ思い出していた。
「ひとつたずねるが、もし父が仕方なく忠興殿を処断せざるを得なくなったらそなたはどうする」
珠子はとっさに返事が出来なかった。
あまりにも明智と細川の距離が近いため、そのような事態など心の片隅にさえあがったことがない。ただちにきっぱりとした返事を返すであろう、次姉のお聡のようにできない自分を恥じた。
「我等は、戦に行き人を弑するのが勤め。武人はどこかで、人であることを棄てねばならぬ」
父はまるで、自分自身に言いきかせているようだった。
「たま、時の運、戦の勝敗ではない。もっと大きく、世の流れの行く末を見定めたるとき、肉親の絆を棄てても為すべきことを成さねばならぬ時が来ることもあるのだ」
「心得ましてございまする」
父の言葉を承った珠子はふと、頭を上げて尋ねた。
「わが夫も、いつかそうする時が来るやもしれぬということでざいますか?」
答えはない。
父が答えないのか、と珠子は思った。
それが、見えているからなのかどうか、珠子にはわからない。めっきり予言めいた言動をしなくなった父の姿は、昔よりやつれて白髪もふえ、額も広くなっている。身の回りの世話をする女たちはいるし、側室も置いてはいたが、美しい坂本城は空虚だった。何かとても大事なものが欠けてなくなってしまった。別のもので埋めようとしてもかなわない、もう二度と戻って来ない何かだった。
父の訓戒を終えた珠子が表屋敷へ移動すると、そこには供をして明智家から細川家へ異動する者たちが待っており、ひとりひとりの挨拶を受けた。
侍女たちの筆頭は小侍従で、他はそれぞれが名乗りながら祝いの言葉を述べ、珠子も声をかけた。顔を見知った女衆たちの最後に、白髪混じりのいかつい武士が物々しい出立ちで進み出た。
「そなたの警護を頼んだ。丹波の出身で、剛勇の武士だ 」
「河北岩見と申しまする」
聞けば五十六の年でもう老年に近かった。よく見るとこの男は片眼がない。眉の下でつぶれて歪んでいた。
「その眼は?」
好奇心に耐えかねて珠子がたずねると、男は恐縮したように頭を下げた。
「かような醜き姿を可憐な姫様にお目にかけるは恥ずかしき仕儀なれど、お許しなされて下さりませ」
戦の最中、目の上に矢が刺さったのだと言う。それで生きているものなのかと、珠子は眼を見張った。岩見は受け渡し役とは違い、細川家に入ってずっと珠子の守りを努めることになるとのことだった。傷を負い年を取った河北にとっては傷病後の慰労なのだろう。そして慶事において彼の強運に肖ったかと思われた。珠子は元気に語気強く言う。
「ちっとも醜いことなどない。立派に戦った勇士の証拠ではないか」
そしてふと思い付いて笑った。
「岩見はわたしのな、いちの家来なのじゃな!」
岩見は深々と礼をした。
「姫様に生涯を捧げてお仕え申し上げまする。この岩見の片眼が開いておる限り、誰一人近付けは致しませぬ」
語気には心がこもっていて、武骨で容易には動かされない丹波武士の心に、若い珠子のかけた言葉が深く染み透ったとみえた。
河北岩見は約束を守った。
だが互いに遠くより姿を見かけることはあっても、対面で言葉を交わしたのは、珠子と岩見にとってはこれが最初であり、次が最後となった。
◇
大きな儀式を間近にして、常に騒がしい勝竜寺城は、さらに輪をかけて大変な大騒ぎとなっていた。赤子や弟妹たちはやはり静かにはなりきれず、いよいよ近づいたという時には、とうとう離れのお堂にまとめて押し込められてしまった。
今年十になる妹の伊也が赤ん坊を抱きながら、兄弟の筆頭として挨拶をするため、忙しく支度を整えている頓五郎に大声でたずねた。
「兄上、いったいどんな方なの?」
頓五郎は顔を曇らせ、生返事をした。伊也はおとなしいたちの娘ではないから、煮え切らない次兄にすぐに眉を逆立てた。
「いつもそればかり!いい加減、教えてくれても良いではない。何しろ、何十万石もあるという坂本城のお姫様であろう?豪華に着飾って、お供をたくさん引き連れてくるであろうな。つんとして気取っておって、母上と喧嘩になったりせぬのかな?」
「母上はもう何度も会っておられる。大丈夫だろう」
「いつ?まことに?」
「あちらの奥方が亡くなられたときに、弔問に伺ったり、お手伝いをしに行ったりしておったようだ」
「それでどんな方なの?」
頓五郎はどうしてもうまく説明が出来なかった。
あの奇跡のように美しい少女は何だか近づきがたい。底知れぬ切れ長の黒い瞳でじいっとこちらを見られると冷や汗が出、顔は白くなり、舌はこわばってしまう。何の緊張もしないどころか心からうちとけている兄が不思議でならなかった。
「しかも兄上と仲が良いのであろう?」
伊也が大きな声でいう。
「あの兄と気が合う女子がこの世におるなど到底信じられぬ。きっとものすごく怒りっぽくて威張っておって、とんでもなく意地悪な、蛇のようなひとに違いないわ!ああ恐ろしい。この城はどうなってしまうのだろう」
頓五郎兄はお行儀が良いから悪口を言わぬだけで、あの生返事はきっとそうなのだ、違いない!
伊也は少女らしい小袖をさっとふり、顎をつんと高く上げた。一人でそう決めてかかっている。
◇
別れに際して、最後に残ったよすがを振り切るかのように、明智十兵衛は言葉を継いだ。
「そなたは人には分があると言い、人の命は平等ではないと言う。大きな話をするときには、自分のことは考えぬもの。いつか我がこととして受け取る時が来たとき、そなたは自分で言うたことの意味を知るであろう。だがそなたはこの明智十兵衛の娘だ。常に備えよ。また、いざというときの覚悟を忘れるでないぞ!」
「この世界のこと、おたまはまだようわかっておりませぬ」
「学び、考えるのだ。細川どのは稀代の知恵者、きっとそなたを導いてくれよう」
なぜもっと父上と話をせなんだのであろう。珠子は悔やんだ。あれこれに紛れて、日々を無為に過ごしてはいなかったか。今ほど父のそばにいてあげたいと思ったことはない。
いざ出立しようという輿の中から、珠子は弟たちが柱の陰に立ちすくんで、目が真っ赤になっているのを見た。小さい十次郎は兄の十五郎に抱きつき、どういうことなのか説明してくれるようせがんでいる。十五郎がうつむいて何か言うと、わっと泣き出して輿を追おうとしたので、皆に総出で止められている。姉上!姉上!と悲痛な声が聞こえ、やがて遠くなった。さような心弱いことでどうする!と奮い立たせるように心うちでつぶやく、珠子の目も赤くなりかけていた。
大好きな父上、自慢の父上だが、お忙しいから自分だけが甘えたいだけ甘えることなどできなかった。父上のようなおひとはどこにもおられないから、おたまは父上のようなおひとを望もうなどとは思わない。
もう二度と、この坂本をわが住処として、帰る場所と成すことはない。
琵琶湖へ張り出した欄干に佇んで、湖水を眺める父上のお姿を見るのもこれが最後となるだろう。
◇
「若、これをお持ちになられませ」
米田宗賢の息子、若い米田助右衛門是政が、横から新調の扇子をすべりこませ、忠興は受け取って懐にぎゅっとおしこんだ。
「おめでとうございまする」
忠興のこわばった顔が、米田是政には少しだけ緩んで笑顔のようなものを見せた。あまりの緊張を少しでも和らげようとする是政の心遣いがありがたかった。
数年前に米田是政がもらった嫁は珠子の母方の親族だったので、忠興ともゆるやかな遠縁になる。仲睦まじいので有名な若妻と共に、是政はあれこれと世話をやき、忠興も頼っていた。
その是政の後ろから、親族代表として列席せよと言われた頓五郎がおそるおそる顔を出した。兄の顔がきゅうっときつくなり、頓五郎はやっぱりかと心内にため息をついた。
正直、頓五郎はたまに垣間見る容姿以外に珠子をよく知る機会はなかった。兄は頓五郎が少しでも近づこうものなら、鬼のような形相で追いたててしまう。
伊也の言ではないが、彼女は気の荒い兄にいつも仲良く寄り添っている。あんな完璧な輪のごとき調和の世界を、騒がしい勝竜寺城で保てるだろうか。
一応、若夫婦の局(部屋)のようなものはあるが狭く、別棟を急いで増築しようとしているものの、どうやらその費用は明智家の懐から出ているらしい。
それでなくとも派手で華々しい小姓の生活、信長は安土に移ってからなお奢侈だ。兄のやれ小袖だ仕立てだ茶器だと、いったい誰がそれらを用立てていると思うのかと母の麝香はいつも愚痴っていた。
父も兄もべったり甘えて、日向守殿はそれを黙って許しておられる──そう頓五郎は考える。父上は昔、日向上殿の上役だったとか。兄上は右府さまのご寵愛をよいことに、当たり前みたいな顔をしておるが、わたしは何だか恥ずかしい。
美しい坂本城は、頓五郎にとっては憧れでもあり、我が家や安土よりも身近な場所だった。仲良しの十五郎も好きだし、穏やかで規律正しい日向守どのを心から尊敬している。忠興が安土を立派と思い、居心地がよい場所であると考えているように、今の頓五郎にとっては坂本がそれだった。
自分なりに見る世の中の力関係や世情からも、いつか自分は明智家に仕え、明智の嫡男である十五郎のそばで共に暮らすのだろうなと漠然と想像している。それがもっとも自然に思えた。
わたしは別に上様に目をかけられておるわけでもないし、長じたら心をこめて明智殿にお仕えしよう。
これは次男の目から見ての、心からの素直な気持ちだった。
◇
花嫁の生家から婚家への受け渡しは滞りなく終わり、輿は細川家の領地に入っていた。
最初は前に待つ不安よりも、後ろに残してきた心残りの方がはるかに大きかった。それが坂本が次第に遠くなり、長岡が近づくにしたがって珠子の心は自然と夫となるあの少年の方へ移っていった。
彼女にとって忠興は、年も同じで気の合う、仲良しの男の子以上ではなかったような気がする。遊ぶ中で無邪気な少女のしがちないたずら心から、忠興の喜びそうなことを文に手すさびで書いたりすることはあっても、珠子はそう簡単に自分の心底をすべて明け渡すような性格でなかった。
ただ、忠興の珠子を思う態度、表情、心、ひっきりなしに届く手紙、それらすべてから彼の心が流れ込んできて、珠子としてもそれが決して嫌ではない。気心の知れた相手に嫁ぐことが出来る自分は、やはり幸運なのだろう。
沿道は人通りがあり、立ち止まってお嫁入りじゃあ、と嘆息がはっきりと聞こえた。
思わず身を乗り出して物見窓から外を伺う。自分たちを眺める長岡京の見物人を珠子も見物しながら、久しぶりに見る外の世界に胸がときめいた。
輿のすぐそばを、あの隻眼の河北石見が今にも刀に手をかける気迫で片目を光らせて守っている。彼のお役目の一つが、いざ、何事か起きた時の介錯、つまり彼女を殺す役目も含んでいるのだということを、今の珠子は知っている。覚悟、覚悟と申すのは死の覚悟をせよと申すのだ。胸の小刀を押える。
私の守り刀は、私を守るのか、それとも命を奪うのだろうか。
母に約束をした時から、毎日毎晩仏前に祈り死を思った。
夫に殉ずるのが妻の務めであることは知ってはいても、父に聞かれたそのとき、夫なくして生きてはおりませぬ、と言下に答えることができなかった。
若さと生きようとする本能が、現実に迫る恐れと反発を感じた。そうだ、何事があったとしても、一矢も報いずに終わるは口惜しい!
臆病者であるものかという気負いとは別に、珠子は死の覚悟に見合うだけの理由が欲しかった。珠子の中に、忠興に殉じて共に自害せねばならぬ、その理由がまだ見つからない。
珠子は考えるのが好きだった。自分なりに答えを出せる問いも、そうでないものも、ひたすら納得を得るまで考え続けた。
岩見はお供つかまつりますと申していた。
どこへ供するのだろう、まるで死出の旅路だ。この一歩はどこへ続いているのか?結婚とは何?
時は仲秋、まだ色濃く残る夏のむせるような暑さの中、日が落ちかけても、土がむきだしの地面から立ち上る陽炎の余韻が残る。炎が揺らぎ、薪が爆ぜる音がする。嗅いだことのない香りがする。
道行く婚礼の行列の周囲、また松明に煌々と照らされた花嫁を待つ勝竜寺城には、どことなく血の匂いが入り交じった気配がした。
物見の人々が不安な顔で見上げる月が奇妙に赤い。
およそ婚礼に似つかわしくない禍々しさと妖気を漂わせている。
急に闇が上から押し伏せるように降りてきて、沿道の人々の顔が変わった。怪しい炎が沿道に無数に並び、一気に百鬼夜行の様相を呈してきて珠子は輿の窓から息を飲んだ。道に並ぶ松明の上に、そんな場所にあるはずのない鬼火が列をなして揺れている。提灯をもつひとつひとつの手が怪しい白さに変わる。
物の怪の花嫁行列だ。灯火が窓から入って、中にいる花嫁の影を映した。それはとても人間とは思われない異形に変貌していて、珠子は目を見開いて凝視した。まさか、物の怪なのはわたしか?
突然、身動きしてこの輿から降りて走りたい衝動にかられた。
父もそうであるように、珠子は物静かに見えて内面には忠興に負けるとも劣らぬ激情を秘めている。ただ、それを隠す鉄の意思も持ち合わせていた。じっと耐えた。極限が訪れるまで。
たとえ今、衝動にかられて飛び出したとしても、その足で走っていきたい先はあの懐かしい利かん気の元気な少年の所であるような気がした。
◇
十兵衛光秀は奧の部屋でひとり座っていた。
ひとり、またひとりと、滞りなく儀式の進捗を伝えに来る使いが来るたびに、ついに最後の宝を手放したという実感が迫って来る。
寂寞の念は如何ともしがたく、十五郎や十次郎が肩を落とし、涙を見せているのをしっかりせよと諌めることもできない。
母親と同じく十兵衛も心配していた。
器量が良いのを喜ぶとしても、程度の問題だ。過ぎたる女の美貌はわざわいになっても、得なことなど何一つない。賢くあっても評価してもらえず、努力をしても何を成しても、容貌が美しいゆえと陰口を叩かれる。心配であるのか、本音では手放したくないのか、自分でも判断がつかなかった。
頑固で執念深く、扱いづらい所のある娘だ。会わせてみれば奇妙に気が合い、睦まじく遊ぶ幼い二人の姿、癇性の熊千代が珠子の前ではおとなしく幸せそうであり、娘もやっと友達が出来たうれしさに打ち解けているのを見た時、この少年ならばたまを一生涯かけて愛し抜き、守り、幸せにしてくれるのではないかとかすかな希望を抱いた。
あの少年は父の藤孝であろうとも容易に動かせない。一度珠子を守ると決めたならてこでも動かないだろう。
お岸はつらい思いをしておるようだし、お聡は織田家の連枝の中に入って気苦労しておる。せめてたまにだけは気の使うことのない、伸び伸びとした生活をさせてやりたい。
輿が細川家に無事届き、完全に彼の手を離れたという、最後の知らせが届いたのを確認して、明智十兵衛はため息をついて、立ち上がった。ふと小侍従の顔が浮かんだ。
あれ自身が強く望んだこととはいえ、本当にこれで良かったのだろうか。
◇
齢わずか十六の少年と少女、本人たちはまだ知りようがないが、夫婦になろうとするこの二人のためにこれからどれほど多くの血が流れるか知れない。藤孝の訳もないように見える不安と不吉な予感はある意味的を得ていたのであって、人々が命を失うのに善悪や罪のあるなしなど何の関係もないことを証明してしまう暗い未来が待っていた。
新郎である忠興も妖気をちらっと感じたような気がしたが、彼にとっては血の匂いなど気分が高揚こそすれ忌避する対象ではないので、平気な顔をしていた。落ち着くとさえ思う。
何かを引きずるような音がして、廊下から白いほっそりした姿が現れたとき、へびだ、と忠興はぼんやり思った。
あの白蛇、坂本の最奥部に鎮座して守られていたご神体が今、儀式とともに移し変えられてゆく。
不安も焦燥も、喜びさえ吹き飛んで、忠興はすべての感情やしがらみから自由になった。目が開かれ、被り物の下の珠子の顔が緊張に満ちているが落ち着いているのを見た。可愛い、いたずらっぽい微笑みが細い鼻梁から切れ長の眼に抜ける。さすが明智の娘、度胸があるとぼんやり思った。
もうひとり、外から婚礼の怪をじっと見守っている少年がいる。
顔は見えぬ花嫁の身体にまとわっている瑞気が帯状になって形を変え、彼には常に見えていた兄のそれと追いつ追われつ、じゃれあいながら睦み合っているのを見た。ねこが遊びながら戦っているのを見るのとそっくりだった。
頓五郎は、ああ、二人はやっと一緒になれたのだな、とぼんやりと考えた。
第十九話 終わり
画像(ルビつき・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。
▼以下の画像では、加筆した縦書きバージョンを画像ファイルでお読みいただけます。





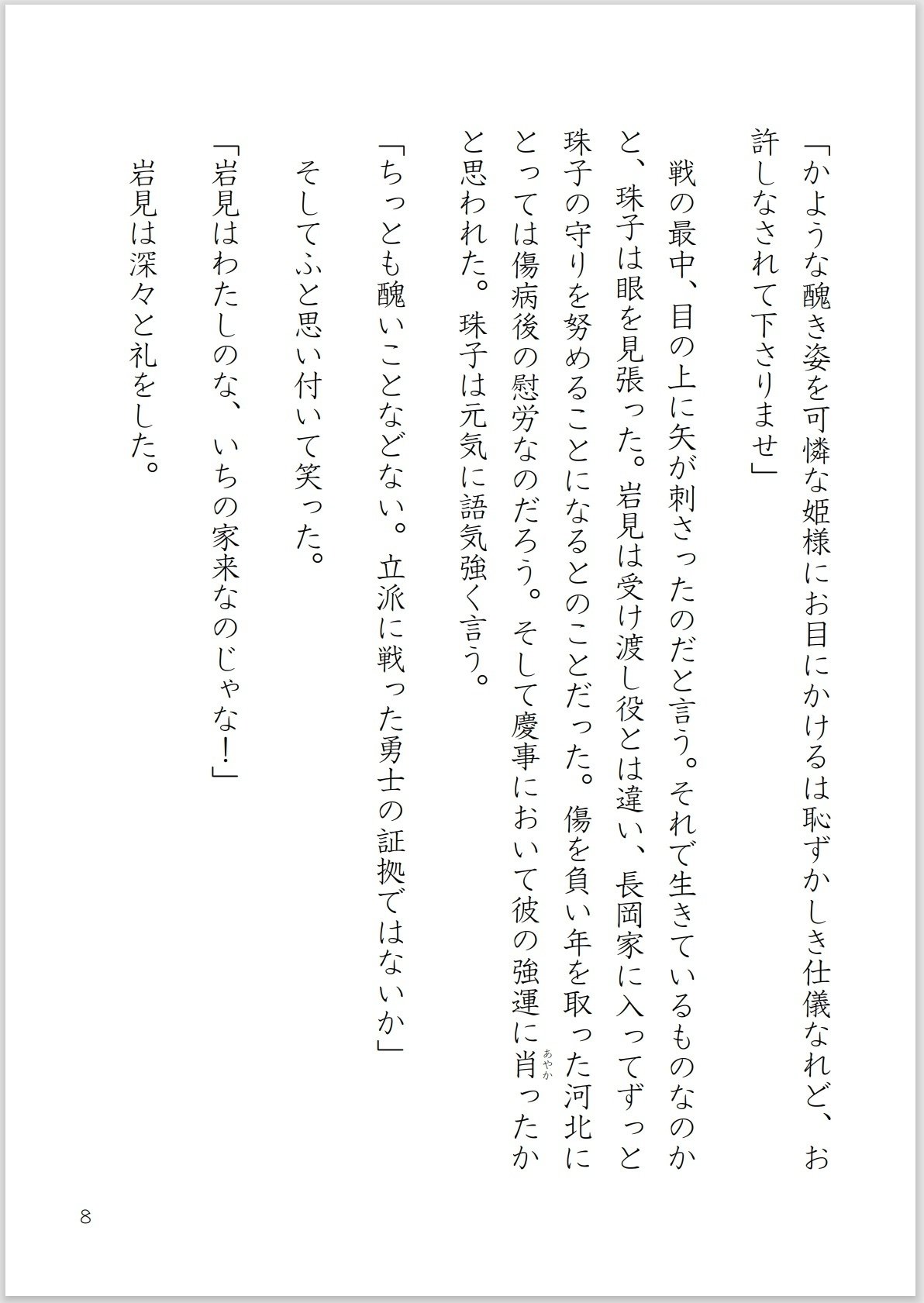








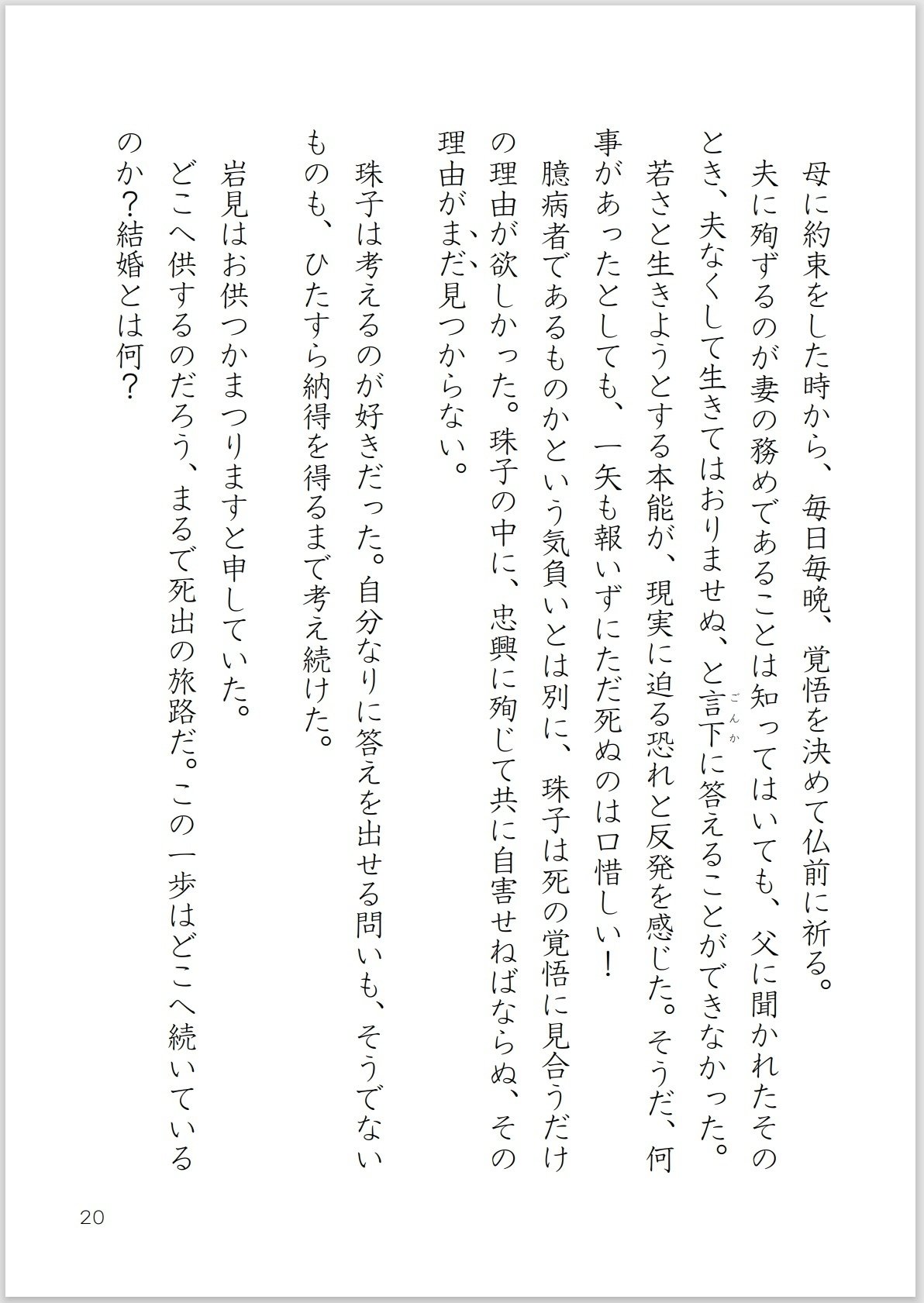
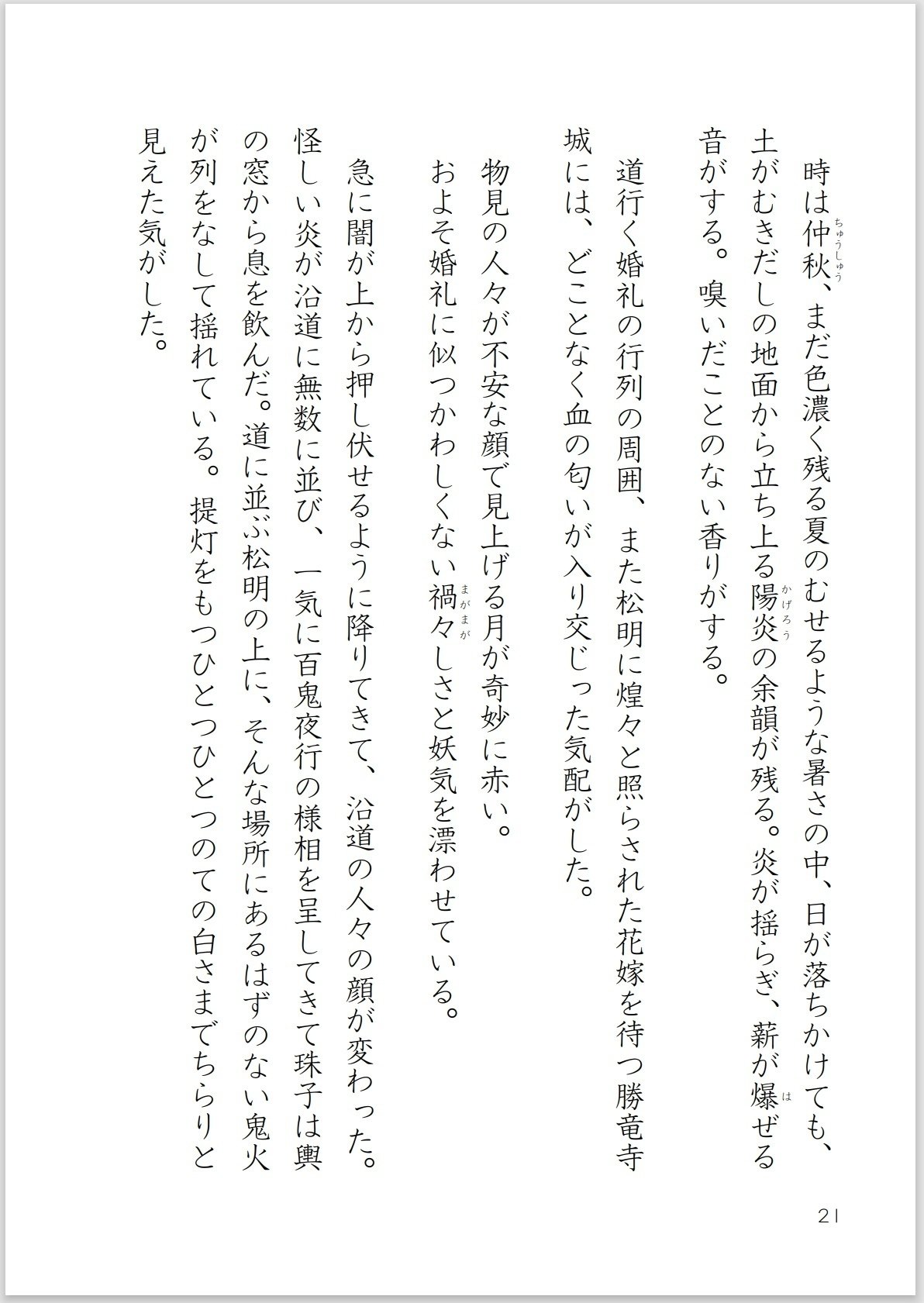



画像。本型。見開き版。











児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
