
熊千代の奇妙な願い(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 2)
※(縦書き画像を公開しています)
熊千代の奇妙な願い
織田家の小姓、細川熊千代は岐阜城で行われた茶器判別の勝負に勝ち、信長にたいそう褒められた。山頂部にある信長のごく私的な奥の間にまで呼ばれ、直々に言葉をかけられる。
元亀四年(1573)、十一月の冬の日のことだった。
横に控える信長の嫡男、勘九郎信重(信忠)もにこやかに言う。
「父上もさぞ、鼻を高くされるであろうな」
熊千代は頭が床につくほど、勢いよく一礼した。些か元気が良すぎるきらいはあるが作法にすぐれ、十歳の若輩とは思えないほど堂々としている。物怖じを知らない性質だった。
「褒美を取らそう。何が良いか?」
信長はぱらりと広げた扇子で顔を隠し、熊千代の頭の上にからかうように囁いた。
「どうだ熊千代、おなごでも良いのだぞ」
扇子がゆっくり差し向かいの部屋向こうに見える、きらびやかな侍女たちを指す。
「好きな者を申さば、|くれてやらぬでもない」
庭と廊下を隔てた扇子の向こうの内緒話は聞こえずとも、何かしら気配を察したものと見え、微かな騒めきが起きて、侍女たちは笑った。ふと吹き付けた風に花びらが舞い散るような華やかさだった。
「戯れでも面白うございます」
信忠も、父の余興に笑った。
十六歳の清々しさ、勇猛でありながら父信長よりも穏やかで優しさの残る雅な青年だ。
四カ月ほど前の七月に元服したばかりで、熊千代もその時に信忠の小姓に選ばれた。城勤めにもやっと慣れて来た頃で小姓姿が初々しい。こちらは小さいが凛とした顔立ちで、だが主君よりもずっと癇の強い面構えをしている。
「さて、熊千代は誰を第一の美女と思し召すのかな」
「どうだ、目当てはいるか?遠慮のう言うてみよ」
「はい!」
顔を真っ赤にして、熊千代は頭を深く下げた。はっきりと言う。
「明智の珠子殿を頂きとうございます!」
もう一度、悦に入ってぐるりと侍女たちを見渡していた信長の顔から笑顔が消え、困惑というよりは虚を突かれてぽかんとする。それから嫡男と顔を見合わせた。
「ここに左様な者はいたか?」
「おりませぬ」
明智の娘とな。珠子だと?
信長は首をひねる。突然この少年が何を言い出したのか、よく合点がいかなかった。
「それは明智十兵衛殿の娘御であろう。確か三女と存じます」
静かに背後に控えていた信長づき小姓の万見仙千代が口を添えた。
「年も十で熊千代と同じ、たいそう利発な娘御と評判でございます。細川と明智の間柄、日頃から仲良うしているのではありませぬか?」
それで合点がいった。
己れが想いを寄せる娘を嫁にもらいたいと、そう言っているのか。
この戦乱の世にあって、婚姻は特別な意味を持ち、意思や恋愛の入る要素はない。子供としても奇異な頼みだ。
だが仙千代の言うとおり、明智と細川(この頃は長岡)は特別に近しい。
お互い苦しい浪人生活を共に支え合い分かち合って、共に将軍義昭を支えて信長と引き合わせてくれた。義昭と信長の仲が破綻してから最後は、手を取り合うように共に将軍家を離れて信長に付いた。切っても切れない縁で結ばれている両家だ。
互いに館を行き来して親しく見知り、想い合っているのではないかと信長は推測した。悪い縁談ではない。支障があろうとは思われなかった。
「その娘と何ぞ、約束でもあるのか?」
感情が激しやすい熊千代の顔が真っ赤に膨れ上がり、気色ばんで怒ったように言う。
「父上は、だめじゃと仰せられました」
「与一郎(藤孝)は反対か。十兵衛が断りでもしたか?」
「明智様は何も知りませぬ。父曰く、そもそも縁談とは親が決めるもの。子供から言い出すなど言語道断の振る舞いにて、また珠子殿は明智様にとっては特別な娘御、お前なぞより余程よい先を探しているであろうとの、仰せでした!」
頬がぴくぴく動くのを隠しもせず、熊千代は真正面を向いてはっきりと大声で言う。この直情的な少年が信長は可愛いと思った。
眺めていると、顔が歪んで不安いっぱいの顔をしている。十ともなれば、そろそろ縁談の話が入り始める頃だ。
若年なりの精一杯の恋をしているのであろう。
「わかった。心配するな。わしに任せておけ」
付け加えて言った。
「与一郎には熊千代が頼みと漏らさぬ故、お前も黙っておれよ。やはりこいつはな、ちと外聞が悪い」
◇
「それは親父どのが怒るも無理はない。はしたなき真似と言われても仕方がないぞ」
主君である信忠に諭されて、熊千代は膝頭に拳をつき、首は落ちそうなほどうなだれていた。
訓戒されても信忠は優しい口調なので、親に言われるような反発はないのだが、その分、胸に沁みる。親元を離れ岐阜城に入って、まだ間もない新参者だ。
かつて斎藤道三の城であった稲葉山城に入って信長は名を岐阜城と改めた。金華山の山頂とあって冷えるので、冬には部屋に大きな黒漆塗の火鉢がしつらえてある。
目に見えて悄気ている眼前の小僧を前に、片手を火鉢の上に伸ばしながら信忠は考えた。
たとえ許婚となったのがまことに心映えよき、我が意に添う姫であったとしても、戦となれば離縁せられるし、親戚となった親兄弟とも戦わねばならぬのだ。
この世はそういう宿縁となっておる。
当時は立派な大人と見做されてはいても、信忠と言えどまだ十六歳、数えで十七の若い少年だった。
元服式は遅いと言われた程だ。父の信長が、慎重に器量を見極めていたことを信忠は知っている。烏帽子をつけ前髪を落とした時に、本当ならばその時に嫁御料の輿入れもあるはずだった。
信忠の許婚は、武田信玄公の娘である松姫と定められていた。
ちょうど一年前の今、三方ヶ原の戦があってから輿入れの話は途絶え、破談になったと見なされている。
武田方はこの信忠の元服式にも沈黙しており、父も無視する姿勢を崩さなかった。松姫との縁はまことに絶えたのであろうか。
「嫁取りは大事な政の一つなのだからな」
信忠は半ば自分に向かって言っていた。
たしなめながらも、この熊千代の落胆ぶりがあまりにも顕著なので、可笑しくてならず、自然と笑顔が湧いてくる。
私室で寛いでいる信忠の前に、いくつかの反物がある。いま彼が選ぼうとしているのは正月に松姫へひそかに送るつもりの品だった。
義母のお濃の方の計らいで文をやりとりするうちに、不思議な心が萌してきた。松姫の筆遣いを見るのが何時しか楽しみになり、敵同士となった今もこうして、秘かな文のやり取りを続けている。戦乱の世ではあるが、正室に迎えるのはこの松姫ひとりと、信忠は固く心に決めていた。反物を前に、ふと声が出る。
「どちらが良いかな」
「こちらが綺麗でござりまする」
相変わらずこの熊千代は、小さいくせに趣味が良い。
今日の茶器比べは、信忠の小姓たちと信長の小姓たちの間で争った。ごく私的な余興だった。熊千代が最後に選んだのは左側の小茄子、多々ある中でも特別の名器だった。
信長になぜこれを選んだのかと聞かれて、熊千代は無邪気に答えた。
「良し悪しは何もわかりませぬ。これが好きでござります」
目の肥えた信長の小姓を下した熊千代のおかげで、信忠も面目を施した。
だがな、私も祝言があげられていないと言うのに、お前だけ我が身の恋の成就を望むというのは些か浅慮だぞ。
そんな無礼もこの熊千代の少年らしい可愛さに紛れてしまう。
信忠は若干、皮肉な調子でからかった。
「それで、文のやりとりでもしておるのか?一人前に」
「文などしたこと、まったくありませぬ!」
「ただの一度もか」
「はい!」
そこは威張る所なのだろうか。
「十兵衛殿の所で会うたのか。坂本の城でのことか」
「いいえ」
「その娘はおまえのことを知っておるのか」
「まったく、知りませぬ!」
これはどうも、おかしなことになってきた。
◇
信忠からこの話を聞いた信長もまた、狐につままれたような顔をした。
「何?会ったこともない。話したこともない。その娘は熊千代を知らぬ。どういうことなのだ?」
「熊千代は嘘を言うような者ではありませぬ。ただ数か月ほど前に寺でたった一度だけ、垣間見たのだそうです」
「いったい、どんな娘なのだ」
「さあ…」
信忠も仙千代も首をひねっている。
「熊千代にはこのこと、父上と私、仙千代だけしか聞いておらぬ所で良かった。決して誰にも言うまいぞと釘をさしまいた。……したが、如何致しましょう?」
わがままと捨ておいても良いのだろうが、いつも元気いっぱいの細川の小僧が肩を落とすしょぼくれた姿に、信忠も哀れを催すほどだった。
信長は息子に聞いた。
「熊千代は信忠が小姓。おまえはどう思うのだ」
信忠は父がやはり同じこと、主の祝言が棚上げであるのに構わぬか、と問われているのを感じた。父にはこのように、思いもかけず心遣いが細やかな所がある。
信忠はもう一度松姫のことを考えた。
自分も、文は交わしているとはいえ、一度も顔を見たことのない娘をこのように恋うている。もし、苦しい想いをしている者がいるのなら、叶えてやりたいと思った。
「よい縁かと存じまする」
熊千代は運が良い。
信長はことのほか機嫌がよかった。去年の今頃はどうなるかと思ったが、その後、信玄の身に何らかの異変が起きた。甲斐一円ではかたく秘されているが、死んだという噂もある。結果、信長は無事に諸悪の根源である義昭を追放することが出来た。
勢いを得た信長は続いてついに浅倉、浅井を討ち取った。長島の一向一揆もねじ伏せた。
何もかもよい風が拭いている。
信長は幸せだった。誰にも、何でも言うことをきいてやりたい気分だった。
藤孝には山城国長岡一万石を加増したし、明智には近江五万石を与え、家臣団の筆頭に置いた。
この正月に公表しようとしている、いくつかの話と一緒に進めてやろうと心に決める。
熊千代一人追加したとしても、何ほどのこともない。あの勇猛な坊主は、深く恩を感じて、よい若駒に育つかもしれぬ。そうだ、そろそろ甥の津田坊にも嫁を決めてやらねばな……。
このとき、肝心の明智珠子の意思などどこにもなく、命じられれば当たり前のように従うと、この場の誰もが疑いもしない。
◇
翌年、正月の年頭挨拶に、信長は筆頭家老の林佐渡守(林秀貞)を通して率直に切り出させた。
「細川殿、上様はそなたの嫡男を明智殿の三女と目合わせよとのご意向なれば、万事よしなに整えらるるよう」
細川与一郎藤孝は居住まいを正すと、思わず眉を寄せた。
寝耳に水と驚いている顔を見て、林は奇妙に思う。事情など何も知らなかったが、敵同士でもなければ知らぬ仲でもない両家なのに、このような反応はいささか心外だった。
相手は静かに礼を返して重々しく言う。
「熊千代は、手のつけられぬ生来の乱暴者にて候えば」
「はて、御辞退したいとでも申せらるるか?」
「まことに恥ずかしき限りながら、並の剛勇(乱暴)ではありませぬ」
「辞退とは……上様の仰せであるのに」
林は困って左右を見、扇子を出して仰いで、さらに尻を動かした。
藤孝は背筋を伸ばして、真正面から家老に向かい合った。
亡き将軍義輝公に若い頃から近習し、すぐれた剣の才を持つ屈指の武人、育ちの良さは隠せない。尾張の田舎武者には気が引ける。
「ご家老様は、十兵衛殿のご息女をご覧になったことはおありか?」
「いや」
「噂は届いておりませぬか」
「噂とは?」
「天性の麗質にて、無上のたおや女なれば、熊千代ごときにはまことにもったいなきことと存ずる。もし何かあれば十兵衛殿に申し訳が立たぬ」
何かとは何であろうかと思うが、熊千代のことならば林も多少は見聞きしている。
もしその明智の三女が無上のたおや女であるというならば、細川の嫡男、熊千代は無類の短気な癇癪もちで有名だった。家中では持て余されていると聞く。
かといって、殿上ではそれなりに弁えて勤めているように見えるし、そこらじゅうに暴れ牛がごろごろしているような織田家中のこと、誰がとは言わないが、例えば……森家。
それに比べれば熊千代など影に隠れてさほど目立たない。
しかし、そこまで言うならよほど心配なのであろうと、林は一度この話を引き上げた。
◇
「与一郎が断るとな?」
信長が不愉快そうに扇子で床を叩いたので、鋭い音が部屋に響き渡った。
近習も思わず首をすくめる。
「何をばかな、熊千代はそんな慮外者ではない。情もあれば性根もある。短気や乱暴など欠点のうちに入らぬわ!それを躾るのが親の勤めであろうが、再三行って重ねて命じよ。主命と心得るよう説得すべし」
どうにも解せぬ顔の林が首を捻りながら退出するのを見ながら、信長は藤孝の顔を思い浮かべた。
明智十兵衛はともかく、細川藤孝について信長も思う所がある。信長を京へ招いたのも、義昭の企みをいち早く知らせて来たのもほかならぬ藤孝なのだ。
有難いと思いもすれば、真っ向から楯突いて裏切るというよりも、形勢を見た挙句にいち早く優位の方に向かうと言った類い、機を見るに敏と言いえば聞こえはいいが、どこかで油断のならぬ奴という心もある。
その点、実直さ、誠実さ、綿密な計算に基づく確実な実行力といった点では、信長ははるかに明智十兵衛光秀の方を買っていた。
明智は命じれば従う。必ず、やってのける。
あの男は物静かで控え目ながらも何処か、いざとなった時、爆発的に発揮される秘めた容易ならぬ力がある。
この畿内の勢力はどこまでも深く、細かく根を張っていて、あまりにも深すぎて誰の手も届かぬほどだ。藤孝には血筋、生まれの柵があった。本家の兄と袂を分ち覚悟を示したのは確かだが、本人も一歩引いて慎重に徹しており、何が何でも頭ひとつ抜けたいとは思っている様子はない。
信長にはどうでもいいことだ。
使える者を使う。だが何でも良いというわけではない。
◇
藤孝は居城である勝竜寺城に戻り、奧屋敷に足を踏み入れた。
「熊千代は戻っておるか?」
久々の休みをもらい、岐阜城から宿下がりしているはずの熊千代だが、若い家老の松井康之の困った顔を見、いつも熊千代についている有吉四郎右衛門がいないのを見ればすぐにわかる。
親の顔を見れば説教されるのがいやで、城内にもさして寄り付かず、すぐに姿を眩ませてしまうのだ。
勝龍寺城は平城でさほど広くない。
藤孝の百芸を好む性分もあって、限られた部屋にはありとあらゆる書物と芸事の品が至る所に積み上げられていて、いつまでたっても片付く気配がない。
妻の麝香を呼びにやろうかと思ったが、思いとどまる。
自分から奧へ向かった。
廊下を渡る前からもう聞こえていたが、歩くほどに騒音が大きくなる。廊下の真ん中に伏せて号泣する七歳の頓五郎(後の興元)が現れた。張り飛ばされたと見え頬が真っ赤になっており、唇に血が滲んでいる。さらに奥に進むと、怒って真っ赤な顔をした娘の伊也がおり、これは五歳だ。
「兄上が、兄上が!破って!投げた!」
と、父の裾に取り付き、手習いの紙を指差して父にしきりと訴える。
騒動の際に突き飛ばされたらしき二歳の赤ん坊は庭に落っこちており、頭にはこぶが出来ている。乳母が必死にあやしているがこれも上体を弓なりにのけぞって、胸が張り裂けるほど号泣していた。
この凄まじい騒ぎの真ん中で、藤孝の妻の麝香が、鬼のような形相で仁王立ちしている。
「なぜ左様に乱暴をするかと雷をくれたら、飛び出して行きおりました」
「また、これらを泣かしたのか」
がっくりしたように藤孝は肩を落とした。
信長家の家老に応対した水際だった礼儀正しさなど、完全に消えている。熊千代が小姓勤めをするようになってからここの所、城内が静かであったのが嘘のようだ。
その場に座り込み、深いため息をついた。
「あれが信忠さまのもとで、上手くやれているというのがわしにはどうしても信じられぬ」
今度はまた、一段と厄介な話が舞い込んで来た。
藤孝は困り果てた顔でつぶやいた。
「嫁取りだと?あやつがか?天地がひっくり返ってもありえぬわ。わしには想像もできぬ!」
第二話 終わり
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。
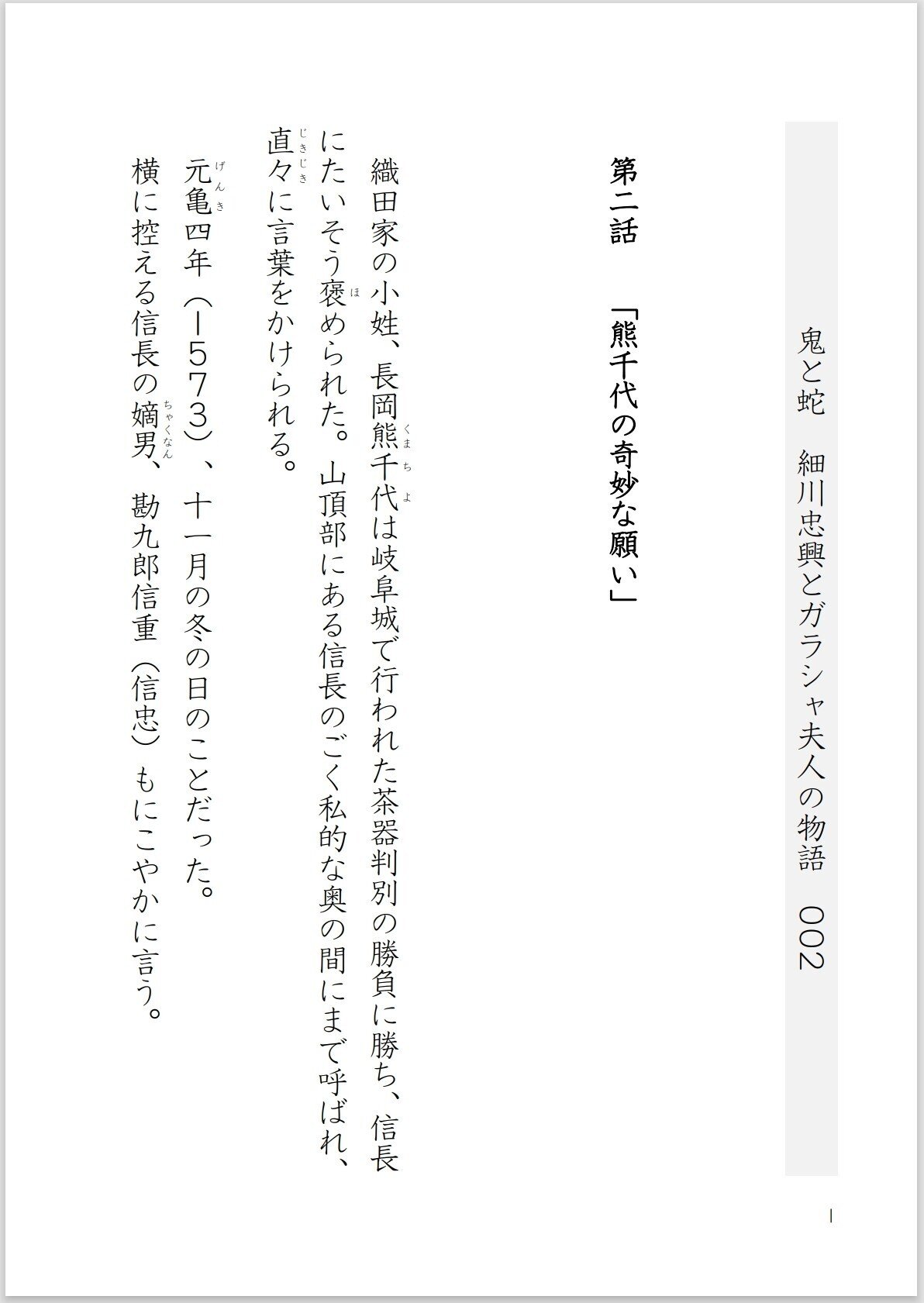








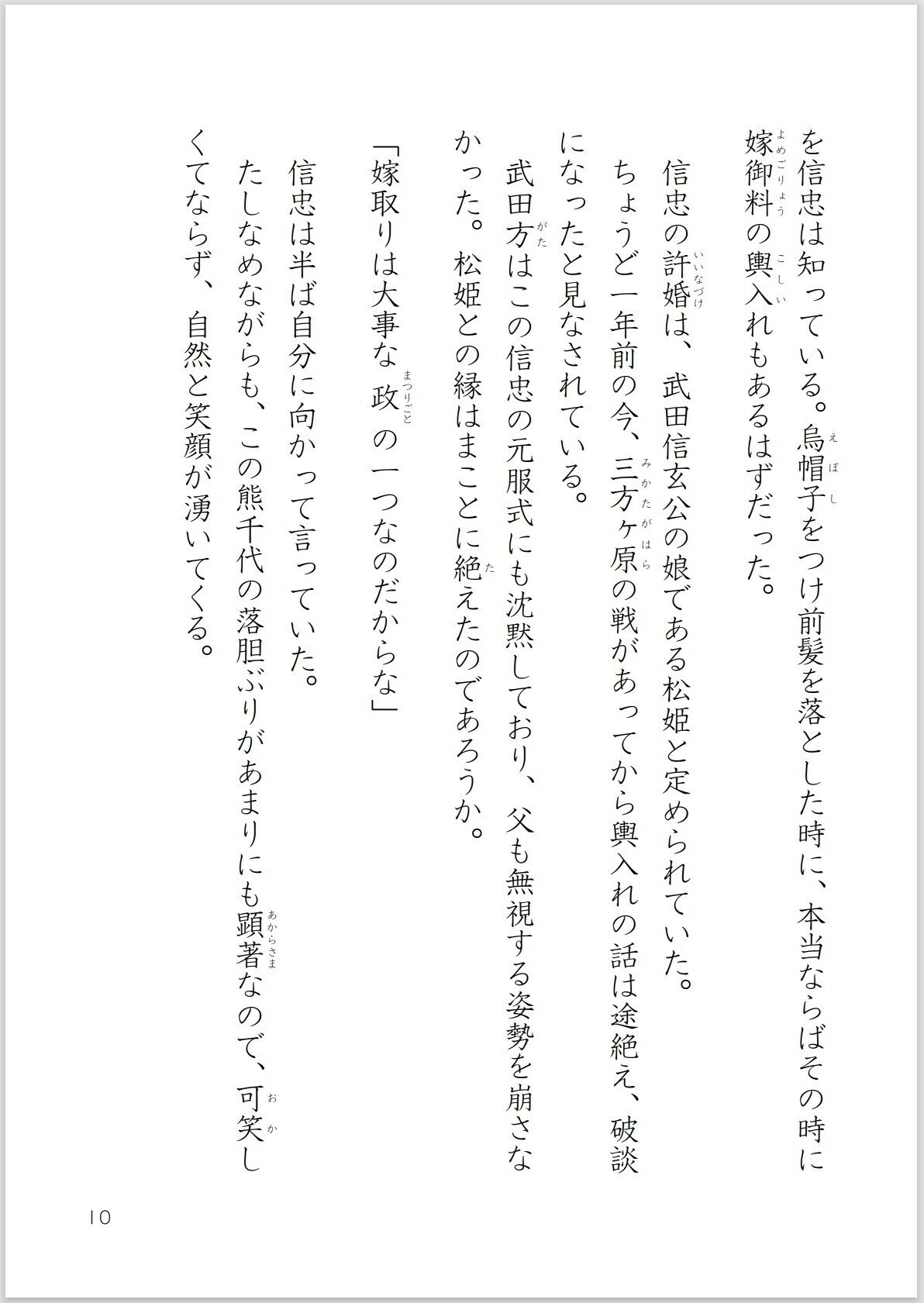
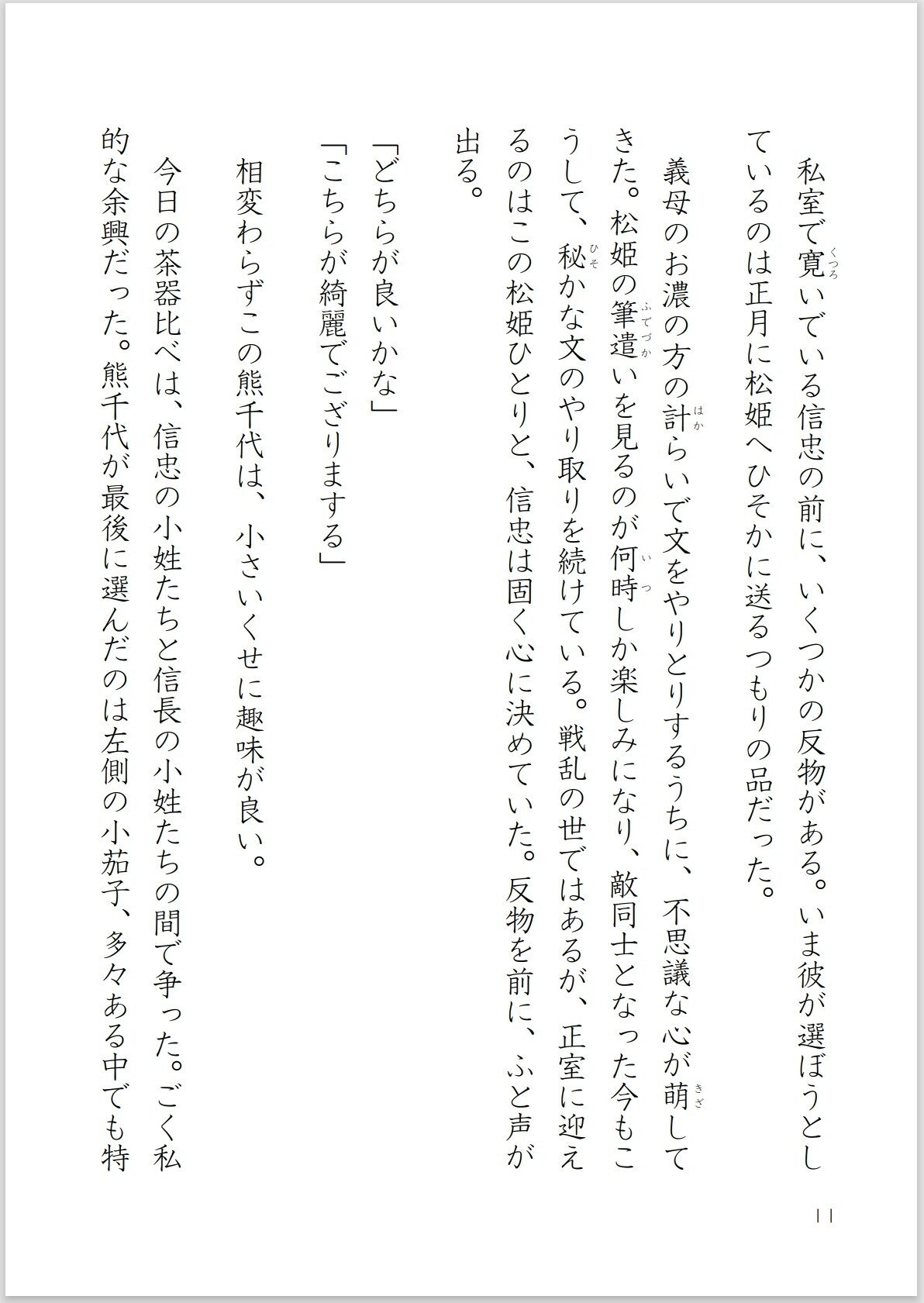
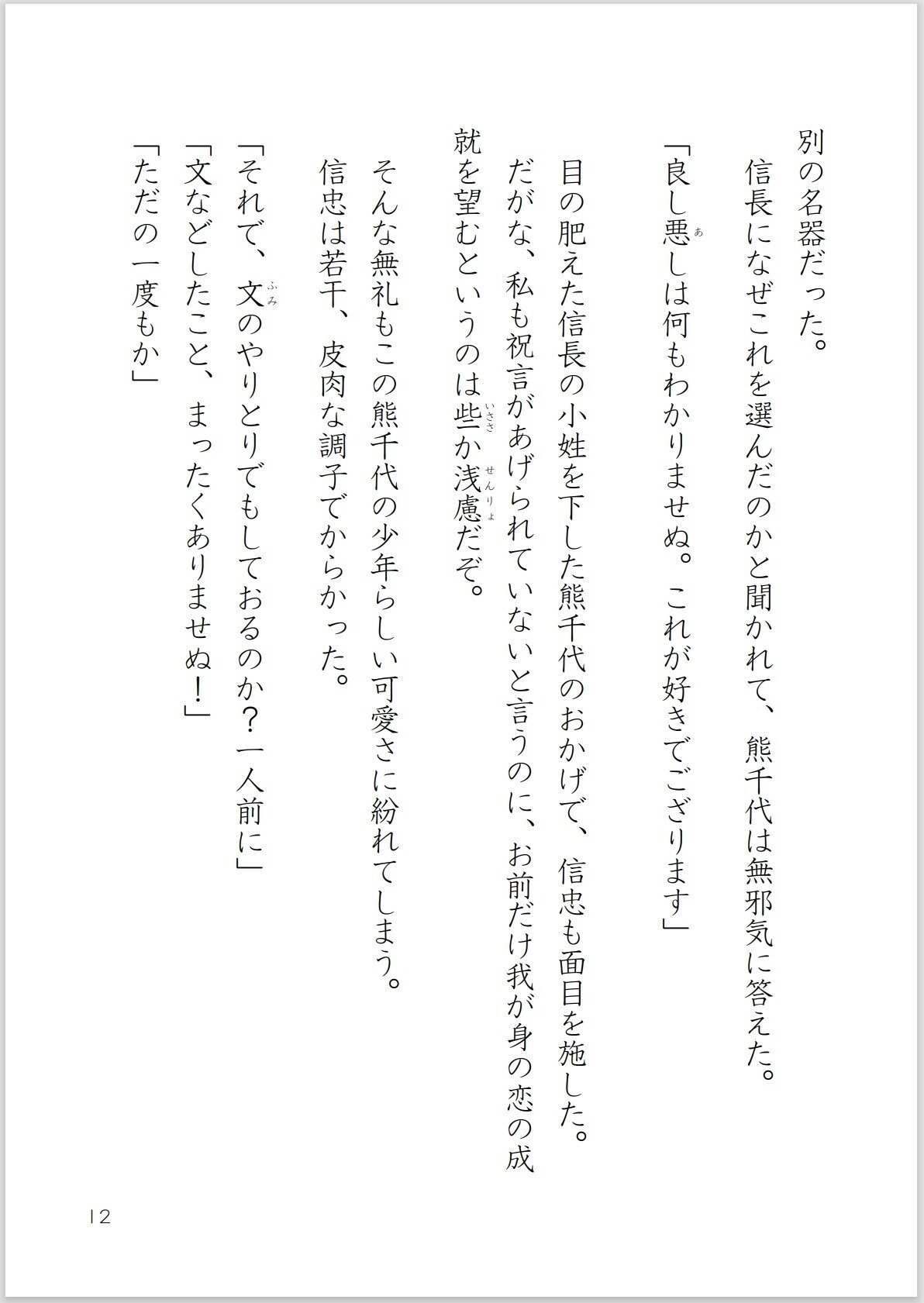
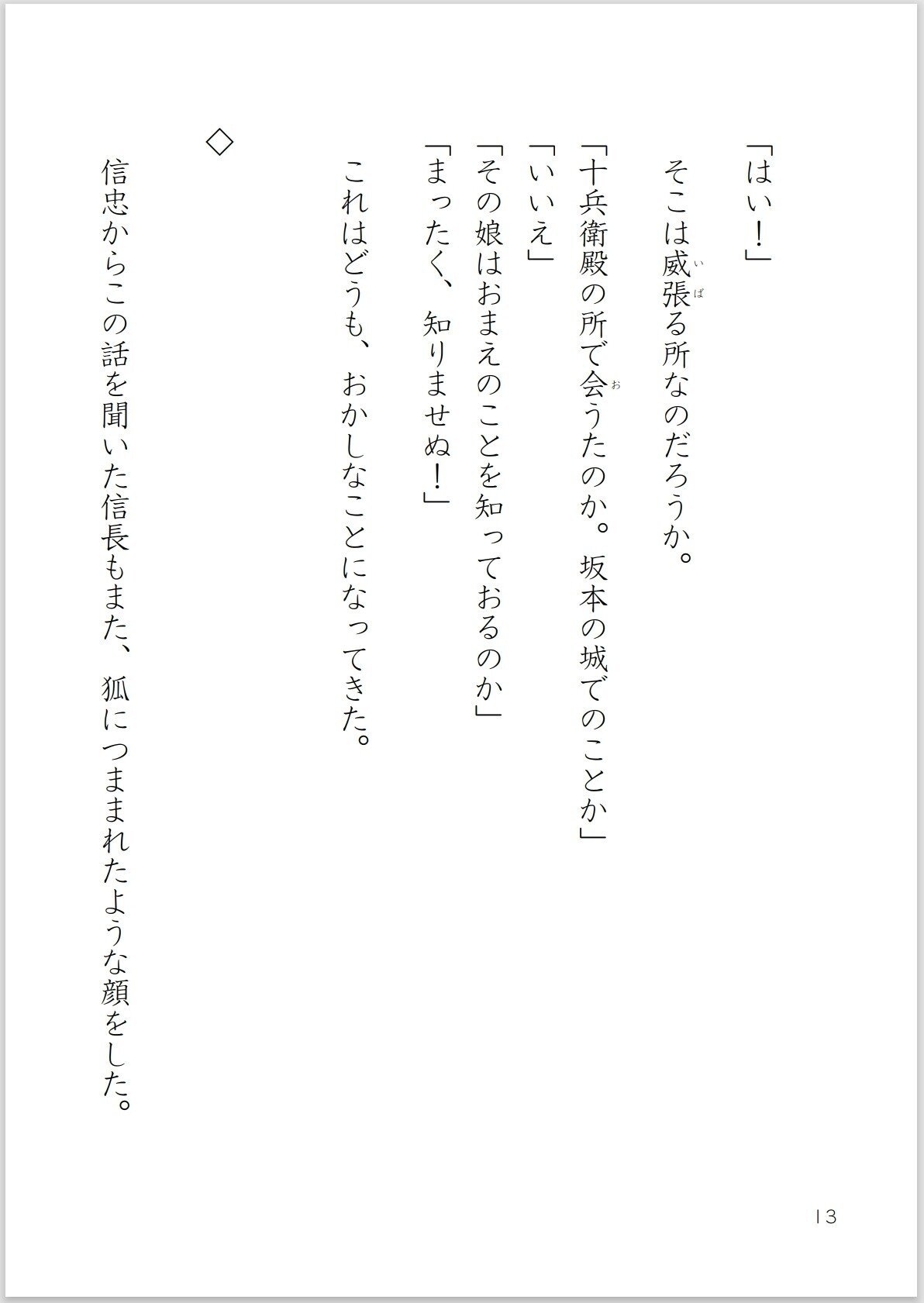








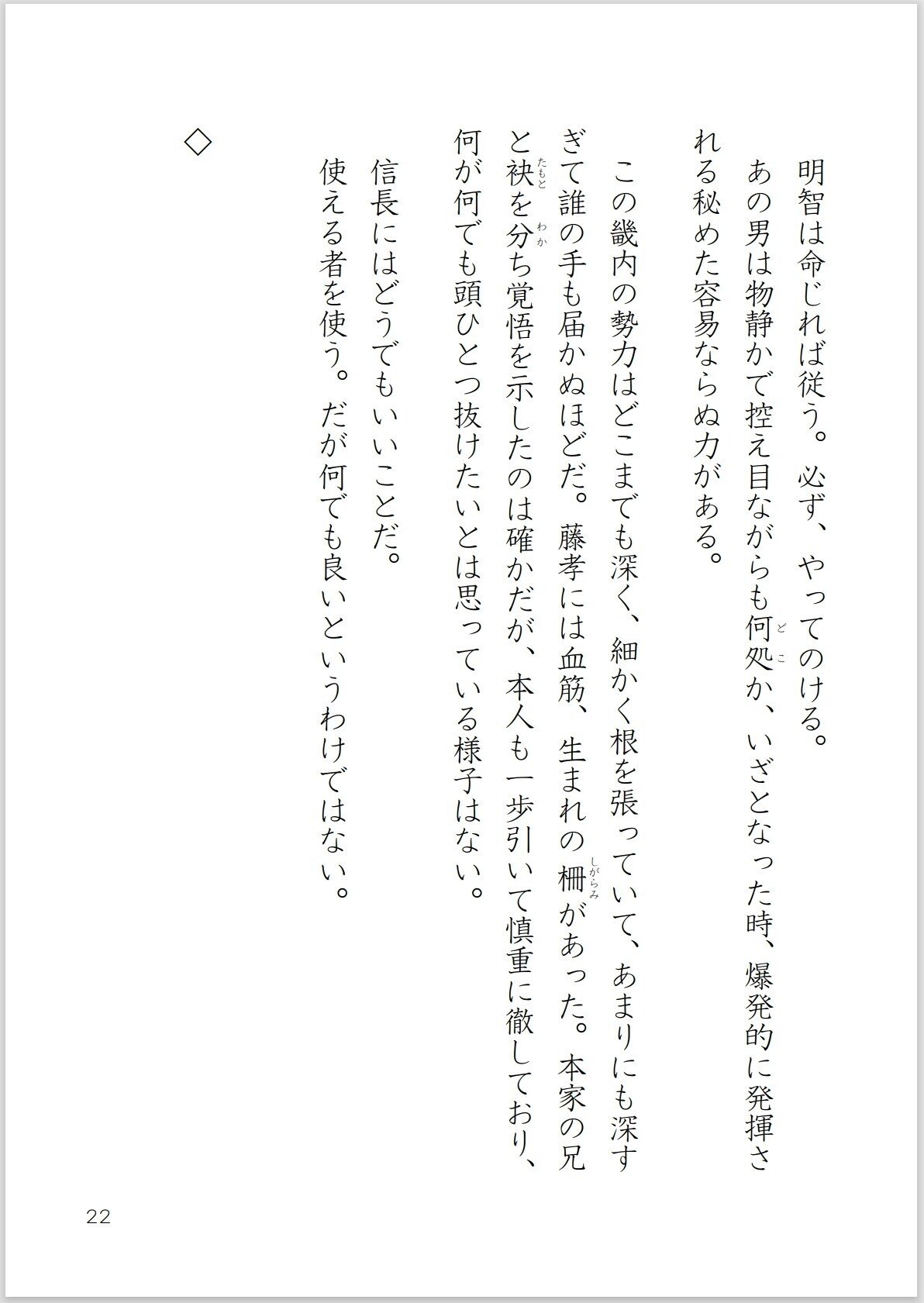




児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
