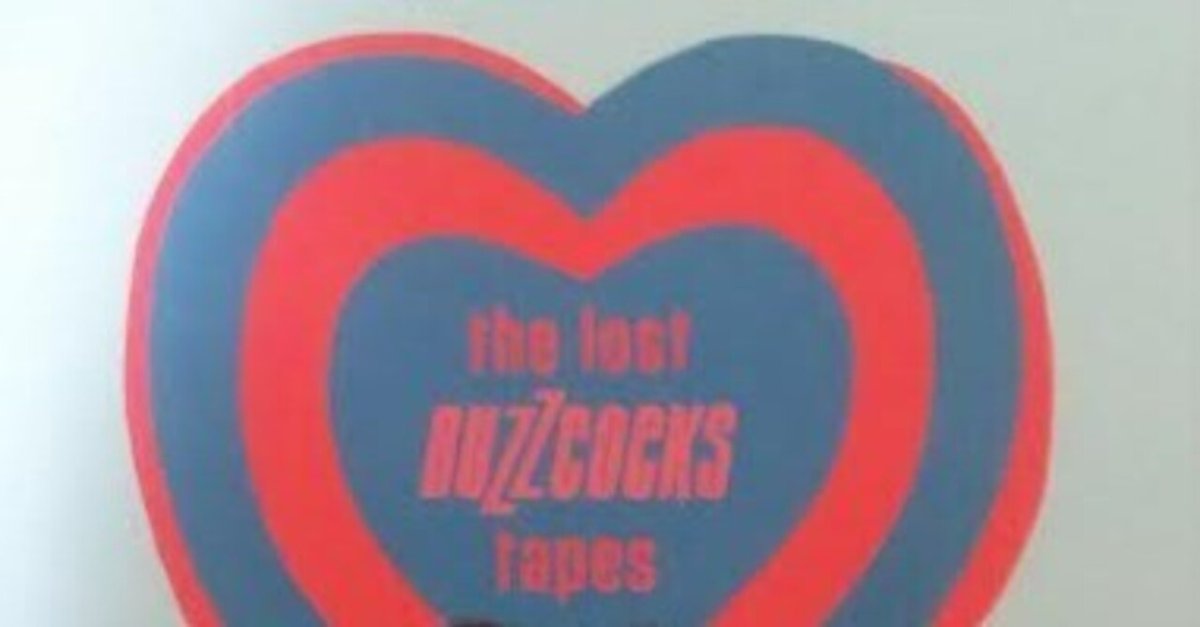
ピート・シェリー/ルイ・シェリー『ever fallen in love-the lost Buzzcocks tapes』(18)
ラヴ・バイツ
LOVE BITS
スタジオ・アルバム
録音:1978年7月26日~8月6日、オリンピック・スタジオ、バーンズ、ロンドン
発売日:1978年9月22日
プロデューサー:マーティン・ラシェント
スリーヴ・デザイナー:マルコム・ギャレット
レコード内溝のメッセージ:「切っ先鋭く壮観也」(サイド1)「何が?」(サイド2)
アルバムはどこでレコーディングを?
オリンピックだね。もうその頃にはなじみの場所になっていた。デモはマンチェスターのハルムに面した、ディーンズゲイト地区の外れにあるアロウ・スタジオで録った。
レコーディングには一週間位しかかからなかった。僕らは絶好調だった。
テープ・オペレーターが業務日誌をつけていて、盗み読みしてた。ホント面白かったよ。レコーディング初日の一曲目にとりかかってる最中だったんだけど、テープ・マシンが爆発しちゃったんだ!でも楽しくて明るい現場だったね。
レコーディング中はどこに滞在していたんです?
ウェスト・ロンドンの、チズウィックにある家に泊まっていた。でっかい家でベッドルームがたくさんあって、芸術家の大先生はこういう所に住んでらっしゃるんだと思ったね。皆,いろんなモノを持ち込んでね。スタジオの中には帽子の入った大きいバッグを持って行った。最初の何日かは皆で帽子をかぶっていたっけ。
レコーディングとミキシングの合間に短い休みが取れたから、リチャードや友人何人かと初めてヨーロッパ-パリを旅した(外国なんて行ったことなかった)。パリにはそれから何回も行った。いい所だよ。フランス録音のことでよく憶えてるんだけど、九十年代初めにパリで収録したライヴ・アルバムのことなんだ。ネット草創期で、僕らはアルバムの宣伝にネットを使ってた。収録から一年かそれ位後にワシントンで共同の記者会見をやることにした。インタヴューを希望するメディアが引きも切らずでね。最初の質問はこうだった。「いつフランスに引っ越したんですか?」皆『BUZZCOCKS LIVE IN PARIS』のネット広告を見たんだろうね。
当時、ロンドンに移住しようとは?
いいや全然。北にいるときは、「かのロンドン」て、ずっと言ってたし。
イギリス・アルバム・チャートでは13位でしたが・・・・。
シルバー・ディスクを受賞して、イギリスでは6万枚売れた。何枚かシルバー・ディスクをもらった。一枚は祖母にあげて、亡くなったときにeベイに売り払った。一枚は両親に、さらに一枚は僕自身にあてがっておくことにした。他のメンバーも全員受け取ったよ。八十年代の終わりだったか、一人の若者が手紙をくれてね。彼は骨肉腫に罹って、チャリティで治療費を募る旨が書かれてあった。僕はシルバー・ディスクをコレクターに売って、そのカネを寄付してあげたんだ。[1]
もちろん、その後もアルバムは装いを変えてリイシューされてきた。CDになった今は、どうにか店の糊口をしのぐ程度だけど。
『アナザー・ミュージック・イン・ア・ディファレント・キッチン』も同じ位なチャート成績でしたけど、シルバー・ディスクに認定されなかったんですよね?
ああ、たぶんね。もしかしたらUAの策略でシルバー・ディスクにしなかったのかもね。
スリーヴ・デザインには幾分ビートルズの『WHITE ALBUM』を思わせるところがあります。
そうかい、それはたまたまだね。ビートルズを意識するようになるのはもっと後だよ。『シングルズ・ゴーイング・ステディ』の裏スリーヴを見てもらいたいね。[2]
写真はどこで撮りました?
写真スタジオでね。担当したのはクリス・ギャブリンで、前にも音楽誌用に撮ってもらったことがある。彼はロック・フォトグラファーだけどブロンディのツアー・マネージャーも務めたね。78~79年には僕らも同行した。
『WITH THE BEATLES』のカバーとちょっと似てるってよく言われるけど、ビートルズの顔はハーフ・シャドウになってて、僕らの方は顔の左右それぞれメイクの仕方を変えてるんだ。片方をより念入りに、もう片方をより軽めにメイクしている(僕らには専門のメイクアップアーティストがいた)。
インサートには写真と見紛うような、エアブラシを使ったイラストを載せてみた。ロビン・ウタラシックが手掛けたんだけど、彼はワーストThe Worstっていうマンチェスター出身の伝説的なパンク・バンドのメンバーだった。てんで演奏できない故に敬愛されたバンドだったね(何度か前座を務めてもらった。一回はクロイドのフォクシィズ、もう一回は77年10月のエレクトリック・サーカスで)。イラストに使われた僕の写真はモス・サイドにあるアレクサンドリア・パークでやったロック・アゲインスト・ザ・レイシズムで撮ったものだけど、朝の時間帯で、飲みすぎてヘロヘロだったんだ(この日はスティーヴがスティール・パルスのステージに飛び入りしたんだけど結局は引きずり降ろされたんだよね)。で、トレーラーハウスの停まってる隅っこでゲロを吐いてたら「よおピート!」って声がしたもんだから、ゲロを吐いたまんま振り向いたらロビンにパシャリ、さ。
アルバムで使ったギターは何を?
ゴードン・スミスを使った。倉庫みたいな工場でハンドメイドでつくられてるんだ。すごく丁寧な仕事をする会社だよ。今日びのギターは殆んどがまず仕様書を中国の工場に送って、中国から現物をコンテナ単位で輸送する、そんなやり方で製造されてるんだろうね。ゴードン・スミスは細かい所まで受注生産なんだ。ピックアップなんか手巻きだし。僕のギターはボディとネックが別々だったんだ。ゴード・スミスはそういう見本を色々見せてくれて、使う方はボディとかネックとか選べるようになってるんだ。直近で手に入れたのは、たぶん二、三年前だと思う。トーン・コントロールは使わないんだ。一度もないよ。使い方が判らないんだ。ゴードン・スミスのギターは「こもり気味な」音に設定してある。ヴォリュームのいじり方がまるで判らないから、オン・オフのスイッチをいじるだけなんだ。ヴォリュームとトーン。この二つのコントロールは使わずにオン・オフのスイッチでヴォリュームを調整するんだ。カスタム・メイドのギターってすごく高価なんだろうけど、ゴードン・スミスのギターはその点良心的だよ。
当時、ジョン・クーパー・クラークのバンド、インビジブル・ガールズThe Invisible Girlsに参加したとか?
参加はしたけど、レコードのどこなのか判らないんだ。真夜中のスタジオ・セッションだったんだ!一発録りじゃなかった。マーティン・ハネットは何度もくりかえしテープを流して、僕はそのテープに合わせてプレイして、マーティンは自分の気に入ったフレーズを拾っていったんだ。スタジオには人がひっきりなしに出入りしてて、ちょっとしたパーティみたいだったよ。[3]
『アナザー・ミュージック・イン・ア・ディファレント・キッチン』の跡を継ぐのは大変でしたよね。複数枚のアルバム制作の契約をしたとき、どうすれば曲作りを続けられるかと思いませんでしたか?大変な賭けで、相当なプレッシャーがあったと思いますが。
そうだね。賭けだね。そうすることで成長できる。レコード会社はいつだって見返りを求めてくる。けどミューズの祝福はあるもんさ!
サイド1
リアル・ワールド
Real World
ソングライター:ピート・シェリー
この曲はペネトレーションとのツアー中につくったということですが。
うん。そうだったと思う。「愉快な仲間たち」ツアー中のとき。「ラヴ・ユー・モア」リリースに合わせてのものだった。ペネトレーションとは上手くやれたよ。
歌詞の内容はどういったことについてなんでしょう?
人は協力し合えば丸く収まるってことなんだ。「同じゲームに出ればウィンウィンになれる」のさ。グズグズしてるヒマはない、最善を尽さなきゃいけない。しんどいけどね!歌詞のことに戻ると、そんなに力強い内容じゃないけど、力強くあるべきだとも思わなかったね。アルバムをつくる十分な時間が僕らには与えられてなかった。さしづめ寄せ集めてバッグに詰め込んだようなものだね。
アルバム冒頭にふさわしい曲だよ。―聴いてもらえば判るだろう。ギターがハーモニクスを出し、ゴキゲンなベースラインが乗る。[4] まさに序曲の如し、だね。
ソング・オーダーは誰が決めたんです?
全員で決めた。時間がかかったけど、一曲目はすんなり決まった。「レイト・フォー・ザ・トレイン」を最後にするってこともね。あれを片面の真ん中に置くと座りが悪いからね。忘れちゃいけないのはアルバムには二面があって、聴く人はまず片面を聞き終えたらもう片方の面を改めて最初から聴く、という行為をしないといけなかったことさ。一つの演劇に二つの幕があるみたいなものだね。CDはぶっ通しで曲が流れる。片面に17分もしくは22分半の制約がある、それに合わせた流れをつくる。いいことだよ。
2009年の「アナザー・バイツAnother Bits」ツァーでも「リアル・ワールド」は出だしを飾った。今も同じエキサイトメントとドラマチックなテンションを与えてくれる曲だね。
エヴァー・フォーリン・イン・ラヴ~
137ページ、参照。
オペレーターズ・マニュアル
Operator’s Manual
ソングライター:ピート・シェリー
「シックスティーン」同様、この曲にも3/4拍子が使われてますよね。
これもどこかイビツな、変わった小節感覚を持ってるね。ワルツをとり入れていて。3/4拍子なんだけど三つ目のヴァースで、一つ目のヴァースよりも強いアクセントが付けられてるんだ。
コンピュータ作業者の仕様書(マニュアル)、というアイデアは、今はそうじゃありませんが当時は馴染みのないものだったと思います。テクノロジーに興味が相当あったと?
コンピュータにはいつだって興味があったね。ボールトン・インスティテュートの電子工学部に入ってHNⅮの勉強をした。[5]コンピュータを自分で拵えたよ。『SKY YEN』(訳注:1974年3月録音。発表は1980年4月24日。レーベルはグルーヴィー)で使った。あれがコンピュータ技術者としての最初の仕事といえるよね。
音楽創作を目的としたコンピュータ・プログラミングのパイオニアですもんね。
1983年に出した最初のソロ・アルバム『XL―1』はZXスペクトラムという初期のコンピュータ専用プログラムを活用した。情報をコード化する作業は友人でコンピュータの学位を取ったジョーイ・ヘッドンにしてもらった。このコードはレコードの内溝にまで達している。スクリーン上に歌詞と計算データが映し出されているコンピュータから音楽情報を抜き出すには、その情報をカセット・テープに移さないといけなかった。計算データはおそろしく単純なものだったけどカラフルで、音楽にピッタリ同期(シンクロ)させることができた(プログラムオタクだよ!)。当時は異端なツールで今となってはレトロな味わいがあるね。Z✕スペクトラムを手に入れなくても今やユーチューブで視聴できるようになってるもんね!
で、「オペレーターズ・マニュアル」はどんな具合に出来上がったんですか?
ステレオセット用に新しいアンプを買ったんだけど、取扱説明書が付いててね。「オペレーターズ・マニュアル」って書いてあったんだ。それで考えてみたんだ。自分の感情を整理するオペレーターズ・マニュアルがあればいいのにってね。これ、結婚のための手引書になりゃしないか、なんていう連想もしたりしてね。「もしその手続mechanicの一部でも判っていたら」!これって「オーガズム・アディクト」に出てくる「諸々のセックスの仕方mechanics」を思い起こさせるよね。
人を機械にみたてるのってある種エロチックなもんだよ。人のセックスのありようっていうのは暗号をコード化するようなもの、つまり何か問題がある毎に取扱説明書を手に取って眺めるような、そんな安易なものになり果てる可能性があるってことなんだ。
ノスタルジア
Nostalgia
ソングライター:ピート・シェリー
この曲はいつ?
1974年、バズコックス結成前だね。すでに完成していたナンバーで、バズコックス調になるようにちょっと直しただけなんだ。元々ジェッツ・オブ・エアっていう僕の最初のバンドの持ち歌だったんだよ。ライヴではやらなかった。だって仲間は皆、ライヴの時間帯はオネンネタイムだったんだから!アレンジは殆んど同じだね。違うところはジェッツ・オブ・エア時代には12弦ギターを弾いてたことだな。
作曲したときどんなことを考えてました?
アイスクリームは昔もっと旨かったよな、でももしかしたら将来はもっと旨く感じるようになるかもしれないってことかね。どんなに「過去」が素晴らしいものでも、「過去」は「今」に置き換わるんだ。ノスタルジアという感情にいつまでも浸っているわけにはいかない。詩人気取りでいた学生時代の産物さ。ロマン派の詩人に入れ込んでたんだよ。だから自分の苗字をシェリーにしたんだ。
こんな若い時分から、思想的な問題を考えてたわけですね。まだ19歳だったのに。
そうだね。「シックスティーン」や「シックスティーン・アゲイン」でも同じテーマを、現状に満足できないというテーマを扱っている。だけどくり返すけど、自分自身のことをとり上げているわけではないよ!
「ノスタルジア」はペネトレーション[6]がカバーしてましたけど、ポーリー・マーレ―とは交流があったんですか?
「カバー」なのかな?彼らのアルバムと『ラヴ・バイツ』がリリースされたのは同じ時期だからね!彼女の声は上手くハマってると思ったし、うれしかったよ。
そう、今も彼女やロブはライヴに来るね。二人はニューキャッスルの山の手で練習スタジオのビルを経営してるんだよ。最近も彼女の歌を聴いた。「ノスタルジア」では高いキーが出せなくなってたね。
ジャスト・ラスト
125ページ、参照。
シックスティーン・アゲイン
Sixteen Again
ソングライター:ピート・シェリー
「アゲイン」では16歳にまつわることが語れます。あなたにとって16歳は良い時代だったんでしょうか?
歌にはひとつのしきたりがあってね。-「6月の月」のような。16歳にまつわる歌はたくさんあるよ。それは世の必然というより、創作の欲求といった方がいいんだけどね。16歳って大人への入り口だろう?グレトナ・グリーンGretna Green(訳注:駆け落ちで有名な、スコットランド南西部の地名)に逃避できる人なら同意するだろうけどね。この年代もすごく誌的になるよね。「ア・ラ・カルトA la carte」なんて言葉を入れた歌なんて、そう多くはないよね!
この曲も1975年に書いた。『アナザー・ミュージック』を仕上げて、その後はツアーとか「ラヴ・ユー・モア」の宣伝とかで十分な時間がとれなかったから、書き溜めてあった曲を『ラヴ・バイツ』では使った。レコーディングした曲は、頻繁にライヴにかけた。-僕の初期の作曲法なんて『ブルー・ピーターBlue Peter』と同じさ。[7]後になって推敲させていったんだ。
1978年に『ホイッスル・テスト』で・・・・。
そう。あと「ナッシング・レフト」だったね。いい曲だよ。「エヴァー・フォーリン・イン・ラヴ」ではなく、これがシングルになる可能性があった。
サイド2
ウォーキング・ディスタンス
Walking Distance
ソングライター:スティーヴ・ガーヴェイ
スティーヴ・ガーヴェイが当時レコードに残した唯一の自作曲です(『クロノロジーCHRONOLOGY』にはデモという形で別の自作曲もありますが)。[8]いつこの曲が書かれたのかは?
ある日彼がスタジオでそのフレーズを弾き出してね。僕もそれについて行き、曲に仕立てたのさ。上々のインストルメンタルになったよ。僕らはミュージシャンとして常に探求心を持っていた。可能性を追求していたんだ。[9]
彼はギターも、ベースともども弾いたんですか?
まあ殆んどのベーシストはギターも弾けるよね。多分クリス〔・レミントン〕(訳注:現バズコックスのベーシスト)が唯一、ギターが弾けないベーシストって自認してるベーシストじゃないかい。
ギター・パートにはカンを思わせるフレーズがありますが。
そうだね。というか、カンよりノイ!かもね。
スティーヴ・ガーヴェイもクラフトワークのファンだったんじゃ?
どうかな。スティーヴと僕とでギター・パートを考えたわけで、それがクラフトワークの影響を受けているというなら、そうだろうねってことになるかな。
ベース・パートが大いにノセる曲ですね。
スティーヴ・ガーヴェイならではだよ。すごく音楽的だね。コードは一切使われていない。ギターとベースの単音フレーズだけで、リズム・ギターもない。こんな曲は僕らには殆んどない。過激な、定型のスタイルからの脱却ってヤツだね。
ピール・セッションでもとり上げましたね。
ピール・セッションは新しいことに挑戦する場になっていたね。一連のセッションはメイダ・ヴァルにあるBBCスタジオで収録されていた。交響楽団用にはデカい部屋があったけど、僕らにはバンド専用の小部屋をあてがわれていた。BBCの認可を得ていたミュージシャンズ・ユニオンは「レコードを放送する時間」しかモノにできなくて、ラジオ1なんかは一日の多くをレコードを流すだけに費やしていたから、ユニオン側はレコード放送以外の時間を手に入れようとミュージシャン達をあてがう必要があった。ピール・セッションが誕生した理由もそこにあったんだ。僕らは手数料を払って三時間のセッションを持った。スタジオの職員は真面目ではあったけれど、ちょっと経験不足だと思ったね。年中型にはまった仕事しかしてこなかったんだね。それだから僕らが妙なことをやり出したらエラく興奮してたみたいだったな。
ラヴ・イズ・ライズ
Love is Lies
ソングライター:スティーヴ・ディグル
この曲はスティーヴの箸休めというか、「オートノミー」とはずいぶん違う雰囲気ですね。
六十年代の伝統的なラヴ・ソングを踏襲してると思うね。エルヴィスのスタイルをパロってるだろう?声とか。エルヴィスとブライアン・フェリーの合体だね!
アコースティックな音、「アンプラグド」が流行る前に登場してたわけだよ。バズコックスに合ってるとは言いかねるけど、「アナザー・バイツ」ツアーでとり上げた。スティーヴの普段は表に出さない繊細さが現れた曲だね。
ナッシング・レフト
Nothing Left
ソングライター:ピート・シェリー
この曲も歌詞の付かない楽曲であったと聞いてましたけど。
77年のクリスマスに作詩を手掛けた。未婚の母と女たちとの、一向に片付かない問題を歌った内容にした。運良く自分の家で書き上げることができたわけだけど!
破綻に到る前に、相手との別れを思い留まる、という展開にはならなかったんでしょうか?
実際のところはね、単に女を見捨てる内容じゃないんだ。それとは別に、心の変節を歌ってるんだ。「オー・シット」とか「ユー・セイ・ユー・ドント・ラヴ・ミー」と同じ傾向の曲だね。場面毎に主人公の心は少しずつ変化していく。憐憫から、理由を求め、受容していくんだ。癒しの時間を得ていくわけだね。
最近のライヴで気付いたんですが、「stranger in the night(訳注:邦題は「夜のストレンジャー」)」から影響があるんじゃないかって。
七十年代からずっと馴染み深い曲ではあるよ。それってメタメタな演奏をする方かい?レス・ドーソンLes Dawson[10]への敬意のつもりで言うけど。彼のあのピアノは酷いもんだったのは憶えているだろ?僕はまともな弾き方を覚えることは、あえてしなかったのさ。クズな演奏をわざとしてみせたんだ!
ESP
ソングライター:ピート・シェリー
この曲はどこで、いつ?
手を付けたのは1974年。歌詞はこの時期に出たピール・セッションでだったと思うんだけどね。
いつもこの曲は美しいなと聴き入ってしまうんですよね。
リフがずっと続いていって、コード・チェンジが行われてもリフはそのまま。一種のトリックみたいなものだね。
ESP(訳注:テレパシー)と人間同士の交流についてを歌ってる。互いに孤立した人々。不変のテーマさ。
テレパシーは信じますか?
いや、疑わしいね。そりゃ殴られたとか感じたら別だよ!人の心を読めるなんて・・・・。
歌詞の中にあった「考えろ・・・・!」と書かれたバッジがありましたね。
そうだね。マルコム・ギャレットがデザインしたんだ。ライヴの終わりに無料配布するためだった。身に着けてくれれば宣伝になる、そうなりゃ値千金の価値になるからね。誰かと触れ合いを求めようとすることがあるだろう?それはどこか疑いつつも、相手へのオープン・マインドを示してもいる。人はつながりが出来ると相手の気持ちを知りたくなるものさ。もっとも、もう判ってしまってるってときもあるかもしれない。何だか同好会か秘密結社を立ち上げたみたいな話だね。
レイト・フォー・ザ・トレイン
Late for the Train
ソングライターズ:スティーヴ・ディグル、スティーヴ・ガーヴェイ、ジョン・マー、ピート・シェリー
これがもう一つのインストルメンタル・・・・。
コード進行に出だしとエンディング、これは僕のアイデアだった。そこにスティーヴが違うアイデアを持ち込んできた。いくつか山場があって、すごく構築美的なちょっとクラフトワーク的な、冷ややかな、親しみにくい雰囲気ではあるね。ジョン・ピール・セッションでもとり上げた。知っての通り、BBCの職員たちはシングル曲とか馴染みのある曲は望まなかったからね。
ピール・セッションの時、この曲の音像をどういう風にしようかと話し合った。スタッフがテープ・ループとかいろんなことを提案してきたけど、僕らがアルバムのレコーディングでとり入れた手法そのものだった。僕らはBBCセッションで今までやったことのないことをやろうとした。スタッフは優秀だったね。僕らに自由にやれせてくれたんだ!
インストなんて、当時のパンクではあり得なかったです(ストラングラーズは例外でしたけど)。
アルバム二曲目のインストで、パンクとしてはちょっと変わってたね。けどさ、ジャンルって何だろう。「パンク」って何なんだろう。その意味するものがよく判らなかったんだ。パンクって縛りつけることじゃなかった。縛るものはない、よりオープンな概念だったんだ。パンク第二世代の連中が鋳型にはめ込んじゃったんだ。定義付けなんて僕らのときにはしなかった。自由に考えることができたのさ。
自分たちはパンク・バンドだと思っていたよ。何せ「ホワイト・ライオット」ツアーに参加したんだから。でも僕らはどこか変わり者でもあった。「ニュー・ウェーヴ」と言われた連中ともね。パンクとして人気を得たけどどう見なしていいか判らない連中がいる。例えばパティ・スミスはパンクと言えるかな?ブロンディは?皆根っこは同じだけどね。皆が皆セックス・ピストルズと同じになるわけじゃないのさ。
「ニュー・ウェーヴ」という呼び名をジャーナリストが使うようになったのは、既存のポップ・スターやティーン・マーケットを牛耳ってきたいわゆるチャップマン:チンthe old Chapman and Chinn[11]路線に乗らなかったミュージシャン達を新しい(ニュー・)波(ウェーヴ)と呼んだところから始まってるんだ。そこから新しい音楽スタイルが生まれ、新しいことに挑戦しようとする動きが起こった。パンクは人々に自由を与えた。きっかけを与え、考えることを促した。「俺にもできるんだぜ!」ってね。
この曲には変わったリズムが使われてませんか?
特徴があるね。6/8拍子で、田舎の踊りではよく耳にするよ!最初は「レイト・フォー・ザ・トレイン」てタイトルじゃなくってね。スタジオの中休みに何か腹ごしらえしようと外出して、ドネル・ケバブdoner kebabsの店に入ったんだけど、その「Doner Kebab」を、しばらく「s」なしで読んでて、何か列車っぽく思えてね。でそういう風にタイトルを変えたのさ。
八十年代、レゴLEGOのⅭFに「レイト・フォー・ザ・トレイン」そシンセ・ヴァージョンが使われてたんだってことなんですけど。
そうさ、僕がつくったのさ!レゴ製の電池で動く電車模型のⅭF。1984年だった。十代の時バズコックス・ファンで、その後メディア関係に就職して結構いいポジションに就く人もいたんだね。広告代理店にいたその男もかつてのファンでね。僕はエレクトロ二クスなヴァージョンに仕立て直した。当時はこのテのサウンドづくりに入れ込んでたし。
プログラミングを全部自分で仕上げて、ロンドンでレコーディングした。音楽を映像やシンセと同期(シンクロ)させなくちゃならなかった。今だったらデジタルで簡単にできるけど、当時はね。音楽と映像、音楽と広告、それを全部耳で同期させた。カンが頼りだった。
テレビのスイッチを入れると広告が出る。それに合わせて音楽が流れるようにしたんだけど、その箇所に静かな通奏低音みたいなノイズを入れてみた。そしたら協賛者からクレームが付いたんだ。「これはダメです。怖くてキケンなイメージを植え付けてしまいます」ってさ。しょうがないから『フラッシュ・ゴードン』な感じのノイズに変更したよ。
あのヴァージョンのテープは持ってないんだよ。これをお読みの広告代理店の方、ご一報を!
[1] これはピートの永年に渡る慈善活動の、ごく一例にすぎない。
[2] 『シングルズ・ゴーイング・ステディ』の裏スリーヴには各メンバーが別々に仕切りの中に入った状態での写真が使用されており、『LET IT BE』との親和性を感じさせる。『シングルズ・ゴーイング・ステディ』のリリース時期は、『LET IT BE』期のビートルズとパラレルな関係、即ちバンドの末期に到り、ほころびが目立つようになった状態にあると指摘する者もいる。
[3] ジョン・マーもこのセッションに参加しており、以下のように発言している:「『THE RECORDING OF THE INVISIBLE GIRLS』というアルバムはストロベリー・スタジオStrawberry Studiosで制作したんだが、あれはマーティン・ハネットの別の面を『体験』させてくれたよ!とにかく実験的な方法で行なわれた。基本となるバッキング・トラックを録ってから俺のドラムを重ねていったんだが、ヴォーカルがどんな感じになるのかまったく知らされなかった。すごく破天荒なレコーディングだった。レコードとライヴではまるで違った内容になったな」
[4] スティーヴ・ガーヴェイは「リアル・ワールド」について、「そのベース・ラインは気に入ってるよ!」と語っている。
[5] ピートはコンピュータ業務を副業の一つとみなし、それを楽しんでいるフシがあった。1983年6月15日付ラジオ5での、リチャード・スキナーとのインタヴューで、ピートはコンピュータ業務をその構造から、(20世紀半ばに全盛を迎えたオモチャのミニチュア機械を連想させる)「ひとつのメカノMeccano(訳注:プラモデルのブランド名)・セット」のようなものだと説明している。
[6] ペネトレーションは「アイ・ドント・マインド」もレコーディングし、2015年のアルバム『RESOLUTION』に収録している。これにはジョン・マーも参加している。
[7] 六十年代から七十年代、日曜大工は子供向けテレビ・バラエティ番組『ブルー・ピーター』の有名な呼び物の一つであり、こぞってパロディの対象となった。「手早く、一丁あがりHere’s one I made earlier」出演者が作業台の前に出された課題に必死にとり組んで完成させ、隣の作業台に置いたときに放つセリフであった。ときにはより難易度の高い芸術的な課題制作にとり組むこともあった。スティーヴ・ディグルはこのセリフを1995年発表のコンピレーション・アルバムのタイトルに冠している。
[8] スティーヴ・ガーヴェイの回想:「ピートは俺にも曲を書けとしきりに言ってきた。俺は曲を聴かされることはあっても、モリッシーやマーのようなことはできなかった。それに歌うのもね。ピートは俺たちをビートルズのようにしようとしたんだ。俺はジョージ・ハリスン役ってわけさ!」
[9] スティーヴ・ガーヴェイ:「ジャム・セッションで出来上がったんだ。ピートと俺はよくカンとかクラフトワークを聴いていて、「そっち方面へ」シフトした曲だった。こういう毛色の変わった曲をプレイする奴は俺たちの周りにはいなかった。いわゆる典型的なパンク・スタイルの曲じゃないという意味のね」
[10] マンチェスター出身のコメディアン、レス・ドーソンは七十年代から八十年代にかけてBBCテレビで自分が主役の番組を持っていた。見せ場のひとつが一分の隙も無いいでたちでグランド・ピアノの前に座り、誰もが知るような名曲を弾き出すのだが、すぐにその演奏は不協和音だらけのメチャクチャになるというものであった。これはいまだに彼ならではの芸風として、そのキザッタらしくも下品な振る舞いともども人々に記憶されている。実は彼のピアノの腕前は相当なものであったのだけれど。
[11] ソングライティング兼プロデューサー・コンビであったマイク・チャップマンとニッキー・チンは七十年代初期において最もよく知られたヒット・メイカーであった。主なミュージシャンにスージー・クアトロ、マッド、レイシー、スモーキー&スゥイート(自作曲をシングル・リリースした途端に不思議なほど売れなくなった)がいる。コンビは50を超えるトップ40のヒット曲を生み出し、現在も二人は活動中だがコンビは解消している。
