
ヘルシンキ大学院修士2年生 図書館がほぼ家みたいな2か月
修士2年目が始まった。8月は修士論文テーマ決めに取り組むべく平日は割と学校に通った(休み期間は図書館に人が少ないので最高)。9月から正式に新しい学期が始まり、現在までまだ2か月しか経っていないが、やるべきことを終えたので、9月10月の様子をまとめておく。(もう5か月くらい過ぎたような感じである。)履修した授業は修士論文セミナー、修士論文方法論、フィンランド語、ロシア法ガバナンス(選択科目)である。2年目は修士論文に集中するカリキュラムのため、授業数は少ない。
1.修士論文セミナー
修士論文セミナーは、今のところ2度あり、それぞれ自身の研究テーマや研究計画について約2500ワードで提出と、プレゼン、ディスカッションを行った。それ自体は全然問題ないが、それに至るまでの修士論文テーマ、リサーチクエスチョン探し、研究計画を考えるために、まあまあの量の文献を読み、これで合ってるのだろうか?と不安を感じながら、でもやるしかないのでとりあえず1ヵ月は図書館に通う毎日だった。(でも絶対この悩みは大学院生が皆通る道だと思うので、問題なし。)そして、指導教官探し、面談もすることができ、結局、早く相談しとけばよかったな、みたいな感じもなきにしもあらず。(指導教官については機会があればまた書きたいが、割と院生のサポートという面で、非常に良い意味でカルチャーショックを受けている。例えば、先日教授が自宅に指導生徒全員を招待しパーティを開催し、人と会う機会を設けてくれた。ああ、研究・学問はただ一人ではなくて、むしろ人との関わりが重要だし、そうあるべきだよなと感じた。こういう機会を提供してくれる教授を選べて、そして受けいれられた私は超ラッキーだなと思う。)
セミナーではクラスメートの研究計画も聞くことが出来たので、テーマは全く違うが、ああ、こういう風に進めればいいのか、みたいな感じで学ぶことが出来た。
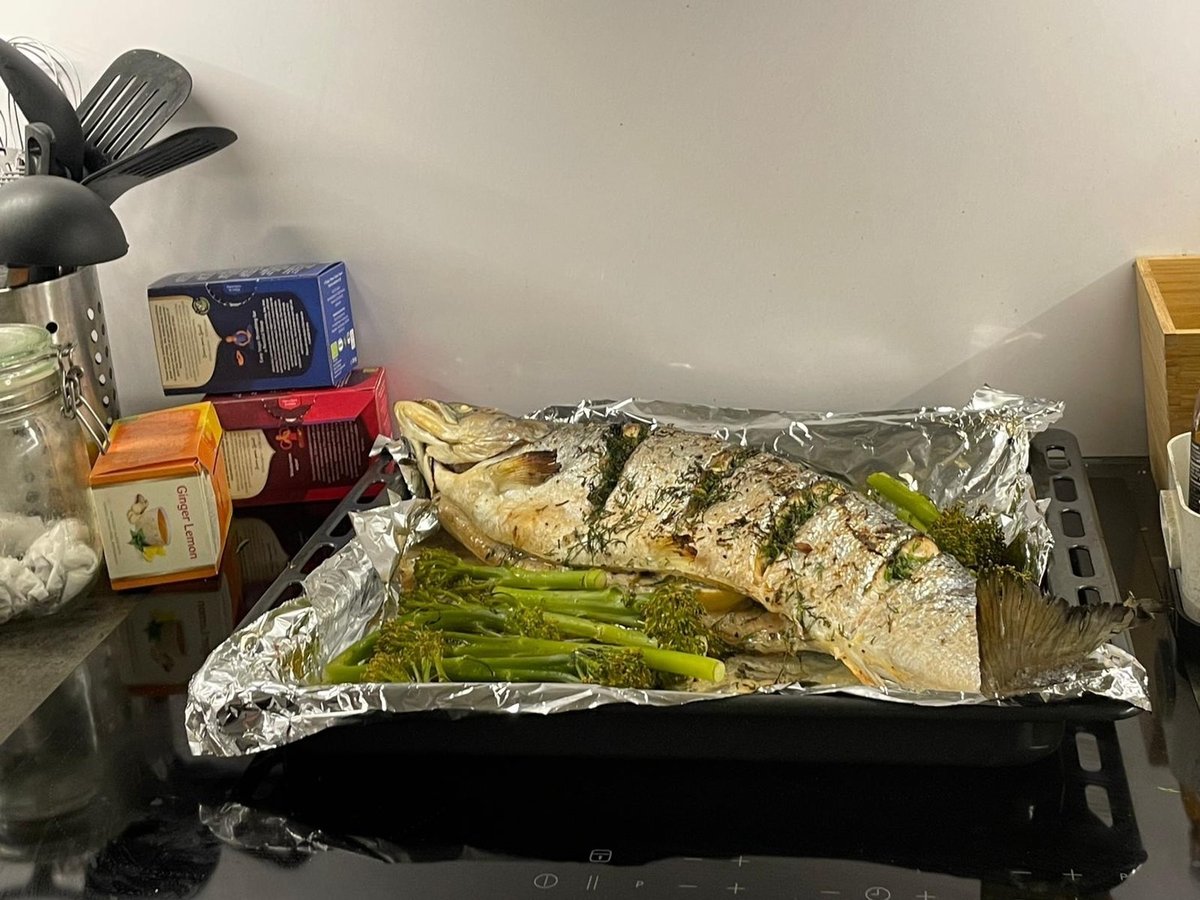
2.修士論文方法論
研究手法の論?(Methodology)という授業を受けた。講義の最初の数回は教授何人かのそれぞれの研究手法について講義を聞き、その後は、2人一組になって15分のプレゼンを行うものであった。2人1組のプレゼンであるが、2年目にして、割と初で、チームワークの難しさ、とまではいかないがチームのバランス?みたいなものを考えるきっかけがあった。ペアの方は前日までほとんど準備をしないような感じで(多少はしていた)、それに伴って明確な作業の分担をし損ねてしまったこともあり、私は数日前から少しずつ準備してきたが、最後の大詰め、みたいな感じの準備は結局前日の夜にすることになった。日本にいるときに読んだ、『最後はなぜかうまくいくイタリア人』宮嶋勲著という本(←面白い!)を実際に味わったという感じだった。ペアの方はある意味超ポジティブで、「あ、私もこんなに真剣にならなくていっか~」と肩の荷を下ろすことができたので、その点良かった。
完成度はというと、少し先生から参考文献が十分良いものではなかったために、指摘を受けた。ちなみに、「法学と人類学について」というかなり広いテーマについてプレゼンが割り当てられており、その過程で今まで全く触れたことのなかった人類学者が書いた文献を読むこともあり結構面白かった。フィールドワークが重要とされる人類学の研究での限界とか、人類学の視点をどう法学の視点と組み合わせることが出来るのか、みたいなことを発表した。プレゼンが終わったので、半月後に最終レポート3000ワードの提出をすれば完了である。法学のmethodologyについては別の日記でまとめておきたい。

朝8時半頃。(つまり極夜の始まり、、)
3.ロシア法ガバナンス。
9、10月の勉強量の大半以上を占めたのが修士論文ではなく、ロシア法ガバナンスである。授業は2週間毎日(1時間半)続いた。
何が大変だったかというと、ロシアについては高校まで学んできたことと、ニュースや新聞で見る程度の知識しかなかったため、それをいきなり英語で勉強する必要があった(が、これは1年目に経験したことと比べれば全然大丈夫だった。)。毎授業のために3本ほど論文を読むことが課されているため、それを読み、また必要な時には追加で論文を読み、また、日本語で調べたりもした。(が、もちろん日本語でロシア法の研究を探すのは限界がある)。
そして、論文をまとめ、ディスカッションのテーマをプレゼン発表することも必須であった。が、これもまた私は第一回目の授業で発表することにしたので、誰一人知り合いがいないなか、いきなりプレゼンするのはかなーり緊張したが、まあまあ普通に終わった。さらに、1週間が終わったころ、2500ワードのテストみたいなものがあり、1週間の授業で学んだことに対する設問に答えた。ちょっと苦労したが、これもOK。加えて、最終授業に向けても2000ワードほどの最終レポートに対する研究計画を出すことも必須でこれは1日提出が遅れた、が結果OK。
最後、5000ワード(日本語だと約12000文字くらい)の最終レポートも必須。が、なんとこれも、合計8日で参考文献も30個引用して完成させることが出来た。(1年前は2500ワードのエッセイに対して2週間くらいかけて精一杯だったので、成長を感じる。)
授業の最後、「決して簡単な講義じゃなかったと思いますが、最後までやりきっておめでとう!」と教授が言っており、「ほんとに!」と一瞬思ったが、もう淡々とやるしかないと思いレポートまで無事に走り切った。
さて、この授業の面白いところは、初めからロシアを悪者として見るのではなく、その起源(3,4世紀くらいの時代までさかのぼった。)や、システムの特徴、何が本当に問題なのか、というところを学生に考えさせていたところである。「ロシアには法がない」という考えが出てくるが、実際には法がないのではなくむしろ、法自体は欧州に近づけた部分もあり、問題ない条文がそろっている。が、法に対する考え方(rule of lawではなくrule by law)や実際に法を好き勝手操ってしまう状況、またその人に問題があるということを考えさせらえた。
ちなみに最終レポートのタイトルは「ロシア法の二重性(Dualism)、裁判官、司法の独立」とし、ロシア法の特徴である二重性(通常の事件には法律が使われるのに対し、政治や経済が絡む事件には法の適用がrule of law(法の支配)に基づいて作用しない状況のこと。)を裁判所の官僚的な仕組みや非公式な取引(裁判官の選任が法で定められている一方で実際には独自の非公式のリストが存在し、国家に奉仕するような従順な人が好まれる。)、裁判長の権力の強さ(裁判長は歴史的にも地方の政治家と強いつながりがあり、裁判官の昇進なども裁判長に裁量権がある。)、ロシアの法教育(法倫理の不足、教育の質の低下、イデオロギーの影響)といった点から論じた。法教育を論じることが出来たのは結構面白いレポートになった。全体のレポートを通して、ソビエト時代の影響が現在の法にどのように影響をもたらしているのか、という対比にも注目した。
2か月前の自分自身と比べてもロシア法、文化、歴史について多少は詳しくなったので、大満足である。

4.フィンランド語
修士一年間フィンランド語を履修しており、今学期もそうしている。現在のクラスでは過去完了形のあたりを学んでいる。驚いたのはクラスメンバーの半分くらいはフィンランド語専攻の交換留学生であり、最近フィンランドに来たばかりの人が多かったり、それ以外の人に関してもほとんどがフィンランド語を流暢に話せる人である。周りの人は自分より出来ている風に見えてしまうのはよくあることだが、今回ばかりは、客観的にみて、確実に前年度までのメンバーの雰囲気とは異なる。
で、人のことはどうでも良いのだが、問題はテストである。私の目標はフィンランド人と話せるようになることで、スーパーやカフェなどはフィンランド語で話すようにしているが、やはり、友人の早い会話には少し理解できるがついていけない。多分それを達成するには多少は文法を無視しても良いような気がしている。(例えば私もぐちゃぐちゃな英語をアメリカ人に話しても会話には問題なさそうだし。)
ただ、テストではもちろん文法や細かな単語の変化が重視されていたし、成績はどうやら相対評価らしい。というのも、中間テストは約65-70パーセントくらいの正答率だったのだが、クラスで下から数えて3番目の順位で、さらに5段階中2をもらった。(3が良い(good)、2は頑張れ!、1はパス、0は落第という基準。)しかも、減点箇所を見てみると、理解はできるけど小さな文法ミスでマイナスされたようだった。授業に行ったら人と話せるし、先生の講義を聴くだけでフィンランド語習得することが出来るし、今回のテスト全体の成績の25%を占めるだけだから、まだ頑張ろうかと思う。一方で、5段階中2という成績が、私の今までやってきた法律の授業の平均成績を相当下げてしまうこと考えたら、普段ほとんど成績にこだわってこなかった私も、さすがに、フィンランド語で平均を下げるのはちょっともったいない、、という気分になり、履修取り消しの道が見えてきた。が、何かをやめるということ(特に大学の講義とか)を経験したことがほとんどないので、踏み出せない。Let it be ということで、未来の私が何かしら決断していることを願っている。笑

店員さんと少し仲良くなった。

(西の魔女の肉とメニューに書いてあったものの正体は普通の美味しいハンバーガーだった。)
5.その他いろいろ
そんな感じでほぼ毎日学校に行っているし、特にロシア法が始まってからは1ヵ月ぶっ通しで休日も学校や図書館に行っていたので、さすがに疲れた(実際日曜1日だけはキノコ採りを楽しんだ。)。が、1年目の後期(今年の3月〜5月)の3ヶ月も休日なしだったので、それと比べれば全然大丈夫だった。
あとは、去年までは図書館の隣の建物にある、立ちながら勉強できる机がお気に入りだったのだが、夏から改修工事が始まり、私の卒業までには終わらなさそうである。その代わりに、新たに大学図書館の地下にお気に入りの席を確保できたのでそれも良かった(確保といっても、自由席なので先に誰かが座っていれば諦める。)。

地味で良い。
大学からインターンの合格通知が来ていた。申し込んだのは3か月前だったので、もう落ちたと思っていたが、ラッキーである。が、修士論文と両立できるか心配で踏み切れないが、これもまた未来の私が何かしら決めているはず。笑。 そして、極夜が始まり始めたので、生活習慣が乱れないように最近朝8時から学校で勉強をスタートしていたのだが、1週間やって、終わってしまった。体調が悪かったのでしょうがないが、また再開したい。
結論、色々書いてしまったが、こんなに毎日勉強できて、毎日脳みそが刺激されるなんて、最高な日々だと心から感じる。引き続き、頑張りたい(まずは2週間後のレポートと一か月後のレポートとプレゼンに向けて淡々とこなしていく)。
最近Suitsというアメリカのドラマを見始めた。日本にいた時にもシーズン2くらいまで見ていて途中で難しくて飽きてしまったが、4年を経て今見ると結構面白い。全ての役に愛があり(イライラさせておきながら結局は思いやりを持った人だったり、脇役にもしっかり注目していたり)、全員が自分自身に自信満々で、自分の価値をちゃんと把握して安売りしないし、法律家たちは(特にHarvey)は苦境に立たされてもちゃんと解決していくところがカッコよい。
Suits Season 4 Episode 8 に登場したLooking too closely
↓もう一曲。Bittersweet Symphony。
I'm a million different people from one day to the next, I can't change, my mold. 毎日違う人間になっているように見えるけど、本当は自分のやり方を変えられないんだ。
