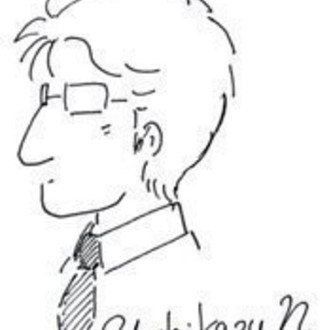2月18日 要件定義と要求定義は肝
2月18日ですね。
NHKとIBMのシステム構築にかかる訴訟が話題になっています。
仕様書に書かれてない仕様が発覚したり、色々と大変そうです。
弊社としてもシステム構築の大変さはよくわかっています。
実際、私も仕様の詰めの甘さをアクロバティックな実装で乗り切った事が何度もあります。
ただ、今のうちの会社は私一人ではなくメンバーが何人もいます。ですから、メンバーにそんな実装をさせるわけにはいきません。
要件の決めと調査がとことん必要なこともわかります。
要求定義と要件定義の違いについてもきちんと認識すべきでしょう。
この件でいうと、NHKの現在のシステムを見る方も、多分、もう要件定義など不可能になっていたと思われます。
システムの利用者に可能な限りヒアリングをしても、内部に使われていない機能がある場合、データ構造やソースコードも吟味しないと、要件は定まりません。
コーディングした技術者が音信不通になっている場合はなおさらです。そもそもその実装の意図は何なのかなど、剣呑な地雷が埋め込まれています。
これからのシステム構築とは、もう、構築やコーディングそのものより、要件定義にかなりの工数を確保すべきでしょうね。
ところがテストも要件定義に基づいて、それがきちんと実装されていることを確認する工程ですから、ここも削減できません。
つまり、これからのAIを用いたシステム構築とは、インプット要件をどう投入し、最終的なテスト結果をどう受け取るか、という部分に人との関わりが収斂されるでしょう。
そうした部分で技術者のニーズはまだまだ尽きないと思っています。
むしろ最初と最後の工程を現場の方とコミュニケーションをとって担える技術者は重宝されると見ています。
ただ、そうであっても今回のように内部の人がシステム要件をわかっていない場合はどうしょうもない可能性があります。
うちも気をつけないと。
いいなと思ったら応援しよう!