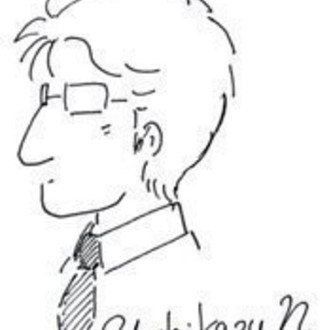10月26日 Cybozu Daysは聞く事から
10月26日ですね。
いよいよCybozu Days 2022が迫ってきました。
二週間後の今日、私も前日入りして幕張にチェックインする予定です。
今年は昨年に比べ、kintone案件の数が顕著に増えています。弊社も忙しく、去年よりもCybozu Daysの準備にかけるエネルギーと時間と工数が足りていません。
そのかわり、今年は協力社さんのお力を借りています。昨年よりもバラエティ豊かな内容になりそうです。今年も楽しみです。
昨年はあっと言う間の二日間でとても充実しました。
が、その一方で、弊社内の課題や技術者としての生き様についても考えさせられた二日間でした。
Cybozu Daysは一種の祭りのようなものです。祭りとはハレの場。他者との交流が欠かせません。
自分の世界に張り巡らせた殻を破り、セッションや展示ブースに積極的に参加する。そして未知の人々と交流し、普段の生活や仕事では気づかない学びを得る。
交流することが前提となる祭りの場ですから、自分の価値観に固執したい方にとっては、自分の価値観が揺さぶられるCybozu Daysは居づらい場になるかもしれません。
技術者にもいろんな方がいます。人によっては、交流が不要でもくもくと作業していれば良い技術者職に魅力を感じている方もいるでしょう。
こうした方がこういう祭りの場にかり出されると、苦痛を感じるのもわかります。
てすが、技術者としてのキャリアを考える上で、いつまで自分の世界に閉じこもっていられるでしょうか。
というのも、そのタイムリミットが刻々と近づいているからです。プログラミングそのものは、いまやノーコードローコードツールや人工知能が代わりに担っていこうとしています。
交流を拒み、自分の脳内のロジックだけで仕事ができる方は、よほど優秀な方に限られていくと思います。
私を含めたおおかたの技術者は他者との交流を前提としたビジネスの現場で戦っていかなければなりません。
ネット上には無数の情報があります。ビジネスの現場は情報によって生きています。そして、その考えや姿を頻繁に変えます。
固定された環境ではないので、他者との交流が前提となります。すると、交流が必須スキルになっていきます。
情報技術の裾野はどんどんと広がっていますが、技術者の仕事は他社との交流が大半を占めていくでしょう。
となると、多くの技術者の中でも仕事が集まるのは、例えば商談の場ですぐに回答を示せる方や、コミュニケーションのうまい方になるのは仕方がありません。
自分の価値観にこもり、他者との交流を求めない生き方を選ぶのはその人の自由です。が、少なくとも人との交流か不要だからとの理由で技術職を選んだのであれば、技術力を相当磨かなければなりません。
どこにでもいる技術者ではなく、数学的な概念を操るぐらいでないと、厳しい未来が待っていると思います。
一方で、柔軟に自分の殻を破り、形を変えたり、繕いなおすことができる技術者にとって、これからの活躍の場は無限に拓けていくでしょう。
わが国の場合、まだ情報技術は浸透していません。ビジネスの場で技術を活かすチャンスはまだ枯渇しないでしょう。
Cybozu Days は交流を前提としています。
また、その交流は自分にも新たな気づきをもたらします。
Cybozu Days から得られるのは、交流によって得られる未来です。その未来は、自分の殻にこもってネットを見ていても得られないはずです。
交流に自信がないと思う方もいるでしょう。が、Cybozu Days の場では拒絶されません。
まずは自分の殻を破って参加してみることをおすすめします。
話し方がよくわからなくても、ブースで質問しましょう。ブースにいる人は、答えることが仕事なのできちんと質問に答えてくれるはずです。
そこから交流が生まれます。別に名刺が交換できなくてもSNSを交換できなくても良いのです。
まずいろんな人に聞くためだけに参加してみてはいかがでしょうか。
https://days.cybozu.co.jp/days/
いいなと思ったら応援しよう!