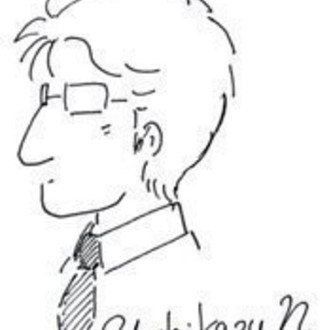12月15日 AIが芸術に与える影響は
12月15日ですね。
また、新たなAIサービスが生まれました。
Sunoです。
https://www.suno.ai
お題を指示するとそれに合わせた歌詞を生成し、さらに曲調を指示するとメロディも生成し、その場で歌声付きで聴けてしまいます。
歌詞とメロディ、そして歌声までも生成してしまう。
なんというサービスでしょう。生成AIは私たちの度肝を抜きつづけてくれています。
画像生成はMidjourneyやstable DiffusionやDALL・E2、文章生成はChatGPTやOpenAIに、そして音楽生成はSunoに。
人類の創造性はどんどんとAIに侵食されています。
が、多くの識者がいうように、これは過渡期だと思います。
これからのAIはますます人間に似てきます。
視覚や聴覚に訴えるAIはすでに不気味の谷現象を越え、そのまま商品として市場に出回りそうです。
短編くらいであれば、小説もそろそろ出てくるのではないでしょうか?いや?作家が言わないだけでもう出ていると思います。
生成AIは芸術のあり方を一変させるでしょう。
もう、デジタルベースで見られるものは簡単に流通し、生成AIが成り代わっていくはずです。
ただ、それによって芸術家が職を失うかというと、そんなことはありません。
おそらく、人間の芸術を味わう場はリアルに特化していくはずです。ディスプレイ越しではなく、リアルの場。
複数の人々が集まって同じ場を楽しむ雰囲気に。
音楽で言えばコンサート。美術で言えば美術館。文章で言えば朗読会。その場の共有感覚を楽しみ、人と人とが交流する場が芸術鑑賞。
芸術家はその方向に活路を見出すと思います。ライブ感覚を活かす方向です。
人類から芸術が失われるのではなく、芸術の創造の場を共有するあり方に変わっていくのではないかとおもいます。
私たちもうまく共存していきたいと思います。
いいなと思ったら応援しよう!