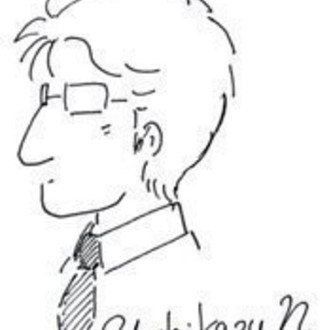5月19日 電子書籍の普及が進みますが。
5月19日ですね。
今日から国立国会図書館において、
「個人向けデジタル化資料送信サービス」
が始まるそうです。
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2021/220201_01.html
つまり、今までは著作権法の壁によって自由に発信できなかった情報が、オンラインで読めるようになります。それが国立国会図書館という国の機関で実施されたことに意義があるのではないでしょうか。
まだ紙の本は国立国会図書館に納本されることでしょうが、いすれば国立国会図書館法に定められた納本制度も改正されることでしょう。
私はいまだに本は紙で読む人です。が、デジタル化の流れはこれからも続くでしょうし、紙の本はいよいよなくなっていくでしょう。図書館という場の存在意義すら問われています。
知識と学びを得る場として有効だった図書館。今も電子書籍が世に出回っているとは言え、ほとんどが有償です。無料のコンテンツの質はまだまだ有料コンテンツの質に及びません。
今後数十年のうちに図書館は、大量のタブレットが置いてある場所に変わってしまうかもしれません。その時、老人の私は図書館に行くことがあるのでしょうか。
私は電子書籍も読みます。が、紙に比べると読んだ感が薄く、おそらく情報も紙に比べて入りにくいてす。
https://kumamoto-nct.ac.jp/file/knct-kiyou-2013/pdf/no8.pdf
のような研究は多数されているようですが、早く電子媒体も紙並みの視認性を持って欲しいと願わずにいられません。
いいなと思ったら応援しよう!