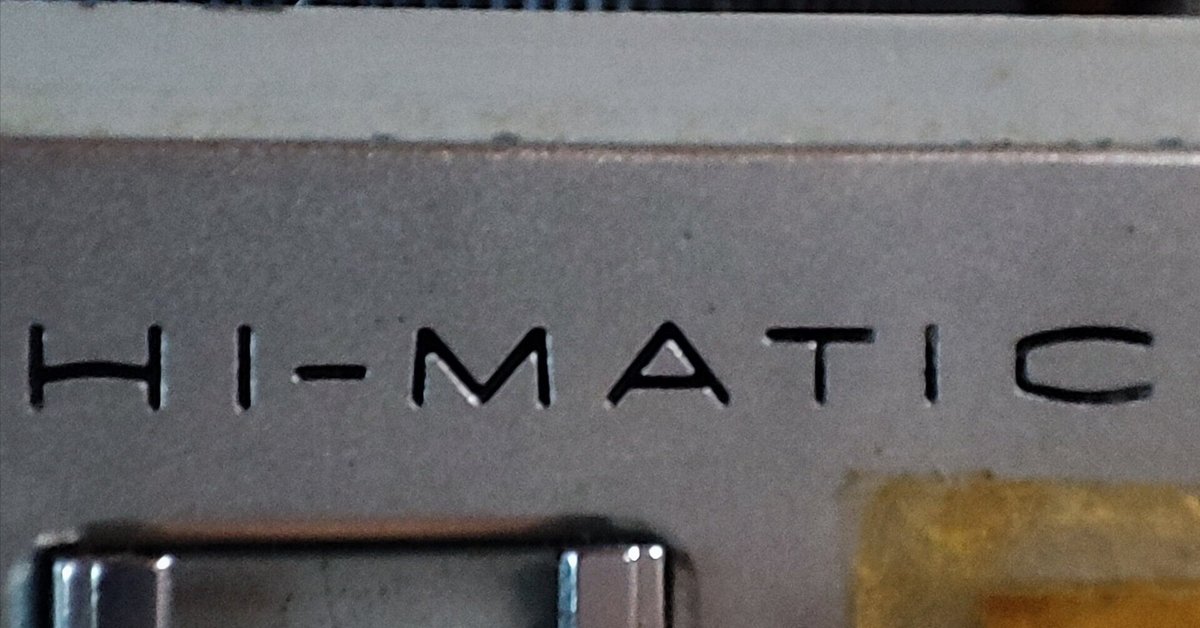
ハイマチックが民生初の宇宙カメラになったことで始まったミノルタの「7」伝説
便宜上、宇宙は地上から100km上空のカーマン・ラインの外と定義されています。 カーマン・ラインを超えて最初に地球を映したのはアメリカ軍がドイツから接収したV2ロケットに積んだ無人インターバル撮影用に改造した映画カメラによる白黒写真でした。
ソ連に宇宙開発で後れをとったアメリカはマーキュリー計画をスタートし、7人の宇宙飛行士候補を選びます。 これがマーキュリー・セブンでオリジナル・セブンとも呼ばれ、1921年生まれのジョン・ハーシェル・グレン・ジュニア(John Herschel Glenn Jr.)もその一人でした。
グレンは1962年2月20日にフレンドシップ7(Mercury-Atlas 6)で軌道に打ち上げられました。 彼の宇宙カプセルは地球を23周し、宇宙から地球のカラー写真を撮影した最初の人間になりました。

このカメラがグレン自身が選んだ「Ansco Autoset」でミノルタで初代ハイマチック(minolta hi-matic)のOEMです。 特徴はセレン光電池による自動露出 EE 機能付き距離計連動式カメラで、当時唯一の自動露光カメラでした。 電池も使用していないので過酷な宇宙環境に対応しやすいものでした。




宇宙開発やミノルタの「7」を語るに欠かせないハイマチックですが手元のものはもはやセルフタイマー周りの挙動が怪しいものです。
そのセルフタイマーのレバーはレンズに付いており、カメラの前面にまるでセルフタイマーのレバーのように見えているのはスライド式のシャッターです。
グレンはNASAを説得しこのカメラを宇宙飛行士のごつい手袋でも扱えるように改造し、宇宙カプセルに持ちこんだのでした。

ミノルタはこれを非常に喜びフレンドシップ7にちなんで、二代目ハイマチックに「ハイマチック7」の名を与えています。
ジョン・グレンが1963年に来日した際に製造番号77777777のハイマチックがプレゼントされています。 1998年10月に打ち上げられたスペースシャトル「ディスカバリー」のミッションに、グレンは77歳で参加しクルーの最年長記録になっています。 1999年に来日した際にはハイマチックの中古完動品を購入して持ち帰ったそうです。
ミノルタはエポックメイキングなカメラに「7」を使うのは有名でα-7000やα-7に使われています。 ジョン・グレンは2016年12月に95歳で亡くなりましたが同じ2016年12月に種子島宇宙センターから打ち上げられた宇宙ステーション補給機「こうのとり」の中に、α7S IIも積み込まれ日本実験棟「きぼう」の船外実験プラットフォームに、新たな船外プラットフォーム用カメラシステムの内蔵カメラとして取り付けられ、民生機として世界初の4K撮影に成功しています。
蛇足ですがフレンドシップ7には民生カメラはMINOLTA Hi-Maticだけでなく改造ライカも持ち込まれオリオン座のベルトの星の分光撮影に使用されたようです。 これは科学写真であり、青い地球を映した Hi-Maticの写真ほどのインパクトはないので半ば忘れられています。
