
「アイホールの課題を考える~演劇と教育~」勉強会に行ってきました!
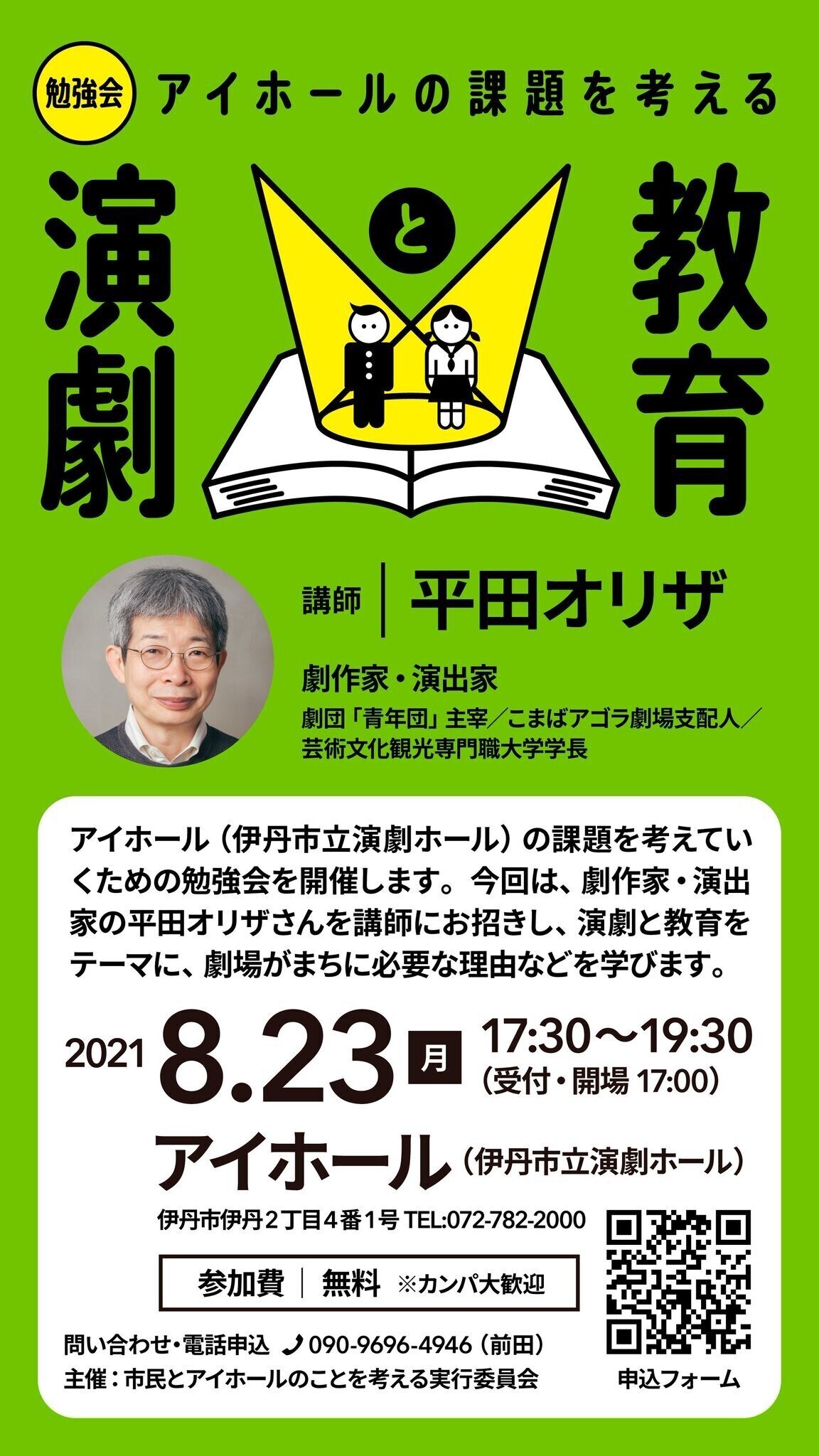
市民のみなさまからの要望により、8月23日(月)にアイホールの課題を考える「演劇と教育」の勉強会が開催されました。講師は平田オリザさんです。
直前での告知であったのにも関わらず、多くの市民の方が参加されていました。

まず最初に「市民とアイホールのことを考える実行委員会」芝田一也さんよりご挨拶があり、続いて
伊丹市の学校を卒業した皆さんがこれまでにアイホールで体験してきたことや、アイホールに対する思いをお話されました。
◎「市民とアイホールのことを考える実行委員会」芝田一也さんのお話
芝田さん:アイホールの現状と課題についてよく知り、これからのことを市民みんなで考えていくために委員会を立ち上げた。アイホールは、学校現場での不登校・いじめ問題解決への取り組み、新学習要領に基づいた子どもたちの育成及び社会人として社会の中で活躍するためのスキル向上、並びに中、高校演劇部の表現活動のサポートに大きく寄与している。
◎「アイホールと私」伊丹市の学校出身の皆さんのお話
土手さん(市立伊丹高校OG):アイホールで先輩と色々な劇団の芝居を観て、台本を作る助けになった。 戯曲講座、スタッフワークショップなどに参加して色々なことを学び、特にアイフェスにて劇場の方と触れ合えたのが一番楽しかった。なくなってほしくないので、参加した。なくならないよう頑張っていきたい。
井上さん(県立伊丹高校OG):講師やスタッフの方に誉めてもらったり、一緒になって劇が良くなる方法を探ってもらったり、新鮮な関わりがあった。他者との関わりに不安を抱えていた自分が、他者と一緒に創ることの楽しさ・嬉しさ・豊かさを知った。アイホールで過ごせた時間が誇りで、これからもアイホールに通い続けたい。
Mさん(県立伊丹高校OG):川西市育ちで伊丹の高校に通ってアイホールを知った。市外からやってきて、駅前のアクセスしやすいところに創作に立ち会える場所があることに衝撃を受けた。人とのコミュニケーションに取り組むことのできる稽古期間で、同年代の葛藤や、子ども真剣に向き合う大人の姿に触れることができた。表現したい気持ちに応え、支えてくれる場所がアイホールだった。
津久間さん(県立伊丹高校OG):大人になった今も演劇を続けている。長く続けられたのは暮らしの近くに劇場があったから。アイホールに行けば面白い作品が観られる、面白い作品が創れるという信頼があった。関西の演劇人、全国の観劇ファンをお迎えできる劇場を持っていることを誇りに思っている。アイホールのより良い形での存続を願っている。
また、司会の石田さんからも、子どもが小学生向けのワークショップに触れて楽しい時間を過ごされたお話があり、アイホールが様々な世代に向けて演劇に関する取り組みを継続してきたことが紹介されました。
【アイホールの課題を考える 平田オリザさんによる勉強会】
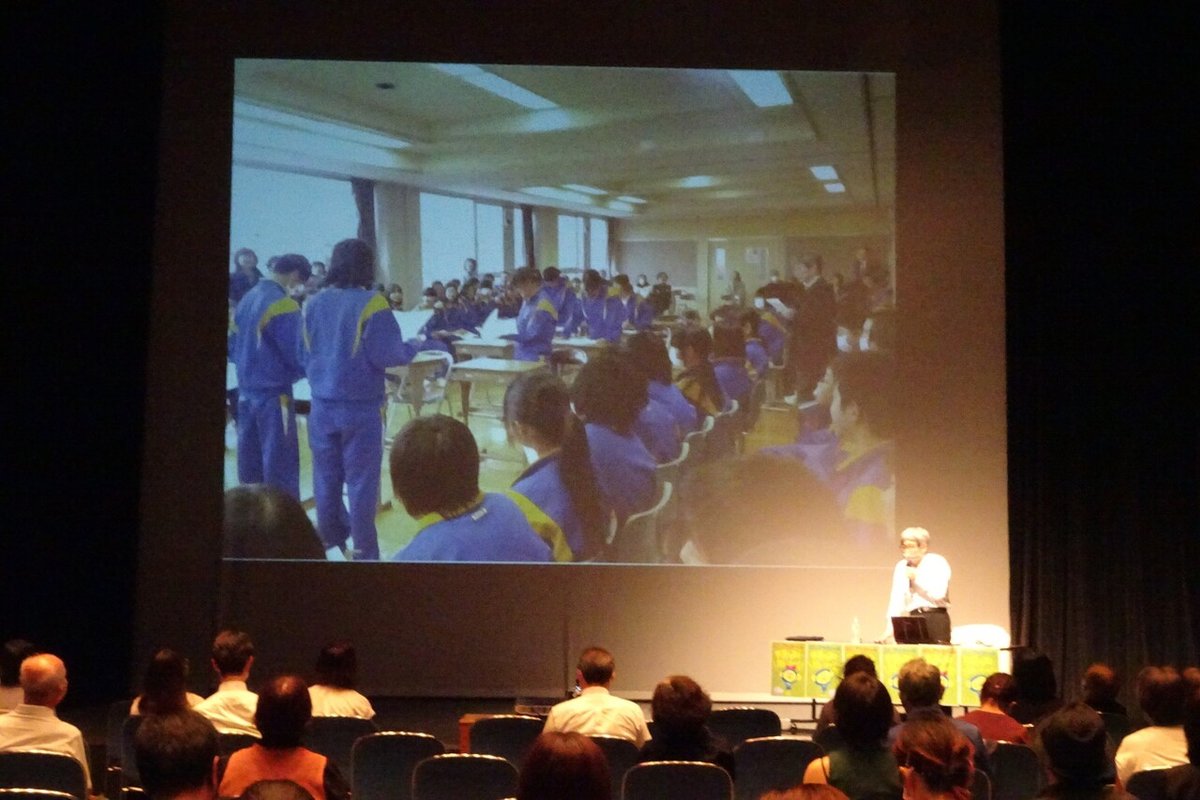
スピーチをされた方の思いに応えるように、平田オリザさんによる講義が始まりました。
常にニコニコと穏やかな口調で、時にスライドを使って資料やデータを見せながら、時にチクリと皮肉を交えながら進められるお話は多くの方の興味を引き、会場内では笑い声も多く聞こえました。話題が豊富で全ての内容を紹介することは出来ないので、特に報告者が伊丹のまちと教育に関わりが深いと感じたものを一部抜粋して紹介します。

◎これからの大学入試と身体的文化資本
これからの大学入試は、1~2年の受験勉強では太刀打ち出来ない「地頭」を問うような試験に変わっていく。詰め込んだ知識ではなく、様々な人と協働する力を問うものが増える。既に世界の大学入試は知識や技能よりも、「主体性・多様性・協働性」を測るものにシフトしており、日本でも多くの大学で、そういった能力を測るグループディスカッションなどを取り入れた試験が始まっている。
そこで必要になる能力のことを「身体的文化資本」と呼ぶ。具体的にどういうものかというと、美的感覚や感性を含むセンス、マナー、味覚やコミュニケーション能力のことである。最近は人種や民族、ジェンダーやマイノリティーに対しての偏見に対する意識なども含まれている。「主体性、多様性、協働性」という言葉も、身体的文化資本に当てはまる。
身体的文化資本は早い段階で身についてしまうため、育てていくためには子どもの頃から「本物」や「良いもの」に触れさせていく必要がある。良い文化や芸術に触れることも身体的文化資本を育むのに大きく影響するが、これらは劇場や博物館が身近にあり、常に本物に触れられる東京と、そうでない地方には大きな格差がある。地方こそ文化政策を充実させていく必要があり、伊丹市は地方でありながらもアイホールがその役割を担ってきた。他の地域にないものを持っているのに何故手放すのか?
◎なぜ、コミュニケーション教育なのか?なぜ、演劇なのか?
「非認知スキル」という言葉がある。IQや学力テストで測定出来る能力(=認知スキル)に対して、測定は難しいが知識や思考力を得るのに必要な能力のことを指す。認知スキルは家庭環境に左右されることが明らかになっているが、非認知スキルは家庭環境に左右されにくい。学力を伸ばすのに難しい家庭環境の子どもでも、非認知スキルの高い子どもは学力も高い。
非認知スキルは、挑戦する、やり遂げる、友だちの意見を聞く、友だちの意見を聞いて自分の意見を持つ、みんなの意見をまとめる中で育っていく。演劇を作る過程にこれらが含まれている。演劇を繰り返し創作していく中で非認知スキルが向上すれば、主体的に学ぶ姿勢が身についていく。結果的に学力の向上に繋がっていくだろう。
◎観光と芸術
韓国(文化観光体育部)、マレーシア(文化芸術観光省)、ベトナム(文化観光スポーツ省)、インド(文化観光大臣)などは、文化政策と観光政策を一緒に進めている。一回限りの観光ではなく、何度も足を運んでもらうためにはコンテンツが必要で、そのためにウイーンのオペラ座は毎日演目を変えている。「ナイト・カルチャー」(夜の公演)があることで、食費・宿泊費の消費が増える。伊丹の場合、空港が近くにあり、大阪、京都への観光客が多いため、それらの観光客を伊丹にも呼んでくることで経済の発展にも繋げられる。既に大阪では枚方、茨木、豊中、吹田などの北摂アライアンスで盛り上がりを作り出そうという提案をしている。新大阪も博物館や劇場などの建設を検討している。北摂アライアンスが実現すれば、伊丹はひょうごゴールデンルート(兵庫の温泉や世界遺産を繋ぐ交通ルート)が交差する絶好の位置にあたる。多くの観光客を素通りさせてしまって良いのか?コロナ後を見据え、もう一度観光に来てもらうためのコンテンツを考え始めている他地域と伊丹は逆の道を進んでいるのではないか?
一通り講義を終えたところで、最後に平田さんが25年間、伊丹で公演を続けて感じられた思いを語られました。
◎25年間、定点観測をして気付いたこと。
25年、アイホールを利用し続けてきて、定点観測をしているような気持ちになっている。
最初はJR側にほとんど店もなく、阪急周辺の方が賑やかだったが、今は逆転した。
アイホールの影響を数値化するのは難しいが、精神的な役割を果たした部分は大きいのではないか。検証できなかったとしても、うまくいった一端を担ったかもしれないパーツを外すのは疑問。
JR伊丹駅の発展に貢献し、アーティストも貢献してきたのに、それを無視してもっと収益性の良いものを求めて乗り換えるべきなのか、伊丹市民の方には考えてみていただきたい。
【感想・質疑応答】
講義の後も、時間ぎりぎりまで参加者の方から積極的に質問や感想を伝える場面がありました。

◎感想
アイフェスで演劇に出会い、社会人になってからも演劇を続けている。アルバイトとの掛け持ちが大変で、どちらが主なのかが分からなくなる時もある。海外では芸術家は尊敬されるのに、日本では逆なのでどうしてだろうと思う時もあるが、続けていて良かったと思えることもたくさんある。今はお金を持っているのが良いという価値観があるが、役に立つことの出来る人も評価されていくようになるとも言われている。今日のお話を聞いて、表現や芸術の、一見目に見えない部分も、世の中の役に立つことが出来るんだということを実感することができて感銘を受けた。
昔、不登校になった子どもを両親が殺害した事件、孫が祖母を殺害した事件が話題になったが、その考察で被疑者の家庭に本がなかったという話を思い出した。お話を聞いて、今公共施設を残さなくても良いと考えることは、子どもたちに文化資産を残さない、子どもたちの部屋に本を置かないというのと同じだと思った。事件が起きた当時から全く進歩していないのではないかと危機感を感じた。子どもたちに文化資産を残したいという強い思いで、この活動を応援していきたい。やれることをやっていきたい。
伊丹の被差別部落で生まれ育ち、ずっと差別を受けて生きてきた。今は少しずつ差別も小さくなってきてはいるが、子どもたちが踊ったり歌ったり、大人が経験してきた差別を劇にして表現したり、そういう取り組みを続けて頑張ってきたからこそである。子どもたちだけでなく、高齢者も三味線や和太鼓を頑張って続けている。兵庫県の方針で、市民会館や公民館などを減らしていく計画があると聞いた。人を大切にするということはどういうことかということを真剣に考える時期に来ている。今、社会の中で何が問題になっているのかを見抜き、連帯し、必要な力を自分たちも身につけることが大切だと思った。ともにがんばりましょう。(その後、拍手も起こる)
◎質問とその回答
質問1:演劇に詳しくはないが、平田さんの活動には興味があった。自分も田舎育ちであるが、その中でも豊岡を拠点に選ばれた理由は何か?伊丹とはどんな違いがあるか?
平田さん:豊岡に移住をしたのは大学の学長になることが決まったから。自身の移住と共に結果的に劇団の拠点も移す必要が出てきた。劇団を移転するには稽古場が必要で、日高町の江原駅前の旧町役場に拠点を構えることが出来た。実は豊岡を積極的に選んだ訳ではない。しかし、豊岡の前市長は演劇やアートを地方創生の切り札として位置付けた。豊岡市の予算ではなく、地方創生の予算で計画を進めていったため、市の予算は減っていない。むしろ地方創生の予算で観光客を集め、そのお金を豊岡市に落としている。
これまでの地方の人口減少対策は雇用を増やすことだった。男子の労働者を囲い込むことに重点を置いていた。昔は工場を建てて高卒男子が残す政策だったが、今はそういうわけにはいかない。
大学進学で都会に出て、帰ってこない子どもが増えた。特に女性の進学率が上がり、男子以上に帰って来なくなった。そこで豊岡市はジェンダーギャップを無くしていこうという取り組みを始めた。加えて、大阪や京都、神戸などの都会に触れた(子育て世代より更に下の)若者がそれでも豊岡に戻って来たくなるまちづくりをする必要があった。そこで必要だったのが(食・スポーツも含めての)文化。雇用ではない。図書館があるのか、大学で始めた習い事が続けられるのか、ジム通いを続けられるのか、これら全体の文化政策の中で、たまたま演劇を真ん中に位置づけることになった。結果大学の誘致にも成功した。
伊丹には伊丹の立地条件に合った文化政策がある。しかし、何もしなければ一気に衰退する。自治体の栄枯盛衰は20~30年もすれば逆転する。伊丹も何もなかったまちからここまでお洒落なまちに成長した。しかし逆もあり得る。みなさんが、30年後、50年後にどんなまちであって欲しいかを考えて文化政策を考えるべきで、目先の利益や収益だけで文化政策を決定して本当に大丈夫なのかと問いたい。
質問2:伊丹市の演劇部OGとして、伊丹市の方とお話させて頂く機会が何度かあった。アイホールを残したい人たちはその思いを真っ直ぐに向けられるが、そうでない人のことが見えて来ないと言われてしまった。15%という低い利用率と、9000万の維持費を市民が負担することについて、残りの85%の市民を納得させるものが必要だと課題に挙げられた。このことについてどういう意見を持たれているか?
平田さん:「誇り」には色々なかたちがあり、ベッドタウンであることを誇りに思う人もいれば、劇場があることを誇りに感じる人もいる。利用率も大切だが、アイホールがあることが誇りであるということを市民の方にどれだけ思ってもらえるか、あるいはなっていけるかが1番のポイントではないか。今は誰でもカラオケを楽しむことが出来るが、そこまでに西洋の音楽の苦難の歴史がある。それをどれだけの人に知ってもらえるかが大切。学校や病院が嫌いな人はたくさんいるが、必要無いと思っている人は少ない。劇場も同様で、劇場に来ない人にも愛されることが重要。お金のことは大切で他との比較検討も必要だが、アイホールはこれまでに外部資金もきちんと取ってきた劇場である。そのお金を種銭にして、伊丹市民は本来、税金以上に多くのものを受け取ってきているが、文化予算の性質上、それらが見えにくい。他に回すこともできない。普通の市民目線では、文化より福祉、と言われてしまう。これらの説明にはとても時間がかかる。
民主主義社会において選挙は大事だが、20年後、30年後の文化政策、教育政策の未来を今の納税者だけの意見だけで、決定して良いのか。日本社会全体に突きつけられている問題でもある。教育委員会が独立した機関であるように、本来ならばアーツカウンシルが独立して文化政策の舵取りをする必要があるが、日本ではその機能が無いため、目先の政治に振り回されてしまうのが現状である。色々知恵を絞らなければならないが、大切なのは、文化や芸術に触れられない子どもたちにいかに届けるか。劇場や美術館に行かせられない家庭の子どもたちをどうやって文化に触れさせるか。絵本が無い家の子どもたちにどうやってアートを届けるか。この問題は永久に続くが、地道に努力していくしかない。

質疑応答中も、うんうんと頷かれたり、熱心にメモを取られたりする参加者の姿が目立ちました。20年後、30年後の子どもたちの未来を見据えて伊丹の文化政策はどうあるべきか。今日は平田さんとひとつの考え方を共有することが出来たことはとても意義があり、伊丹のまちに対する視野も大きく広がったのではないかと思います。きっとこれから市民の皆さんがもっと議論をし、検討をする時間が必要になってくると思います。今日の勉強会をきっかけに、より市民の輪が広がり、対話が深まっていくことを私たちも願っています。
教育について、平田オリザさんのもっと詳しい話は、「22世紀を見る君たちへ」(平田オリザ)という本に執筆されています。
気になる方はタイトルが本の紹介ページへのリンクになっていますので、ご覧になってみてください。
