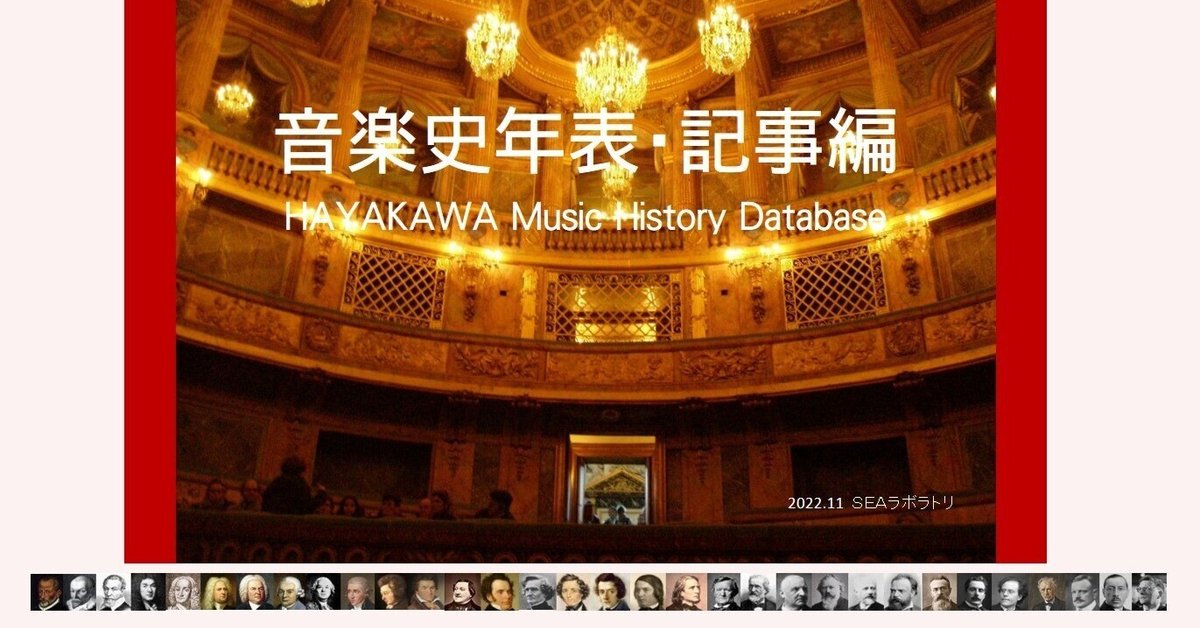
音楽史・記事編148.前期古典派の音楽史・・・古典派誕生への胎動
一般にセバスティアン・バッハが亡くなった1750年までをバロック期、1750年から1800年を古典派期とされています。バッハは亡くなるまで対位法の探求を続けていましたが、バッハの後、どのようにモノフォニー的様式とソナタ形式を中心とした古典派が生まれたのか・・・ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンを代表とするウィーン古典派がどのようにして誕生したのか・・・本編では、古典派誕生の背景を中心に見て行きます。なお、ウィーン古典派誕生の背景については次の6項目が考えられますが、本稿では(1)~(5)の前期古典派について見て行き、(6)の政治的背景は次稿で触れて行きます。


(1)ドイツにイタリアの音楽様式がもたらされる
ドイツに最初にイタリア音楽をもたらしたのはドレスデンの宮廷楽長シュッツであるとされ、ドイツ音楽の父と呼ばれています。バロック初期の1609年にシュッツはベネツィアのサン・マルコ寺院のジョバンニ・ガブリエリの弟子となり、マドリガルや宗教音楽などのイタリアの声楽様式を学び、30年戦争のさなか1628年には再びベネツィアを訪問しモンテヴェルディに師事しているところからイタリア・オペラ様式をドレスデンにもたらしたものと見られます。ドレスデンに戻ったシュッツはドイツ語のカンタータ、オラトリオ、受難曲などを作曲しています。
30年戦争でオーストリア・ハプスブルク家に勝利したプロイセンはヨーロッパにおけるキリスト教宗派としてのプロテスタントが認められ国力も増し、フリードリヒ2世の大胆で革新的な啓蒙思想のもと、フランス音楽やイタリア音楽を積極的に取り入れます。この時期ドイツとイタリアの音楽家の行き来が盛んになり、どのようにイタリアのコンチェルト、シンフォニーなどの器楽様式がドイツにもたらされたのかははっきりとしませんが、後にプロイセンの宮廷楽長となるゴットリープ・グラウンはイタリアのパドヴァで名バイオリニスト・タルティーニに師事しており、この折にミラノのサンマルティーニのシンフォニー様式を学んだのか、グラウンは生涯に100曲のシンフォニーを残したとされます。また、協奏曲様式を確立したボローニャのトレッリは1697年にはプロイセンのブランデンブルクに招かれ、合奏協奏曲を創始したコレッリはパリ、バイエルンに招かれています。ベネツィアのヴィヴァルディは多くの協奏曲を作曲し、晩年はオペラの上演のためプラハ、アムステルダム、ウィーンを訪問し、またアムステルダムでは四季などの多くの作品を出版しており、これらはヨーロッパの宮廷等で演奏され人気を得ています。
声楽の分野ではドイツではもともと質素な音楽劇であるジングシュピールが上演されていました。このジングシュピールに華やかなイタリアの歌唱を初めて持ち込んだのはシュッツとされ、1627年にシュッツが作曲したドイツ語の歌芝居「ダフネ」に初めてイタリア歌劇の影響が示されたとされています(1)。そして、1678年にはハンブルクにゲンゼマルクト(鵞鳥市場)の歌劇場がオープンし、ドイツ歌劇の中心地となります。ハンブルクではフランクやカイザーなどがジングシュピールを、そしてのちのテレマンやヘンデルがイタリアオペラを作曲し上演を行っています。また、ハノーファー近郊に生まれたアドルフ・ハッセはイタリアに遊学し、ナポリ・オペラの祖となったスカルラッティやオペラ・セリアを創始したメタスタージョと親交を結び、帰国後はドレスデンの宮廷楽長となりドレスデンばかりではなく、ウィーンやイタリア各地をたびたび訪れ、オペラ・セリアの上演を行っています。
(2)セバスティアン・バッハの平均律の実証
セバスティアン・バッハは平均律クラヴィーア曲集を作曲し、調性ごとに調律することなしにすべての調性で音楽を演奏できることを実証し、平均律の登場により転調を多用する交響曲などの作曲が可能になりました。しかし、ハイドンが交響曲を書き始めたころは、まだチェンバロを伴奏に使っていたようで、ハイドンが平均律で演奏した形跡は見当たらず、おそらく生涯、純正和声が可能な中全音律で演奏を行っていたものと思われます。この時期、ウィーンの貴族の館ではクラヴィーアの普及が進んでいたようで、これらは平均律で調律されていたものと見られます。モーツァルトは中全音律で演奏を行っていたものの、1784年頃に平均律で調律されたクラヴィーアに出会って戸惑い、モーツァルトは純正な和声を弾けないじゃじゃ馬のようなクラヴィーアを使いこなすために苦労した形跡が見られます。ベートーヴェンはボンでライプツッヒ大学で学んだネーフェにクラヴィーアを師事し、教材にバッハの平均律クラヴィーア曲集を使っていたことから平均律に抵抗はなく、多様な和声を使った作曲を行い、さらに転調を多用した交響曲などを創作しているところから、ベートーヴェンに至って初めてソナタ形式において調性の制限なしにいかなる調性への転調も自由に行える平均律が生かされるようになったと見られます。
(参考)音楽史年表記事編10.バッハの平均律が古典派様式の道を拓いた
(参考)音楽史年表記事編116.セバスティアン・バッハの創作史
(参考)音楽史年表記事編143.調律史とモーツァルト
(3)セバスティアン・バッハの主題労作の実践
セバスティアン・バッハはゴールドベルク変奏曲を作曲し、主題の変奏、彫琢などのいわゆる主題労作を実践し、ソナタ形式の展開部のあり方を示しました。セバスティアン・バッハは音楽における対位法だけではなく、バッハ以降、現代に至るすべての音楽の調律法となる平均律、また古典派期におけるソナタ形式や交響曲様式で重要になる主題の展開、変奏、彫琢などの主題労作の分野においても大きな成果を残しています。サンマルティーニのソナタ形式とセバスティアン・バッハの音楽様式を融合させたのはバッハの3男エマヌエル・バッハと見られます。エマヌエル・バッハの音楽は多感様式として知られますが、ソナタ形式においてはその展開技法や再現部の主題再現において、エマヌエル・バッハの様式の礎石とみなすべき一種の動機変奏を作り出したとされます。(2)
(参考)音楽史年表記事編52.ピアノのための変奏曲創作史
(4)ソナタ形式の誕生の謎
ソナタ形式はイタリア・ミラノのサンマルティーニのシンフォニー以降生まれたものと考えられますが、どの作曲家あるいはどの楽派がどのように関わり成立したのかは難しい問題であり、謎に包まれています。本編の出稿にあたりニューグローヴ世界音楽大事典(2)のジョヴァンニ・バッティスタ・サンマルティーニの記載項目を参照しましたので見て行きます。以下、ニューグローヴ世界音楽大事典によれば・・・
①サンマルティーニの初期の交響曲19曲は急・緩・急という3楽章構成で、いくつかは終楽章がメヌエットになっている。
②長いアレグロ楽章はたいていソナタ形式で、緩徐楽章とメヌエットには単純な2部構成がよく用いられている。
③ソナタ形式で書かれた楽章は、明確に定められた調性の範囲、複数の主題ないし主題的な対比、長い展開部、ほとんど常に主調に置かれた冒頭主題で始まる明快な再現部などを有している。
④サンマルティーニはコンチェルトの叙情的な緩徐楽章を交響曲に取り入れた。彼は古典派の緩徐楽章の標準的な型となる2/4拍子のアンダンテを好み、メヌエットは速い3/8拍子より中庸のテンポの3/4拍子であることが多い。初期の交響曲に主に影響を与えたのはイタリア序曲よりむしろコンチェルトやトリオ・ソナタであった。
⑤中期の37の交響曲のほとんどは弦楽の他にホルンかトランペットを2本必要としており、またその終楽章はメヌエットであって、その幾つかはトリオの部分を持っている。ほとんどの楽章は、緩徐楽章やメヌエット楽章を含めて、ソナタ形式で書かれている。
これまで筆者にとってもサンマルティーニの実像は謎に包まれていましたが、ニューグローヴ音楽事典の記載では、サンマルティーニは単にオペラのイタリア序曲を演奏会用に置換えたのではなく、後の古典派のソナタ形式などの様式を交響曲で積極的に試み、しかもこれらの交響曲はヨーロッパ各地で演奏されていたとされています。プロイセンからイタリアに渡ったグラウンなどの作曲家はイタリアでサンマルティーニの交響曲様式を学び、その楽譜を持ち帰り、新しい管弦楽様式に魅せられたドイツの人々は競ってシンフォニーを作曲し、さらにエマヌエル・バッハなどによってセバスティアン・バッハの対位法、主題労作などの様式を融合させ、これらを交響曲に応用したマンハイム楽派のシュターミツやウィーン楽派の作曲家によって古典派交響曲様式に完成していったものと見られます。
以上のように、ソナタ形式はドイツの音楽家によって形作られたというよりも、既にイタリアのサンマルティーニによってほぼその形を整えており、ドイツに伝わりバッハの対位法や主題労作などの作曲技法が融合し、さらにマンハイム楽派のシュターミツ、ウィーン楽派のヨーゼフ・ハイドンによって古典派の主要な様式に成熟していったものと見られます。
(5)ウィーンのフックスの対位法教程とメタスタージョのオペラ改革
マリア・テレジアの父の皇帝カール6世の宮廷楽長フックスは1725年対位法教程である「グラドゥス・アド・パルナッスム」を著し、ウィーンの対位法がヨーロッパにおける作曲様式を主導します。セバスティアン・バッハも対位法の大家となりますが、バッハの対位法の真価が認められるのは後のこととなります。また、1730年にはメタスタージョがウィーンに招かれ、新たなオペラ台本の創作を行い、従来のバロック・オペラから喜劇的部分を排除したオペラ・セリアの様式を確立しします。このようにウィーン楽派と呼ばれる音楽家たちはウィーン古典派とよばれる輝かしい音楽史への基盤を着実に築いてゆきます。
(参考)音楽史年表記事編13.教程書となったフックスの対位法理論
【音楽史年表より】
1730年頃作曲、サンマルティーニ(32)、シンフォニア
イタリア・ミラノのジョヴァンニ・サンマルティーニはオペラの序曲であるシンフォニアを演奏会用シンフォニアとして作曲するが、これはもう交響曲(シンフォニー)というべきである。サンマルティーニはすでにオペラのシンフォニアの第1部にみられた対比する2つの動機を対比する主題に拡大し、ソナタ形式の提示部の形をととのえるようにした。つづく展開部では動機的処理をみせ、好んで対位法的書法もみせた。第2部のカンタービレでは規模を大きくし、第3部では従来の3/8拍子からもっとテンポの遅い3/4拍子のメヌエットのテンポにすることが多かった。(名曲解説全集より)
【参考文献】
1.堀内敬三著、音楽史(音楽之友社)
2.ニューグローヴ世界音楽大事典(講談社)
SEAラボラトリ
