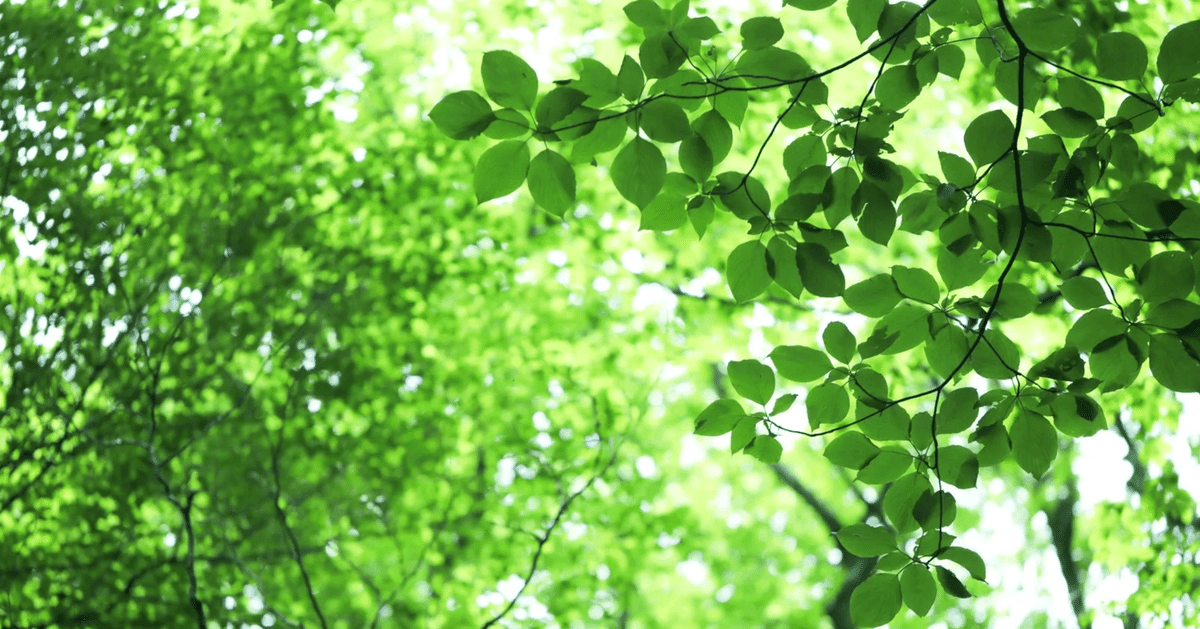
【長編小説】 初夏の追想 1
――今年も、あの季節が巡ってきた。
野山は息を吹き返し、来たるべき夏に向けて威儀を正し、身支度を整える。花々は春のあいだの狂気じみた宴を恥じるかのように少しずつ身を隠し、取って替わって、木々の若葉が芽吹きを競う。一年じゅうで生物がもっとも成長するとき、初夏と呼ばれる季節である。
ここを離れてから三十年ぶりに、私は戻って来た。
いや、正確には、ここに戻って来ることを三十年間躊躇っていた、と言ったほうがいいのかもしれない。それほどに、この土地には、私にとって大切な、安易に犯すべからざる数々の記憶が眠っているのだった。
これまでにも何度かここへ足を運ぼうとしたことはあった。だが、そうしようとするたび、かつて過ごした日々のイメージが甦り、その圧倒的な力でもって、私の足を地面に縛りつけてしまった。当時ここで起こった出来事のすべてがあまりにも鮮やかに脳裏に焼きついているがために、私は、実際そこに立ち戻ってそれらのものの面影が少しでも損なわれているのを直視する勇気が持てないのだった。
その勇気を出すことがようやくできたのは、六十の齢を迎え、人生の終末を予感する時期が来たときであった。そのころから、その古い記憶は折々に私を訪れるようになった。私は夢に彼の面影を見、晴れた冬の日の夕刻に、縁側の籐椅子に座ってうとうとしている目の前で、昔撮った8ミリフィルムの映像のようにあの日々が再現されるのを見たような気がした。
記憶の断片たちは、次第に頻繁に訪れるようになり、いまや意識の底から私に思い出してくれとせっついているかのようだった。
そのことは、私を懐かしく微笑ましい気分にさせたが、同時にそれとはまったく逆の、悔悛にも似た苦い想いを運んできた。あの出来事はしつこく私の心の中に根を張り、肉体の奥深くに巣食いながら、なおも生き続けようとしているかのようだった。私はその感情をどう処理していいかわからず、しばらくのあいだ、思い悩んだ。
――そして、ついに私は決意したのだった。この場所に立ち戻り、このことを、物語にして書き出すことを。そうしないわけにはいかなかった。あのときこの場所で起こったすべてのことを、私にできたこと、できなかったこと、当時は理解できなかったが、ずいぶんあとになって少しずつわかりかけてきたことなどを、すべて偽りなく書くことで、あの出来事が結局自分にとって何を意味するものだったのか、理解しようと思った。いや、少なくとも、理解できるよう努力してみようと思った。
私はこの土地の不動産会社に問い合わせ、いまでもあの家屋が残っているか調べてもらった。不動産会社は、すぐに報告を送ってきた。その報告によると、あの土地はいまや空き物件だらけで住んでいる人はほとんどいないとのことだった。
あの浮かれ騒いだ経済景気の時代が終わりを告げたあと、人々は相次いでその土地を去っていた。彼らも私がそこを離れてからしばらくして家と土地を手放したということだった。
私は早速その家屋を買い求めた。当然ながら経年劣化が著しく、建物のあちこちが傷んで大幅な修繕が必要とのことだったが、そのおかげでちょっと考えられない価格で手に入れることができた。この規模の、この造りの家としては破格の値段だった。
けれどそれを、私はごく当たり前のこととしてとらえていた。まるで、家が私を呼び、私の終の棲家はここしかないと囁いているかのようだったから……。
