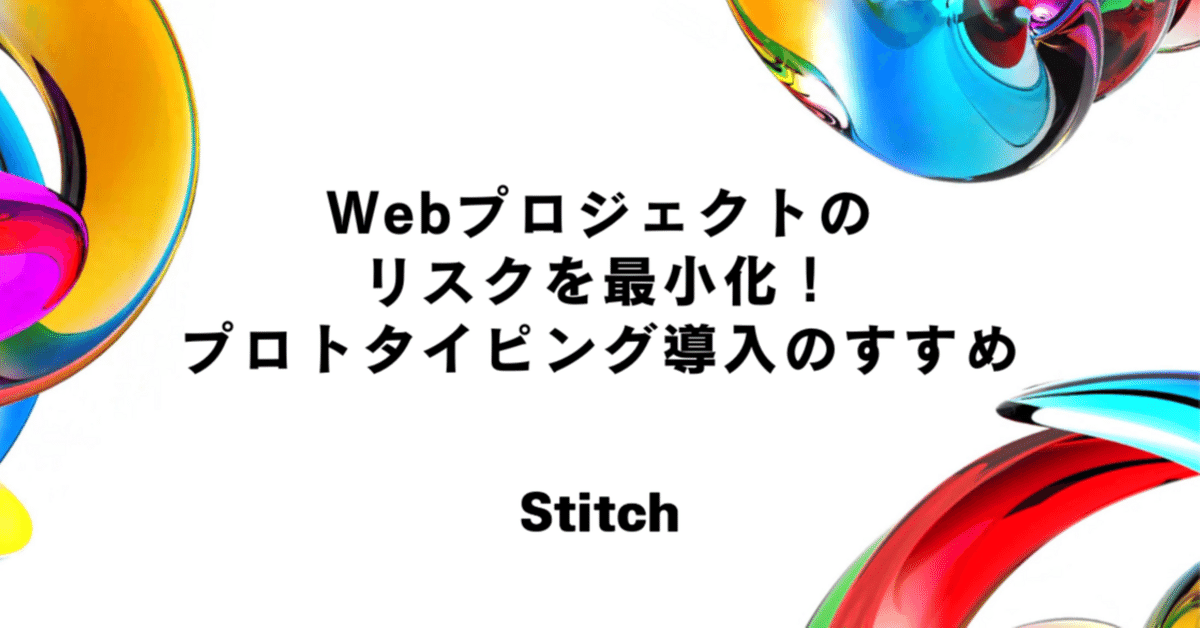
Webプロジェクトのリスクを最小化!プロトタイピング導入のすすめ
Web制作・運用などのプロジェクトにおいて、「成果物の認識ズレ」や「初期段階で課題に気づけずスケジュール遅延」などの課題に陥った経験はありませんか?こうした課題は、多くのプロジェクトで繰り返されてきました。
その解決策として注目されているのが、「プロトタイピング」です。
弊社執行役員 兼 S&D PROTOTYPING株式会社リードディレクターである三冨は、プロトタイピングの専門家として、さまざまなプロジェクトの課題解決を支援してきました。
本記事では、プロトタイピングの手法やその効果、そして実践的な活用方法について解説します。Webプロジェクトをスムーズに進めたいとお考えの企業担当者や広告代理店の皆様、ぜひご一読ください。
プロトタイピングとは?
プロトタイピングとは、Webサイトの完成前に「仮の成果物」を作成し、関係者間で共有・確認を行うプロセスです。この仮の成果物を「プロトタイプ」と呼び、以下のような種類があります。
構造プロトタイプ
ページの情報構造やレイアウトを視覚化した試作版。具体的なデザインや機能を含まない、低解像度のプロトタイプであり、主に全体の構造やナビゲーションを整理する目的で使用されます。
例:ワイヤーフレーム、 サイトマップなどインタラクティブプロトタイプ
画面遷移やボタン操作といったユーザーインタラクションを再現する試作版。静的なデザインではなく、実際の操作感を体験できるプロトタイプで、ユーザーエクスペリエンスや操作フローの検証を目的とします。
例:デザインツール(Figma、Adobe XDなど)を使用したクリック可能なモックアップ機能プロトタイプ
システムの動作やユーザーの操作フローを再現するための試作版。UIだけでなく、基本的な機能やデータフローを実装することで、動作確認や検証を行います。
例:ノーコードツール(Bubble、Webflowなど)を使用した簡易的なシステム
プロトタイプは作成された「もの」そのものを指し、それを活用して行う検証プロセスが「プロトタイピング」です。この手法は単なる試作ではなく、プロジェクトの成功確率を高めるための重要な戦略として機能します。
Webプロジェクトで発生しがちなトラブル
Webプロジェクトで発生しやすい課題をいくつかご紹介します。
関係者間の認識のズレ
完成形に対する理解が共有できておらず、リリース直前に大幅な修正が必要になる。期待外れの成果物
開発が進むまで成果物の問題に気付かず、結果としてユーザーのニーズに合わない仕上がりになる。修正コストの増加
完成後の問題対応が発生し、スケジュールの延長や追加コストが避けられない。スケジュール遅延
初期段階で課題が十分に共有されないため、後工程にしわ寄せが発生。
こうした課題は、新規事業開発の分野でも顕著であり、非効率なプロセスによる資源の浪費がしばしば指摘されています。特に、プロトタイピングを適切に活用しない場合、手戻りが増加し、プロジェクト全体の投資収益率に悪影響を与えることが先行研究でも示されています。
プロトタイピングで解決する方法
プロトタイピングは、上記のトラブルを未然に防ぐための効果的なアプローチです。その理由は以下の通りです。
認識の共有
試作品を用いることで、関係者全員が成果物のイメージを視覚的に共有できます。特に、情報量の多いプロトタイプは、言葉だけでは伝えきれない細部まで共有するのに役立ちます。早期のフィードバック
プロトタイプをユーザーや関係者に操作してもらい、リアルな反応を確認することで、改善点を早期に特定できます。課題解決の効率化
プロトタイピングを通じて行われる検証やテストは、「コミュニケーション」「学習」「意思決定」の3つの役割を持つとされています。これにより、最終成果物の品質を大幅に向上させることが可能です。コストと時間の最適化
プロトタイピングは、開発後の大規模な修正を未然に防ぎ、スムーズなプロジェクト進行を実現します。
プロトタイピングの導入手順
以下のステップでプロトタイピングを導入すると、効果的にプロジェクトを進めることができます。
目的と範囲の明確化
プロトタイピングの目的を明確にし、試作する部分や検証したい内容を具体的に設定します。
例:「ユーザーの操作フローの確認」「画面遷移の分かりやすさの検証」。試作品の作成
ワイヤーフレームやモックアップなど、必要に応じて適切なプロトタイプを作成します。必要であれば、実際の体験を再現する「体験プロトタイピング」を採用します。テスト計画と準備
ユーザーに試してもらうテストの目的や対象者、検証項目を具体的に整理。実施環境やシナリオを整え、スムーズなテスト運用を準備します。テストの実施とフィードバック収集
プロトタイプを実際にユーザーに操作してもらい、インタビューやアンケートを通じて改善案を収集します。改善案の策定と実行
フィードバックを基にプロトタイプを修正し、数回繰り返して完成度を高めます。最終成果物への反映
最終的にブラッシュアップしたプロトタイプを基に、本番開発へと移行します。
おすすめツール
プロトタイピングを進める上で、目的や用途に応じて最適なツールを選ぶことが重要です。以下に代表的なツールをご紹介します。
Figma
特徴: クラウドベースで共同編集が可能。リアルタイムでチームメンバーと作業できるため、リモート環境でも円滑に進行できます。
用途: ワイヤーフレーム、デザインモックアップ、クリック可能なプロトタイプの作成に最適。STUDIO
特徴: ノーコードツールで、デザインから実際のサイト公開まで対応可能。プロトタイプを本番環境に近い形で試せます。
用途: サイト全体のデザイン確認や、運用も視野に入れたプロトタイピングに最適。Bubble
特徴: ノーコードプラットフォームで、バックエンド機能(データベースやAPI連携)を含む高度なWebアプリケーションのプロトタイプを作成可能。
用途: 複雑なWebアプリやSaaSプロジェクトなど、システム全体を試作したい場合におすすめ。
プロトタイピングを活用した成功事例
S&D PROTOTYPINGでは、さまざまな企業様と連携し、プロトタイピングを活用したサービス・プロダクト開発やキャンペーン設計を支援しています。
本記事では、その中から2つの事例をご紹介します。それぞれの取り組みがどのようにプロトタイピングを活用し、成果を生んだのかお伝えします。
事例1: サントリーホールディングス株式会社
"金麦"のサービス・キャンペーン開発プロジェクトにおける、短期間での集中的なプロトタイピングスプリント

課題
サントリーの人気ブランド「金麦」において、新しいキャンペーン施策を迅速に開発し、ユーザーニーズに即したアイデアを実現する必要がありました。しかし、膨大な数の初期アイデア(20案)の中から、どれをブラッシュアップすべきか選定し、限られた時間で高精度な成果を生み出すには、効率的なプロセス設計が課題となっていました。
アプローチ:採用したプロトタイピング手法
プロトタイピングスプリント:6週間で2回のスプリントを実施。ユーザーの反応を確認しながら段階的にアイデアを絞り込みました。
並行プロトタイピング:複数のアイデアを同時に進め、学習効果を最大化。
ダークホースプロトタイピング:あえてリスクの高いアイデアも残し、予期せぬ発見を生むプロセスを採用。
体験プロトタイピング:ランディングページの作成やLINEを活用した仮想体験を通じて、ユーザーから具体的なフィードバックを得る方法を導入。
取り組みの詳細
初期段階で20案のアイデアを評価軸に基づき選別。第1スプリントで6案、第2スプリントで3案に絞り込み。
チラシやランディングページを作成し、ユーザーインタビューを実施。特にLINEを用いた3日間の体験プロトタイピングでは、ユーザー行動を詳細に記録し、具体的なフィードバックを収集しました。
プロトタイピングの成果を基に、ステークホルダーへの説得材料を強化。ユーザーインサイトを反映した説得力のあるプレゼンが可能となりました。
結果
プロトタイピングにより、ユーザーに需要の高いキャンペーンアイデアの生成に成功。さらに、関係者全員で課題を共有し、意思決定のスピードと精度を向上させました。特に、体験プロトタイピングはユーザー行動を深く掘り下げる効果を発揮し、成果物の品質向上に寄与しました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
事例2: パナソニック ホールディングス株式会社
高齢者を対象とした新価値創造を目的にしたプロジェクトのデザインプロセス設計・伴走

課題
パナソニックでは、高齢者を対象に新たな価値を生み出すプロジェクトを進める中で、解決すべき課題や提供すべき価値が不明確な状態に直面しました。ユーザーインサイトを迅速かつ正確に把握し、それを基に価値を具体化するプロセスが必要とされていました。
アプローチ:採用したプロトタイピング手法
定性リサーチ:高齢者や専門家へのインタビューを実施し、KJ法で分析することで課題を抽出。
定量リサーチ:ウェブアンケートを実施し、相関分析やクラスター分析を通じて、行動や心理の傾向を把握。
探索型プロトタイピング:高齢者の身体的・心理的な状態を疑似体験するプロセス(「高齢者疑似体験セット」やVR活用)を実施。
エクスペリエンスプロトタイピング:ユーザーが具体的な価値を体感できるプロトタイプを作成し、フィードバックを得る。
取り組みの詳細
プロジェクト初期段階では、デスクリサーチやペルソナ・カスタマージャーニーを策定し、チーム内で課題認識を共有。
専門家や高齢者へのインタビューを通じて課題を深掘りし、KJ法を用いて発言をグルーピングすることで、課題の構造を可視化。
並行して実施した定量リサーチでは、家族との交流頻度やコミュニケーションに関するデータを分析し、課題に関する傾向を数値的に把握。
1回目のプロトタイピングスプリントで4案のプロトタイプを開発、2回目のスプリントではさらに3案をブラッシュアップし、ユーザーインタビューを実施しました。
結果
高齢者向け仮想散策アプリ「つれづれめぐり」のアイデアを具体化。30日後の利用継続率が75%と、一般的な健康アプリの約5.4倍を達成。
探索型プロトタイピングにより、高齢者の身体的制約や心理状態に関する深いインサイトを得て、より価値のあるサービス設計を実現しました。
定性・定量データの統合的な分析を通じて、課題の明確化からアイデア創出、具体化まで一貫したプロセスを確立しました。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まとめ
Webプロジェクトを成功に導くためには、初期段階での認識の共有や方向性の明確化が欠かせません。しかし、これを実現するには、関係者全員が同じゴールを共有し、ユーザーのニーズに基づいた改善を迅速に進めるための仕組みが必要です。
その鍵となるのが、プロトタイピングです。
プロトタイプを活用することで、認識ズレや期待外れの成果物を未然に防ぎ、開発プロセス全体の精度と効率を高めることができます。また、「コミュニケーション」「学習」「意思決定」という3つの役割を通じて、プロジェクトの成功確率を大きく向上させることが可能です。
プロトタイピングについてもっと知りたい、または具体的に導入を検討したい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
記事監修

三冨敬太(S&D PROTOTYPING株式会社 リードディレクター 兼 株式会社ステッチ 執行役員)
プロトタイプの構築からプロトタイピングプロセスの研究まで、プロトタイピングに関して具体と抽象のレイヤーを行き来して活動している。広告会社でのデジタルサービスの開発経験が長いため、デジタル周りのプロトタイピングが専門。破損した彫像や完結していない小説、プロトタイプなどの未完成なモノが好き。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了、研究員。
