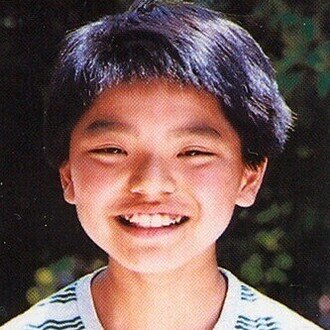変分原理 6(完) - 僕と変分原理
続きです。完結編。
変分原理とは?
変分原理とは、「自然界では何かを最小(または最大)にする道が選ばれる」という物理学の法則のことです。かなり幅の広い法則で分野ごとに様々な装いを見せます。
解析力学でまず衝撃を受けました。
それまでは、古典力学というのはニュートン力学の3法則から始めるものだと思い込んでいたのですが、最小作用の原理という運動の経路は作用というものが最小になるように決まるという法則から始めて、ニュートンの法則を導いてしまうという展開。僕がそれまで思っていたより物理は自由だなと感じた出来事でした。
幾何光学においてはフェルマーの原理という光路は時間が最小になるように決まるという法則からスネルの法則を導くことができます。この導出も最小作用の原理からニュートンの法則同様に感激しました。
スネルの法則は光の屈折の法則で高校でも習いますが、高校までの説明だとなんかふわふわしていて釈然としない。まあ、光というのはかなり厄介な存在で大学で勉強しても依然としてよくわからないのですが・・・。
量子力学の中で迷子になっていた僕に手を差し伸べてくれた一人はやはりファインマン。ファインマンの経路積分は、最小作用の原理の拡張になっていて、量子力学と古典力学を統一的に理解する手助けをしてくれます。それでもいまだに迷子のままですけれど。
物理学以外では
ここまでは純粋に物理学の中での話なのですが、本屋で偶然、変分原理の地理学的応用という本を見つけました。この本の中で、変分原理の説明から始めて、架橋や登山道の形成などの中にも変分原理が成り立っているのではないかということを論じています。
ここで思い出したんですよ、東横線の多摩川橋梁を。
僕の小学生時代は1980年代。この本に出会ったのが2003年。
なにかのテレビ番組で野坂昭如さんが「どんな問題でも20年ぐらい考え続けると自分なりの答えが見つかるものだ」みたいなことを言っていたのを覚えています。
子どもの頃の疑問や引っ掛かりをもにゃもにゃ考え続けることだけが生きがいの僕からするとこの言葉は大きな支えになっています。
税制の方向性を見ておけば国が何を考えているのかわかる
最後にもう一つ。最近税制が話題になっているのでそれにまつわることを。
義理の父は会計や税務を仕事にしている人なのですが、パソコンの調子が悪くなると呼び出されまして、色んな話をします。
父が言っていたことで印象に残っているのは「税制には国がどうしたいと思っているのかわかりやすく現われるからそれだけ見ておけばいい」。
これを変分原理に即して説明してみましょう。
われわれはとにかく税金を払いたくありません。払う税金がより少なくなる方向に行動する力が働きます。最小税金の原理ですね。(僕が今、適当に名付けました)
このことを国はよくわかっています。税制を変えることで社会の方向性を誘導できると。しかも、助成金や補助金を配るのと違って、税制を変えるのにはほとんどお金がかかりません。(税制が変わるとインボイスのように民間は迷惑被るんですが、これ自体も景気対策になっていると思っている節がある。)
国や行政は新しい種類の税金を導入したがりにみえますが、それは税収の安定とともに、社会の方向を誘導する手段を増やしたいと考えているのだと思います。
これでこのシリーズは終わりにしたいと思います。
相続に備えて、相続税最小になるたたき台は作っておきたいがやる気がおきない今日このごろ。
いいなと思ったら応援しよう!