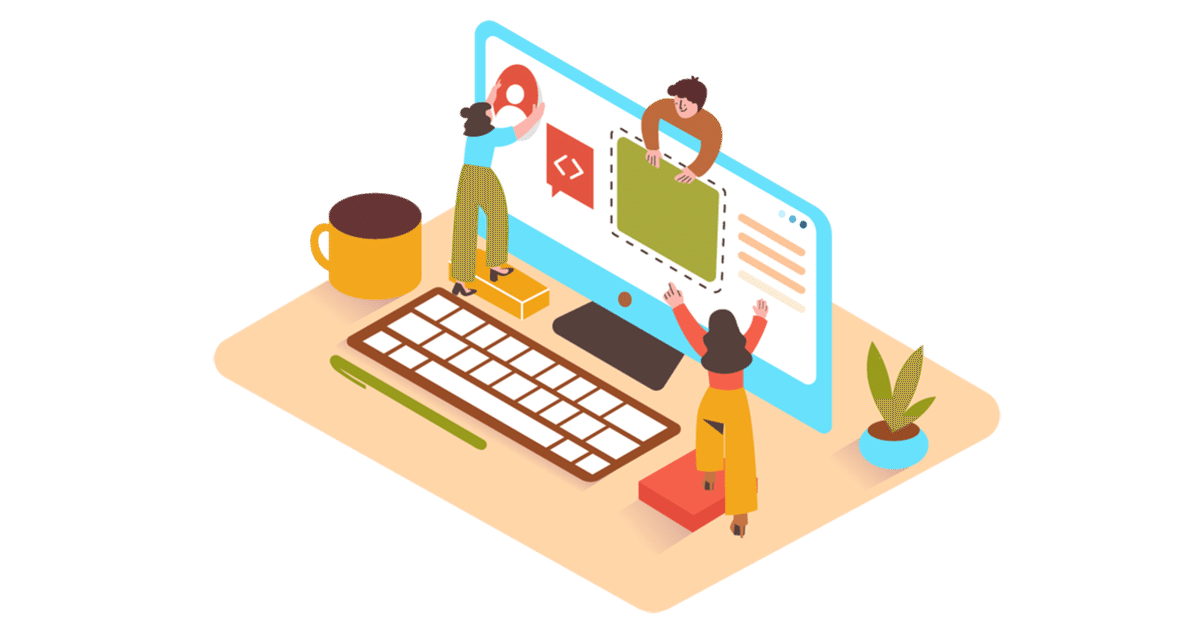
「タスク指向UI」と「オブジェクト指向UI」の狭間で
※ このノートは「DHU Kuriyaゼミ Advent Calendar 2021」12月16日分の記事です。
さて アドベントカレンダーと言えば、もともとは お菓子などが入った小窓のあるカレンダーを開けて、クリスマス当日が来るのをワクワクしながら待つものです(毎回 この書き出しで文章をスタートしています、笑)。
ただ 近年の Web/IT系の業界では、「アドベントカレンダー」と言えば 特定のテーマに沿って クリスマスまで 毎日ブログなどに記事を投稿していく企画として定着をしています。もちろん、Web制作やWeb活用を軸に置いた研究活動を行なっている ワタシのゼミですから、毎年 アドベントカレンダーを実施しているという訳です。
さて、今年のアドベントカレンダーの一巡目のテーマは「WebのUIについて どんな観点でもよいので 記事を書いてみよう!」。
ということで、ワタシは「OOUI」(これが何か?は後述)を切り口として、「WebのUIはどうあるべきか」を気軽にお話して行きたいと思います。

そもそも「UI」とは何でしょうか。この言葉は「User Interface(ユーザーインターフェイス)」の頭文字を取ったもので、直訳をすると「ユーザーとの境界や接触面」となります。Webサイトでは 掲載されるコンテンツの在り方すべてが(Webページそのものが)UIとなります。そして、UIが ユーザーとコンテンツ(サービス)をつなぐものである以上、そこには「使いやすさ・分かりやすさ」が求められることになります。

そして 使いやすいUIを設計するための考え方として、「OOUI」という言葉が聞かれるようになりました。またまた 横文字が出て来ましたね(笑)。この言葉もまた 英語の頭文字を取っています。「Object Oriented User Interface = オブジェクト指向UI」を指すものです。ユーザーが目当てとするモノ(オブジェクト)を起点として UIを設計しよう!という考え方になります。
例えば、スマートフォンの写真アプリは オブジェクト指向UIで設計されています。「写真を選ぶ」(モノを起点にする)→「メールで送る」or「複製する」or「削除する」or「SNSに投稿する」などのタスク(行動)を選択する と流れていきます。そもそもスマートフォン自体も オブジェクト指向UIで設計されています。画面には さまざまなアプリ(オブジェクト)が並んでおり、それらを選択するところからスタートをして、各種タスクを選択して行くという流れを取ります。
でも、このようなUIは 今でこそ 当たり前のように使われるようになりましたが、以前はそうではありませんでした。写真アプリを起動すると、まずはタスクの選択を求められます。
「メールで送る?」or「複製する?」or「削除する?」or「SNSに投稿する?」
↓
「SNSに投稿するんですね!では、どのSNSへ投稿する?」
↓
「Facebookへ投稿するんですね!では、どの写真を投稿しますか?」
という具合です。このように、タスクの選択からスタートして、次のタスクに進んで行き、目的のモノ(オブジェクト)に到達させるUIを「タスク指向UI」と呼びます。このような方法は、例えば 銀行のATMのように 目的のモノを選ばない時には ユーザーを目的に対してエラーなく導くことができるため有効に働きますが、タスクの数が多く複雑になればなるほど「ユーザーの目的への到達」を遠ざけてしまう結果になります。
そして、Webデザインの分野では 長らく このタスク(目的への間口)を増やすことで ユーザーをさまざまな情報へナビゲートすることに重きを置いてきたように思います。ただ、この手取り足取り 手厚くナビゲーションをすることは、かえって「情報が煩雑になる」「目的に達するまでの手数を増やす」「違うタスクを行ないたい時に、手戻りが発生する(結果、さらに手数が増える)」ことを生み、ひいては UIを「使いにくく・分かりづらい」ものにして来たのだと思います。
オブジェクト指向UIは 目的とするモノが見えているため、ユーザーは直感的に操作をすることができ、容易に目的へたどり着くことができます。
「タスク指向UI」と「オブジェクト指向UI」の狭間で。
ワタシのゼミのみなさんには、これまでの固定概念にとらわれず、「自由に・大胆に」WebのUI構築に臨んでもらいたいと思っています!
P.S.
ここまで 記事を読んでくださったみなさま、本当にありがとうございます。ここで行なった「オブジェクト指向UI」の話は、ほんのさわりの部分です。ご興味をお持ちの方は、ぜひ 深掘りをしてみてください。
