
SUNABACO DX人材育成講座 第11回 ユーザビリティとエンジニアリング
今、ここで明かされる真実。全ての伏線を回収した先にあるものとは!
「僕たちはドラえもんになるために訓練されていた‼️」

仕事ができるとは、まさに
「あんなコトいいな、できたらいいな」を実現する力である!
今までの講座は、
あんなコト(全ての関係者から、解像度の低いニーズを拾い)いいな
できたら(具体的な実践を積み上げて、ユーザーの望む形でかなえる)いいな
のための、準備と知識でした。
今回の講座を受講し、全ての講座を人繋がりで解釈した我々受講生は、
あらかじめ計画された再現性のある「量産型ドラえもん」
となるべく、卒業制作へと挑むのであった・・・

実際は、その時その時のあんなコトをきき、その時のできたらいいなを叶えるサイクルを回すことになります。
それでは具体的に実行していきます、
前回の質問コーナー


人が商品を買わない五つの理由
「人の行動には必ず理由がある」
1)あなたの商品について納得していない
2)あなた自身を信用していない
3)あなたの会社を信用していない
4)行動の境界線が高く、なかなか決断しない
5)痛みを感じていない、焦っていない
医療業界において、製品としてできてはいるが、使われないのは、
4)の要素が大きいかなぁ(新しい行動ができない)
5)だけども、すでに痛みを感じなくなっているってのもあるかもしれない。

前回マーケティングの裏の部分の説明もした。
マーケティングは人の心にどうやって響かせるかが本質になってくるので、ダークサイドは自ずと必要となってくる。
それも含めて上手に使いこなす。

何よりも、「顧客に聞く」が重要であるが、
うまくいっているものを「パクる」から始めるのがいい。
ただし、そのものを模倣するのではなく、どういうナラティブから来ているかを調べてそれを模倣することが重要。

実際に商品を作ると、コストもかかる。
観測気球を掲げる「まだ何も決まっていないことをXで挙げてみる。」その反応を見て、その傾向を見て必要なものを組み立てる材料のする。
「プロセスエコノミー」
完成していない情報でもどんどん出していく。それを作っていく工程から見せていく。
途中の状態で出していくことで、「お客さん」から「自分の」ナラティブになってくる。共犯者に仕立て上げる。
途中経過を出して行ったり、問いかけたりすることで、その反応を観測しそれによってお客さんの目処が立つ。さらに、反応をくれる見込みお客さんにアジャストした内容を準備できる。
それが採用されるとさらにお客さんにとっての自分のナラティブになって味方を作っていく。
クラウドファンディングはナラティブに引き寄せるマーケティングである。
話題性+支援者のナラティブにする。

市民のみんなにとって優先度が高いのなら、そうである。

今まで
質問コーナーに時間をとって解説していること
スラックのコメントを「名前付きで」紹介すること
Xの発信を推奨し、講座以外での繋がりを作ること
これら全てが、この講座をSUNABACOと自分自身で作る「受講生のナラティブ」になるための、大きな仕掛けだった!
SUNABACOは我々受講生を「お客さん」ではなく、「参加者」「共犯者」に仕立て上げる。

Webでの講習会は、講義(定着率5%)のさらに下をいく。
SUNABACOのDX人材育成講座は、Web上でもこういった仕掛けにより自分のナラティブにすることで、受講生は自分のナラティブになります。
可処分時間を大量に(週三回3時間)を捧げることや前述の「仕掛け」で、前のめりになる受講を促し、形だけではない「グループ討論」+「自ら体験する」(定着率75%!)を実践する。
おそらく卒業制作により、一部の受講生は「他の人に教える」(定着率90%)に到達する可能性もありうる。

第11回ですよ!終わったから「こんなもんか」と思っているかもしれませんが、我々は、2ヶ月可処分時間を「33時間」チャージして使用しているのです!
最終回!(卒業制作を除く)SUNABACOが伝えたかったこと。
ユーザビリティエンジニアリング

今までの講座は、それぞれ独立した講義体系があり専門の書籍があった。
「ユーザビリティエンジニアリング」は、体系的に学習する方法がない。
DX人材育成講座は、この「ユーザビリティエンジニアリング」をできるようになるまでの講座である。
これを学ぶために必要な基礎知識を今までの10回で学んできた。
仕事ができる天才とは?
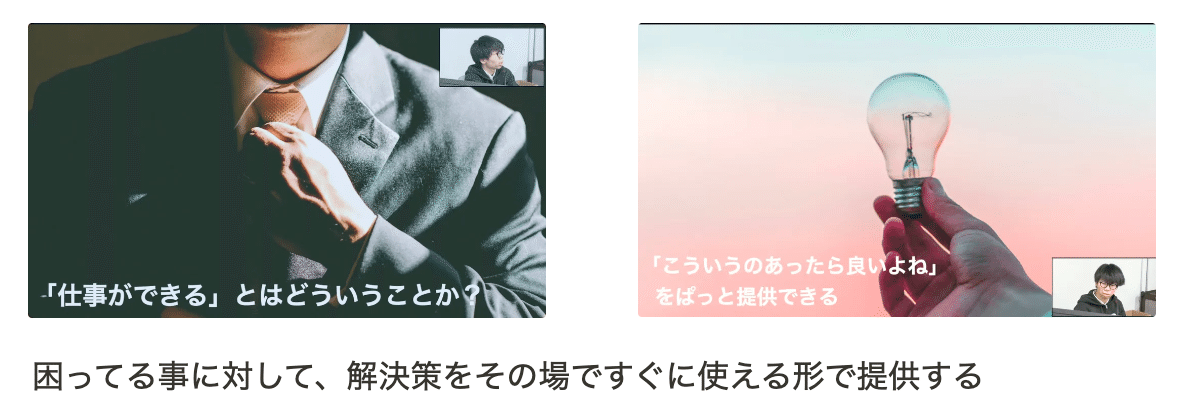
仕事ができる人材とは、真に求められるものをすぐに提供できるか
「再現性を持って関わる人たちに価値を提供する」人材を作る
つまり、「シゴ出来人材」を量産する
天才を理屈に落とし込む講座である→再現性を持たせる
小さく、無理無駄なく価値を生み出す。
一発でそれを見つけることは才能ではあるが、確実に積み上げることで、天才や才能を再現可能にする。
ドラえもんが最強なのは、
「のび太くんの言葉にならないニーズを適切に汲み取り、無数にある秘密道具から適切なアイテムを選び出し、どうやって解決するかを説明し、利用可能にしている」


ではどうすればいいのか?
抽象度を下げる、解像度を上げて具体化する。

売り上げを上げなきゃ!(抽象度が高い)ではなく、どこがダメなのかを細かく分解し、それぞれの要素で解決(実は仕事内容の共有が悪い等)できる問題を考える。


さらにお客さん自身もわからない。
パーソナルな需要の時代に変わっている。その時その需要はどうやって拾い上げるか?

(聞いてもわからないので、いっぱい聞いて、本人の気づかないニーズを見つける)

「ユーザビリティエンジニアリング」とは何か?
使われるサービスを、提供する側の能力・想像に依存せずに、顧客に求められるものを作ることができる。
「ユーザーインタビュー」
関わる人たち全てに話を聞く。その情報・優先順位を洗い出しす。その情報がファクトとなる。自分の意見を含めない。
「分析」
それを分析して、言葉にする。言語化することで見やすくなる。
言葉にされたファクトを関わる人ごとに全て、その人のナラティブに立って(本人に聞く+メタ認知)優先度を考える。
「MVP」
全ての人の優先度の中から、「これは外せない」という要素確実に入れたMVPを考えてプロトタイプを作る
「プロトタイプ」
そのプロトタイプを実際に使ってもらう
「ユーザビリティーインタビュー」
実際のユーザーの声を確認、とったデータから自分たちの建てた仮説は正しかったのか、実際の使われ方はどうだったのかを検証する。
これを繰り返していく。
確認しながら進めるには二つのステップがある

「ユーザーに聞く」には「調査」と「評価」がある
「評価」今あるものをどんな感じか?を聞くこと。
→ここからイノベーティブなものを生み出すのは難しい。
「調査」顧客から、得られるものは困りごとを聞いても出てこない。その人たちの動きを確認し、そのナラティブを拾い上げて調査する。
対象の観察から始まる。関わる関係者全てに聞く
TobeはAsIsの延長線の「評価」ではうまれない。
「顧客は、本当に必要だったものを言語化することができない」
「観察」「調査」を関わる人全てに行うことで洗い出す。


ここから実例のお話
「リアルの中村コンサルを共有(門外不出)」
おそらく、DX人材育成講座を受けていなければ、「ふーんすげぇなぁ」で終わっていた天才のコンサルにしか見えなかったであろう。
ただ、DX人材育成講座を受けたことにより、「もしかして、これ頑張れば自分で再現できたりしないかな?」と考えることができるようになる。
インタビューを上手に行うことが重要
インタビューは質問は一つだけ準備する。相手の答えの中から、言葉をクリックするように聞き出して深掘りをする。
インタビューと問診
インタビューの仕方は、「問診」に近い。
しかしゴールが真逆なことに気がついた
「今日はどうしましたか?」(オープンクエスチョン)から始めて、患者の情報を深掘りする。インタビューで深掘りはするやり方は、ほぼ問診と一緒。患者の出してくるキーワードごとに、その内容を突っ込んで広げて話をさせる。
しかし
問診は「今患者本人が持っている困りごとを解き明かす」
→医者の思っている科学的に妥当な一つのゴールに収束させる
(ロジカルシンキング)
インタビューは「本人も気づいていない問題を浮き彫りにする」
→相手の喋りたい事を上手に喋らせて、その中から最終的に優先度をつけて複数の課題を見つけ出す
(イノベーションの種)
最終的には関係者すべて、インタビューで拾った複数の課題を同時に解決する必要がある。
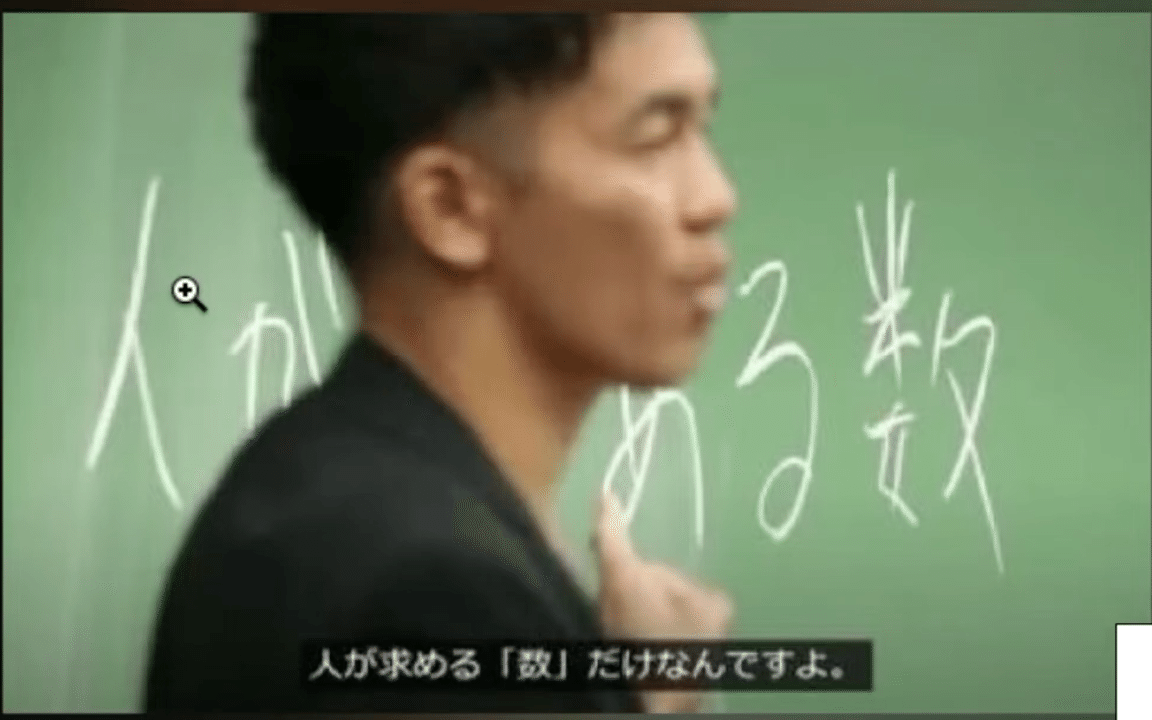
分析
誰のどんな要望から叶えていくかを考える。
分析に最も注力して行う。
解決策に偏りが出ないように分析しなければならない。
MVPで必要な要素はどこにあり、すべての関係者の必要最低限を満たしているかを考えていく。
一つの表にまとめていく→それがプロダクトバックログになる
MVP

プロダクト→ユーザビリティーインタビュー(評価)
プロダクトを出した後、その評価をすべての関係者にいただく。

ついに来た⭐️⭐️⭐️+文献
これを徹底的に理解して読み込んで、これから実践する。
そして、実践へ・・・
実際にカンパ先生主導で関係各所すべてのインタビューを見せてもらう。
受講生の中で、実際の問題を提示してもらい、
関係者;受講生
仮想:すべての関係者を受講生に演じてもらう
これで、実際にインタビューを行った

すべての関係者から、広げて聞いてくる。
赤:関係者
青:現在問題になっている事象
黄:解決策になりそうな点
で色分けすることで、見やすくなる。
昼コースでは「看護師の記録問題」
夜コースでは「空き家を用いた地域のコミュニケーション拠点をどのように作るか?」
をテーマに受講生実際に落とし込んでいく、
1)全員の関係者を書き出す
2)インタビューを直接聞く
2)

それぞれの貢献度、影響度、関心度、関わり方を相対評価する。
さらに、インタビューから、それぞれの優先すべき問題をリストアップ
3)それぞれの関係者の中で、絶対に外してはいけない優先度の高い項目をチェック
インタビューと最初の分析は、個人の意見・想像を出さない。
この表が完成するまでは、関わる人たちのファクトを取り出していく。

インタビューでAs-Isを取り出す(ファクト)

これを解像度高く、言葉にする。さらに、関係者すべてのAs-Isを叶えるActionを考える。

それぞれが必要な利益をリストアップし、
プロダクトバックログを作成する。(すべての関係者が最低限叶えたい課題を含める)


最後個別内容になるので、ざっくりで申し訳ない。
このカンパ先生のインタビューから
ユーザビリティエンジニアリングを実践する、卒業制作へと続きます・・・

