
税理士竹ちゃんの「HAPPY税務会計」 ~勘定科目は「親と子でつながろう」~(補助科目の話)
税務会計は、あなたを、そして、周りの人を、HAPPYにする存在でなければなりません。
もし「難しい」とか「数字が苦手」というイメージがあれば・・・
おめでとうございます!
あなたはHAPPYになる資格があります!
さて、今日は、「勘定科目」でHAPPYになるお話です。
Q. 通信費って何?
Ans. 電話代とか切手代とか・・・あ、インターネット代もそうかなぁ。
Q. じゃあ、接待交際費って何?
Ans. 取引先を食事に接待したり、お中元とかお歳暮とか・・・。
はい、大正解!
だいたい、皆さんは大まかな科目は分かるんですよ。
たまには難しいのもありますが。まぁ、大半は何となく分るでしょう。
でも、今回お話したいことは「これは何費になるのか?」という「勘定科目」の話ではありません。
ボクの経験上、皆さんの多くは、「これは何費?」ばかりに気を取られています。でも、それだけじゃ、「子供が迷子」になってしまうんです。
なんのこっちゃ?
あのね、勘定科目は、例えるならば・・・「親」なんですよ。
つまり、勘定科目は「お父さん・お母さん」。
そして、勘定科目の中身が「子供」なんですよ。
でも、皆さんは、いつも「どの親に当てはまるか?」ばかり考えて、
「子供」のことは考えない。
子供が生まれたら、役所に「出生届」を出しますが、
その出生届の中で、あなたにとって、一番大事な内容は何ですか?
住所ですか?生年月日ですか?
・・・ちがいますよね。
子供への初めてのプレゼント・・・「名前」・・・でしょ?
会計の世界、勘定科目も全く同じなんですよ。
皆さんの多くは、「親がどの名前に当てはまるか?」ばかり考えて、
子供の名前は気にしない。
だから、経理をするときでも、子供にも名前を付けてあげるんですよ!
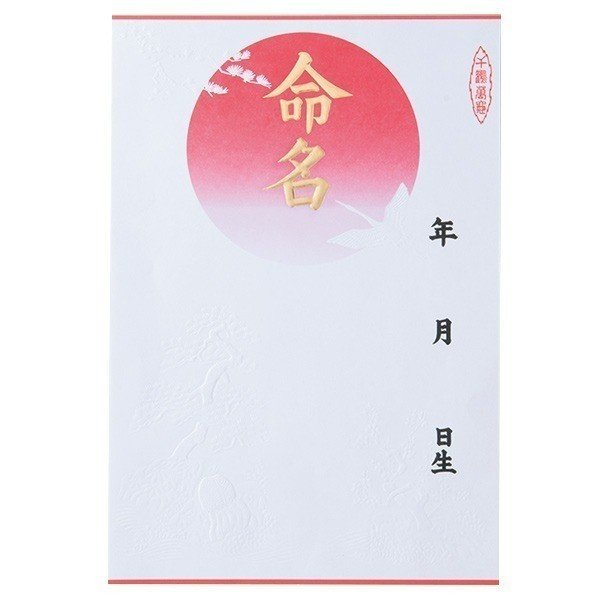
では、ここから「HAPPYの極意」を伝授しますよ。
例えば、通信費。
「通信費」という「親」には、どのような中身(子供)がいるのか一度あなたの会社の帳面(会計ソフト)を見てください。
・NTT
・ドコモ
・インターネット通信料
・プロバイダー料
・郵便代
・切手代
・はがき代
・・・一般的には、ざっとこんな感じでしょうか。
彼らが【通信費一家】の【子供たち】です。
次に、子供たちの特徴(個性)、応じて命名してあげます。
そうすると、【通信費一家】は、こんな【親子関係】になります。
【親】通信費
【子】・固定電話
・携帯電話
・インターネット通信料
・その他
※【子】の名前、例えば、固定電話なら「NTT」など、
固有名称でもOKですよ。
はい、これで子供たちに名前が付けられました。
会計の世界では、【子】のことを【補助科目】と言うんです。
(ちなみに、【親】のことを「主科目」・「親勘定」・単に「科目」と言います)
では、もう1つ、例題として【消耗品費一家】を見てみましょう。
【主科目(親)】消耗品費
【補助科目(子)】 ・ガソリン代
・事務用品代
・その他
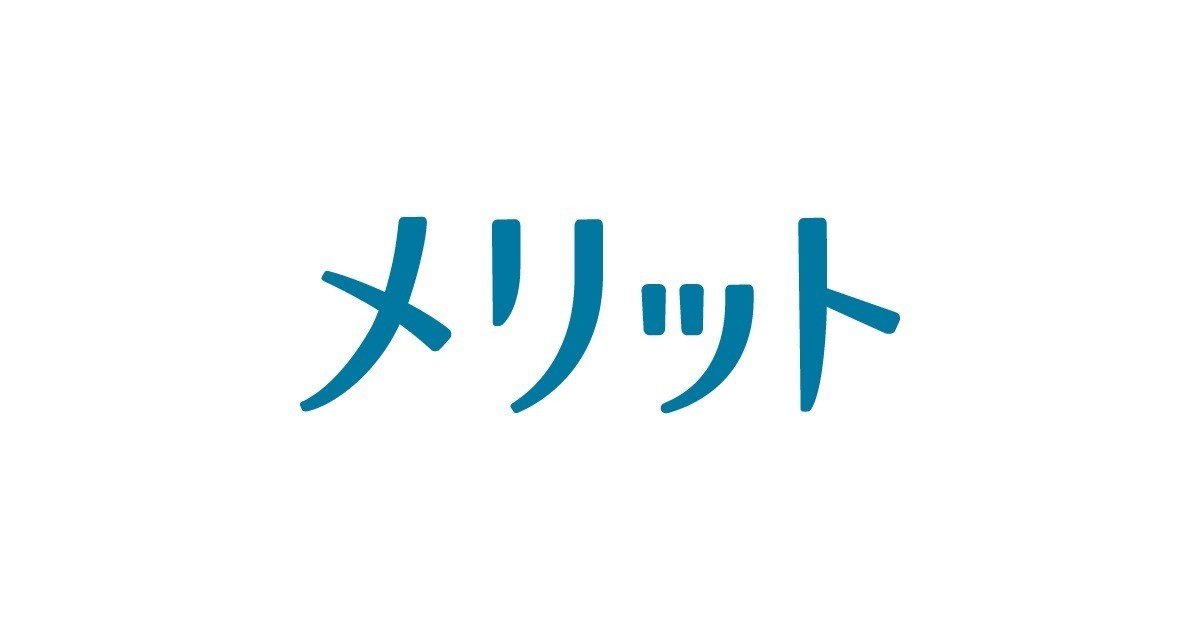
では、補助科目を作ることで、どんな良い事(メリット)があるんでしょうか?
①各科目の内訳がすごくスッキリして見やすくなります。例え「通信費」という分類わけをしているとは言え、その中身がグチャグチャだと見づらいでしょ?
②見やすい=気持ちいい。
③気持ちいい=見る気になる。
④見る気になる=チェックしやすい。
⑤チェックしやすい=間違い(計上もれ、科目違い)が大幅に減る。
つまり、補助科目を使うことによって、毎年継続したルールで記帳をしていくことが出来る・・・ということなんです。
去年は自動車税を3台分ちゃんと計上したのに、今年は1台分しか計上していなかった・・・なんてことは無くなるんです。
そうすれば、「悪魔のささやき」(ウソの金額を入れたり、商売に関係のない個人的な遊びの支出を経費にしたり=脱税)を聞く必要が無くなるんです。
そして、そして、一番のメリットは・・・
事業の成績が「正しく映し出されるようになる」ということです。
めちゃくちゃで、適当な数字を見ても仕方ないでしょ?
ウソの健康診断の数値を見ても仕方ないのと同じですよ。
本当に儲かっているのか?
どこが悪いのか?
どこを改善すべきなのか?
去年と比べてどこがどう変わったのか?(しかも、補助科目レベルでの比較が可能となる!)
同業他社と比べて、当社はどう違うのか?
多くの人は、自分の足元をよく見直さずに、「やれ経営分析だ」「やれキャッシュフロー経営だ」とか、よくも知らない耳障りの良さそうな世界に目を向けてしまいがちですが、
【前提の数字が正しくなければ、あらゆる分析もテクも無意味!】
ということです。
補助科目の利用方法は、経費科目だけではありません。
・普通預金は、口座番号ごとに補助科目を設定する。
・売掛金は、得意先ごとに補助科目を設定する。
・買掛金は、支払先ごとに補助科目を設定する。
・借入金は、相手先ごと(同銀行で複数の場合は契約口ごと)に補助科目
を設定する。
・売上は、得意先ごとに補助科目を設定する。
・仕入先は、仕入先ごとに補助科目を設定する。
・・・こうすることで、とても、とても、あなたの会計力は飛躍的にUPするんです。
今までは、「親科目」だけしか見ていなかったのならば、ぜひ「子供(補助科目)」のことも見てあげてください。【親と子の手】をしっかりとむすんであげて下さい。
親と子がつながってHAPPY !
すっきりして、間違いが減って、あなたもHAPPY !
それが【補助科目】のチカラです。

