
act9 : One more chance
◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17th から読む
目覚めた時、私は薄暗い部屋の中に居ました。
打ちっ放しのコンクリートで囲まれた室内。
そこに窓はなく、自分の居場所はおろか、今が朝なのか夜なのかさえも判然としませんでした。
私は後ろ手に縛られていて、目の前には何人かの男女がいて。
私の起床を待ちわびていたらしく、彼らは飢えたような視線を注いでくるのでした。

彼らは、自らを「傀儡」と名乗りました。
父が伏せていた組織の名を、私はここに至ってようやく知ったのです。
そして、それに伴う衝撃もまた大きいものでした。
傀儡。ドールを用いてテロ活動を行う反政府組織。
薄々感づいてはいたことでしたが、実際にその事実を突きつけられると、やりきれなさは募るばかりでした。
「ドールはどこにある? 知っているだろう?」
傀儡は、開口一番にこう問いかけてきました。
彼らの目的は、やはりドールの回収ということのようでした。
一方的に話す組織の人間に、しばらくは口をきくこともできませんでした。
口々にドールの所在を尋ねられ、しばらく経ったところで、ようやく静寂が訪れました。
その頃合いを見計らって、私は口を開きました。
「……父は……堂崎社長は?」
まぶたの裏に、凄惨な光景が浮かびます。
こみ上げてくる嘔吐感を必死に抑え、私はできる限りの虚勢を張って尋ねました。
その問いは、ほとんど愚問と言えました。
現に、私は父の無残な姿を目の当たりにしていたのですから。
それでも、かすかな希望にすがらずにはいられなかったのです。
「残念だが、亡くなったよ。ほぼ即死だったから、手の施しようはなかった」
それを聞いた途端、目尻に熱いものが溢れました。
放心しかかったところに、目の前の男が言葉を継ぎました。
「堂崎社長は私たちが手をかけたのではない。自ら命を絶ったのだ。本来ならば、君と同じく、拘束してゆっくりと話を聞き出すつもりだったんだがね。そこだけは誤解しないでもらいたい」
「拉致とは……ずいぶんと頭の悪い方法をとったものですね」
「できることなら、もっと交渉を深めたかったのだがね。そうも言っていられなくなったのだよ。しかし、もっと穏便に済ませるはずだった。今回の件は、血気盛んな連中が先走ってしまってね」
「ドールを回収できなかったことが、それほど悔しかったと?」
皮肉を込めて尋ねてみたものの、男はさして気にした様子もなく首を横に振りました。
「それとはまた別の話だ。堂崎社長は、裏切りを犯していたのだよ」
そう言って、男は私に再び視線を戻しました。
「……三ヶ月ほど前に、堂崎氏が組織のためにドールを作りたいと言ってね。それに被せるための記憶データをとりたい、ということで記憶同期システムを我々に使ったのだよ」
男が言うには、組織のドールはすべて自前で用意していたものらしく、まさしく戦闘用として作られたものだということでした。
ただ、ドール自体の技術水準はカンパニーに及んではいませんでした。
銃器の扱いなどには長けていたものの、訓練を積んだ人間のスキルに比べれば、いくぶん劣るものだったのです。
そのため、実際の攻撃手法としては、捨て身の特攻や自爆が主でした。
その運用方法は、いわば「道具」そのものと言えるでしょう。
そこへ、父は新しく開発したばかりの記憶同期システムの試用を勧めたというのです。
父が強調したのは、ドールを「道具」としてではなく「人間」として運用するという点でした。
人材の不足が目下の課題であった組織に、「幹部級」のドールの作成を提唱したのです。組織の頭脳とも言える幹部を模造し、指令系統の安定化を図る……というのが父の弁でした。
かくして組織は父の案を受け入れ、システムを適用したのでした。
──しかし。
「それから、組織の拠点が警察によって相次いで摘発されるようになった。最初は不思議でたまらなかったね。これまで摘発を免れていた拠点が、短期間のうちに制圧されていった。おかげで、少なくない数の仲間を失った」
事実が発覚するのに、それほどの時間は要しなかった。
傀儡の人間は、苦々しげにそう吐き捨てました。
「高官のひとりを拉致して吐かせたところで、ようやく理由が分かったよ。堂崎社長が、記憶同期システムで得た私たちの記憶データ。それをドールに被せ、政府に横流ししていたとね」
男の口元が、引きつったように歪められました。そこには、はっきりと憤怒の色が見て取れました。
「記憶をかぶせられたドールを尋問して、居場所を炙り出していたらしい。いわば私たちの分身を作りだし、それに自白させていたというわけだ」
傍らに控えていた組織の人間たちが、ぐるりと私を取り囲みました。
「記憶同期システムが使えたらね。同じ方法で、洗いざらい吐き出させてやるんだが……あいにくとシステムは手に入れられていない」
「自白剤のストックは、拠点を押さえられたことで無に帰してしまった」
「──だから、残念なことに、私たちは原始的な方法で君から事情を聴きださねばならないのだよ」

数ヶ月が経った頃でしょうか。
私は、依然として同じ部屋に閉じ込められていました。
「まだ、言わないつもり?」
わずかばかりの食糧を手にやってきたのは、若い女でした。差し入れられたのは、コンビニもののおにぎり二つと、ペットボトルのミネラルウォーター。
簡素ではありますが、一応はそれなりの食事と言えました。
今となっては、これだけが唯一の外界との繋がりなのでした。
「早いとこ言った方が楽になるわよ? ドールの行方さえ分かれば、こちらとしては貴方を解放するつもりなのだから」
組織は、私に対する姿勢を変化させていました。
拷問めいた扱いを受けたのは、初めの一ヶ月月ほどの間だけでした。
折檻を受けはしましたが、それは死に瀕するほどに苛烈なものではなかったのです。
これには、少し意外でした。
目的の為には手段を選ばない、というイメージがあったぶん、徹底的に痛めつけてくるだろうと予想していたからです。
それでも、背中や腕には、びっしりと傷が残りました。
この施設にはシャワー室も付いていて、三日に一度ほどの頻度で使用を許可されていました。
そこに備え付けられた鏡を見れば、傷は否応なく目につくのです。
それは同時に、沈黙を守り通した証でもありました。
折檻が得策ではないと判断したのか、組織はそれ以降、打って変って静観するようになったのです。
とはいえ、ドールの捜索を諦めてはいないようでした。
尋問は度々されますが、その回数や時間も、日を追うごとにまばらになっていくのでした。
どうやら、自力で探す方針に切り替えたものと思われました。
私への態度が柔らかくなっているのは、捜索が順調に進んでいるからなのか、それとも別の理由なのか……。
浮かびかけた想像を打ち消し、私は食糧へと手を伸ばしました。
「ここの一員となったっていいのよ? 堂崎社長の娘なら、工学に関する素養はあるでしょうしね」
「……拒否します」
「つれないものね」
いかにも残念そうな素振りで、やれやれと笑うのでした。
「そんな格好をしていれば、あなたも傍目には組織の人間なのにね」
「好きでこんな格好をしているわけじゃ……」
私にあてがわれていた衣服は、組織の装束でした。
つなぎのような構造の、黒い布地。
もともと着けていた衣服はとうに奪われ、今はこの装束に甘んじているのでした。
工作員然とした組織の衣服に身を包むのは、決して心地よいものではありません。
汚れに強いし動きやすいのだよ、と組織の人間は軽口を叩いていましたが……。
深読みすれば、これもある意味で精神的な拷問と言えそうでした。
「……どうして、あなたたちはこんなことを?」
「あなたをお招きした理由は、最初にお話ししたはずだけど?」
「そうではなくて……
なぜ、わざわざドールを用いて反政府行動をとるのか、ということです」
ドールの軍用技術は、それほど発達してはいないのです。
単に政府への武力反抗を目的とするならば、まっとうに銃器を使った方が手っとり早いように思えました。
工作員としての運用ならまだしも、対人兵器としてはドールは不向きといえました。
だからこそ、組織のドール運用は自爆テロじみたものにならざるを得ないのです。
しかも、ドールの製造には多大なコストがかかります。
正直、捨て身の特攻に使うというのは、費用対効果の面からみても非効率的なのでした。
「傀儡」は確かによく知られた組織でしたが、組織としての体力はそれほど盤石ではないというのが警察関係者の見方だったと記憶しています。
「不死の軍団、なんてものを夢見ているのだとしたら、それは滑稽としか。現状の技術からして、そのレベルで運用をするには気の遠くなるような時間と労力が必要になるというのに」
「そうね。確かに、私たちの技術じゃまだまだ時間はかかるでしょうね。……でも、いいの。先に、政府がそれを実現してくれるはずだから」
私は、女の口ぶりに違和感を覚えました。
あたかも、政府がドールを兵器として運用するのを待ち望んでいるかのような……。
「堂崎のお譲さん、諸外国のヒューマノイド事情はご存知?」
女からの、唐突な問い。
私は首を傾げながらも、知っている限りの情報を並べたてました。
「……諸外国のヒューマノイド技術は、現状では日本に比べて数段劣っている。エンジェルドールのような精巧なヒューマノイドは、まだ開発されていない」
「その通りね。でも、彼らには一つのアドバンテージがある。日本では禁止されているにも関わらず、諸外国では許容されていること……それは何かしら?」
その言葉を反芻し、考えを巡らせること数秒。
ふと、あることに思い当たります。
「……ヒューマノイドの軍事運用?」
女はゆっくりと首を縦に振りました。
「そう、当たり。彼らは確かに総合的な技術では劣っているけれども、ヒューマノイドの兵器運用に関して言えばノウハウの蓄積がある。その点、軍事運用を禁じているこの国においては、そういった技術はほぼ皆無」
お手上げといったふうに、女は大げさな素振りで手を広げました。天井を仰ぎながら、言葉を続けます。
「ドールに匹敵する精巧なヒューマノイドが開発されていない……というのは建前。外国では、すでにほぼ同等の性能を持つヒューマノイドが製造されているわ。それは、実際に試験運用の段階に入っているらしいの。あなただって耳にしたことはあるでしょう?」
「…………」
「国だって、秘密裏に兵器運用を考えていた時期は確かにあった。けれど、あなたも知っているように、その計画は頓挫してしまった。以来、政府はヒューマノイド法を遵守しているわ。水面下で何か計画を立てているのかと思いきや、兵器運用に関する話はとんと出てこない。……そうしている間にも、諸外国は着々と研究を進めている。ドールの「兵器」が開発されるのは時間の問題といったところかしらね」
「……政府は、そのことを知っているの?」
「ええ、もちろんよ。私たちが、きちんとそのことを伝えた。ああ、まだ組織が作られる前の話よ? 証拠資料も、揃えて送ったわ。──でも、政府は動かなかった。デマだと決めつけて、情報提供者を拘束した」
ふぅ、と女の口から忌々しげな溜め息が漏れました。
「……実際の脅威を目の当たりにしないと、ダメなのよ。でも、それからでは遅い。だから、私たちは『傀儡』を作り、目先の脅威を演じているの。組織のドール運用を実際に見れば、政府も腰を上げざるを得ないでしょう? 毒をもって毒を制す。ヒューマノイドを制するには、ヒューマノイドが必要だと言うことも認識するはず」
「あなたたちは──」
その時、私はようやく組織の意図をうっすらと理解したのでした。
「そうよ。私たちの目的は、政府がドールを兵器として扱うようにさせること。私たちは国を潰したいわけじゃない。むしろ、国のためを思ってこその行動なの」
誇らしげな微笑。その表情は、さながら悪魔のようでした。
「でも、やっぱり政府は動いてくれないのよね。あまり報道されないことだけど、これまでのテロで死者は出ていないのよ。でもね。それは、別に奇跡でもなんでもないわ。だって、私たちは『死人が出ないように』テロを起こしていたんだもの」
「……わざと殺さなかったというの?」
「そうよ。私たちは人殺しがしたいわけじゃないもの。政府がドールを脅威に感じ、その対抗手段としてドールを用いるようになれば満足」
目を細めつつ、陶然とした口調で話す女。
しかし、それもつかの間のことで。
その表情は、すぐに冷やかなものに転じました。
「けれど、それじゃ生ぬるいみたい。やっぱり、尊い人命が失われなければ、事の重大さを認識できないのよ。──そこで、私たちは考えを改めた。目的達成のためには生贄が必要なのだとね」
「まさか──無差別テロを起こすとでも?」
「そんなことしないわ。もっと効率的なやり方があるわ。ドールの軍事運用に反対する議員を暗殺してやるのよ。そうすれば、軍事運用の動きも加速するだろうし、脅威も認識させることができる。一石二鳥だわ」
「そんな……無理でしょう、だって……」
ヒューマノイド法においては、ヒューマノイドが人間に危害を加えることは禁じられています。そのため、生命に危機を及ぼす恐れのある行為はプログラムによって制限されているのです。
「そうね。私たちが使用している心理プログラムは、研究機関から横流しされたものや、市販のドールから抽出したもの。例外なく『危険行動』が制限されているわ。このプログラムを解除するには、多大な労力が必要でね。労力と成果のバランスが釣り合わないわけ」
私が口にしかけた反論は織り込み済みのようで、女の口調に淀みはありませんでした。
「だったら、『安全』と設定されている行為に則って、処置を施してやればいいのよ。自覚なき殺人を起こせるように、ね」
そのための策が──セクサロイド。
「標的にしている議員たちはみな、女遊びが大好きでね。愛人を密かに囲っている者だっている。──そこで、最も成功率が高いとされたのは、性交を介したウイルス感染だった。邪魔者を消せるうえに、スキャンダル発覚で派閥の権力もガタ落ちだなんて、素晴らしい話じゃない、ねぇ?」
さも愉快そうに口元を歪めながら、女は言うのでした。
「……そこで、あなたのお父さんの出番だったというわけよ」

閉じた空間の中で、淡々と時は過ぎていきました。
滞留した空気が乾き、コンクリートの床が氷の板のように底冷えするようになった頃。
季節は、おそらく冬なのでしょう。監禁されてから、すでに一年が経とうとしていました。
「まだ、吐く気はないのかね。気丈なものだ」
もう何度目になるか分からない尋問を受けながら、私は沈黙を貫いていました。嘆息混じりの台詞も、もはや聞き慣れたものです。
時間を重ねた賜物なのか、当初に感じた怯えや恐怖はすでに消え去っていました。麻痺していると言ってもいいかもしれません。ともかく、私はこの環境に慣れてしまっていたのです。
扱いはいまだに「様子見」のようでしたが、もし初めの頃のように暴力を振るわれても、例えそれより酷いことをされたとしても、私には耐え忍ぶだけの自信がありました。
ただ、私の胸には別の懸念がありました。
それは、「哲くん」のことです。
いま、彼はどうしているのか。
傀儡とのやり取りから察するかぎり、組織はまだ彼の存在に気付いていないようでした。
おそらくは無事なのでしょう。けれど、最大の問題は──彼に内蔵されている予備電源の寿命なのでした。
我が家に組織が押し入ってきた、あの日。
彼専用の充電装置は、破壊されてしまいました。
彼の部屋に搬入されるはずだったそれは、もう無いのです。
「哲くん」は充電もできないまま、新居のマンションで暮らしているのです。つまるところ、電池切れはそのまま彼の「死」を意味していました。
襲撃される前に充電は済ませておいたものの、それだけでどれくらいもつのか……。
彼の行動量にもよりますが、予想するに、およそ一年ほどが限度だと思われました。
もう、彼の「死期」が迫っているのです。
そう遠くないうちに、彼は動作を停止するのでしょう。
誰にも看取られることもなく、知られることもなく。
ただの一人で、あの部屋で……。
朽ちることのない身体。発見はいつになるのでしょう。
仮に見つかったとして、その後の展開は目に見えています。
病院に運ばれ、ドールであることが発覚して。
調査の名のもとに、研究機関にいじり回されて。
そして、行き着く先は廃棄処分。
──ならば。
身体の奥で、小さな火種がくすぶりました。
彼が停止する前に……一目でいいから会いたい。
できることなら、その「最期」を看取りたい。
それが叶うならば、もう私はどうなったって構わない。
願いの火は、すぐに猛々しく燃えさかり、全身に熱を灯していきました。
息絶えかけていた心が、脈動するのを感じます。
ここから逃げて──彼に、会いに行く。
そう、静かに決意したのでした。

そんな折、組織から恐ろしい情報がもたらされました。
「現在、堂崎社長から受けた技術でセクサロイドを作っているのだがね。面白いことが分かったよ」
尋問にやってきた男は、開口一番、嬉々とした調子で告げたのです。
「彼らは『暴走』するリスクが高い。プログラムとしては、かなり不完全なものだったらしい『身体状況』が万全でない時……例えば、バッテリーの残量が少ない時などは、プログラムが暴走してしまうようだ」
「……なぜ、そんなことが分かるのですか」
「そりゃあね、実際に作戦に使ってみたからさ。計画では、政府の要人を狙っていたんだがね。悪いことに市街地でバッテリー切れを起こしてしまってね」
殺人鬼もかくやというほどの壊れぶりだった──そう言って、男は卑しい笑いを浮かべました。
「もちろん、その個体はこちらで回収しておいたがね」
その時に感じた困惑と怒りを、どのように言い表せばよいのでしょう。
故意でないとはいえ、一般人に被害を与えたという事実。
それを軽々しい口調で語る目の前の男。
そして、新型ドールが「暴走」するという情報。
諸々の負の感情がない交ぜになり、すぐには言葉にできませんでした。
「堂崎社長が開発していたドールについても、興味深い噂を耳にしたよ。なんでも、人間の自我を持つヒューマノイドだとか。そして、そのドールは今も『人間』として暮らしているらしい、とね。……どうだい、心当たりはないかな?」
舐めるような視線に貫かれ、私は息を呑みました。声を発することもできず、動揺が顔に出ていないようにと祈るばかりでした。間を置かず、男は畳みかけるようにして言葉を継ぎます。
「これは推測なんだがね。堂崎氏の手掛けたドールが、今も実社会で暮らしているとして、だ。バッテリーの切れかかったタイミングで、同じように誤作動を起こすのではないかな。そういった類の犯罪者が出て、それがドールだと判明する日も近いかもしれないね?」
「…………」
「だから言っているだろう? 早めに話せ、と。警察に処分されるよりは、私たちの研究対象になったほうが有益と思うのだがね。丁重に扱ってあげられるよ。どうだね?」
「…………」
「だんまり、か。──まぁ、ドールが暴走すれば、すぐに分かることだな」
内心、穏やかではありませんでした。
傀儡は、父の研究をどこまで把握しているのか。
「佐藤哲」がドールであることを知っているのか。
そもそも、彼は無事に生活できているのか……。
焦燥感が、ちりちりと胸を焦がしていきました。
早く確かめなければという焦り。
どうやってここから逃れるかという難題。
まるで思考は働かず、じっと頭を抱えることしかできませんでした。
そうしているうちに、ぼんやりとした眠気が襲ってきます。
押し寄せる倦怠感に身をゆだね、私は暗闇の中に意識を手放しました。
どれくらい眠っていたのでしょう。
薄目を開くと、視界には相変わらずの殺風景な部屋が広がっていました。
何気なく視線を巡らせたところで、ある一点に目が吸い寄せられました。
部屋の扉が、薄く開いていたのです。
これまでは、一度たりともなかったことでした。
この部屋の扉は、外から鍵をかける方式のもので、常に閉め切られていて。
それが開かれる機会といえば、組織の人間が尋問に訪れる時と、食事を差し入れられる時ぐらいのものでした。
私は、じっと扉の隙間を注視していました。
しかし、しばらく待っても、誰かが入りこんでくる様子はありませんでした。もしかして、と淡い期待が芽生えます。
そっと立ち上がり、なるべく足音を立てずに扉へと近寄りました。
意を決して古びた扉を押すと──扉は、軋んだ音とともに開いたのでした。
自然と、私は部屋の外へ足を踏み出していました。
人の気配は、まったく感じられませんでした。
この部屋から出る機会は、シャワー室へと移動する時のみでしたが、それでも廊下で組織のメンバーとすれ違うのが常だったのです。
基本的には、この施設に何人かが常駐しているものと思われました。
だからこそ、この静寂がひどく不気味なものに感じられたのです。
けれど、この状況を疑っている暇はありません。
これは、施設から脱出する好機なのですから。
施設の構造については、まったく分かりませんでした。
ただ一つだけ知っていることは、ここが地下のフロアであるということだけ。
出口を探すには、とりあえず一階部分へと上がることが必要です。
地下にも出入り口があるのかもしれませんが、可能性は低いように思えました。基本的に、建物の一階には出口があるものですし、そこを中心に探した方が確実だと踏んだのです。
……階段は、すぐに見つかりました。
素足が床に触れる音だけが、ぺたぺたと反響します。
上のフロアに辿りついたところで、階段は終わっていました。
それが意味するのは、ここが最上階であり──一階であるということでした。
廊下に出ると、両脇に数個のドアがありました。
そして、突き当たりには、一つだけ色が違う扉。
両脇に設置してある扉が灰色の質素なものであるのに対し、最奥の扉は赤色で重厚なつくりになっていたのです。
私はそれが出口だと目星を付け、一直線に進んで行きました。
ぎぃ、と重々しい音がして、ゆっくりと扉を押し開きます。
──そこに広がっていたのは、外の景色ではありませんでした。
目に入ってきたのは、大ぶりの棚と、壁に立てかけられた銃器の数々でした。思わず、ごくりと唾を飲みこんで、私は異様な光景に見入っていました。
どうやら、ここは武器庫のようでした。早く離れなければ、という切迫した焦りを覚えます。
しかし、それを覆うように、もう一つの声が脳裏に響きました。
──何かしらの武器は、持っておいた方がいいかもしれない。
今のところは、幸運にも組織の人間に見つかっていませんが……探索中に鉢合わせしてしまう可能性は、十分に考えられました。
手元に武器があれば、仮に発見されてしまったとしても、即座に連れ戻されることはないでしょう。
強行突破できるかどうかは分かりませんが、抵抗する術を持っておくことは必要だと思いました。私は、棚の上に無造作に置かれていた拳銃を手に取りました。携行のしやすさを考えれば、これが最もベターな選択だと思えたのです。
小ぶりな外見に反して、ずしりと重い感触がありました。
内ポケットに拳銃を忍ばせ……それから、棚の上に転がっていた銃弾をかき集め、外ポケットに押し込みました。
部屋の外は、依然として静寂に包まれていました。
反対側の通路に目を移すと、そちらにも色の違う扉が見えました。
今度こそと期待を胸に、再び扉を押し開きます。
扉は難なく動き──瞬間、身を切るような冷気が全身を打ちました。
雪が降り積もった森林。天を仰げば、光る半月。
薄い闇のなかで、木々の合間に光の点が垣間見えます。
星とは違う、人工的な灯りの群れ。
そのなかで、ひときわ目を引いたのは、ゆったりと点滅する青い光でした。
見覚えのある発光の仕方……それは、街を流れる川に掛かっていた鉄橋の照明灯。だとすれば、方角から察するに、ここは街の南側のようでした。
この施設は、私の街からほとんど離れていなかったのです。
てっきり、私は街から遠く離れた場所に連れてこられたものだと思い込んでいました。
しかし、それは嬉しい誤算と言えました。
灯台もと暗し、とはまさにこの事を言うのでしょう。
扉を後ろ手に閉じて、私は施設を後にしました。とにかく山を降りたい一心で、足を前へと進めます。
静寂のなかで、雪を踏みしめる乾いた音だけが響いていました。
大丈夫……このまま……彼のもとへ。
その刹那──背後から破裂音が鳴り響きました。
一回、二回……いや、三回。
矢継ぎ早に聞こえた銃声。同時に、近くの草木が跳ねたように揺れ、雪を飛沫のように散らしました。とっさに振り返ると、五〇メートルほど離れた場所に複数の人影が見えました。
心臓を直接握り潰されたような心地でした。
私は、無意識のうちに拳銃へと手を伸ばし、引き金を引いていました。
予想以上の轟音と衝撃に、全身が総毛だちます。狙いなく闇雲に振るった銃弾は、あらぬ方向に飛んでいったようでした。
しかし、人影の動きには変化が見られました。
自らの存在を示すかのように躍りでていた影。
それが銃声とともに姿を消したのです。
おそらくは木陰に身を隠しただけなのでしょうが、それだけでも救いでした。
こちらが武器を持っている以上、向こうも迂闊に手出しはできないはずなのです。ならば、すべきことは決まっています。一刻も早く、山を降りなければなりません。
遠くから、再びの銃撃音。
身を翻して、緩やかな斜面を転がるように駆け抜けます。
檻の格子のように幾重にもそびえ立つ木々をくぐり抜け、夢中で走り続けました。
これまでろくに動かしてこなかった脚が、急激な動きに悲鳴をあげました。
喉元に迫ってくる叫びを噛み潰し、転がるように前へ、前へ。
視界の端に舗装された道路をとらえ、これ幸いと飛び降ります。
脚の節々に伝わる衝撃を無視して、そのまま道沿いに進んで行きました。

それからのことは、よく憶えていません。
麓にようやく辿りつき、電灯を目にした時の高揚感。
それだけが、鮮烈に印象に残っています。
麓から街へ。街から彼の住むマンションへ。
住んでいた街は依然と変わりなく、泰然とした佇まいを見せていました。
下山して以来、銃声は聞こえてきませんでした。
私は、それに安心しきっていたのかもしれません。
組織を振り切ったものと、そんな楽観を抱いていたのです。
しかし、その淡い期待もすぐに打ち砕かれました。
「哲くん」が住むマンションの近くまで来たところで、銃声が耳を刺しました。
閑静な住宅街。
治安の良さをうたっているこの一帯は、銃声などとは無縁の場所なのです。
にも関わらず、それが聞こえてくるという現実。
この場所で、このタイミングでの発砲音。
銃の担い手が誰を狙っているかは、火を見るより明らかでした。
物陰に身を潜め、追手をやり過ごすこと数回。
隙を見て、徐々にマンションへと接近していきます。
そして、マンションへと続く路地へ踏み込んだところで──再びの破裂音が鼓膜を震わせました。
ほぼ同時に、右脚に大きな衝撃。それでも脚は動いていました。
平衡感覚を失ったのもつかの間、体勢を立て直して路地を一直線に抜けました。
背後から足音が追いすがることは、もうありませんでした。
マンションに入り、エレベーターに身を投じます。
扉が閉まった瞬間、思い出したかのように全身から汗が吹き出しました。
生身の部位はもとより──「疲れ」を知らないはずのパーツ部分までも、疲労が染み渡っていく感覚がありました。
彼が住む部屋は、確か40階にあったはず。
位置は……廊下の突き当たりだったでしょうか。
それだけの記憶を頼りに、私はふらふらと歩を進めました。
極度の疲労に意識が蝕まれていくのを感じながら、やっと部屋の前に到着しました。
けれど、そこまでが限界でした。
インターホンに伸ばした手は、届くことはなく。
足元からふっと力が抜け、目の前が真っ暗になりました。

「……もしもし、大丈夫ですか?」
霞のような意識のなか、聞こえた声。
ぼやけた視界に映った姿は、徐々に明瞭さを増していきました。
そうして、単なる人影が、ひとりの人物としてようやく認識できた時……私は夢かと思ったものです。
「……凛?」
私の名前を呼んでくれた、そのひとは──紛れもなく「佐藤哲」でした。
確かな意思をこめて、私は頷きました。
そして身体を動かそうとした瞬間、パーツ接続部に鈍痛が走りました。
酷使しきった身体は、わずかな休息を糧にして、盛大に不平を訴えていました。
その痛みは、この状況が──「哲くん」の無事が現実であるという証でしたが、私は耐え切れずに呻き声を漏らしていました。
瞬間、彼の表情が一変します。
「どこか痛いのか? 病気か!? ケガか!? 待ってろ、いま救急車を……」
そう言うと、彼はコートのポケットに手をかけました。
携帯を取り出そうとしているのだと理解したところで、私はその腕をとっさに掴んでいました。
「やめ……て、呼ばないで、救急車。警察も、だめ……お願い、だから」
残り時間は、ほとんど残されてはいないのです。
正確な日時は分かりませんが、そう遠くないうちに彼は「死んで」しまいます。
病院に行けば、私は入院を余儀なくされるでしょう。
そして何よりも、「行方不明」とされていた私が生きていたと分かれば、警察からの聴取も行われます。
そうなれば、彼と過ごす時間が自然と削られることは明らかでした。
それに、捜査の手が広がれば、彼が「兵器」であることが発覚しかねません。
「哲くん」は困惑した様子でしたが、私の要望を聞き入れてくれたようでした。
ポケットに伸びていた手が引っ込み、代わりとばかりに私を抱き上げます。
いくばくかの痛みと浮遊感を感じながら、私の意識は再び闇に吸い込まれて行きました。

目を覚ました時、私はベッドに横たえられていました。
もともと着ていたはずの黒装束は脱がされ、代わりにジャージが着せられていました。
そばに哲くんの姿はなく、他の部屋からも物音は聞こえてきません。
どうやら、外出しているようです。
身体の節々には、いまだに疼くような痛みが張り付いていました。
上ジャージのジッパーを下ろして、自分の身体を確認します。
身体の各所には、包帯が巻かれていました。
おそらくは、彼が手当てしてくれたものなのでしょう。
続いて下のジャージを脱ぐと、脚にも同じく包帯が巻かれていました。
そして、右脚の部分にはひときわ厚く手当てがなされていました。
不意に、昨夜の路地での銃撃が脳裏に蘇ります。
綿布越しに触って、傷の状態を確認すると……ぼっこりと陥没している箇所があると分かりました。
「……まさか」
悪い予感に急かされ、私は重ねられた包帯を解いていきます。
隠されていた「傷」が露わになったところで、私は息が止まりそうになりました。
そこには、抉られたように穴が空いていたのです。
傷は二センチほどの深さで、そこからは疑似筋肉と金属骨格が見えていました。
昨晩の銃撃で受けた傷であることに、疑いの余地はありませんでした。
「哲くん」は手当の際に、この傷を見たに違いないのです。
冷え切っていく頭の芯を振り起こし、私は脚パーツを入念に確かめていきました。
足裏に手をかけると、皮が剥がれているような感触がありました。
心臓に氷を押し付けられたような感覚。
足の裏を返して視線を注ぎます。
あろうことか、そこには堂崎カンパニーのエンブレムが露出していました。
エンブレムを覆い隠していたはずの人工皮膚は、ほとんど剥がれ落ちてしまっていたのです。
思い返せば、私は一年もの間、ずっと裸足でした。
ましてや、施設からこのマンションまで長い距離を駆けてきたのです。
その道のりで、足裏の人工皮膚は摩耗してしまっていたようでした。
これもまた、おそらく彼は目にしたものと思われました。
彼は、私の脚がドールパーツであることを「知らない」のです。
植え付けられた記憶のなかでは、私は五体満足の人間なのですから。
この傷とエンブレムを見たとなれば、彼は私を「堂崎凛」だとは思わないでしょう。
状況から考えれば……むしろ私は、人間ではなくドールだと認識されたはずなのです。
それ以上のことを考えるのが恐ろしくて、私はあてもなく視線を巡らせました。
彼の部屋は至ってシンプルなものでした。
デスクに書棚、ベッド……と家具が並ぶなか、棚の上の小型テレビが目に留まりました。
部屋にカレンダーの類はなく、私は今日の日付を確認するために、テレビの電源を点けました。
放映されていたのはニュース番組で、ちょうど天気予報を伝えていました。
「12月18日、今日のお天気は──」
アナウンサーのが口にした日付を耳にして、私は驚きを禁じえませんでした。私の家が襲われた日も、確か同じ日だったと記憶しています。
つまり、あの日から今日で丸一年、ということなのでした。
チャンネルを切り替えると、別のニュース番組では、その事件がトップで取り上げられていました。
「会社社長宅襲撃事件から1年」というテロップとともに、かつての私の家を映した映像が画面に登場しました。
──事件から一年。そして、彼に最後の充電をしたのは、事件の前日。
私が見積もっていた、彼のエネルギーの総量は約一年間。
計算に照らし合わせれば……彼の「命」は、いつ果てても不思議でない状況でした。
その時、ドア越しに扉を開ける重い音が聞こえました。
足音が近づき、やがて哲くんが部屋に入ってきました。
思いつめたような表情を浮かべ、そのまま無言で立っていました。
「手当……してくれたんだね」
ああ、と短い返事。気まずさを隠すような素振り。
その原因は、おそらく……。
「傷……見たんだよね?」
「見た。結構ひどいケガだったな。特に、右脚のやつなんかは」
淡々と紡ぎ出される言葉。予想はできていたことでした。
それなのに、身体は正直なもので……意思に反して肩がびくりと震えます。
彼はそれを見逃さなかったようで、見る間に険しい顔になっていきました。
「足裏のエンブレムも、見てしまった」
追い討ちをかけるかのように、とつとつと紡ぎだされる声。
私は、すっかり平静ではいられなくなっていました。
彼の顔を見ることが怖くて、じっと下を向いていました。
彼にとって、今の私は不審者も同然なのです。
訝しげな目で見られることに、耐えられる気がしませんでした。
「聞きたいことがあるんだ……昨晩、近くで発砲事件があったらしいけど、その傷と何か関係があるのか?」
何も答えられず、うなだれるばかりでした。
自分がドールであると認識されているのは、ほぼ確実。
けれど、事情を話したところで信じてもらえるとは思えませんでした。
それでも、何か言わないことには、状況は変わりません。
だんまりを押し通せば、彼はますます私を疑うでしょう。
そのまま追い出されるか、あるいは警察に通報されるのか……。
いずれにせよ、悪い想像しか浮かびませんでした。
「疑問もたくさんあるだろうし、自分が怪しまれてるのも分かってる。
でも──」
顔を上げ、必死に言葉を絞り出します。
「……お願い。一週間だけ、ここにいさせて欲しいの」
適切な言い訳はついに思いつかず、ただ懇願することしかできませんでした。
彼が首を縦に振る可能性は、万に一つもないように思えました。
しばらくの沈黙の後、テツくんはゆっくりと口を開きました。
「条件がある。……去り際でいい、その時に全部、包み隠さず教えてくれ」
意外な返答に、一瞬だけ反応が遅れました。
すぐに思考が追い付き、私は即座に頷きました。
「……うん。約束するね」
正直に言えば、私はテツに真実を告げようとは思っていませんでした。
「あなたは記憶を模造された人形なのだ」と言ったところで、彼は信じないでしょうから。
それに、一週間もあれば彼のバッテリーは切れてしまうと私は踏んでいました。
彼を「人間」のままで逝かせてあげたいと──そう考えていたのです。
しばらくの間、「哲くん」は考え込むような表情を浮かべていましたが……
やがて、緩やかな声で言いました。
「……家にいる間、包帯は自分で取り替えてくれ。
血がけっこう出てたから、昨日は夜通しで手当てしてたんだぞ。
本当に大変だった。……もう出血はないみたいだけどな」
──出血?
彼の意図が読めず、内心で首を傾げました。
私が傷を負っていたのは、腕と脚。
いずれもドールパーツで補われた部分であり、血が出るはずもないのです。
訝しむ私をよそに、テツは意を決したように言葉を続けました。
「おまえは人間なんだ、そうだろう?」
射抜くかのような、力強い眼差し。
そこで私は、ようやく彼の言わんとすることを理解したのでした。
おまえのことは人形ではなく、人間として接する、と。
「おまえは、『堂崎凛』なんだ」
思い出したのは、幼い頃の記憶。
手術を受け、ドールパーツで四肢を補われた私に、彼がかけてくれた言葉。
──『おまえは人間なんだ。そうだろう?』
──『どんな姿になったって、凛は、凛なんだ』
「……うん。ありがとう……」
もちろん、あの時と今とでは状況が違います。
ドールの彼。家族を失った私。
その言葉が持つ意味も、大きく異なるでしょう。
今の私は、「堂崎凛によく似た人形」なのです。
たぶん、私を人間扱いするのは、葛藤に折り合いをつけるためなのでしょう。
それでも嬉しかったのです。
やっぱり彼は「哲くん」なのだと……そう思えたのでした。
「包帯、今日から自分で取り替えるね。
痛みはもうないけれど……何かの拍子で『出血』するかもしれないから」
私は、調子を合わせました。
自分に与えられた役は、「堂崎凛を演じるエンジェルドール」なのです。
表面上は大正解でも、その内実は大間違い。
このいびつな役柄を、完璧に演じ切らなければならないのです。
──ねえ私ね、「本物」なんだよ。
そう言えたら、どんなに楽でしょうか。
でも、それは叶わないことです。
これは、報い。
彼を兵器として「生かした」ことに対して。
そして、彼の記憶を改ざんしたことに対して。
もっとも、こうして彼と会えたこと自体が奇跡といってもいいのです。
それだけで、十分すぎる幸運でした。
「よろしくね、『哲くん』」
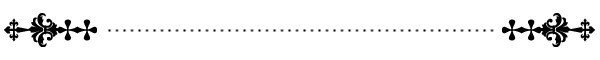
独りで逝かせはしない。
その「命」を永らえる方法がないのなら、せめて最後は安らかに。
私にできることは、彼の最後を看取ること。
それが叶うならば……もう、生きるつもりだってありませんでした。
だからこそ、私は彼と交わったのかもしれません。
もちろん、そこには自分の願望もありました。
あの日、別荘でできなかったことをしたい、してあげたい。
けれども、それは同時に自らの退路を断つという覚悟もはらんでいました。
その後──マンションでの生活の中で、私は二つのミスを犯しました。
一つは「哲くん」がテレビ通話をしているところに踏み入ってしまったこと。
運の悪いことに、通話の相手は鈴木くんでした。
彼は私のことを知っているのです。
そう、私の四肢がドールパーツで補われていることも含めて。
鈴木くんが哲くんにそれを明かせば、私が人間であることが知られてしまいます。
それだけは、何としてでも避けなければなりませんでした。
しかし、その懸念は思わぬ形で回避されました。
鈴木くんは、私のことをドールだと勘違いしたのです。
それに乗じて、テツは私を「レンタル品」という設定に仕立て上げました。
勘違いと嘘が重なり、私は当面の危機を脱したのでした。
鈴木くんと通話した時、彼は涙を流しました。
私をドールとして見ていると同時に、そこに私自身を重ねていたのです。
嬉しさと悲しさが入り混じった、複雑な気持ちでした。
……失敗の二つ目は、「哲くん」に拳銃が見つかったこと。
本来ならば、マンションに来る前に捨てておくのが正解だったのでしょう。
私はすっかり失念していたのです。
彼が拳銃を差し出してきた時は、背筋が凍る思いでした。
心証は最悪になったとみて間違いありませんでした。
彼の尋問に備えて、私は戦々恐々としていたのです。
けれど、予想に反して、彼は何も問い詰めようとはしませんでした。
「リンに返しておくよ、身を守れるようにね」
たった、それだけでした。
彼は私を信用してくれている。
なのに、私は彼を騙すような真似をして。仕方のないこととは言え、後ろめたさを感じずにはいられませんでした。

彼の命の終わりは、刻々と近づいていました。
その証拠に、彼は一度寝つくとなかなか起きなくなっていました。
残量わずかなバッテリーの消費を抑えるための、自動プログラム。
人間で言うところの防衛反応が、彼の身体に起こっているようでした。
無理に起こそうとは思いませんでした。
むしろ、努めて睡眠をとらせるようにしていました。
プログラムの導き出す生活リズムに従わせることこそ、彼が長く生きるための最善の措置なのです。
よほどの事態が起こらない限りは、無闇に起こすべきではありませんでした。
もっとも、彼自身は「寝坊してしまう」ことがもどかしかったようで。
日が経つうち、朝に起こしてくれるよう私に頼むようになりました。
正直、心配でたまりませんでした。
身体のリズムに逆らって外出することが、どれだけバッテリーの消費を早めることか。
けれど、事情を明かせない以上、私にその頼みを拒む理由はないのでした。
外出から帰宅した彼は、いつも疲れ切った表情をしていました。
本人はいたって平気なふうを装っていましたが、精巧な表情筋は、疲労を敏感に映し出していたのです。
そして訪れた、早めの誕生日祝い。
その時になって、事実は明らかになりました。
私が作ったケーキ。
見栄えよく作ることができ、味にも自信はありました。
しかし、テツが口に運んだ瞬間、その表情が固まったように見えたのです。
「ああ、おいしいよ……俺にとってはちょっと甘いけど」
微笑みながら、彼は言いました。
そういえば、哲くんは甘いものが苦手でした。
生前の彼の嗜好は、当然ながら「哲くん」にも反映されているわけです。
少し砂糖を入れすぎただろうか、と後悔しつつ、私は切り分けられたケーキを一つ口に含みました。
──瞬間、クリームの甘みとともに、強烈な苦みが広がりました。
「けほっ、ごほっ……」
不意打ちの刺激。
喉元までせり上がる異物感に、私は思わずせきこんでいました。
苦みの原因は、スポンジ生地でした。
どうやら、重曹を多く入れ過ぎてしまったようなのです。
「大丈夫か!?」
彼が血相を変えて駆け寄ってきます。
注いでくれた水でケーキを飲み下しました。
彼は私にケーキを食べないようにと言い含めて──
残りのケーキを、黙々と食べ始めたのです。
とても食べられるような代物では、ないはずなのに。
──味が、分かっていないの?
そこで気付いたのは、彼の味覚が機能しなくなっているということ。
ドールにとっては、もともと不要な機能。
残りわずかなエネルギーで活動するために、オプション要素は自動的に遮断されてしまうのです。
つまりは、それだけ彼の「死」が近づいているということでした。
あと、どれだけ持つのか。
次の日は大学に行かなければならない、と彼が言っていたのを思い出します。
本当は、身を挺してでも止めるべきだったのでしょう。
でも、私は目を背けました。
「大学に行くのは明日が最後で、それからは冬休みなんだ」
彼の言葉に免じて「一日ぐらいは」と許してしまったのです。
それが甘い見通しだったと思い知らされたのは、翌日のことでした。

次の日、彼が帰宅した時。
床に土足で踏み込んできた彼の目は、虚ろでした。
そのまま、荒々しい手つきで掴まれ、押し倒されて──
ここに来て初めて、身の危険を感じた瞬間でした。
しかし、彼はすんでのところで踏みとどまりました。
そして、そのまま意識を失ったのです。
……その夜。
彼の懺悔と独白を聞いて、私は自分を責めていました。
『新型ドールのプログラムは不完全でね。
劣悪な状況では暴走する可能性が高い』
頭をよぎったのは、組織の人間の言葉。
もはや、テツは己を制御できないぐらいに弱っている……。
今や彼は、いつ暴発するとも知れない不発弾と同じなのです。
今度こそ、私は認識を改めざるを得ませんでした。
今日は「運よく」衝動の矛先が私に向いた。
けれど、もし街中で暴走したら?
バッテリーの残量が残り少ないとはいえ、その可能性は捨てきれない。
仮にそうなってしまったら、私は後悔してもしきれない。
ならば。
私の手で、ひと思いに壊してあげることが。
せめてもの救いになるのだろうか?
彼が寝静まってから、私は拳銃を持ちだしました。
私が、終わらせる。
他の誰にも、弄らせなんかしない。
そのまま、人間として死なせてあげる。
さあ、早く。
ひと思いに引き金を──
………………
…………
……
「……撃たないのかい?」
闇に浮かんだ声で、はっと意識が引き戻されます。
小さく震える指は、引き金に掛けられたまま強張っていました。
──殺せなかった。
目の前には、どこまでも静謐な瞳がありました。
──殺せるわけが、なかった。
目の奥が、じんじんと疼きます。
熱い塊が次々とあふれ、頬を滑り落ちていきました。
何が「彼のために」だ。
ただ、私は自分が楽になりたかっただけなんだ。
父が、私が彼にしてきたことを、知られたくなかっただけで。
責められるのが、怖くて仕方なくて。
すべては、保身のためでしかなかったんだ。
「──約束、守りたいと思った、から」
彼に全てを教えてあげなければいけない。
それが、私の義務。
そのために、あの研究所へと連れていこう。
それが終わったら、最後に──
`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。

