
act4 : Wed. Dec. 20th
◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17th から読む
居間の空気を、暖房が緩やかに掻き回していた。
カーテンを開ければ、ガラス窓は結露した水滴にびっしりと覆われている。
手で表面をぬぐうと、ひんやりとした感触とともに明瞭な景色が現れた。
太陽はすでに高く昇り、さんさんと光を降らせている。
コーヒーを口に運びつつ、眼下の街並みを眺めてみる。
昨夜も雪が降ったらしい。
見渡す限りの家々は、軒並み白帽子をかぶっていた。
テレビの天気予報は、今日も厳しい寒さになると告げていた。
その前では、ブランケットを羽織ったリンが
ホットミルクを手に縮こまっている。
そんな様子を微笑ましく感じながら、俺はゆったりとコートを羽織った。
「もうすぐ、外に出るの?」
「ああ」
時計の針は十二時をまわったところだった。
約束の時間には少し早いが、それぐらいで丁度よいだろう。
玄関先に向かおうとしたところで、
リンに言っておく事があったことに気付く。
「リン、起こしてくれてありがとな」
「うん」
まずは、感謝。
昨夜、朝八時に起こしてくれるようリンに頼んでいたのだ。
昨日のように、夕方まで寝入るようなヘマを防止するための策だった。
むろん、目覚まし時計をかけて置くことも忘れなかったけれど。
果たして、彼女は時計のベルが鳴るより先に、
きっかり時間通りに目覚めさせてくれたのだった。
「それと、昼ごはん買っておいたから」
「うん」
次に、食事についての言い置き。
念のため、コンロなどの火は扱わないように言っておいた。
だから、食事は相変わらずのコンビニ製品だけれど、
そこは大目に見てほしい。料理はあいにくと不得意なのだ。
その代わりというわけじゃないが、
青汁パンとドリアンミルクはたっぷりと買いためてある。
そして、最後に……。
「あと──これ、返しておくよ」
棚の引き出しから拳銃を取り出し、リンに差し出した。
途端に、彼女の顔に緊張が満ち、ばつの悪そうな表情へと変わる。
叱られた子どものような悄然とした面持ちのまま、じっと固まっていた。
無言のリンに、俺はなるべく優しい調子で話しかけた。
「あの黒い服に入ってたよ。リンのものだろう?
……マンションの防犯設備はしっかりしているけど、
俺がいない間、危険なことがあっても身を守れるようにな」
仮に「傀儡」のような組織に追われていて……
最悪、リンの居場所が割れているとするならば、
家主の不在をいいことに彼女を奪還しに来るかもしれない。
そんなケースも、十分に考えられた。
凶器をリンに握らせたくはなかったが、自分なりに悩んだ末に、
彼女に拳銃を返しておくことが最善だと考えたのだった。
受け取るように視線で促して、
リンはようやく、黒光りするそれに手を伸ばした。
ジャージ姿の若い女性が持つには、あまりにも不釣り合いだったけれど。
「じゃあ、行ってくるよ。遅くても夕方六時までには帰るから」
「……気をつけてね」
リンの気遣わしげな声を背に、俺は扉を開いた。
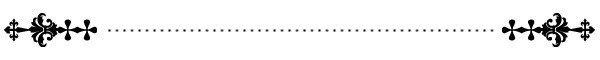
「あ、いたいた!」
アルミは、待ち合わせ場所へ三〇分遅れで現われた。
天候は曇り、辺りには粉雪が薄く舞い始めている。
「ごめんごめん、ちょっと用事が長引いちゃって」
悪びれた様子もなく、アルミがからころと笑う。
俺のほうは予定より三〇分早く着いてしまったから、
正味で一時間は待ちぼうけを食らった計算になる。
不平の一つも言いたくなったが、それよりもまず指摘すべきことがあった。
「……なんで、そんな格好なわけ」
「え? お気に入りの服だから」
「いや、そういうことを訊いてるんじゃなくてさ」
アルミの服装は、およそ冬の装いとしては
あまりにも相応しくないものだった。
襟ぐりの大きく開いたトップスと、ショートパンツという出で立ち。
言うなれば、完全に夏の装いである。
覗いた肩と露わになった脚を見ているだけで、
見ているこちらが寒くなってくるくらいだ。
昼時とあって人通りは多く、行き交う人々が
ちらちらと好奇の視線を投げかけてくる。
十二月も半ば──言うまでもなく、誰もが厚着だ。
その中にあって、薄着のアルミはどうしようもなく浮いていた。
「……寒くないのか?」
アルミはいたって平然としていたが、いちおう尋ねてみる。
「あー、そういうことね。大丈夫だよ。
あたし『レイカク』のプログラムを修正されてるから、
ほとんど寒さは感じないの。
もちろん、機能の維持に関わるようなデカい刺激は感じるけどね」
レイカク……ああ、冷覚のことか。
どうやら、身体感覚でさえもプログラムで調整できるということらしい。
改めて、アルミがドールである事実を認識させられる。
「それはまた、ずいぶんと羨ましい身体だな」
「でしょ! 冬場は便利なんだよ!
たっくん、こーゆー服が好きだから……
さて、じゃあ行きますか。立ち話もなんだしね!」
そう言うと、アルミはすたすたと歩き出した。
俺もつられて、隣を歩く。
「そうだ。携帯、忘れないうちに返しとくね」
「ああ、ありがとう」
途中で携帯を受け取り、それを機に話題は携帯のことに移った。
アルミも、携帯を持っていた。
見せられたメールボックスは、鈴木からのメールで埋まっていた。
いつ帰宅するか。夕飯のメニューは何がいいか。
大学で何があったか──などなど。
メールの末文には、決まって「好きだよ」と付け加えられていた。
それを見て苦笑しつつも、もう滑稽だとは思わなかった。
むしろ、微笑ましいとさえ感じられる。
鈴木が、いかにアルミを大事にしているかが伝わってくる。
「ねぇ哲、アドレス交換しようよ」
「ああ、いいよ」
互いに携帯の通信部を近づける。
すぐに、アルミの携帯からアドレスが送られてきた。
アルミの方でも通信は上手くいったようで、
「きたきた!」と弾んだ声があがった。
「知ってるアドレス、これで二件に増えたよ!」
隣で小躍りするアルミを横目に、はっとした。
明るい性格の鈴木は、友人も多い。
だから、ドールと暮らしていることだって、
他の面々にもおおっぴらに喋っていると思っていた。
さぞかし、存分に見せびらかしているのだろう、とも。
けれども、それは俺の思い込みだったのかもしれない。
思い返せば……あの日、鈴木がアルミのことを
最初から「ドール」だと紹介したのは……
ひとえに俺の事を信用してくれていたからじゃないのか。
それに対して、「所詮は人形」と切り捨てたのが俺だった。
その時、鈴木はどんな心持ちだったのだろう──
ふっと想像が巡り、途端にきりきりと胸の奥が痛んだ。
彼女の携帯に登録されている、二件のアドレス。
うち一つは当然ながら、ユーザーである鈴木のもの。
そして、二件目が……俺。
認められた、ということなのだろうか。
受け容れられた、ということなのだろうか。
アルミのアドレスは、とても貴重な証のように思えたのだった。
寄り添って歩くアルミは、満面の笑みを浮かべている。
俺は、彼女に「ありがとな」と小さく言った。
「大事にするよ」
アルミの電話番号と携帯アドレスを確認する。
『arumi-forever-with-s.takkun@……』
何ともまあ彼女らしいアドレスで、俺はまたひとしきり苦笑した。
……と、しばらく歩いたところで、ふと違和感を覚えた。
「あれ? ビル街のほうに行くんだろ?
いま進んでる方向って逆なんじゃないか?」
「そうだよ!」
事もなげにアルミが頷く。
いや、「そうだよ」じゃなくて。
俺の胸中を察したかのように、彼女は悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「ちょっと先に、別の用事を済ませてからね!」
あくまでもマイペースなアルミなのだった。

「ここは……」
到着したのは、ドールストアだった。
家電量販店もかくやというほどの規模を誇る、大きめの店舗だ。
話には聞いていたが、実際に足を運んだのはこれが初めてだった。
店舗を見上げて感嘆のため息を漏らしているうちに、
アルミはさっさと店内に入っていく。
後を追うようにして、俺もその背中に続いた。
外見に違わず店内は広々としていて、
カスタマイズ用のパーツが整然と陳列されている。
関連商品の豊富さは、大手電器店のそれを思わせた。
しかし、そういった店に特有の雑然とした空気はない。
白を基調としたシンプルな内装が、洗練された雰囲気を醸し出していた。
アルミは迷いのない足取りで、フロアを颯爽と歩いていく。
その様子からは、彼女がこの店舗に
足しげく通っているであろうことが窺えた。
エンジェルドールが、自身の「身体」を販売している
ドールストアに居るというのは、かなりシュールな光景だった。
とはいえ、それは「人間」から見た感想であって、
彼ら人形からすれば、化粧品や衣服を買う感覚と同じなのかもしれない。
いくつかの区画を越え、
フロアの奥まった場所に辿りついたところで、
その足はようやく止まった。
「五分ぐらい待ってて。すぐに終わるから」
そう言い残して、アルミはカウンターへと駆け寄っていく。
店員らしき人物と短い会話を交わしたかと思うと、
連れられるようにして奥へと姿を消してしまった。
それを見送った後で、ひとまず傍のソファーに腰を降ろした。
ぼんやりと店内に視線を巡らせると、
実に様々な商品が並んでいることに気付く。
「……せっかくの機会だしな」
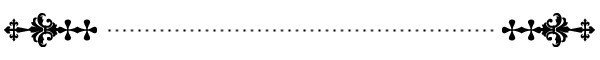
興味の赴くままに、フロアを巡り歩くこと数分。
最初に目に留まったのは、特設のショーウィンドウに
展示された三体のドールだった。
玄関口の舞台セットに、若い成人女性型のエンジェルドールが立っている。
近くでは、同年代と思しき男性型のドールが土間に腰を降ろしていて。
その背には、少年型のドールが抱きついていた。
女性型ドールはエプロン姿、
男性型ドールはスーツにネクタイを着用している。
さしずめ、帰宅した父を母と子が玄関口で迎えるという構図か。
幸せそうな日常の一瞬が、立体的に再現されていた。
ともすれば、今にも会話が聞こえてきそうなほどの現実感がそこに在った。
──もう戻らない家族の団欒を遠く思いながら、俺はその場を離れた。
次に立ち寄ったのは、身体の主要部位パーツを取り扱った区画だった。
手・腕・脚・足・胴・頭部……販売されているパーツは、
それぞれマネキンに取り付けられている。
カウンターの傍では、客の男性が店員と一緒に
ドールの各部位を着けたり外したりしていた。
理想のドールを形にするために、試行錯誤を繰り返しているようだった。
──ふと、リンの右脚の傷を思い出した。
歩行に支障はないようだったが、
包帯でずっと隠しているというのもどうかと思う。
なにせ、化学素材の肌に自然治癒なんてものは見込めないのだから。
──だったら、彼女の脚の部分を別のものに取り換えたらいいんじゃないか?
客がパーツを頻繁に着脱させているところを見ると、
どうやら接続部の規格は統一されているらしい。
リンをここに連れてくることはできないが、
ここでパーツだけ買って部屋で付け替えてあげれば……。
そんな一連の考えが脳裏をよぎり──打ち消すように首を振った。
「……それは『ルール違反』だよな」
リンを「人間」として扱う以上、
ドールを想起させるようなことは極力遠ざけたかった。
新しい脚パーツを着用させること、すなわち人形として扱うことは、
彼女への裏切りのように感じられたからだ。
心持ち早足で区画を離れ、別の売り場へと歩いていく。
何も考えずに足を踏み入れた先は、心理プログラムの区画だった。
そこには「新商品」として、
最近デビューした若手アイドルの心理プログラムが宣伝されていた。
区画に設置されたPVには、
ポップなBGMとともにアイドル本人の姿が映し出されている。
「まゆみんが! いつも おそばにいますよっ♪」
ぷりぷりとした口調で、ウィンクを飛ばしまくっていた。
傍らの人気商品ランキング(心理プログラム版)では、
彼女は堂々の首位に輝いている。
その下に続くのは、最近ブレイクしたというお笑い芸人や、
大御所タレントたちの名前だった。
ちらりと横に目を写すと、「recommend」の表示が見える。
その下に続く文言……「記憶同期システム、受付中」。
数日前の、鈴木とのパソコン通話が脳裏をかすめる。
これが、鈴木の言っていたものだろうか?
「──心理プログラムをお求めですか?」
横からの声に振り向くと、
そこには店員らしき女性がにこやかに佇んでいた。
「あ……ちょっと『記憶同期システム』が気になりまして。
これ、どんなサービスなんでしょうか?」
商品に興味を示したことで、店員の表情が嬉々としたものになる。
待ってましたとばかりに、彼女はにこやかな笑顔で説明を始めた。
「簡単に申し上げますと、
ユーザー様の記憶をドールに組み込むものです。
ユーザー様とドールの関係構築を補助するサービスとして、
ご好評を頂いておりまして」
「記憶の共有、ですか。
どれぐらいの範囲まで共有できるんですか?」
「基本的には、ユーザー様の記憶を複製するわけですから、
ご本人様が憶えていらっしゃる事柄であれば、
全般的にドールにも共有されることとなります。
──例えば、人間関係から食事の好み、
印象に残った出来事にいたるまで、すべて。
もっとも、ご本人様がお忘れになっている記憶は、
ドールの方でも反映することができないのですが」
「つまりは……記憶の『強度』も、
等しく共有されるということでしょうか」
「おっしゃる通りでございます。
明確な記憶──印象に残っているものほど、
ドールのほうでも反映されやすくなります」
こほん、と咳払いを一つして、店員が続ける。
「ただ、明確な記憶だからといって、
必ずしもユーザー様にとって喜ばしいものとは限りませんよね。
忘れたくても忘れられない記憶……
ご本人様にとっては辛く悲しいものも、
そのままドールに反映されてしまうのです」
「……なるほど」
「お客様によっては、その点を気になさる方もいらっしゃいます。
そこで、私どもではオプションサービスとして
『記憶処理』も行っております。
ドールに移された記憶データを、お客様のご要望に応じて消去、
または修正プログラムを組み込んで改変するのです」
俺は、店員の説明にすっかり聞き入っていた。
純粋に興味深い内容だったし、仕組みとしても良くできていると思えた。
「このサービスには別の用途もありまして。
お客様から移された過去の記憶データをもとに、
その記憶にドール自身を介在させることも可能です」
「……と、いいますと?」
「例えばですね、お客様が過去に旅行に行かれた時などの
記憶をもとにプログラムを制作し、あたかもドール自身が
その旅行に同伴したものとして認識させる、といったように。
こちらは主に、ご年配の方が利用されることが多いですね。
お亡くなりになった配偶者の代わり身として、
ドールをお求めになる方々です。
そういったご利用のされ方もありますね。
ユーザー様にとって喜ばしい記憶をドールが共有し、
そこに疑似的に『関わる』ことで、
関係の構築も格段に容易なものとなります……」
「なるほ──ぐぇっ!」
背後から急にマフラーをぐいっと引っ張られ、
思わず奇妙な声を出してしまう。
きつく絞まったマフラーを慌てて緩めたところで、
後ろから怒ったような声が上がった。
「や〜っと見つけた! もー、うろつきすぎ!
電話かけても全っ然出ないし!」
しまった、アルミだ。
パーツを見ているうちに夢中になって、
すっかり彼女の事を失念していた。
「悪い悪い……って、え?」
振り向きざまに、一瞬、我が目を疑った。
……アルミの身長が「縮んでいた」。
馬鹿な、だってアルミは俺と同じくらいの身長だったはずだ。
なのに、今は……彼女の頭が、俺の胸あたりの位置にあった。
大まかに見積もっても、三〇センチは低くなっている。
アルミの口元が、したやったりと言わんばかりに緩む。
こちらの動揺を分かっていて、しかも楽しんでいるような節があった。
「ねぇ、早くお洋服かいにいこうよー!」
幼げな、あざとい口調でアルミがせき立てる。
「あ、ああ、そうだな……
すみません、詳しい説明をありがとうございました」
店員に会釈して、ひとまず店を出ることにした。

「アルミ、おまえ身長が……」
街を歩きながら、ようやくアルミに尋ねる。
ふふふ、と不敵な笑みを浮かべつつ、アルミは誇らしげに胸を張った。
「脚のパーツを変えたの! 一週間前から予約してたんだ!」
どうりで、と合点がいった。
「って、それも鈴木の好みなのか」
「うん、そうだよ!
たっくんは、『小さい方がかわいいかな』って言ってたから。
どうよ、似合ってる?」
似合っている、という表現が正しいかどうかはさておき、
新しい脚はアルミにしっくりと馴染んでいるように見えた。
もともとが幼い顔つきということもあって、自然に見える。
ランドセルを背負っていても違和感がなさそうだ。
……ただ、そのぶん胸の大きさが強調されて、
余計に凶悪な体つきになってはいたけれど。
ドールのカスタマイズの仕方は、ユーザーによって千差万別だ。
そこにはユーザーの意図がはっきりと表れる。
例えるならば、ドールは持ち主の嗜好を映し出す鏡だ。
そう考えると、今の鈴木のトレンドとしては──
(ロリ巨乳ねぇ……)
「なんか、良からぬ妄想してない?」
「してないから」
ついつい見とれていたとか、決してそんなことはない。
断じて、だ。
……大きく深呼吸し、思考を切り替える。
アルミは、なおも疑わしげにこちらを見上げている。
その視線に圧されるようにして、俺はどうにか言葉を継いだ。
「いや、思ったのは……
アルミは本当に鈴木のことが好きなんだな、って」
弁解するように言うと、アルミは「うん!」と大きく頷いた。
「たっくんのことなら何でも知ってるよ!
身長体重スリーサイズ、好きなものから嫌いなものまで
何でもござれですよ!」
「……それは、記憶同期システムを使ったからか?」
先ほどの、店員との会話を思い出す。
あのサービスさえあれば、ユーザーの趣味嗜好を
把握することなど造作もないことなのだろう。
だが、アルミはあっさりと首を横に振った。
「ううん。あたしは使われてないよ。
たっくんが自分で教えてくれたのもあるし、
自分でも知りたいって思ったから」
嬉々とした口調で話すアルミ。
しかし、その表情にふっと陰が落ちた。
「同期システムね、使えたらいいなぁって思ったことはあるよ。
でもね、あれってものすごく高いんだ。
たっくんはまだ学生だし、
あたしを購入するだけでも大変だったみたいだし。
……だから、そのぶん色々とお話するようにしたの。
今はね、システムを使わなくたっていいって思えるんだ」
「そうか……
アルミはさ、鈴木のところに来てどれくらいになるんだ?」
「そうね、三ヶ月ぐらいかな?」
鈴木がアルミと過ごした時間。
その間に、二人はどれだけの会話を交わしたのだろう。
ドールとの関係構築には、一定の時間がかかる。
生前、堂崎氏はそう言っていた。
絶対的な存在であるユーザーを慕い、
愛玩されることを喜ぶプログラムはすべてのドールに備わっている。
しかし、それでも……一般的には、
およそ半年から一年ほどの期間が必要なのだと聞いたことがある。
鈴木とアルミの関係は、過ごした時間以上に深いように見えた。
てらいもなく、互いに「恋人」と言えるだけの繋がりがある。
それだけの関係を築くのに、
三ヶ月という時間は驚くべき短さのように思えた。
「哲さ、さっき心理プログラムのところ熱心に見てたよね」
「……うん」
「リンちゃんをカスタマイズするの?」
「いや、そういうつもりは全然なかったよ。
なんとなく興味があってさ」
「そう……。なんかね、店員さんの話を聞いてる時、
すごく寂しそうな顔してたから」
「あー……ちょっと考え事をしててね。それでそう見えたのかも」
「考え事?」
「そうだな。例えば……
恋愛感情の心理プログラムをインストールすれば、
リンは俺じゃなくて他のやつを好きになれるのかな、ってさ」
アルミが一瞬、目を丸くする。
呆気にとられたような表情は、すぐさま笑顔に変わった。
「──ふふっ、あはははっ」
堪えきれなくなったように、アルミが笑い声を上げる。
それはもう、周囲の通行人たちが振り向くぐらい盛大に。
「笑わなくてもいいだろうに……」
なおも可笑しそうに笑うアルミを横目に、俺はぼそりと抗議してみる。
「いやごめん、その心配はないと思うよ」
口に手を当てて笑いをおさめつつ、アルミが言った。
「あんた、ちゃんとドールの説明書を読んでないでしょー?
面倒くさがっちゃダメだよ?
まあ、あれって辞書一冊くらいの厚さはあるけどさ」
「……確かに、読んでないけど」
というか、実際のところ購入もレンタルもしていないのだから、
マニュアルなんてそもそも手元にないのだけれど。
そんな抗議は、心の内でつぶやくだけに留めておいた。
「てゆーか、哲ってメーカー社長の“家族”だったんでしょ?
てっきりそういうことは知ってるかと思ったんだけどなー?」
……そう言われると、反論のしようがない。
率直に言えば、俺は堂崎氏の事業に対して好感を持てずにいた。
だから、彼が事業について話していたことは憶えていても、
自分から進んで調べたことはほとんどない。
それだけ、俺はエンジェルドールに関して
浅い知識しか持っていなかったのだ。
アルミはやれやれと肩をすくめ、
「説明書に載ってる事なんだけどね」と前置きして話し始めた。
「喜怒哀楽、その四つの感情はデフォルトで内蔵されてるよ。
でもね、恋愛感情はまだ開発されてないんだって」
「……そうだったのか。でもどうして?」
何気なく質問してみると、アルミは困ったような表情を浮かべた。
「どうして……って。ドールのあたしに訊かれても。
……まぁ人間だって、自分で迷ったりするもんでしょ?
『この気持ちは恋なのかぁー!?』ってさ。
そんなつかみどころのない感情なんだから、
当然と言えば当然なんじゃない?」
ふわりと微笑み、アルミが俺を見上げた。
「要するに、そういう系の感情は
ユーザーとドールで育てていくしかない、ってことなのです」
「……そういうものなのか」
どことなく、もやもやしたものが胸に残る。
それなりに納得したものの、どこか釈然としないのも事実だった。
その正体がつかめなくて……とっさに別の疑問が湧いてくる。
「アルミは鈴木のことが『好き』なんだよな……
でも、それって恋愛感情なのか?」
──そう口走って、即座に後悔した。
人間の自分ですら曖昧で分からないものを、
ドールに尋ねること自体どうかしている。
それ以前の問題として、誰であっても
真っ向からそんなことを言われれば、気分を害するだろうに……。
ごめん、と言いかけたところで、アルミの声が被さった。
「うん、この気持ちは恋ですよ!」
返ってきたのは、戸惑いでも反発でもなく、自信にあふれた言葉だった。
「あたしもね、自分でギモンに思ったんだ。
だからね、いっぱい勉強したよ。
恋愛ドラマとか映画とか、マンガとか、たくさんたくさん。
──でね、そうしていくうちに分かったの」
嬉々とした口調。
アルミの横顔は、心なしか赤くなっているように見えた。
「たっくんを好きな気持ちはウソじゃないって。
それから、ただ単に「好き」なだけじゃないんだって。
胸を張って言えるもの。たとえ、作られたココロでも。
あたしは、たっくんのことが大好きだよ」
でもね、とアルミは続ける。
その横顔に、ふっと影が落ちた。
「あたしの存在も……
いつかは、たっくんにとって重荷になるのかもしれないね。
人間の女の子と仲良くなって、ゆくゆくは結婚したりして。
その時、あたしは『家事手伝い』になるのかもしれないし、
メーカーに送り返されるのかもしれない」
語り口は儚げで、言葉には哀愁が滲んでいた。
一陣の風が、街路に吹き渡る。
冬の乾いた冷気が、ひんやりと頬を撫でていった。
「ははっ……アルミは最後まで粘りそうだよな。
『あたしを捨てるの!?』とか言ってさ」
どう返したらいいか分からなくて、俺は軽口を叩くことしかできなかった。
「なにそれ! ないない、ありえない! だって……」
一瞬の間を置いて、途切れかけた声が再び宙を舞った。
「お別れの時は、記憶を上書きしちゃえばいいんだもん」
とっても簡単なことだよ。
そう言って、彼女は微笑んだ。
「積み上げるのは大変だけど、消えるのは一瞬で。
たっくんが望めば、あたしは明日からでも赤の他人になれるもの」
「……それは……虚しくないか」
「ううん、ムダだとは思わないよ。
たっくんを好きな私が存在したことは事実でしょ?
誰も憶えていなくても、それを証明する方法がないとしても。
その事実は、確かにあったんだよ」
アルミは、自分の最期を知っている。
自身の取り扱われ方を、悟っている。
それが良いことなのか悪いことなのか、俺には分からなかった。
「……哲は、リンちゃんのことを人間として扱ってるよね」
「……うん」
「それはそれでいいと思うの。
でもね、あたしは人間になりたいわけじゃないんだ。
エンジェルドールのままでいい。
おとぎ話の人形のように、人間にならなくていい。
だってあたしは──マリオネットでもなければカカシでもない、
『天使の人形』なんだもの」
緩やかなステップを刻み、アルミが半歩先へと躍り出る。
低い空の下、雲間から太陽が顔を覗かせていた。
淡い光を一身に浴びながら、アルミは天を見上げた。
「そう、あたしは天使になりたいの。
ゆくゆくは恋の天使として、たっくん夫婦の仲をとりもつの。
──ねぇ、それってステキなことじゃない?」
さながら歌うように、アルミは語る。
その背中を、俺はただじっと見つめていた。
「たっくんが許してくれるなら、ずっとそばにいたいなぁ。
恋人役じゃなくていい。お手伝いさんでもなんでも……
そばに居させてくれるなら、十分だよ」
たん、と軽やかな靴音が響き、アルミがこちらに向き直る。
同時に、弾むような声音が耳をくすぐった。
「壊れるくらいに、好きだから」

笑顔が、そこには咲いていた。
その表情に、俺は不覚にもどきりとしてしまう。
「いま、ときめいたでしょ! そんな顔してた!!」
「ないから。俺がときめくのは『りん』に対してだけだから」
どちらの「りん」なのかは、あえてうやむやにしておいた。
いや……どちらにせよ、俺も大概か。
アルミはそんな俺を見て、
「アツいですねぇ」とほんわり笑うのだった。
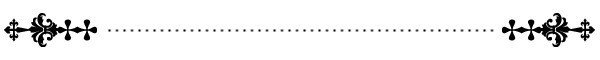
穏やかな光を放つ照明の下で、私は静かな時間を過ごしていました。
とても平和な、安穏としたひととき。
けれど、それが仮初めのものであると知っています。
終わりが近いと悟っています。
降りしきる雪を窓越しに眺めながら、私はホットミルクを口に運びました。
喉を潤す、温かで優しい甘みを感じながら……彼のことを想うのです。
「テツくん、大丈夫かな」
家主のいない寂しさを紛らわすように、私はテレビの電源を入れました。
私がここに来てから──
彼は、ただの一度も自分からテレビを点けようとはしませんでした。
かくいう私も、テレビを点けるのは今回で二度目なのです。
ここに来た翌日の朝、最初にテレビを点けた時に気付いたのは、
リモコンがほこりをかぶっていたことでした。
彼は、テレビを長いこと見ていないようでした。
あえて、見ないようにしていたのかも知れません。
……私にとっては好都合でした。
そして、おそらくは彼にとっても。
『二時のニュースを、お伝えします……』
『警察は、相次ぐ『新型ドール』の被害について、
反政府組織『傀儡』が関与していると断定しました』
『この事件では、治民党衆議院議員の小笠原氏に加え、
各省の政府関係者が被害に遭っており、
政府は各方面に対し厳重な警戒を呼びかけています』
『これを受けて野党は、エンジェルドールに関する規則の厳格化と、
現行のヒューマノイド関連法案の見直しを政府に求める構えです』
『民間人の被害はこれまでに確認されてはいませんが、
エンジェルドールをお持ちの方は、
早急に検査を受けて頂きますよう──』
「……知らなくていいことも、あるものね」
──そう、この世は知らなくて良い事で溢れている。
彼が自ら情報に近付くようには思えませんでしたが、
万が一ということもあります。念には念を入れておくべきでしょう。
私は席を立ち、ハサミを携え、テレビのコードを持ち上げます。
刃でコードを挟むと、ぷつり、と線が断ち切れる手応えがありました。
同時に、室内に響いていた音声がぱたりと途絶えます。
続く目標は、棚の上に置かれた無線ルーター。
そこから伸びるコードに、先ほどと同じく処置を施します。
ほどなくして、ルーターは明滅を止めていました。
数日のうちに確認した限りでは、この住居の情報経路はこの二つのみ。
簡単かつ単純ではありますが、携帯電話を除けば
情報の遮断はとりあえず上々と言えました。
私はハサミを棚に戻し、昼食の入ったナイロン袋に手を伸ばします。
「……テツくん、早く帰ってこないかな」
青緑色のパンを頬張りながら、私は彼の無事を祈るのでした。
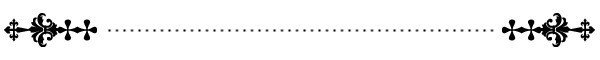
平日の昼間とあって、ファッションビルの客足はさすがに少なかった。
それでも、やはりレディースフロアに足を踏み入れるのはためらわれた。
場違い感というか、自分がここに居てはいけないような気がしてしまう。
二の足を踏んでいる俺を尻目に、アルミはずいずいと進んでいく。
「なに。どうしたの、固まっちゃって」
「……アルミ、リンの服のサイズは男性服でいうならSサイズだ」
「ふむふむ、身長は一六〇センチぐらいかな。
あたしも、脚を変える前は同じぐらいだったから、
服選びには好都合だね」
「そうかそうか。よし、じゃあ後は任せ──げぇ!」
くるりと踵を返そうとしたところで、またもマフラーを引っ張られる。
……本日二度目の奇声。
初回に比べて容赦ない力で絞められたせいか、
声の裏返り具合もひとしおだった。
「なに言ってんの、哲も一緒に選ぶの!」
「いや……だって、俺も付いていく必要はないだろ?
財布は渡しておくから、代わりに選んで買ってきてくれよ」
「はぁ? それじゃ、あんたが来た意味ないじゃない!
自分の『彼女』なんでしょ?
だったらちゃんと自分の目で、
カワイイと思ったやつを選んであげなよ!」
……そういうわけで結局、
俺は引きずられるようにして入店する羽目になったのだった。
店内には、色とりどりの冬物が取り揃えられていた。
メンズコーナーに比べて色彩に溢れていて、
そのカラフルさが逆にアウェイな心境を際立たせる。
売り場の各所から発せられるフェミニンな雰囲気に、
俺は早くもあてられそうになっていた。
「ほらほら、これなんてどう?」
アルミがラックに掛けられていた
一枚のワンピースを手に取り、ばっと広げてみせる。
「ちょっと寒そうじゃないか」
冬ものにしては、これまた薄手のものだった。
ニット地ではあるけれど、いかんせん露出が多いような気がする。
思うに、アルミは自身に似た服装を選んでいるようだった。
「もっと大人しめで、温かそうなやつがいいと思うんだけど。
これはどう?」
「地味すぎ。却下」
俺が広げてみせた服を、アルミは一瞥しただけで切り捨ててしまう。
(……やっぱり、俺が居る意味ってないんじゃないか?)
そんな事を思いつつ、俺はアルミと二人で服選びに勤しむのだった。
幾度かの意見交換、もとい衝突の後に、
俺たちは妥協点を見出して──
と言っても、八割がたアルミの好みに合わせたものだったが──
どうにか二着の服を選び出したのだった。
その後、マフラーや耳あてなどの防寒具、それに靴などを見て回った。
二時間もした頃には、
俺の両手はすっかり買い物袋でふさがってしまっていた。
アルミも少し買い物をしたから、そのぶんも含めて。
「アルミ、少しは自分で持てよ」
「あっ、これかわいい!」
「話を聞いてくれ頼むから」
「ねぇねぇ、他になんか着せたいものとかある?」
まるで耳を傾けず、屈託なく聞いてくるアルミ。
とりあえず、近くの休憩スペースに腰を降ろして、俺は考えを巡らせた。
今まで買った商品を改めてチェックしてみる。
衣服に関しては、上下ともに二着ずつ揃えた。
いずれも、アルミの好みが多分に反映されたものだった。
肌が少し表に見えるぐらいの、わりとアクティブな服装である。
──いや、待てよ?
よくよく考えれば、それは不都合なことだった。
似合う、似合わないという話ではない。
肌が見えれば、それだけリンの身体の傷が見えてしまうからだ。
……トップスに関して言えば許容範囲だった。
肩口は見えているが、そこに傷はなかったはず。
一応は長袖だから、二の腕辺りにあった傷は隠せるだろう。
問題は、ボトムスにショートパンツとスカートを選んでしまったことだ。
このコーディネートでは、最も目立つ右脚の傷が晒される形になってしまう。
ジーンズやチノといった丈の長いものを
買っておくべきだったと、今更ながら後悔した。
しかし、あいにくと今は持ち合わせがない。
ほぼ服装一式を揃えた形となったので、
出費もそれなりに膨れ上がっていた。
後日、また買いに来たらいいか……と考えたところで、
アルミがぽんと手を叩く。
「あ、そうだ! 靴下買ってなかったね」
──靴下。
そうだ。丈の長い靴下ならば、どうにか傷を隠すことができる。
それなら、残り少ない財布の中身でも買うことができそうだった。
かくして、俺らはつかの間の休みの後、再び店へと足を運んだ。
「……値段、意外に高いのな」
値札を見やりながら、俺は自然にそうつぶやいていた。
ファッションビルに入居している店舗だけあって、
靴下ひとつにしてもそれなりに値が張るようだった。
ファストファッションをうたう量販店であれば、
服の一着は買えるくらいの価格だ。
しかし、ビル内にある店舗にとっては、
どこもこれぐらいの価格水準なのだろう。
量販店はこのビルからまた遠く離れているし、
今の俺には、そこまで行く気力もない。
腹を決めて、ここで靴下も買ってしまうことにした。
「なぁアルミ、丈の長いソックスってないかな。
で、それなりに安いやつ」
「丈の長い……ニーハイとか?」
「ああ、そうだな。それ系でお願いするよ」
お目当てのコーナーは、アルミがすぐに見つけてくれた。
種類の豊富さに目移りしつつも、
その中からアーガイル柄とシンプルな黒を選び出す。
金額も、ぎりぎりで足りた。
これで、当面の懸念は一応のところ払拭されたことになる。
「やっと……終わった……」
ほっと安心すると同時に、いくぶんの疲れを感じた。
考えてみれば、朝からずっと歩き通しだった。
それでも大した時間は歩いていないが……
久々の外出ということも影響しているのだろう。
「ごめん、ちょっと気分悪いから会計済ませてくれるか?」
「そんなこと言っちゃって。だるいだけでしょー?」
訝しそうに眉根を寄せつつも、
アルミは商品を会計カウンターへと持っていってくれた。
ショーウィンドウにもたれかかりながら、大きく息をつく。
……なんだか、ざわめきが増しているような気がした。
ふと辺りを見回してみると、女性客が多くなってきたことに気付く。
壁掛け時計を見れば、時刻は午後五時を過ぎている。
これから、このフロアは学生や会社帰りの女性たちで賑やかになるのだろう。そう考えると、何となく心細い気分にもなった。
……しかしまあ、誰もが華やかな格好をしている。
街の中心部にあるファッションビルなのだから、当然なのかもしれない。
ぼうっと眺めているだけでも、あちこち目移りしてしまいそうになる。
ああ、まったくもう……
犯したくなるじゃないか。
………………
…………
……
──────えっ?
瞬間、全身が悪寒に包まれた。
いま……俺はいったい何を思った?
自分の思考が空恐ろしくなり、慌てて目を背けた。
しかし、その先には、またしても女子の一団がいた。
目を反らしても、首を回しても。その先には、客の姿がある。
とっさに下を向いていた。
いや、その場に膝を折っていた。
両手に提げていた紙袋が床に落ち、
続けざまにばさばさと乾いた音を立てた。
「お客様? どうかされましたか?」
耳元で声がわんわんと鳴った。
次いで、視界の端に映るのは、女性店員の心配そうな表情で。
──やめろ、やめてくれ。
──頼むから放っておいてくれ。
視界は歪み、激しく明滅を繰り返していた。
獣のような衝動が、全身を這いずり回る。
締めつけるように、あるいは切り刻むように、蝕まれていく。
手を伸ばせ、
その手で掴み、
引き倒し、
服を
破り棄てて──
壊せ。
「具合が 悪い
よ うでし
たら、
医
務室ま で……」
震える手が、声の主へと寄っていく。
衝動を叩きつける相手として、欲している。
……駄目だ……!
この手に、ヒトを掴んではいけない。
歯を食いしばり、伸ばした指先を握り締めた刹那。
ふいに聞こえたのは、短く甲高い叫び声。
視界の片隅には、尻もちをついた店員の姿があった。
一瞬遅れて、自分が突き飛ばしたのだと、頭の隅で理解する。
──ここにいてはいけない。
──何故?
──壊して、しまうから。
がくがくと笑う脚に力を込め、転がるように区画を抜ける。
そのまま、俯いて通路を駆けだした。
何度も何度もぶつかって、所々で罵声を浴びて──
俺は無我夢中で走り続けた。
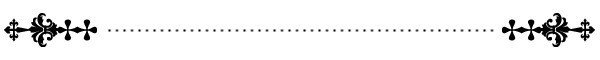
行き着いた先は、人気のない非常階段だった。
音もなく、光もろくに届かない薄暗がりの空間が、
今は安息の場所に思える。
全身の力が急速に抜け落ちていき、俺はその場にへたり込んだ。
しかし、迫る足音がすぐに聞こえてきた。
慌ただしい足取りは、明らかにこちらに向かってやって来る。
身体が強張り、本能的な恐怖が全身に染み渡っていく。
かつん、かつんと床が鳴る。
追ってきている。捕まってしまう。
そして──フロアから差し込む光に、大きく影が落ちた。
「……アルミ」
目の前に立ちはだかった人影は──アルミだった。
「……どうしたの、いきなり?」
買い物袋を両手いっぱいに提げたアルミが、
不安そうにこちらを見つめていた。
俺が落とした荷物を集めつつ、ここまで追いかけてきたようだった。
「ちょっと……気分が悪くなっちゃってさ。
ごめん、心配かけて」
……結局、俺は非常階段でそのまましばらく休んでいた。
一〇分もした頃には、混乱はほとんど鎮まっていた。
けれど、フロアに戻る気には到底なれなかった。
エレベーターには乗らず、そのまま階段を降っていく。
レディースフロアは3Fで、
出口がある1Fまでそう遠くない事が唯一の救いだった。
アルミに支えられながら、人混みを避け、どうにか駅まで辿りついた。
街中を歩いている間、俺はコートに付いたフードをずっと被っていた。
人の群れが、怖くて仕方なかった。
雪で白みがかったアスファルトを見つめつつ、
一歩一歩、確かめるように歩き続けていた。
「ねえ……本当に、大丈夫?」
別れ際、アルミは俺に手荷物を渡し、心配そうに尋ねてきた。
「大丈夫だよ。なんだろうな。たぶん貧血なのかな」
そう言って、笑ってみた。
上手く笑えていたかどうかは、まったく自信がないけれど。
「……鈴木には、俺の具合が悪くなったことは言わないでくれ。
あいつ、大げさに心配するからさ」
「……ん、わかった。無事に帰ってよね?」
取り繕ったような笑顔を残して、アルミがこちらに背を向ける。
駅に向かう途中、ちらちらと振り返っていたものの、
その姿も人混みに紛れて、すぐに見えなくなってしまった。
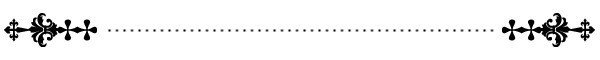
約束の六時を過ぎても、彼は帰ってきませんでした。
はやる思考を抑えつつ、頭をもたげだした不穏な想像を払いつつ……
私は、彼の帰宅を待っていました。
──大丈夫。おそらく、奴らには知られていない。
でも、と私は思います。私と彼の関係を洗い出せば、
ここに身を寄せていることは容易に想像できるはず。
しかし、この数日間、襲撃の気配は微塵も感じられませんでした。
もしかすると、その必要は無かったのかもしれません。
この高層マンションで騒ぎを起こすことがどれだけリスクの高い行為か、
奴らは熟知しているはずなのです。
──だとすれば、目標が外から出てくるのを待っていた?
──奴らが、私ではなく彼を標的にしているのだとしたら?
「……まさか」
私は迂闊でした。
彼を長いこと外出させるのは、あまりにも危険だったのです。
そのことに思い至らなかったのは、内心浮かれていたからなのでしょう。
彼と過ごす時間の心地よさに、酔いしれていたからなのでしょう。
──と、その時でした。
ぴーん、ぽーん、と。
突然、インターホンの音が鳴り響きました。
おそらく彼ではありません。
彼なら、自分で鍵を開けて入ってくるはずなのですから。
つまり、鳴らしたのは他の何者か。
弾かれたように席を離れ、私は受話口へと駆け寄ります。
画面に映っていたのは、宅配業者風の男性でした。
「お届けものでーす!」
息を潜めていると、男性の快活な声がスピーカーを震わせました。
私は「はい」とだけ返答し、机の拳銃を手に玄関へと向かいました。
ドアにチェーンを掛け、慎重に扉を押し開きます。
「すみません、サインお願いします」
隙間から差し出される伝票とペンを手に、受領のサインを書き終えます。
男性に不審な素振りは見えませんでしたが、
用心するに越したことはありません。
「荷物は、軒先に置いて頂けますか?
……今、手が離せないので」
「分かりました。では、玄関横に置いておきますんで、
お早めに家の中へ入れてくださいね」
宅配員の足音が遠ざかり──やがて完全に聞こえなくなってから、
私はようやくドアを開きました。
置いてあった小ぶりの段ボール箱を手に、室内へと素早く戻ります。
送り主は、隣街に住む人物からのものでした。
彼の友人でしょうか。
そう思いながら、宛先の欄に目を走らせた瞬間、私は凍りついていました。
そこに書かれていた名前は──「堂崎凛」。
はっと我に返り、荷物を居間へと運びこみます。
包装を手早く解くと、何か白いものが目に入りました。
中に詰め込まれていたのは、女性ものの下着でした。
組織の仕業であることを、私は瞬時に理解します。
送り主の氏名・住所も、きっと架空のものでしょう。
「……ふふっ」
私の居場所が、すでに割れていること。
その事実を「贈り物」は雄弁に物語っていました。
そして、入れられた下着が三セット──
三日分だけ用意されているという事実。
そこから推察するに、
私は三日間の猶予を与えられたということなのでしょう。
それは同時に、期限後には行動を起こすという
脅迫をも示唆していました。
「……ずいぶんと、粋な計らいをしてくれるのね?」
ただ、笑うしかありませんでした。
これは彼らなりの配慮ということなのでしょうか。
だとしたら、なんとも悠長なことです。
見方を変えれば、それは余裕の裏返しということでもあるのですが。
その時でした。だしぬけに、玄関から扉の開く音が聞こえたのは。
「──ただいま」
続いて、彼の声が大きく響きました。
よかった……無事だったんだ。
安堵しつつも、私は段ボール箱を
クローゼットの奥に手早く押し込みました。
ほどなくして部屋に入ってきた彼に、私は笑いかけるのでした。
「──おかえりなさい、テツくん」
大丈夫。だいじょうぶ。
時間はまだ、十分に残されているのですから。
`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。

