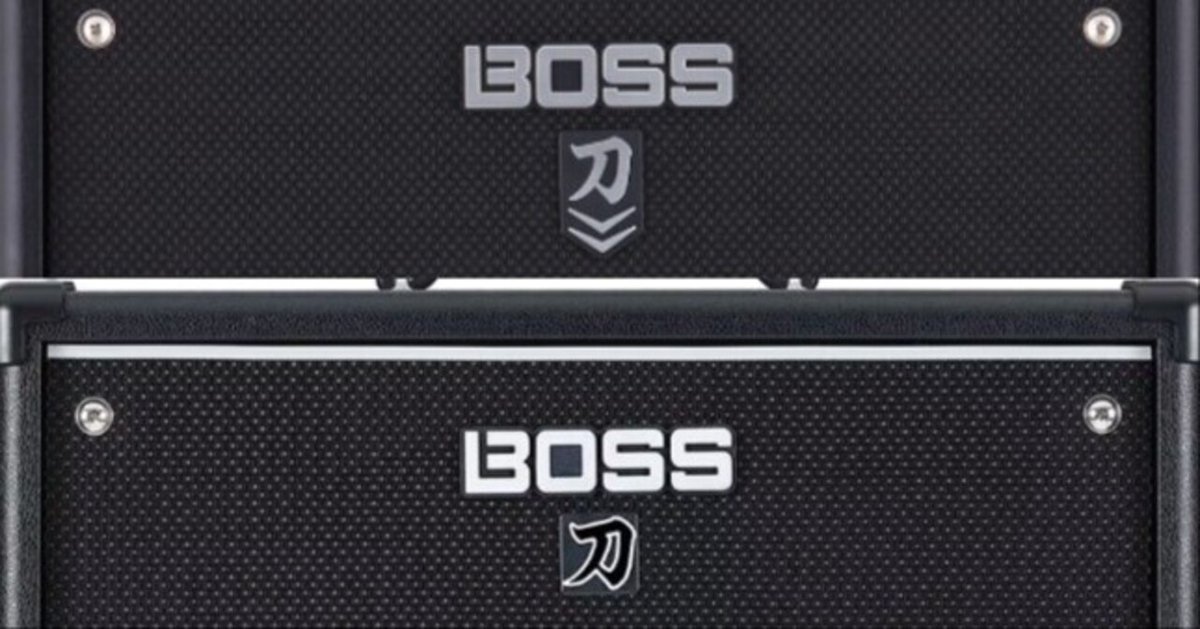
BOSS「KATANA-50」シリーズの良い点と悪い点
BOSSの「KATANA-50」シリーズは、多機能でコストパフォーマンスに優れたギターアンプです。
海外のAmazonのレビューでも評価が高く、Redditなどの掲示板サイトでもKATANAアンプに関する激論が交わされていたりと、特に海外で人気になっているという印象です。
「KATANA-50」を実際に使ってきて感じた「良い点」と「いまいち」な点を挙げていきたいと思います。
◆世代の違い
この項目では「KATANA-50」の世代の違いを簡単に説明しておきたいと思いますが、「世代の違いは分かっている」という方は読み飛ばしていただければです。
「KATANA-50」は、第1世代(無印)、第2世代(MKⅡ)、第3世代(Gen3)があります。
現行機種の第3世代(Gen3)は
・別売りの部品を購入することでBluetooth接続に対応出来る
・PUSHEDというアンプモデが追加された
・USB端子に「タイプC」が採用された
などのメリットがありますが、他方で
・価格が大幅に高くなった
・「AIRSTEP Kat Edition」というサードパーティー製のフットスイッチが2025年1月時点で使えない(たぶん)
・純正のフットスイッチの挙動も変更になった
という、残念なポイントもいくつかあります。
そのため、私は現在も第3世代(Gen3)ではなく、第2世代(MKⅡ)の「KATANA-50」を使っています。
ただ、上記の点以外では第3世代(Gen3)も第2世代(MKⅡ)も大きく変わっているところは多くないため、第3世代(Gen3)の購入を検討している方にも参考になるように、「KATANA-50」を実際に使ってみて感じた「良い点」と「いまいち」な点を挙げていきたいと思います。
なお、第3世代(Gen3)も第2世代(MKⅡ)のどちらを購入したほうが良いかという点については、以下の記事で書いていますので、興味がある方は参考にしていただければです。
◆良い点(おすすめできる点)
◇軽い(他のアンプと比べた場合)
「KATANA-50」の重さは12kg弱であり、一般的なギターアンプと比べると軽い部類になります。
私は「KATANA-Artist」という100Wタイプのアンプも持っているのですが、「KATANA-Artist」は重さが20kg近くあり、筐体が大きくて重心も取りにくいため、階段を上り下りする時にバランスを崩すとヒヤッとします。
そのため、スタジオ練習などでも気軽に使えるアンプとして別途「KATANA-50」を買ったのですが、約10kgの違いは大きく、「KATANA-50」のほうは階段でも大きな苦痛を感じることなく上り下りできますし、サイズも小さめなので台車がなくても駐車場からスタジオまで持ち運ぶことができます。
50Wクラスのモデリングアンプでさらに軽くするとなると、VOXの「VX50 GTV」などが選択肢になってきますが、「VX50 GTV」のほうは
・筐体が小さく軽いので独特の「箱鳴り感」がある
・本体のイコライザーでは「TRBLE」と「BASS」しかない(MIDがない)
・「AIRSTEP Kat Edition」のような多機能なフットスイッチがない
などのデメリットもあるので、個人的には「KATANA-50」のほうが便利だと感じることが多いです。
◇「パワーアンプイン端子」が付いている
「KATANA-50」の第2世代(MKⅡ)、第3世代(Gen3)には「POWER AMP IN端子」(パワーアンプイン端子)が付いており、いわゆる「リターン挿し」と同じようなことができます。

「リターン挿し」と「POWER AMP IN端子」を使用する場合の違いはBOSSのウェブサイトで解説されていますが、「KATANA」アンプのプリアンプ部分を通さずに、マルチエフェクターやアンプシミュレーターなどの元の状態に近いサウンドを出力することができるというメリットがあります。
アンプシミュレーターをスタジオやライブハウスで鳴らす方法としては、パワーアンプとキャビネットを使うという方法もありますが、時前でパワーアンプとキャビネットの両方を用意する場合には費用がかかりますし、持ち運ぶ荷物の量も増えてしまいます。
単体機のパワーアンプとしてはプレイテックの「GPA-100」という持ち運びに便利な小型の製品もありますが、スタジオに置いてあることが多い16ΩのキャビネットにGPA-100を接続すると、ジャンルによっては音量が足りないと感じることもあるため、別途8Ωのキャビネットを自分で用意しなければならないケースもあり、悩ましいところです。
そこで「KATANA-50」を「パワーアンプ付きのキャビネット」として使うことで、コストも押さえることができますし、キャビネットを持ち歩くよりも軽いので楽です。
また「KATANA-50」は、ツインギターのバンドでも埋もれないくらいの十分な音量を出すこともできるので、小型のパワーアンプよりも対応できるジャンルが広く汎用性があります。
◇多数のエフェクト類が使える
「KATANA-50」には、マルチエフェクターと同程度の大量のエフェクターが内蔵されています。
アンプ本体には液晶画面等はなくツマミの数も限られているため、PCなどを接続した上で大量のエフェクトの中から自分が使いたいものを選んでアンプ本体にセットしておくと、本体だけで様々なエフェクトを操作できるようになります。
◇音量の微調整が簡単 = 自宅でもスタジオでも使える
ギターアンプは基本的に「家で使うには音量が大きすぎる」か「スタジオなどで使う場合には音量が小さすぎる」といういずれかのパターンに当てはまることが多く、自宅で使っているアンプをそのままスタジオで使えない、ということが良くあります。
しかし「KATANA-50」は出力を「0.5W」「25W」「50W」から選ぶことができるだけでなく、プリアンプ部分のボリュームとは別に、マスターボリュームが容易されているため、サウンドの変化が少ない状態で音量を自由自在に調整することができます。
自宅で演奏できる程度の小さい音量に設定することもできますし、スタジオやライブハウスでドラムにも負けないくらいの大きな音量を出すこともできます。
さらにヘッドホン端子も付いているので家族が寝ている時にも自宅で夜中にアンプを使った練習をすることもできます。
そのため「KATANA-50」が1台あれば、自宅練習用としても、スタジオやライブ用としても、使うことができます。
◇クリーントーンからハイゲインサウンドまで音作りの幅が広い
「KATANA-50」シリーズは第2世代(MKⅡ)までは「CLEAN」「CRUNCH」「LEAD」「BROWN」「ACOUSTIC」の5種類のアンプタイプを選ぶことができ、第3世代(Gen3)にはさらに「PUNCH」という音色が追加されています。
そして歪み系のエフェクターも大量に内蔵されているため、これ1台で透き通るようなクリーントーンから、メタル系の超ハイゲインサウンドまで作ることができます。
他社の製品でも最近は様々な音色が出せるアンプは増えてきてはいますが、Fenderの「Tone Master」シリーズや、Rolandの「Blues Cube」シリーズのように、限られた音色に特化したモデリングアンプも少なくないことを考えると、1台に様々なアンプモデルが搭載されているのはメリットであると思います。
◇各アンプモデルの音色に統一性がある
海外のYoutuberの方が「KATANA-50」のサウンドについて「どのアンプモデルを選んでも歪みの量が違うだけで同じような音に聞こえる」という点をネガティブな側面として説明していました。
しかし個人的には「どのアンプモデルも同じ系統のサウンドがする」という点はメリットであると思います。
アンプシミュレーターを使う場合に良く遭遇する問題点として、クリーン、クランチ、リードなどの各音色に統一性がなく、プリセットを切り替えた瞬間に「別世界」「違う曲」のようなサウンドになってしまう、ということがあります。
このような場合、大量のアンプモデルの中から「同じ系統」の音色を探すという非常に手間のかかる作業が発生することがあります。
しかし「KATANA」シリーズのアンプモデルは、クリーンからクランチに切り替えても、リードサウンドに切り替えても「同じ系統」のサウンドであるため、音色を切り替えた際の違和感が少ないです。
◇PCでもスマホでも編集ができる
「KATANA-50」はPCやMacに接続して「BOSS TONE STUDIO for KATANA 」というアプリを使うことで、PCなどで音色の編集や管理ができます。
また第1世代(無印)と第2世代(MKⅡ)では「Katana Librarian」というサードパーティー製のアプリを使うことでスマホで音色の編集や管理ができ、第3世代(Gen)からは公式のスマホアプリが使えるようになっています。
アンプやマルチエフェクターの中には
・PCでもスマホでも編集ができないもの
・PCでは編集できるけどスマホでは編集できないもの
・スマホでは編集できるけどPCでは編集できないもの
など不便な機種もありますが、KATANAシリーズはPCでもスマホでも編集できるので、自宅ではPCの大画面で編集をして、スタジオやライブなどではスマホを使って管理をする、という使い分けができるのが便利です。
なお「Katana Librarian」を使うと、何故かKATANAアンプの仕様にはないアンプモデルも選択できたり、非常に細かい設定ができるようになります。
◇AIRSTEP Kat Editionが便利
「KATANA-50」は、基本的に「FS-6」「FS-7」などのスイッチが2個だけ付いたフットスイッチにしか対応しておらず、3種類~4種類の音色を使い分けるのは難易度が高めです。
「KATANA-50 EX」や「KATANA-100」などの上位機種の場合には、「GA-FC」という4チャンネルの切り替えが可能なフットスイッチを使えるのですが、(EXではない」「KATANA-50」では「GA-FC」は使えません。
しかし「KATANA-50」第1世代(無印)と第2世代(MKⅡ)では、サードパーティー製の「AIRSTEP Kat Edition」というフットスイッチを使うことで、4種類の音色を簡単に切り替えることができるようになります。
しかも「AIRSTEP Kat Edition」とスマホをBluetoothで接続することで、無線でアンプの音色の編集や管理をすることもできるようになります。
(AIRSTEP とアンプは有線のUSBケーブルで接続する必要があります。)
「KATANA-50」と同じくらいの価格帯のアンプで4種類の音色切り替えに対応している機種はほとんどないと思いますので、この点は大きなメリットだと思います。
2種類の切り替えしかできない場合には別途歪み系エフェクターなどを組み合わせる必要が出てくることがありますが、4種類の切り替えが可能であればエフェクターがなくてもライブでも十分に対応ができることが多いと思います。
なお、2025年1月の時点では「AIRSTEP Kat Edition」が第3世代(Gen3)に対応したという情報は見つけられなかったので、上記のメリットは現時点では第1世代(無印)と第2世代(MKⅡ)に限った話になると思います。
◇電源ケーブルをキャビネットに入れて持ち運べる
とても些細なことですがアンプを持ち運ぶ時に、良くある事故が「電源ケーブルを家に忘れてきた」というケース。
アンプがクローズドバック(背面に隙間がないタイプ)で、電源ケーブルを巻き付ける部品もない機種の場合には、アンプ本体とは別に電源ケーブルを持ち運ばなければならず、意外に荷物になったり、置き忘れてしまったりすることがあります。
たとえばVOXの「VX50 GTV」というアンプは本体は非常にコンパクトで軽いのですが、本体に電源ケーブルを格納する場所がなく、しかも電源が大きめのアダプターのタイプなので、ギターのギグバックにも入りにくく持ち運びが少し不便です。
しかし、「KATANA」シリーズのアンプは基本的にオープンバック(背面が開いていてスピーカーが見えているタイプ)なので、キャビネットの中に電源ケーブルやUSBケーブルを入れておけば、持ち運びも楽ですし忘れ物をするリスクも防ぐことができます。
(ただ、スピーカーやキャビネットに傷を付けないように注意が必要です。)
◇古いモデルが安く入手しやすい
現在、新品で販売されている「KATANA-50」の現行機種は第3世代(Gen3)ですが、古いモデルの第1世代(無印)と第2世代(MKⅡ)は中古市場で安く入手することができます。
第3世代(Gen3)が2025年2月13日時点で3万5000円~3万8000円くらいですが、第2世代(MKⅡ)は過去に新品価格で2万5000円程度で販売されていた時期もあり、中古価格だと2万円ちょっとで入手できるケースが多いと思います。
第1世代(無印)は音色の数が少なかったり、パワーアンプイン端子が無いなどのデメリットがありますが、2万円以下で販売されていることもあります。
「安くて使えるアンプが欲しい」という場合には、初心者でも手の届きやすい機種だと思います。
◆イマイチな点
◇出音の良し悪しは好みによる
「KATANA-50」のサウンドは、「良い」「好き」という人もいれば、「高域がシャリシャリしていて苦手」と感じる人もいるようで、万人受けする音ではないという印象です。
上位機種の「KATANA-Artist」のサウンドは高域が強めながらも何も考えなくても良い音が出せる気軽さがあり、イコライザーなどで調整をすれば十分に太いサウンドを作ることもでき、様々な好みにも応じてくれそうな懐の深さがあります。
他方で「KATANA-50」のほうは調整をしても「高域が強い」という印象があり、極端に高域を下げると「細い音」になってしまうこともあるので、音作りがなかなか難しい印象です。
海外のサイトのレビューを見ていると高域部分を柔らかくするために5khz~6.3khz周辺からカットしているというコメントも多いです。
「スピーカーを交換すれば音が良くなるのではないか?」と思う人もいると思いますが、海外のYoutuberの方が実際にスピーカーを交換した動画を見た範囲では、スピーカーというよりも入力レベルの問題や、プリアンプ部分の音色やキャビネットのサイズの問題なのかも?、という印象でした。
また自宅で小音量で弾いている時は高音域の強い部分が気になりますが、スタジオで大音量を出すと低音域や中音域の成分が増えるので、バランスを取りやすくなる印象です。
色々試してみた結果、ギターから直でインプット端子に接続するのではなく、ブースターやプリアンプなどを挟んで、インピーダンスを下げた上で、入力信号のレベルを上げると、音の芯が太くなり迫力のあるサウンドが出やすくなりました。
「EP Booster」を挟むと音が太い感じになりますし、「MXR M133 MICRO AMP」を入れると音が明るい状態のまま前に出てくるような印象がありました。
「ブースターなんて持っていない」という人は、マルチエフェクターのエフェクトをオフにして前段に挟むだけでも良いと思いますし、「SD-1」などの歪み量が控えめのオーバードライブ系ペダルを挟んだ上でゲインツマミ(ドライブツマミ)をゼロにするという方法でも良いと思います。
その他の解決方法として、前記のとおり「KATANA-50」の第2世代(MKⅡ)、第3世代(Gen3)には「パワーアンプイン端子」や「AUX端子」があり、他社のマルチエフェクターやアンプシミュレーターを接続することができるので、「KATANA-50」のモデリングの音が苦手な場合には、他のマルチやアンプシミュレーターと組み合わせるという方法もあります。
◇公式アプリが少し使いづらい
前記のとおり「KATANA-50」はPCやMacに接続して「BOSS TONE STUDIO for KATANA 」というアプリを使うことで、PCなどで音色の編集や管理ができます。
ただ、この公式アプリは少し使いづらいです。
プリセットをPC側のライブラリに保存したり、逆にPC側のライブラリからアンプ本体にプリセットを移動させたりする、という作業も地味に時間がかかったりします。
ただ、他のメーカーのアプリも使いづらいと感じるものが多く、LINE6のPOD Expressのアプリは頻繁にクラッシュしたりすることを考えると、KATANAシリーズのアプリは比較的使い勝手が良いほうなのかも知れません。
◇見た目が・・・
KATANAシリーズは海外でのマーケティングに力を入れている製品という噂もあってかアンプの目立つ場所に「刀」という漢字のロゴが入っています。
海外の方から見るとオリエンタルな雰囲気があってカッコ良く見えるのかも知れませんが、日本人からみると「小学生の筆箱」などを想像してしまい、自宅外に持ち出すのを躊躇したくなる人もいると思います。
以前にフリマサイトで「刀」のロゴが外されたKATANAアンプが出品されており説明欄に「どうしても我慢できずに外してしまいました」とのコメントがありましたが、その方の気持ちも理解できるところです。。。
「Roland」「VOX」「Marshall」「Fender」などの見慣れたアンプのロゴと比べてしまうと、ロゴを自由に外せたり交換できたら良いのにな・・・と思うことがあります。
◇本体を傾けて音を聞きやすくする機能が無くなった
「KATANA」の第1世代(無印)には、アンプの筐体をを上向きに傾けて音を聞きやすくする「スタンド」が装備されていました。

https://www.boss.info/jp/products/katana-50/support/
しかし、第2世代(MKⅡ)、第3世代(Gen3)からは、この「スタンド」の機能が無くなってしまいました。
BOSSからは純正の「BAS-1」というアンプスタンドが販売されているので、こちらの別売りのスタンドを購入して使えば良いのですが、「BAS-1」は畳んだ状態でも存在感のある大きさなので、持ち運びも面倒ですし、置き場所に困ることも良くあります。
ドアストッパーなどでアンプに角度を付けるという方法もありますが、大きく角度を変えることができないので、この方法だと音が聞こえにくいこともあります。
そのため、第1世代(無印)の本体に付いていたスタンドは非常に便利だったのですが、第2世代(MKⅡ)、第3世代(Gen3)でスタンドが無くなってしまったのは残念なところです。
◆まとめ
「KATANA-50」のデメリットにも触れましたが
・ 比較的気軽に持ち出せる大きさ
・ 1台でクリーンからハイゲインサウンドまでカバーできる
・ 大量のエフェクトが入っている
・ パワーアンプ付きのキャビネット的な使い方もできる
・ 自宅練習用としても使いやすい
・ スタジオ練習やライブでも十分な音量を出せる
などのメリットを考えると、非常に使い勝手の良いアンプだと思います。
私はこれまで、Rolandの「Cube」、VOXの「VX50 GTV」、小型のPAスピーカーなど、「KATANA Artist」、小型のパワーアンプなど色々と試してきましたが、最近は持ち運びの利便性と使い勝手の良さのバランスが良い「KATANA-50」を使うことが多くなってきました。
前記のとおり第3世代(Gen3)が2025年2月13日時点で3万5000円~3万8000円くらいなので機能の豊富さを考えると十分に安いですが、第2世代(MKⅡ)中古価格だと2万円ちょっとで入手できることもあるので、自宅に置き場所を確保できる場合には、安く入手できるタイミングで買っておくと色々な場面で活用できると思います。
