
人は勉強したほうが良いと言える本当の理由とは
なんで勉強しないといけないの?
なんで毎日学校にいかないといけないの?
子どもから尋ねられたとき、どう答えていますか?
なぜ勉強が必要なのか
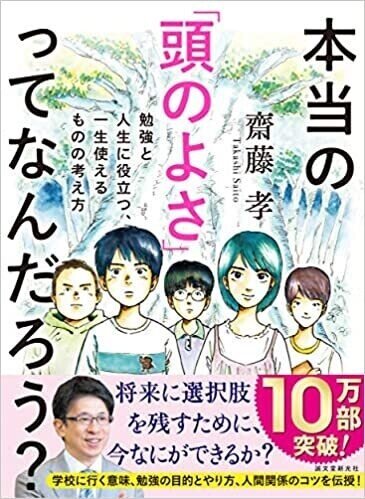
この本を手に取ったのは、子どもから聞かれたときに、納得感のある答え
を与えて、「やらされている勉強」ではなく「意欲的にやりたくなる勉強」
に意識を変えてあげることができたらと思ったからです。
著者である斎藤さんが伝えたかったのは、この社会で生きていく力を身に着けるために勉強が必要であるということと、学校は単に知識を与えてもらうために行く場所ではなく、人間関係を体感的に学ぶ場所であるということです。
「自分のこの先の可能性は可能な限り広げておいたほうが良い」
という一文があります。
さぁどうしようかという局面に立った時、可能性を広げている人は、数多くある選択肢の中から選ぶことができます。
やりたいことが、もうはっきりしているならその道に進めばいいのですが、はっきりしてないならなおさら勉強によって可能性をひろげておくことが、将来、自分のやりたいことをできるようになっていきます。
学ぶことは楽しい
学ぶとは本来楽しいことであるはずだと、斎藤さんは書いています。
本当に同感です。英語で学生を意味する「スチューデント」という言葉は原語であるラテン語で情熱を持つという意味も含まれているそうです。つまり、学ぶことに情熱を持っている人のことを指していたのです。
勉強できる人のことを指して「あの人は頭が良い」ということがあります。もちろん、勉強だけが頭の良さの全てではありませんが、あながち間違いでもないと思います。なぜかと言えば、頭が良くなるには志と情熱が欠かせないからです。
何もしないのに頭が良い人はおらず、
勉強をしているから頭が良くなるんです。
苦手科目を克服する秘訣
読んでいて、この発想はなかったと感じたのが、数学に対する見方です。
正直、小学校のころからずっと算数が苦手で、中学、高校と進んでも、頑張ってはみましたが、相変わらず苦手でした。
高校は電気工事士の資格を取りたいという情熱だけで、工業高校の電気科に進学したので、7割の授業が数学系という現実に打ちのめされたのを思い出します。
大人になってからも、数字が苦手という思い込みは消えず、お金の計算からも逃げてました。最近は「お金の勉強会」に参加して、毎日出納帳を付けることで数字に触れるようにしています。
さて、本題に戻りますが、数学は論理的な思考回路を手に入れるために学ぶというのが新鮮でした。
「因数分解なんて覚えても、大人になったら使うことないし・・・」
確かに、そう思っていましたが、因数分解の考え方をすると、ものごとが整理しやすくなるというのは、納得です。
バラバラになっているものを( )でまとめると整理できるんです。
こうして考えていくと、勉強をして得になることはたくさんありますし、生きていきやすくもなります。損になることは1つもないとわかります。
とはいえ、勉強って楽しいものばかりではありません。当然のことながら、苦手なものもあります。どうすればいいのでしょうか。歯を食いしばってやりますか?
自分らしい戦術を見つけろ
常々、何をするのでも仕組みを作って、どうすればやりたくなるか、あるいは、やりやすくなるか考えるのが自分の得意分野です。そのことが、「自分らしい戦術」という言葉でまとめられていました。
自分にあったやり方を見つけて取り組めば、疲れないし、楽しくなってきます。さらには、大人になってから仕事のやり方としても応用が利きます。
この本の中で、もう一つ共感した言葉があります。
「本はどこでもドアだ」という言葉。
本を読めば、瞬時に空想の世界にも飛び込めるし、著者がまるで先生のように考え方ややり方を教えてくれます。
だから、昔から本を読むのが好きでした。小中高と図書室の本を全て読破したことは、すべて雑学となって、どんなことがあっても生き残れそうだという自信につながっています。
今日から実践すること
今日から早速実践していきたいことも、見つかりました。
本を読んで「すごいな!」と思うことに出会ったら、心の師匠にしてしまうことです。
心の師匠は何人いてもいいので、どんどん師匠たちに出会っていきたいと思っています。
そうして自分の中に蓄積された知識や知恵の言葉が、根を生やして太くて大きな自分の軸を作ってくれるのだと思います。
なぜ勉強するのか?という、誰もが一度は通るであろう疑問にスッキリ答えてくれる素晴らしい1冊でした。
