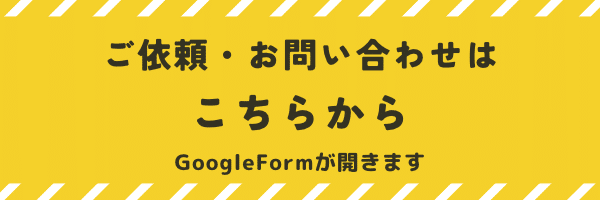【選挙ツール】あなたはいくつ知ってますか? 選挙にまつわる広報物の世界
こんにちは、地方選挙専門の選挙広報プランナーhanaichiです。
今回は選挙(に出ると決めてからの活動)にまつわる主な広報ツールについて、どんなものがあって、どんな役割で使われるかなど、簡単に解説したいと思います。
今年の4月には統一地方選挙がありますね。選挙に出る方はもちろん、選挙に出ない方も何かの参考になる内容かもしれません。
ぜひ、ご一読ください。
本題の前に、自己紹介を。
地方選挙専門で選挙ツールの制作をしています、hanaichiと申します。選挙ツールの制作を含む、企画・デザイン会社で勤務後、2021年からフリーで活動しています。
選挙ツールの制作については30回以上、県政レポートなど議会報告の編集についても50本以上の実績があります。
※リピーターの方を含むため「人」ではなく「回」とさせていただいております
基本の3ツール
選挙に出るにあたり、必ず制作すべき3つのツールがあります。それがこちら。
リーフレット(後援会入会のしおり)
掲示板ポスター
選挙はがき
私はこの3つを基本の3ツールと呼んでいます。まずは、こちらの3つについてそれぞれお話ししたいと思います。
リーフレット(後援会入会のしおり)


リーフレットは候補者の説明書です。候補者の主張、主義、信条、政策など、どんな人で何を考えているのかを記載した広報物になります。ご自宅のポストに入っていたりして、見たことがある方も多いのではないのでしょうか。
リーフレットは「後援会入会のしおり」や「後援会入会案内」などと呼ばれることも多く、その名の通り、後援会への入会を促す役割があります。そのため、下の画像のように入会申込書が切り取れるようになっている場合が一般的です。

後援会に入会してくれる人を募り、書いてもらった申込書を回収するために切り取れるようにしてあるわけです。しかし、この役割はメインではありません。前提として、候補者に強力な後援組織がある場合、たくさん配って回収することも可能ですが、往々にしてそうではない候補者の方が多いです。その場合、物理的に回収が難しかったりします。
そのため、どちらかというと名刺代わりのように配りものとして使われるケースが多いです。立候補を決めリーフレットを作ったら、会う人会う人に必ずお渡しするイメージですね。
規格や仕様に制限はないですが、A4サイズの用紙を三つ折りにしたものが一般的です。当店のセミオーダープランでは、ポスターとのデザインの親和性から、タテヨコの縮尺が近い三つ折りにしてはがきサイズになる形を採用しています。
(もちろんA4サイズも制作可能です。お気軽にご相談下さい)
中身として何を書くかは、候補者(もしくは依頼する業者)それぞれの考えや個性が出ます。また、選挙によっても変わってきます。その街の行政のトップである首長選挙の場合、政策が重要な要素になります。候補者が少なく、議員と違ってやれることが多いため、政策で差別化しやすいからです。
一方、市議会議員選挙の場合、政策をたくさん書き連ねるのはあまりおすすめしません。立候補者が多く、抽象的な政策原稿では差別化が難しいためです。
例えば、「子育て支援に力を注ぎます」と書いたとします。それ自体は全然悪いことではないですし、私も書くことはあります。が、今の時代、「子育て支援に力を注がない候補者」のほうが少ないですよね。市議会議員(特に新人)の場合、具体的に政策を書くのは難しいという側面もあります。
もちろん、力を入れたい政策については記載すべきですが、私の場合はそれよりも候補者の人となりや考え方、姿勢などがポジティブに伝わるように意識して制作をしています。
リーフレットは名刺代わりです。あくまで、候補者の入口として興味を持ってもらうことに注力し、サイトやSNSなどに誘導してファンになってもらうことが大切です。
また、リーフレットは基本的に政治活動中に使用するものです。そのため、「〇〇市議会議員選挙に立候補予定」や「ぜひ皆様の一票を入れてください」などの表現はできません。選挙を特定し、投票をお願いできるのは選挙運動と言って、選挙期間中(公示・告示から投票日前日まで)にのみ許されています。ご注意ください。
掲示板ポスター

掲示板ポスターは誰でも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。選挙期間中、至る所に貼り出される、あれです。

私は掲示板ポスターと呼んでいますが、選挙ポスターなどと呼ばれることもあります。正式には選挙運動用ポスターですね。
サイズに決まりがあり、基本的に420mm × 300mm以内となっています。
(国政選挙や都道府県知事選挙の場合、演説会の告知を入れれば420mm × 400mm以内のポスターを作成することができます)
基本的にはA3サイズ(420mm × 297mm)で制作します。縦長、横長どちらも可能です。また、掲示板ポスターには掲示責任者と印刷者の明記が必要です。制作する際にはご注意ください。
町中の至る所に掲示板が立ちますので、選挙の広報物と言えばこれ!といった感じでしょうか。役割としては、言わずもがなかもしれませんが候補者の名前と顔を周知することになります。
市議会議員選挙の場合は、特にたくさんのポスターが貼られ、定数の多いところでは候補者が50人を超えます。似たようなポスターが並ぶ中で差別化するのは難しいですが、ここに各候補者が知恵を絞ることになります。写真を工夫して撮ってみたり、文章を入れてみたり、色合いでインパクトを出したり。もし選挙に出る際は、色々試行錯誤してみることをおすすめします。
もちろん、当店にお任せいただける場合は遠慮なくご相談ください。
ちなみに掲示板ポスターは公費の対象です。公費についてはこちらの記事にまとめていますので、良かったらご一読ください。
ポスターはデザインのベースと私は考えています。ポスターのイメージ、雰囲気とマッチするように他の広報物を仕上げます。
投票する際にポスターを見て、「あ、この人のリーフレット見たことある」と思い出せるようにデザインイメージを統一するのです。その元になるのがポスターというわけです。
選挙はがき
基本ツール、最後は選挙はがきです。これも掲示板ポスターと同じく、選挙期間中に使用するものになります。そのため、リーフレットと違い、はがきには「〇〇市議会議員候補者」や「清き一票を」などの文言を入れても大丈夫です。また、選挙はがきには、大きさや重さに規格がありますが、一般的なサイズ(148mm × 100mm)で通常のはがきよりも極端に厚い or 薄い紙を使わなければ問題ないです。

選挙期間になると、選挙はがきを有権者へ送ることができます。枚数に限りがあり、市議会議員選挙では政令指定都市で4,000枚、それ以外で2,000枚。市長選挙では政令指定都市で35,000枚、それ以外で8,000枚です。
選挙はがきの制作費・印刷費は自己負担ですが、郵送費は公費が出ます。ただし、定められた方法で指定された郵便局の窓口にて手続きする必要があります。ポストに投函したり、有権者に直接手渡すのはNGです。ご注意ください。
記載する内容としては、プロフィールや、推薦者がいる場合は推薦者の名前を書くことが多いです。
意外と重要な2ツール
基本の3ツールの紹介が終わったところで、ここからは有権者にアピールするにあたって、意外と重要な2つのツールをご紹介します。
どちらも選挙運動期間中に使うことがポイントです。
選挙公報
選挙公報は選挙期間中に各家庭に配布されます。新聞のような用紙で各候補者の主張が一覧で並ぶものになります。よく選挙「広報」と誤字を見かけますが、「公報」が正しいです。
新聞などへの折り込みや、ご家庭の郵便受けに直接ポスティングするなどして配布されます。選挙公報は印刷・配布に関しては公費のため候補者の負担はありません。デザインを私のような業者に依頼する場合、制作費は自費負担になります。
国政選挙、都道府県知事選挙については公職選挙法で定められており、必ず発行されます。他の地方選挙については条例で決まります。よって、選挙公報がない選挙もまれに存在します。残念ながら、私の住む町はないのです。。
選挙の大体1ヶ月前に立候補予定者向けの説明会が行われます。
余談ですが立候補を予定している方はこの説明会、忘れずに出席してくださいね!
その際、ボール紙でできた公報用の台紙が配られます。この台紙に、自分の公報原稿を印刷し、貼り付けて、公示・告示日に提出します。
公報には、候補者の顔写真、氏名、経歴、政策などを記載します。選管の方にも言われると思いますが、新聞の様な感じで印刷が鮮明ではないので、細かいデザインはきれいに出ない可能性があります。グラデーションなどは避けて、はっきりしたデザインの方が無難です。
選挙公報は意外と投票の参考にする人が多いツールです。以下は前回(2019年4月)の統一地方選挙に関する調査報告の引用です。
次に、政党や候補者による情報提供について、選挙期間中に見たり聞いたりしたものと役に立ったものを、選挙報道とほぼ同様に尋ねている。
(中略)、見聞きしたものとして 20%以上の回答があったのは、「候補者のポスタ ー」(51.5%)、「街頭演説」(31.5%)、「連呼」(25.5%)、「選挙公報」(22.4%)であった。
それらが役に立ったかどうかを見ると、「役に立った」という回答が最も多かったのは「選挙公報」 (15.5%)、次いで「候補者のポスター」(12.3%)、「街頭演説」(10.0%)であった。
http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2011/03/1219-houkokusho.pdf
この調査では、選挙期間中のツールの中で、選挙公報が最も役に立ったという報告がなされています。侮るなかれ、選挙公報。覚えておいて損はないかと思います。
政策ビラ(選挙運動用ビラ)
政策ビラは正式には「選挙運動用ビラ」といいます。選挙期間中に配ることのできるビラになります。A4サイズのチラシですね。政策ビラは元々、国政選挙と首長選挙(都道府県知事・市長)でしか配れませんでした。しかし、2019年3月に都道府県議、市議に解禁され、2020年12月より町村長、町村議にも解禁されました。
解禁前は、選挙期間中の広報ツールはポスターと公報、はがきのみでした。有権者に情報を届けるため、解禁されたというわけです。ただ、好き勝手配れるわけではなく、配り方が限られます。選挙事務所にきた人に配る、街頭演説中に配る、他にも新聞折り込みも可能です。
作成できる枚数に限りがあり、はがきの2倍となっています。一般市議で4,000枚ですね。印刷費として公費が出ますが、ポスターに比べて少額の傾向があります。多少補助がある、くらいにお考えいただくと良いと思います。また、候補者ご自身がプリンター等で印刷した場合、公費が出ませんので注意してください。
掲示板ポスターと似ているのですが、政策ビラは頒布責任者と印刷者の記載が必要です。また、証紙というシールを貼らなくてはいけません。証紙は選管からもらえます。政策ビラを作る際は注意してください。
他にこんなものも
推薦御礼ポスター
どこかの組織や団体などに推薦してもらうことがあります。推薦とは要するに「〇〇さん(候補者)は市議にふさわしい! 我々は〇〇さんを応援しています」と推してもらうことです。基本的には、勝手に応援してくれることはないので、候補者から推薦依頼をします。
無事推薦をもらえたら、お返しに渡すのが推薦御礼ポスターです。ポスターがお返しになるかと言えば…別になりませんが笑。「ご推薦ありがとうございます」という文言が入ったポスターになります。
このポスターを組織や団体の事務所など、室内に掲示してもらいます。デザインは、制作する時期にもよりますが基本は掲示板ポスターと合わせます。
また、掲示板ポスターはユポタックという裏面がシールになった用紙を使宇コトが多いですが、推薦御礼ポスターに同じ用紙を使う際は注意が必要です。ユポタックのシールはとても粘着力が強いので、きれいに剥がれないケースがあります。私の場合、推薦御礼ポスターは裏面がシールになっていないユポを使います。
後援会だより
リーフレットでは物足りない。私は書きたいことが、あふれんばかりにありすぎて到底リーフレットには入りきらない、という方がよく使うのが後援会だよりです。
現職の方は市政レポートのような広報物を日頃から出しているケースがあるのですが、新人の場合はありません。そのため、使われるのが後援会だよりです。A4のチラシタイプのものが多いです。ただ、私が関わったある市長選挙では、A4サイズ16ページに、4年間の実績と今後の政策をまとめた冊子タイプの後援会だよりを制作しました。
特に決まりはないので、自由に作れるのが後援会だよりの良いところです。
その他諸々
その他、広報ツールというと語弊があるかもしれませんが、選挙関連で様々なツールがあります。
街頭の立て看板
街宣車(ラッピングやパネル)
選挙事務所用看板
たすき
のぼり
SNSや動画などのデジタル関係
定番もあるので、イメージが湧くものもあるのではないでしょうか。
ここまでご紹介してきたツールと同様に、こういったアイテムはそれぞれの仕様や使える場所・期間などに制限がある場合があります。制作の際は専門業者に頼むか、よく調べることをおすすめします。
まとめ
今回は選挙広報に関するツールを紹介してみました。
結局なにが言いたいかというと、選挙ツールは細々と決まりがあり面倒なので、ちゃんと分かっていて、まるごと任せられる人を探した方がいい、ということです。私でなくても構いません。そういった業者さんを知っておくと便利です。
そんなことを勉強している時間があるなら、候補者は少しでも多くの人に会って話を聞いてください。というのが私の持論です。
私がお世話になったある参議院議員は、有権者の人たちに「3人集めていただければいつでもどこでも伺います」と言っていました。人と会って話を聞き、自らの考えを話す。議員にとってそれ以上に大事なことがあるでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました!