
古書の流通でも本の作り手に還元する仕組みは可能か?ーー本棚記録サービスを作りたい(2)
前回「本棚を写真で記録するサービス」を作りたい、と書いた。人の本棚を「見たい!」と思う理由を探り、「本棚人格」の現れがその理由ではないかと考えた。現状では物理的な本棚にそれが最も現れるので、本棚の写真をベースにした本好き同士のコミュニケーションの場を作りたいのだ、と。
そしてもう一つ理由がある。「二次流通(以降)でも作り手(著者、出版社など)に利益をもたらす仕組み」が必要だと考えるからだ。それがなぜ「本棚を写真で記録する」こととつながるのか。順を追って整理したい。
古書流通で「印税」などが支払われないのは「当たり前」?
出版流通の仕組みの問題点については、指摘され続けて何十年も経っており、出版社、取次(書店-出版社間の流通を担う会社)、書店、印刷会社などなど、第一線で働く方々がさまざまに努力を重ねてきた。それでも厳しい状況が大きく改善されているとは言い難い(電子で大きく変化している漫画などの分野については、非常に重要ながら言及するには能力不足のため措かせていただく)。
エンターテイメント産業全般に言えることだろうが、内容や表現に何らか新しい点がなければ書籍にならないので、投機的な要素が大きく、出してみなければ売れるかどうかわからない。だからこそ刊行点数を増やすことが「当たる」確率をあげる一つの方策になる。関連して「初速」が良い(発売後すぐの売れ行きが好調な)タイトルでなければ大ヒットにつながりにくい状況が生まれる。刊行点数の増加(と書店数の減少)により販売スペースの競合が起きてしまい、店頭の書籍の回転を速めざるをえないからだ(大型店や独立系書店など一部の書店にしか置かれないタイトルも多い)。例えば読むのに時間がかかり、書くのにも時間がかかっている重厚な内容の本が、売れにくいだけでなく出版もしにくい状況になっている(そういう本は後世に残したほうがいい場合も多いだろう)。著者の印税も、書店の利益も薄いことはよく指摘されているが、版元がとくに大きく儲けられているというわけでもない。
こうした状況の元となっている、出版業界に独特な「再販制(再販売価格維持制度)」と「委託販売制度」について、2013年に刊行された内沼晋太郎さんの『本の逆襲』に端的にまとめられているので、ここで参照したい。

仕入れた本がたとえ思ったより売れなかったとしても、書店は割引セールをせずに、定価で販売することになっています(再販制度)。その代わり、ほとんどが委託商品で、出版社に返品することができます(委託制度)。そして新しい本は、注文しなくても自動的に毎日入荷してきます(パターン配本)。店として確実に売りたい本は別途事前に注文しますが、いらない本も同時に入ってくるので、それらは一度も並べることなく、売れない本と一緒に返品します。毎日取次のトラックがやって来て、たくさんの本を置いていくと同時に、たくさんの返品を回収していきます。そして月に一回まとめて、入荷と返品の差額が、取次から書店に請求されます。
たくさんの例外はありますが、大まかにはこのような大規模な仕組みで、流通が成り立っています。そのおかげで、ぼくたちは日本中どこの書店でも同じ値段で、ほとんど発売日に、遅くとも数日以内に本を買うことができ、店頭になくても注文さえすれば、数日〜十数日でほとんどの本を取り寄せることができます。
他の業界でお仕事をされている方は分かると思いますが、これは出版業界独自の、かなり特殊な仕組みです。(中略)
このようなことができるのは独占禁止法の適用除外となっているからですが、その理由は本という商品、そこに書かれた知恵や情報というものが、部数が少ないからといって必ずしも重要でないわけではないからです。もし本が市場原理にさらされ、売上重視の価格競争になってしまうと、たくさんの人が読む本ばかりが作られ、ごく少数の専門家しか必要としないような研究書は流通しなくなってしまう。そうした事態を避け、多様性を担保しながら、できるだけ日本全国津々浦々どこの書店にも遍く、なるべく安く、早く、知恵や情報を届けたい。そういった理想のもとに、このような大規模かつ特殊な流通の仕組みが作られてきたのです。
知識や情報の入手がなるべく偏らないようにしたり、一部の人にしか読まれないタイトルも同じように重視したりといった、公共的な役割に配慮して作られてきたのがこれらの仕組みなのだ。書影にもあるように「本の未来」についてさまざまな角度から現状を分析し洞察を深めたこの本は、10年を経た現在でも多くの読者に読まれ続けている(BRUTUS No.999 2024 1/1・15合併号「理想の本棚」特集号でも紹介されている)。では、同書の中で古書の流通についてはどのように言及されているか見てみよう。
古書店は昔からありますが、ブックオフをはじめとする新古書店と呼ばれる業態が大きな販売力を持つようになったこと、インターネットでの古本の売買、とくにAmazonマーケットプレイスが日本に上陸したことは、<出版社ー取次ー書店>のビジネスにも、旧来の古書店にも、直接的な打撃を与えています。ブックオフが目の前にできたことで新刊書店がつぶれたり、Amazonマーケットプレイスで安値で売られることで、出版からそれほど経っていない本の売れゆきが落ちたりといったことはたくさん起こっていますし、古書店もそれらの打撃を受けています。
同時に、古書店ではこれまで長年の修業による蓄積が必要だった値付けの作業が、素人でもインターネット上の価格を基準にできるようになったことや、ブックオフなどで仕入れができてしまうようになったことが参入障壁を下げ、価格競争もシビアになっています。新品の本は定価販売が義務付けられていますが、古本であれば値付けは自由です(後略)
ここで示されているように、ブックオフとAmazonの影響は大きい。両者に共通するのは、規模の大きさによる変化だ。古書の売買は昔からあったが、ひとつの会社がこれほど大きく、効率的に古書の流通に携わることはなかった。「スケールメリット」の出現によって史上初めて問題となったのが、作り手に利益が還元されない、という点なのだ。
ここでまず、現状最大の古書販売プラットフォームとしてのAmazonに目を向けたい。というのは、ブックオフやもったいない本舗なども含め、多くの古書店はオンライン古書販売の入り口として、Amazonのマーケットプレイスを利用しているからだ。
ひとつのページ上で新刊と古書が併売されているAmazon
Amazonで書籍を購入したことがある人なら一度は見たことがあると思うが、Amazonの書籍ページには、新刊の購入ボタンと古書を扱うマーケットプレイスの購入リンクが下記のスクリーンショットのように並んでいる(一応新刊が上だが、「中古品」を選択すると「カートに入れる」ボタンが新刊同様に出てくる)。


新刊は送料が無料だが、古書の場合もアマゾンの倉庫を利用していれば無料配送が可能だ(この仕組みはFBA、フルフィルメントBy Amazonと言う)。いずれの場合も(FBAを使っているか否かにかかわらず)、約250円〜350円ほどが送料+手数料として徴収されている。プラットフォーム利用料のような位置付けで、アマゾンへ一定の金額が支払われているのだ。
そもそもAmazonマーケットプレイス事業はなぜ生まれたのか。同社を研究分析した書籍によると、「地球上で最も豊富な品揃え」を達成するため、とある。

あらゆる商品が扱える「マーケットプレイス」という仕組み
こういった品揃えは、「マーケットプレイス」のおかげである。マーケットプレイスとは、アマゾン以外の外部事業者が出品できるサービスのことだ。簡単に言うと楽天市場のようなものだが、違うのは、画面上ではアマゾン直販の商品や他の出品者も全部同じフォーマットで買えるということだろう。消費者にとっては、売っているのがアマゾンなのか他の事業者なのかが特に気にせずに買える。このマーケットプレイスで扱う商品は、アマゾン直販の品数の30倍以上で、約3億5000品目にも上る。
この書籍の刊行はコロナ禍前の2018年。数字の変化は当然あるはずだが、仕組み自体の存在意義は変わっていないだろう(むしろ増しているかもしれない)。2022年刊行(原書は2021年)の次のタイトルでは、マーケットプレイスの立ち上げ時のエピソードが次のように語られている。

ブラッド・ストーン/著 井口 耕二/訳
ベゾスはFBA[引用者注:フルフィルメントBy Amazon]を軌道に乗せるのと並行して、これと連動する事業、アマゾンマーケットプレイスの育成に力を注いだ。サードパーティーの売り手がアマゾンウェブサイトで新品や中古品を売れる仕組みである。導入から数年を経た2007年、マーケットプレイスに並ぶのはほこりっぽい古本ばかりで、取扱もサイト全体の13%を占めるにすぎなかった。歩みが遅すぎるといらだち、もっと意欲的なものを出せとOPIで企画書を破り捨てたこともある。また、マーケットプレイス部門のトップに据える人材を探す際には、どうすれば売り手を100万軒、マーケットプレイスに集められると思うかと候補者に尋ねたらしい。(中略)
ベゾスが面接で尋ねていた問いに対する答えはひとつしかない。ファリシー[引用者注:担当者]はそう考えていた。1カ所ずつ売り手に誘いをかけて100万軒を集めるのは不可能だ。集めるのではなく、逆に売り手がアマゾンに集まってくる仕組み、それもセルフサービスの仕組みをつくる以外に方法はない。
Amazonにとっては、出品者のセルフサービスによって取扱商品数を増やすことができる、メリットの大きい仕組みということだ。Amazon側だけでなく、もちろん出品者側にも利点が多いからこそ利用されている。最大のメリットは集客力にあるが、「セラーセントラル」などの出品者向けの仕組みが充実している点も重要だ。規模の経済はここでも働いている。便利だからお客さんが集まり、利益が上がるので、管理画面という相対的にコストをかける意味が少ない部分にもしっかり開発費をかけることができ、使いやすい機能を実装でき、出品者が集まるのだ(購入者は出品者の何倍も多いので、購入者側の機能のほうが開発の優先順位は高くなる)。豊富な品揃えは書籍に限ったことではないが、書籍を探す時にまずAmazonで検索する、という人も一定数いるだろう(私自身もそうだ)。「なんでも売っている」と思われていることで、データベースとしても利用されているのだ(実際には扱っていない書籍も一定数ある)。そのまま購入に至る可能性が高まるという意味でも、どこよりも豊富な品揃えを実現するマーケットプレイスの仕組みはメリットが大きい。
新刊の発売後すぐに古書が流通すること、それ自体は避けられないし、一冊の本が何人もの人の手に渡っていくこと自体は良いことだ。問題は、作り手に利益が還元されないことだ。新刊と古書の間に価格差があり、急ぎの注文でなければ、古書を選ぶ場合も多くなるだろう。著者・出版社の利益がないことを考慮してあえて新刊を選択する人は多数派ではないはずだ。
マーケットプレイスの手数料の一部を原資として、少しでも著者や版元へ還元する仕組みは、アマゾンがやろうと思えばできるはずだが、そのような動きはいまのところないようだ。「著者セントラル(著者向けの管理画面)」などで著者と、また「e託セントラル(直接取引の場合の管理画面)」などで出版社と、それぞれ直接やりとりする仕組みはすでにあるので、やろうとすれば可能なはずだ。このような古書の流通で得られる利益の一部を、広い意味での出版産業をもっと良くするために使えないだろうか。マーケットプレイス事業自体も永続的とは限らない。今のところは考えにくいかもしれないが、Amazonの方針転換でなくなるかもしれないものだ。
古書で作り手に利益が還元されるとどうなるか?
例として、内沼さんの書籍で言及されていた「研究書」のような場合を想定して、5000円の本を2000部刷った場合を仮定してみる。最初の1年で書店で1000部売れ、図書館に500部収蔵され、じわじわ読まれていく。読むのに時間のかかる本は、一定の間家の本棚に積んでおかれることも多いだろう。一般に流通する1000部のうちの1%、10部くらいはその年のうちに古書市場に流れるとする。Amazonならマーケットプレイスの価格も同じ画面上に表示される。たとえば定価の8割、4000円だとしても買う側にとっては1000円の節約。本は劣化しにくいから、刊行後1年以内くらいならほぼ新品同様の可能性が高い(状態によって古書価格はもちろん変動する)。初めに売れた1000部の中からどんどん古書として市場に戻ってくるので、新刊として売れるのは1000部に止まり、残りの500部は倉庫で出荷を待ち続ける。この本が世の中に必要な部数は1500部ということになるだろう。堅牢に作られた書籍であれば、5回や10回、それ以上の人の手に渡っても読むのに支障は出ないから(図書館はそれを前提にした仕組みだ)、流通しているのは1500部だとしても読者は5000人にも1万人にもなり得る。
現状の仕組みでは、一次流通の場合にしか出版社に利益はない。しかし本という商品の性質的に、二次以降の流通でも利益を還元するのが筋ではないだろうか。というのも、古書で4000円で購入した書籍は、CtoCの仕組みがあれば、ふたたび4000円で販売できる可能性があるからだ。そこまでではなくても、3000円で販売できた場合でも、実質1000円でその本を購入して所有できていたことになる。骨董品のように、再び「ほぼ同じかそれ以上の値段で売れる」のであれば、それを前提にした購入行動がなされるようになるのではないだろうか(衣料品については実際にそのような変化が起きている。日経新聞2024年2月13日「Z世代のコスパ変化 中古活況、安さより将来の買取価格」など)。
この点は実際、メルカリを始めてみて実感したことだ。内容の古びない古典や、堅牢なつくりの書籍は、古書で購入したものであっても同じかそれ以上の価格で販売できている。
作り手に還元したい人は潜在的に大勢いるのではないか
当然だが、新刊を購入する人がいなければ古書の流通もない。私はこれからも新しい視点で書かれた面白い本が読みたいから、なるべく著者さんや訳者さんが現役でいらっしゃるなら近所の新刊書店で購入している(刷り部数印税が主流のはずなので著者には印刷時に支払い済みの場合が多いだろうけど、重版してほしいので。たくさん出回ることがわかっている、ものすごく売れている人の場合は、申し訳ないけれどまずブックオフで探すこともある)。安いからつねに古書で買うという人の中にも、著者や版元に還元したいと考える人は少なからずいるはずだ。著者だけでなく出版社にも還元する必要があるのは、編集という仕事の重要性はもちろん、初めにリスクをとって制作・流通などを担っているからだ。紙代も印刷費も運送費も増えているいま、二次流通以降でも出版社に還元する仕組みがあれば、少しでもコスト回収の助けになるのではないか。そもそもその仕組み自体がいまだに存在しないこと、それ自体が不思議なことではないだろうか。
ブックオフの創業社長は、印税の支払いを考えていた
ブックオフの創業者である坂本孝氏のインタビューを読んで驚いたのが、この点について真剣に検討されていたことだ。古書の市場は近代以前からあったが、一度購入された本は持ち主のものであり、希少性が高まって価格が高騰しても、その利に与っていたのは所有者である古書の売り手だけなのが普通だった。ブックオフによって組織的に新古書販売の流通網が生み出されたことで、影響力の大きさからこの点が問題視されるようになったのだ。さっそくそのインタビューを見てみよう。

著者保護、著作権保護は真剣に考えるべき
村野 書籍には著者の著作権があります。その書籍を中古でビジネス展開すると、いまの仕組みでは著者に一切お金が落ちない。これがブックオフ批判のもうひとつの柱となっている意見ですね。著者や著作権の保護についてはどう考えていますか。
坂本 著作権を守ることは、非常に大切なことです。書籍の創造者たる著者が枯れたら、元も子もありません。著者にあたる人々を育て、著者の権利を守ることは常に真剣に考えなければならないでしょう。
ではどうするか、というとブックオフ単体で行うには話が大きすぎる。それにブックオフでは商品の単品管理を行なっていないですから、現実問題として著者の方に直接印税を支払うようなことは難しい。
「源が涸れてしまったら元も子もない」という考えはあったものの、「直接印税を支払うようなことは難しい」と言われているのは、当時は商品の単品管理がされていなかったこととあわせて、まだ現在ほどインターネットが普及しておらず、システム開発のコストも高かったこともあるのではないだろうか。代替手段として、以下のような案を挙げている。ニュアンスを感じていただきたいので、やや長めに引用する。
基金の形は考えられないだろうか
村野 坂本さんが著作権について前向きに考えているのはわかりました。しかし、やはり具体策が必要です。著者を守り、出版文化を育てていくための仕掛け作りとしては、どのような形を考えているのですか。
坂本 ひとつ参考になるものにカラオケにおける著作料のとり方があります。また聞きですので正確な話ではありませんが、たしかカラオケの場合、全国の膨大なお店で歌われた曲をすべてきっちりデータ管理しているわけではないそうです。ある程度のサンプルをとってどの曲がどの程度歌われたかを類推する方法がとられており、その類推データをベースに著作者に著作料が支払われていると聞きました。似たものにテレビの視聴率調査があります。テレビの視聴率も500世帯をベースにマーケットでの視聴状態を類推してます。
こうした方法を使えば、ブックオフでもある程度著作料の類推はできる。各店舗で何が売れているか、サンプル店やサンプル期間を設け、個々の本の売れ行きデータを集め、全体を類推する仕組みを作れば、金額を推計できる。この計算方法を明確にし、そのうえで著作者の方たちに認めていただけるのであれば、著作料なり印税なりを支払うことにやぶさかではありません。ひとつ知恵をしぼって、業界みんなが円満にいくようにしたいですね。(中略)
具体的にいうと、私はファンドを集めようと提案しています。それについては基本的には合意したんですよ。それを元に何ができるか検討してみました。著作料を印税として払うことは不公平になるからできない。だったら、次の新しい漫画家、作家のためにファンドを集める。奨学金とかそういうものにしようという方向にまとまりつつあります。実はね、それが起爆剤になって、「古本屋がやるのなら、新刊書店もファンドを作ろう」ということになることをいま祈っているんですよ。
できることはいろいろあります。うちが先にやろうと思っていることは、目が見えない方のための点字の翻訳です。(中略)点字図書館というのがあるのですが、点字で一冊を仕上げるのは大変な時間がかかるし、コストも高くつくから、需要に供給が追いついていないのです。また点字は日本中で共通ではなく、何種類かあるので大変です。だから、本を点字に翻訳をするためのファンドを出したいと思っています。
別の形ではあるものの、なんらかの形で出版文化への還元を真摯に考えていることがよくわかる。しかし30年ほど経過した現在であれば、もっと直接的に、作り手に還元する古書流通の仕組みも可能ではないだろうか。もっと言えば、メルカリなどの企業努力によりCtoC市場が活発化している現在、仮にバーコードがついている本だけだったとしても、どの出版社のどのタイトルが何冊売れたのか、といった数字をとること自体は、それほど難しい技術がなくても可能なのではないか。
当時のブックオフで推計するしかないと考えられていた理由は、以下のようなシンプルなビジネスモデルで商品を扱っていたからだ。坂本氏が社長退任後にあらたに起こした飲食店事業について語った別の本の中で、ブックオフ時代を振り返って次のように言っている。
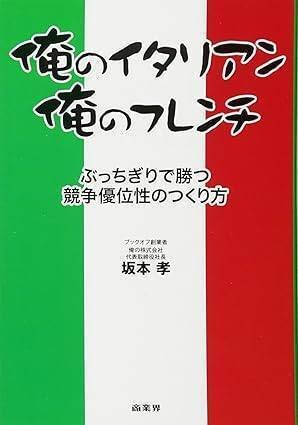
ブックオフのビジネスモデルは、たった5分で説明できるものです。定価1000円のきれいな本を100円で仕入れて500円で売る。3ヶ月経過して売れないものは100円に値段を落としていく。これは、価格と価値がアンバランスになって市場が「500円は高いよ」と言っているということだからです。
こちらの本の中でも、作り手への還元について次のようなエピソードに言及されているのであわせて見ておきたい。これによると、はじめに声をあげたのは漫画の著作権団体だった。現在、電子版という二次以降の流通ができない形でコミック市場が活況を呈していることを考えると、訴えの切実さが感じられる。
コミックの著作権団体から「私たちの本を売っているのだから著作権料を支払え」と言われました。古本流通の中でそのような法律はありませんでしたが、それに対して、私は日頃繁盛させていただいているご恩返しと社会貢献という意味を含めて1億円を差し上げるという申し出をしました。
ここで言われているように、古本の流通において著作権料の支払いは義務付けられているわけではない。しかし、本が好きな人のためにこそ、作り手に還元したいという気持ちの受け皿が、仕組みとしてあってもよいのではないか。誰もが「見たい」と思う個人の本棚を入り口として、本好き同士がコミュニケーションを楽しみながら売買できるCtoCプラットフォームがあれば、古書の流通マージンをそれに充てることができるのではないか。そして古書をためらいなく売買できるようになることは、高額な書籍でも気軽に購入できるような購買行動につながり、新刊の市場をも活発にするのではないか。
ここまででずいぶんと長くなってしまったので、具体的にどのように計上・還元できるか、といった点については回を改めたい。次回は「本棚=古書店」という考え方の提案を起点にしていく予定だ。メルカリを利用した本の販売の楽しさについてもレポートしていく。
*ご意見・ご感想はもちろん、異論、反論大歓迎です。間違いがあればご指摘いただけると大変ありがたいです。
いいなと思ったら応援しよう!

