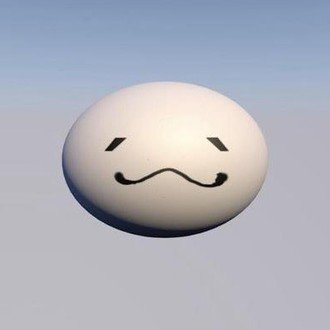二次創作とAI画像生成は同じなのか、という話について
AIについて前回の記事から時間が空いたので、現時点での考えを書き留めておきたいと思います。
その後、AI画像生成はクオリティが上がりましたが、欧米アーティストを中心に大きな反対運動が力を増しました。基本的には健全なことで、そうした肯定否定の議論の中から落とし所を探っていくのが民主主義というものだと思います。
さて「二次創作をしている人間にAI画像生成を批判する資格はない、二つは同じものだ」という論があります。結論から言うとこれは二次創作の社会状況を誤解した論です。
そもそも二次創作は一次創作者の黙認のもとに許容されている特殊な文化である、というのは同人誌文化の基本的なコンセンサスであるはずです。実際、ウマ娘や映像研など「性的な二次創作は控えて」というアナウンスがされた作品に対してはそれに応じる形がとられていますし、「私の作品の二次創作は完全にやめてほしい」と作者からメッセージが出れば応じざるを得ない、あるいは「訴えられないように隠れてこそこそやる」くらいしかないでしょう。今回、画像生成AIに対して反対の記者会見をしたクリエイターが芳文社の二次創作規定に触れていたという話が言われていますが、そのクリエイターは規定を知って謝罪し、以降は作品を削除しているわけです。
画像生成物AIと二次創作が同じかどうか少し考えてみれば分かることですが、「二次創作というテクノロジーが出来たのだから、どんどん取り入れて少年サンデーで『鬼滅の刃』の続編を勝手に掲載しましょう。技術の進歩は止められません」「うちの連載でも勝手にコナンやルフィを出しましょう。この2人が共演するのはオリジナルの発想なのだからこれは我々の創作物です」みたいな理屈が成立するでしょうか?政治家が「二次創作で日本は勝てます。ディズニーに無断でアナ雪やトイストーリーの続編を勝手に作って世界に輸出しましょう」と宣言してアメリカが黙っているでしょうか?一次創作者に二次創作を送りつけて「お前より二次創作の方が上手い」と煽ったり、「もう過去の名作の二次創作をしていればいいのでコストの高い一次創作は不要です」と宣言する人に支持は集まるでしょうか?最初に言ったように二次創作は一次創作者によって「黙認」されているだけであって、「画像生成AIと二次創作は同じ論」に立てば「画像生成AIはメジャーな商業には使えないし、学習元が拒否すれば作品を取り下げなくてはならない」ということになってしまいます。
もうひとつの論、「人間だって多くの作品を見て影響を受けているのだから、機械学習も同じだ」という論があります。これについても、人間が身体的に行うことについては認められても、機械を用いてすることは禁じられていることなんて山ほどあるわけですね。
例えば法廷画家。裁判所内での写真撮影は認められないが、人間が手で描くスケッチは認められてるから絵が使われる。あるいは感想。映画や演劇を見てセリフを引用したり、感想のイラストをSNSに投稿することはよくありますが、映画館や劇場でビデオカメラやスマホで録音録画した映像音声をSNS投稿したら、そりゃ盗撮でしょう。人間の身体能力の範囲では許容されるが、マシンパワーを使えば違法になることなんていくらでもあります。
例えば世の中には物真似芸人という人たちがいて、プロアマチュア問わず人気歌手やタレントの声を真似していますが、だからと言って最近出た音声合成AIを使って、歌手や声優の丸ごとコピーをした声で芸能活動することを社会が許容するでしょうか?それは人間が声真似をするのと同じだから有名人の無断音声クローンも全面的に認めろ、と彼らは主張するでしょうか?
AIを全面的に禁止するべきだとは思いません。しかしその利用のラインをどこに引くのかはこれから社会が決める、あるいは常に考え続けることであって、「二次創作と同じだ」とか「人間が画風に影響を受けるのと同じだ」というような論は単に猫だましのように錯覚を起こさせて議論を封じる詭弁でしかないと思います。
AIが特殊なのはマシンパワーで量産できることで、たとえば著作権ひとつとっても、音楽の合成を大量に無限にさせて著作権取得を認めたら、今後の音楽著作権のほとんどを巨大企業のAIサーバーで作られた音楽が取得してしまうことがありうる。
新しいテクノロジーは新しい権利を生みます。写真集を出版したタレントには多くの印税が入りますが、これは著作権や肖像権という権利がテクノロジーの後に誕生したからです。「写真は撮影した写真家の作品であって、被写体に権利などない」という立法がゴリ押しに通されていれば、写真集の印税はタレントに入りません。機械学習において誰がどのような権利を所有するか、それをどう分配し、拒否する自由をどう担保するのかはこれから社会が話し合って決めていくことで、すでに決定されていることではないのです。
また、法の解釈そのものも時代や技術とともに揺れ動きます。21世紀初頭のインターネットにはアイコラが溢れていました。「政治家を風刺するパロディ権があるのだから、アイドルコラージュもその範疇として許容される」という解釈があり、マイナー雑誌などにもネットからさらに転載する形で(目線を入れて)掲載されていました。Photoshopは今も規制されていませんが、1人の芸能人の訴訟とともに、ポルノコラージュが堂々と投稿されることはなくなりました。(今でもアングラな形ではあるかもしれません)新技術と社会は常にその時の状況によってラインが引かれますし、ラインが引かれたあとも揺れ動きます。
二次創作がそうであるように、著作権が曖昧な新分野から多くの文化が育ってきたことも事実です。おそらくAIにおいても、新しい文化が育つ可能性があるでしょうし、それが全面的に禁止されるべきだとは思いません。
今は画像生成AIとイラストの画風が焦点になっていますが、遠からず芸能人や、あるいはSNSに自撮りをあげているだけの一般人の画像が機械学習に使われたモデルの是非が社会的議論になるでしょう。(すでに海外でも日本でも有名女優の学習モデルは拡散されています)また、音声合成によるボイスクローンを使った詐欺事件はすでに海外で多発しています。リアルさを増すバーチャルヒューマンと、現実の人間との類似はどこまで認められるのか。新しい技術に対して議論を重ねなくてはなりませんし、その議論は専門家以外にも開かれてあるべきです。その意味で、赤松健先生の「日本は勝てる」というような言説は極めて粗雑だと思います。
なんというか、僕が今回のAI問題について強い違和感を感じるのは、海外では「今後この技術をどうするか話し合おう」というスタンスなのに、日本でAIについて語る人たち(とりわけ業界人たち)が、あたかもAIの取り扱いがすでに決定されており、何を言おうと覆せないかのような抑圧的な態度を取りたがることなんですね。それが日本の大衆を政治的にコントロールするのに最も効果的な態度だからそうしてるとしか思えないのですが、それは極めて異常な態度であることは言っておきたい。
なんというか、もうこれはAIだけの問題ではなく、「自分たちの社会をどうするか自分たちで考えよう」ではなく「上がそう決めたんだから従え」みたいな態度が日本のSNS全体に染みついてるんですよね。それが一番深刻な問題なのではないかと思う。
AI自体はこれから多くの場所で使われていくと思います。社会的に合意が得られるラインが引かれれば使われていくでしょうし、僕も使います。だからこそ、産業革命が引き起こした公害や貧困の問題に社会が対処したように、社会全体でそれをコントロールすることを考えていかなくてはならないわけです。重要なのことは、二次創作と一次創作の間にラインが引かれているように、AIという新しい技術と古い技術との間のどこに線を引くかということだと思います。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?