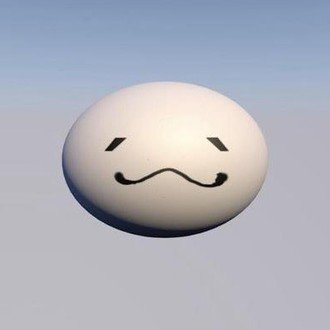『見たくないものを見なくてすむ権利』は何が危険なのか、左派がもう一度『憲法第21条 表現の自由』に立ち返るべき理由
『月曜日のたわわ』が日経新聞に掲載されたことに関する論争について、以下のような記事を週刊女性Primeに書かせていただきました。
週刊女性prime様から依頼があり、『月曜日のたわわ』日経新聞広告論争について、思うところを書かせて頂きました。フィクションの欲望に対して必要なのは広い議論と批評であって、事前の条件に基づいた自主規制ではないように思えます。双方の立場に読んで頂けたら幸いです。https://t.co/2sUzosXwws
— CDB@初書籍発売中! (@C4Dbeginner) April 8, 2022
記事の中にも書いたように、SNSを中心に投稿されている『月曜日のたわわ』の内容に対する批判、批評は否定されるべきではない、貴重なものです。それは「見る側」から書かれた物語に対する「見られる側」からの異論であり、それが必ずしも女性の総意ではないとしても、さまざまな意見が作品について述べられることは社会を成熟させます。
しかし、記事にも書いたように、「だから日経新聞に広告を載せるな」という主張はまったく別の次元の問題です。
批判の中の最も目立ったものに、ハフィントンポストの治部れんげ氏のコメントがありました。
日経新聞が「月曜日のたわわ」の全面広告を掲載、批判の声が相次いでいます。
— ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア (@HuffPostJapan) April 8, 2022
治部れんげ准教授(@rengejibu)は3つの問題点を指摘。
「これまで大手メディアとしてジェンダーのステレオタイプを克服するために取り組んできたことは、全て偽善だったのでしょうか」 https://t.co/BRdNmjsYsz
この記事の中で語られた広告への批判に対して多くの反論がSNSで寄せられ、それに再反論する形で治部れんげ氏は以下のようにツイートしています。
①あるコンテンツを合法的な範囲で制作・販売・消費するのは自由(議論の余地なし)
— 治部れんげ/ Renge Jibu (@rengejibu) April 9, 2022
②そのコンテンツを特定組織が「広告に採用」する意思決定は①とは別であり、
③主体となる組織が公的機関であったり法律以上に厳しい規則の順守を公言している場合は批判の対象になりうる
簡単な話です。
この②に、非常に重要な、今回の問題の本質があると筆者は考えています。
つまり、
②そのコンテンツを特定組織が「広告に採用」する意思決定
という表現を治部れんげ氏は使い、その基準が問題だと言っているわけですが、
「広告に採用する」とは通常、日経新聞が『月曜日のたわわ』とコラボレーションし、日経新聞イメージキャラクターとしてあの女子高生を打ち出すような状況を意味するのであって、ただ単に講談社が金を払って日経新聞に『月曜日のたわわ』の広告が掲載することを「広告に採用する」とはフツー表現しないわけです。その2つの基準はまったく違います。
失礼しました。つい力が入って文字を大きくしてしまいました。
しかし、これは根本的な問題なのです。
過去の炎上を思い出してみてください。キズナアイ。宇崎ちゃん。のうりん。温泉むすめ。すべて「自治体や企業、公的機関とのコラボ」という形でなされた広告です。そのコラボが問題だった、いや問題なかったという議論はいったんここでは傍に置きましょう。
それらは企業や自治体とのコラボだったからこそ問題視されたわけです。
今回は違います。単に出版社が金を払って作品の広告を出しただけであり、しかもその広告にはきわどい表現はおさえられ、青のモノトーンできわめて抑制的にデザインされているわけです。
「この広告を日経新聞が受諾するのはまかりならん、なぜなら広告の絵や文言には問題がないが、作品を読むとジェンダーバイアスを感じるからである」という理屈が通れば、日本のあらゆるコンテンツと広告産業の関係は根底からひっくり返ってしまうのです。
失礼しました。また文字を大きくしてしまいました。
実は、過去の炎上に対して批判に参加していた多くの学者、弁護士、運動家のかなりの部分が、今回の日経新聞たわわ広告について「静観」に回っています。それはぶっちゃけ「今回の件、かなり無理筋である」ということが専門家にはわかっているからです。
端的に言いましょう。3月25日の毎日新聞には、幸福の科学総裁、大川隆法氏の新刊『ゼレンスキー大統領の苦悩と中国の野望』の広告が掲載されています。『守護霊インタビュー』という人気シリーズで、宗教も文化も違う外国の首脳を対象にその内心を守護霊の伝言として著述する形式です。

また、よく知られていることですが、毎日新聞のようなリベラル誌を含む多くの全国紙には『WIll』『Hanada』といった保守系論壇誌の激烈な文言の広告が多く並びます。
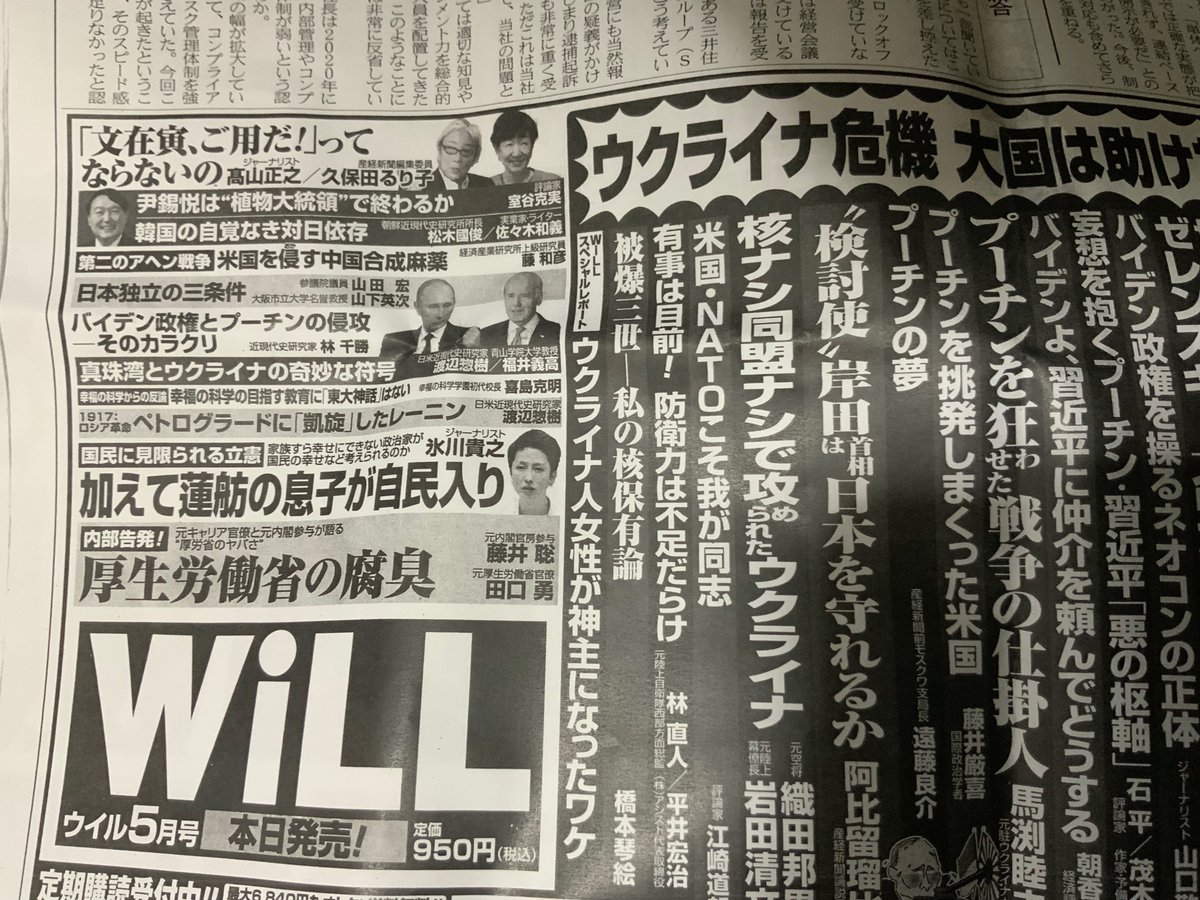

また、朝日新聞にはかなり一般的ではない医学の広告が掲載され、テレビメディアや街角の看板には、APAホテルやDHC、そして高須クリニックの広告が溢れています。APA、DHC、高須クリニックの広告はその広告単体では極めて普通の営業広告です。しかし、広告ではなく作品の内容にまで踏み込むのと同じに、その経営者の社会スタンスまでさかのぼって「このような思想の企業の広告を…」と糾弾する手法が成立するなら、日本のマスメディアの広告ビジネスは根底から大きな影響を受けることになります。
実は今回、それで困るのは講談社や『月曜日のたわわ』ではなく、日経新聞をはじめとする各全国紙やテレビメディアなわけです。
全国紙とテレビは今、明白に広告の出稿が減り、経営が傾きつつあります。
だからこそ、毎日新聞が思想的に正反対の右派論壇誌の広告に、朝日新聞がイレギュラーな医学本の広告に、テレビが高須クリニックの広告にすがって生き延びる状況にあるわけです。
おそらく講談社、ヤングマガジン、『月曜日のたわわ』は、日経新聞に広告が出せないからと言ってそれほど困らない。しかし、「金をもらって掲載する広告に、その広告作品の思想や内容まで吟味せよ」と外部から言われるのは、相当にメディアにとってキツいはずです。
抗議をしている人たちは、いまだに日経新聞が高級レストランのような存在であり、広告主に対して「失礼ですが、このような作品は当社の品位に関わりますのでお断りします」と慇懃に断ることを期待しているのかもしれません。しかし日経新聞の紙面で広告を読めばわかりますが、『月曜日のたわわ』どころではない右派系論壇広告にすがって生き延びている状態であり、講談社のマンガ、それも日経用にきちんと配慮した図柄の広告の『月曜日のたわわ』全面広告案件は広告主としてまったく筋の良い部類に入ると思えます。
しかしながら、「困るのは日経新聞の方だろ、止められるものなら止めてみろ」で済ませるわけにはいきません。ハフィントンポストの記事には見逃せない記述がありました。
“1つ目は、あらゆる属性の人が読む最大手の経済新聞に掲載されたことで、「見たくない人」にも情報が届いたことだ。
「読みたい人がヤングマガジンを手に取って読むことは、今回の問題ではありません。それよりも、女性や性的な描写のある漫画を好まない男性が『見たくない表現に触れない権利』をメディアが守れなかったことが問題です」”
この、
女性や性的な描写のある漫画を好まない男性が『見たくない表現に触れない権利』
という部分がSNSを中心に激しい議論になりました。もちろん、世の中にはヌード画像をそのまま掲載しないように、というような広告規制は存在します。しかし繰り返したように、『月曜日のたわわ』の広告はそれ単体には肌の露出もなく、そもそも作品内容としても裸もなく、年齢制限のないコミックです。
今回の『たわわ』について、「未成年を性的に見ているから…」という声もあります。しかし、つい最近、有村架純主演でテレビドラマ化された『中学聖日記』は、中学生男子と女性教師が恋に落ちる内容のフィクションです。『美少女戦士セーラームーン』の主人公月野うさぎは中学生で大学生の彼氏と交際しますし、新世紀エヴァンゲリオンシリーズには90年代から今にいたるまで、14歳の少年少女の裸身と性が描かれ続けます。
「女性や性的な描写のある漫画を好まない男性が『見たくない表現に触れない権利』をメディアが守れなかったことが問題」というロジックが成立するなら、膨大な数のフィクション作品が該当します。日経新聞に広告が出せないなら、テレビCMやWEB CMだって「あらゆる属性の人が目にする」ことになります。しかもその広告の表彰ではなく、内容にまで遡るわけです。
また、ヤクザ漫画から『東京リベンジャーズ』にいたるまで、アウトローを主人公にしたヒロイックなフィクションは古今東西かぞえきれないわけですが、「暴力団排除のコンプライアンスに反している」「青少年の非行を推進する」という理屈でこれを締め上げることが可能になってしまうわけです。
「いやいや、単純にそうした作品すべてを規制するのではなく、内容を吟味して規制すればいいのだ」という声もあるでしょう。しかしいったい、その「内容を吟味する審議委員」の椅子には誰が座るのでしょうか?
これは「維新八策」と呼ばれる、日本維新の会の公約です。この公約を掲げて、維新の会は先の選挙で躍進しました。引用しましょう。
https://o-ishin.jp/news/2021/images/3858edd04d0a9813e048310faac8023c0a057034.pdf
(4)ヘイトスピーチ・誹謗中傷対策
239. 表現の自由に十分留意しつつ、民族・国籍を理由としたいわゆる「ヘイトスピーチ(日本・日本人が対 象のものを含む)」を許さず、不当な差別のない社会の実現のため、実効的な拡散防止措置を講じます。
240. SNS などにおける誹謗中傷問題につき、行政による過剰な規制や表現の自由侵害には十分に配慮しつつ、 発信者情報開示請求を簡素化するなど司法制度を迅速に活用できる仕組みを整備し、被害者保護と誹謗 中傷表現の抑止を図ります。
ここ数年、リベラル市民運動が提唱してきた「ヘイトスピーチ禁止」の概念に対して、『「ヘイトスピーチ(日本・日本人が対 象のものを含む)」を許さず』という驚くべき解釈がなされています。日本人どころか、日本という国家に対してまで「ヘイトスピーチ、許さない」という規制が宣言されているのです。
また先日、フジテレビのニュース番組において、津田塾大学の萱野稔人教授が、「菅直人氏が橋下徹氏の演説手法についてヒトラーを思わせるとツイートしたのは、外国ならヘイトスピーチに当たる。外国では、移民排斥の極右政治家が台頭しても、ヒトラーに例えるのはタブーである」と述べ、女性キャスターが「なるほど、ヘイトスピーチは許されないのですね(大意)」という形で締める一幕がありました。
むろん、荒唐無稽な話であり、膨大な反証が寄せられました。というか、今や誰もがプーチンをヒトラーに例えています。しかしいまだ、フジテレビも津田塾大学の萱野稔人教授も、なんの訂正もなく、膨大な視聴者に「菅直人の発言は外国ならヘイトスピーチである」という見解はそのままになっています。
「それは本来のヘイトスピーチ定義とちがう」と学者や専門家が意見を述べることは可能でしょう。(驚くべきことに、同じアカデミズムの中から萱野教授の発言に意義を申し立て、直接対決する発言はあまりに少ないと言わざるをえません。こんな重大なヘイトスピーチの定義の問題に、なぜ学者たちの声が小さいのでしょうか)しかしながら、維新がマジョリティの不満を吸い上げ、自民との連立政権でも組んだとすれば、おそらくこの荒唐無稽な定義は現実味を帯びてしまうはずです。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?