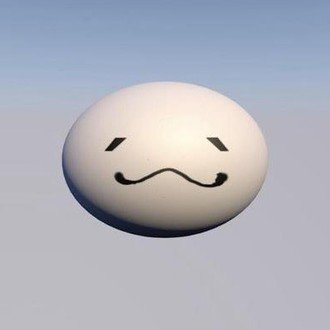映画『大怪獣のあとしまつ』とSNSの反応について思うこと
https://twitter.com/c4dbeginner/status/1489495312242999298?s=21
昨日まで『批評家ぶった批判は嫌われる』『好きになれなければ立ち去ればよい』『今のオタクが大切にするものは推しへの愛、粗探しや吊し上げのノリはもう過去の痛いオタクの遺物』という論調だったツイッター民が、公開初日にして『大怪獣のあとしまつ』をトレンドに乗るほどぶん殴っているという事実
— CDB (@C4Dbeginner) February 4, 2022
公開初日からツイッタートレンドに乗るほど叩かれている映画『大怪獣のあとしまつ』、もともと楽しみにしていたので初日に自腹で見てきました。
最初に言うと「令和のデビルマン」みたいな叩きは違うと思う。CGや映像にはかなり資金を投じてそれなりの映像に仕上げているし、俳優陣も豪華で演技も上手い。
この映画がなんで炎上しているかというと、予算や才能が足りなくて完成形に行けず失敗しているのではなく「シン・ゴジラ的なヌーベルバーグ怪獣映画と思わせたのに、シンゴジラのパロディのようになっている、シン・ゴジラを大好きな観客が一番嫌いな要素で埋め尽くされている」という観客層との相性の悪さ、フィーリングのミスマッチが大きくて、映画の出来自体は「こういうものを作ろうとして、実際にその通り作っている」映画だと思う。あとはそれが合うか合わないか。
この映画がシンゴジラを意識しているのは冒頭の字幕の微妙に変えた明朝体からも明白に観客にメッセージしてるんだけど、そこにギャグをたくさん盛り込むわけです。そのギャグというのはなんというか、庵野秀明がまず排除する下ネタと絶叫とフィジカルなリアクションの、言ってしまえばすごく福田雄一的なギャグなわけですね。庵野秀明と福田雄一というのはいまや日本映画の実写においての二大ヒットメーカーなんだけど、この二人の作風というのは水と油というか、ものすごく相性が悪い。寿司飯にフルーツ巻いてケチャップとマヨネーズかけたアメリカンスシみたいな食い合わせになってる。
なんでこんなにSNSが怒っているかというと、その福田雄一っぽいギャグというのが、本気の怪獣映画を見たくて劇場に来た観客の期待をいちいちズラして、茶化しているように感じるからだと思う。というか、実際にズラしているし、茶化している。でもそれって福田雄一作品がいつもやってることなんだよね。いやこの映画の監督は三木聡監督だけど。
この映画はたぶん怪獣映画に思い入れをもってる人にとってすごく反発を感じると思うし、怪獣映画への愛も希薄なんだけど、この映画が怪獣映画というフォーマットに対してやってることというのは、言わば福田雄一監督が「新解釈・三國志」で三國志に対してやってることと同じなわけです。それはスタッフが観客を怒らせようとしてやっているのではなくて、庵野秀明というすごく孤独で私小説的な才能と、福田雄一というパーティピープル的な才能の手法を2つミックスしたら2倍売れるんじゃね?と混ぜてみたら、期せずして福田雄一が庵野秀明をバカにしてるみたいな映画になってしまったということだと思う。別にそれは意図したことではなくて、文体とか手法というのは、機械とか薬品のように、いったん作品というフラスコに混ぜた後は、その性質に沿って勝手に化学反応を起こすものだから。
正直言って、僕も『大怪獣のあとしまつ』は合わなかったし、予告編で期待していたものと違った。これだけのキャストと予算を揃えたら、庵野秀明とも福田雄一ともちがう別の方向があったんじゃないかと思う。
でもこれが駄作、失敗作と言い切れないのは、怪獣映画にまったく思い入れのない世間一般では福田雄一っぽい要素がゲラゲラ受けるかもしれない、それはわかんないから。そもそも『新解釈・三國志』も映画ファンからは白眼視されつつ、40億ですからね。他の日本映画が福田雄一っぽいギャグを盛り込み始めてしまうのも無理はないわけです。
個人的には、この手法はキツい。広瀬すずの『一度死んでみた』も明らかに福田雄一っぽい方向を狙ったギャグ映画だけど、僕には全然合わなかった。(吉沢亮のクールな落とし方は上手かったと思う)でも、まわりの観客は「堤真一が変な顔している」みたいなすごいベタなギャグで大笑いするわけ。こんなんでいいんだっていう。でもそれは味覚や感性の違いだから否定しても意味ないわけですよ。「酢の入ってないライスにフルーツ巻いてマヨケチャかけたアメリカン寿司、うめー!これぞ寿司!」って言われたら「そうかあ」と思うしかないわけ。
で、思い出すのは『シン・ゴジラ』だって本当はめちゃくちゃ好き嫌い分かれる映画だったわけです。80億行ったし日本アカデミー賞もとったんで万人受けしたみたいになったけど、映画館でははっきりと楽しめた観客とそうでない観客に別れていた記憶がある。今でも忘れられない光景だけど、立川シネマシティの極音上映で何回目かのシンゴジラ見た時、上映が終わったら前の方の人たちは立ち上がってスタンディングオベーションして、すごい熱狂しているんだけど、僕がいた後部席の周囲の観客はすごい冷めてて、ため息ついたり「眠くなって寝ちゃったよ」とか愚痴を言っていた。それくらい観客の中に温度差がある作品だった。
でもSNSでは『シン・ゴジラ』を好きな観客の方が雄弁で、ネット世論を支配しやすいので、そのことは忘れられがちになる。世の中でオタクが多数派になったとは思わないけど、ツイッターみたいな局所的なところではもう本当に圧倒的に議論を支配してしまう面があって、そういう「少なくともこの場では、自分たちがあまりに数で優勢すぎるな」という警戒は持っておいた方がいい気がします。
無料部分はここまで。このあとは月額マガジン向けに、『大怪獣のあとしまつ』のネタバレに関する部分、ネタバレなのともう一つはキャンセルカルチャー的に炎上しかねないのであまり派手に拡散したくない部分について書きます。『大怪獣のあとしまつ』には庵野秀明と福田雄一の他に、政治風刺、ポリティカルフィクションの面があるので。それともう一つは『シン・ゴジラ』以降、庵野監督とSNSの「シンクロ率」があまりに高くなりすぎていることへの不安について。興味があったら読んでみてください。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?