
Vol.3【卒業制作②】〜チーム開発の進め方〜プレゼン編
開発編は時間がかかりそうだったので前後しますが、
今回は卒業制作のプレゼン編についてご紹介したいと思います。
卒業制作発表会の直前に講師の方から、
「こんな内容で発表してくださいね〜」
という項目が記載されたレジュメを配布されました。
しかし、事前に簡単にでも良いので、
発表スライドを作成しておいた方が何100倍も伝えやすいです。
そしてポートフォリオでアプリを紹介するための資料にもなります!
デプロイできたのがギリギリで、
プレゼン資料は実質1日で作成しました…!
なるべく短時間で作成するコツも一緒に掲載しています。
他の用途でも使える方法なのかなと思います。
チーム制作でアプリ開発のプレゼンについてご紹介しますが、
個人制作でもWeb制作の場合でも使える部分はあるかと思いますので
ご参考なれば幸いです🌿
使用したツール
ChatGPT
Canva
ChatGPTの活用方法
こちらでは、プレゼンの構成内容についてたたき台を作成してもらいました。
生成AIの上手い使い方としては、
自分ができることを時短して、ブラッシュアップに時間をかけることです。
一から構成を考えたり、文章の案を作成することって結構時間かかりますよね。
ここは生成AIにうまく指示を出して案を作成してもらった後に、
自分なりにアレンジとブラッシュアップに時間をかけた方が効率が良いです。
ここで重要なのがうまく指示を出すこと。
きちんとできれば思い通りの案を出してくれます。
以下でプロンプトと回答を参考に載せておきます。
(前段でアプリの仕様まで伝えてあるとさらに精度が増します。)
このアプリケーションの卒業制作発表のプレゼン資料を作成します。
どのようなページ構成で発表すれば良いか提案してください。
入れたい内容は以下の通りです。
- 制作メンバー
- アプリの概要
- アプリのターゲット、ペルソナ、差別化
- 制作期間
- 使用している技術、ツール
- 基本機能
- 工夫したポイント
- 大変だったこと
- 改善ポイント
- 今後機能追加したいこと以下の構成でプレゼン資料を作成すると、伝わりやすくなります。
各スライドにビジュアル要素や簡潔な説明を盛り込み、スムーズな流れを意識しましょう。
---
### **プレゼン資料構成案**
1. **タイトルスライド**
- アプリ名
- チーム名または「卒業制作発表」タイトル
- 発表者(代表者名)
2. **制作メンバー紹介**
- メンバーの名前、役割
- 各自の担当(例:フロントエンド、デザイン、バックエンド)
3. **アプリの概要**
- アプリの目的・コンセプト
- 簡単な説明(何を解決するか、どのように使われるか)
4. **ターゲット、ペルソナ、差別化**
- 具体的なターゲット(例:資格取得を目指す20代~30代女性)
- ペルソナ(例:Misaki Sato)
- 他アプリとの差別化ポイント
5. **制作期間**
- プロジェクトのスケジュール(何週間でどの機能を実装したか)
6. **使用技術・ツール**
- フレームワーク、ライブラリ(例:React, Supabase, DaisyUI)
- 環境(例:Vite, GitHub)
- デザインツール(例:Figma)
7. **基本機能紹介**
- 主要な機能一覧(Pomodoroタイマー、学習記録、ランキング機能など)
- 各機能のデモ映像またはスクリーンショットを活用
8. **工夫したポイント**
- 励ましメッセージ、UIデザインの工夫
- 成長を可視化するアニメーションなど
9. **大変だったこと**
- 技術的な課題や開発中に直面した問題(例:Supabase連携のトラブル)
- チーム内の連携やタスク管理の工夫
10. **改善ポイント**
- 実際に使ってみたフィードバックから得た改善点
- 今後のUI・UXの向上案
11. **今後機能追加したいこと**
- ロードマップ案(例:SNS連携、追加の成長アニメーション)
- ユーザーからの要望に基づく改善
12. **まとめ**
- 発表の総括
- チーム全員で一言コメント(もし余裕があれば)
13. **質疑応答**
- 質問を受け付けるタイミング
---
これをベースに、各スライドに適したスクリーンショットや
アニメーションを加えることで、説得力が増します。
また、発表の際には1スライドあたり1~2分程度で進めると、時間管理もしやすいです。こんな感じでプレゼンの構成案と各項目について詳細に提案してもらえました。
ここから自分なりのアレンジを加えていきます。
この段階で誰がどこの発表を担当するかまで割り当てられると、
この後の同時編集作業がスムーズになります。
Canvaの活用方法
今まで仕事ではPowerPointでしかスライド作成したことなかったのですが、
Canvaはテンプレートがおしゃれなものばかりで操作も簡単だったことから
今回はCanvaで作成しました。
作成も操作方法も直感的でかなり使いやすい!
無料の範囲内で作成できちゃいます。
※アカウント作成はしてくださいね!
Canvaでプレゼンテーション 使い方
新規作成から『プレゼンテーション』を選択
テンプレートが表示されるので、好みのテンプレートを選択
テンプレートを編集・アレンジ
右上の【プレゼンテーション】から発表者モードで、スライド毎に読み原稿を作成
右上の【共有】でURLを共有すれば、メンバーも閲覧や編集できる
テンプレートが優秀すぎる
テンプレートの種類が豊富だし、テンプレートの中でもスライド毎にデザインされてて、かつ全体に統一感があってとても勉強になりました…!
1つのテンプレートで最初から最後まで完結しているのでプレゼンの参考にもなります。
発表者モード
私は2画面だったので、発表者モードにすると
1画面はスライド資料表示用に画面共有して、
もう1画面は自分用に読み原稿と時間計測をしつつスライド操作
をすることができました。
確かパワポだと発表者用に同じような画面にする場合は、
操作が少し面倒だった気がしますが、
Canvaはクリック2回でできました。
今回は仕様しませんでしたが、上部にあるキーボードボタンにマジックショートカットというものがあり、
ドラムロール、カーテンコールなど場を盛り上げてくれそうなエフェクトがその場でつけることもできます🤣(もちろんショートカット操作もできます)
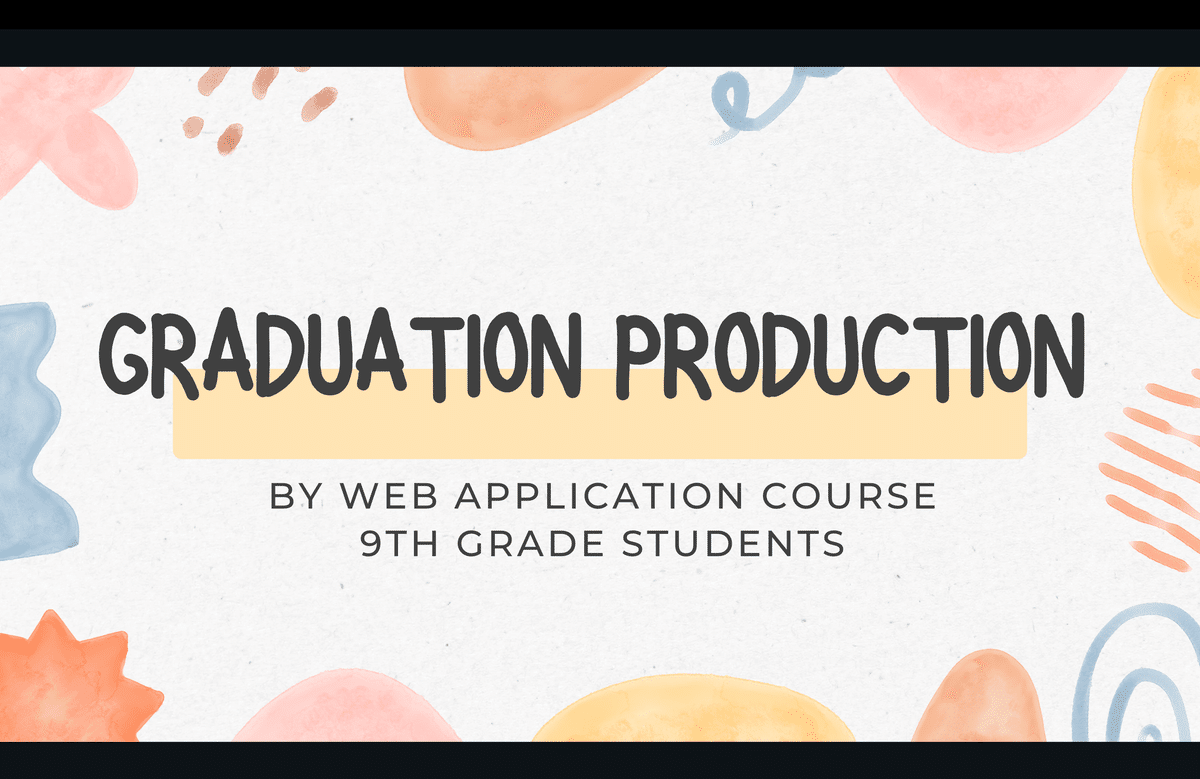

共有が簡単
チームメンバーに内容を確認してほしい、
同時編集がしたい、
そんな時に右上の【共有】から
【コラボレーションリンク】で
『リンクを知っている全員』を選択し
『編集可』にすると
発行したURLを伝えたメンバーが
このスライドにアクセスできるようになり、
同時編集が可能になります。
読み取り専用にしたい場合は、「表示可」「コメント可」にもできます。
いやー、簡単すぎて
「本当にできてる?」とメンバーに確認しました。笑
同時編集とかイメージ共有する場合、
構成とデザインも含めて早めの段階に共有した方が良いですね。
自分は3ページくらいスライド作成した段階で、
「構成案、スライドイメージ、発表割り振りはこんな感じでやろうと思ってます!」
とメンバーにイメージ共有しました。
スライド作成は自分が担当して、
原稿はできたところからメンバーに担当部分を作成してもらいました。
リアルタイムで進捗が共有できるので安心でした。
スライドと原稿作成
上記にもあるように、読み手に伝わりやすくするための文字数は、
1スライド105文字以内が適切だそうです。
今回は、文字数まで調整が間に合いませんでした…
中には1スライドにめちゃめちゃ詰め込んでしまい
文字数がとてつもなく多くなっているところもあって見づらすぎる😭
𝕏の1ポストあたりの文字数制限が140字なので、
あれよりも少なめな感じです。
見やすいスライドにするには、
要点だけ書いて、言葉で補足説明をする
ということを意識して原稿を作成したほうがよいです👌
そして先程ChatGPTの回答でもあったように、
スクリーンショットを入れながら、
1スライド1〜2分にすると発表がスムーズです。
行ったり来たりしすぎると
「あれ、どこだっけ?」とその場で探すことになるので
スクリーンショットで見せるだけで良い部分
成果物の操作を実際に見せた方が良い部分
に分けておくと落ち着いて発表ができます。
(私はあがり症なので、実際に操作する箇所には、原稿に「ここでポモドーロタイマー画面を操作する」と具体的な動きも読み原稿に落とし込んでました)
スマホから編集できるのが便利
Canvaアプリをスマホにもダウンロードしていれば、
PCでの作業の続きをスマホからでもできるんです。
移動中とかにも作業できるのでとても便利でした!
注意点?
いざ発表!
スライドを流している途中、表示されない箇所がありました。
使用技術にロゴの画像データを入れてましたが、
作成段階では問題なかったものが発表時に非表示になってしまいました。
最初からテキストで入れておけばよかったなと思いました。
ポートフォリオで掲載する予定なら、
著作権の問題もあるのでロゴの画像データは入れない方が無難かもです。
発表のスライドはこちら
ポートフォリオの宣伝もしつつ笑
完成版のスライド資料も掲載しているのでご覧ください。
掲載のスライドからは省いてますが、基本機能の詳細の後に、メンバーそれぞれから工夫点と苦労した点についても口頭で発表をしています。
最後に
作業できるのが約1日という
時間が限られた中でプレゼン資料を作成したので、
なるべく時短して効率よく作業するために
という部分にフォーカスしています。
内容は雑な部分もありますが…
ChatGPTの注意点は、しれっと嘘が混ざることがあるので、
鵜呑みにせず内容が正しいかどうか判断できるレベルで使いこなしましょう笑
以上で、プレゼン編は終了です!
卒業制作の開発編はまた後日掲載予定です!
