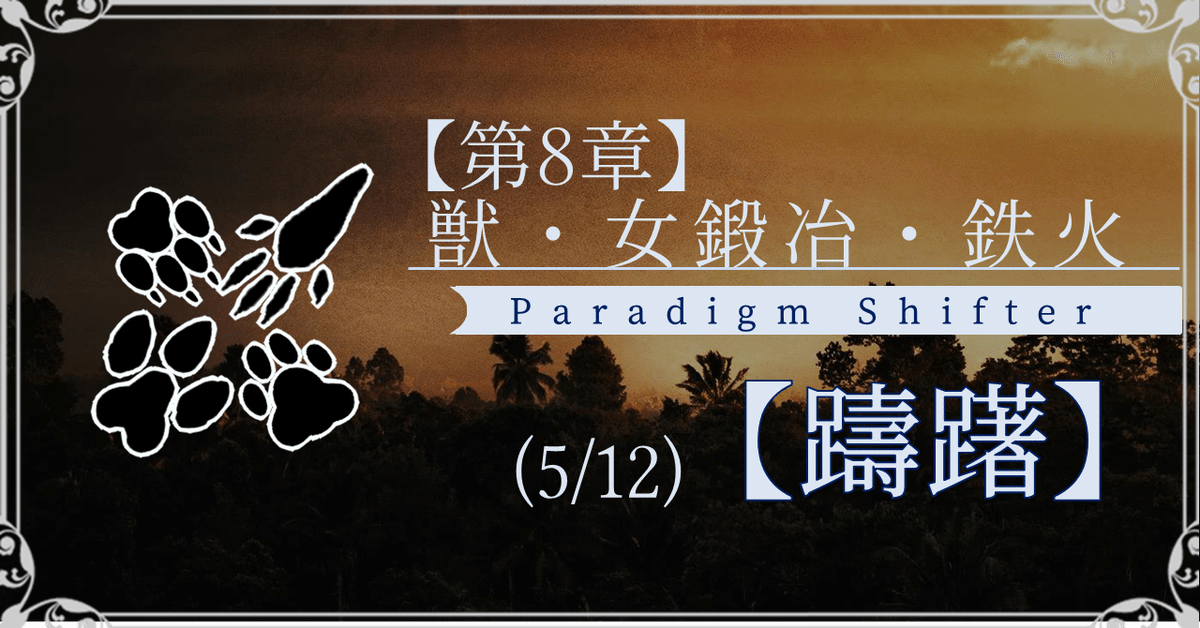
【第8章】獣・女鍛冶・鉄火 (5/12)【躊躇】
【救難】←
「いったい、なにがあったのよな……と尋ねても、答えられる様子ではなし」
女鍛冶の刀の切っ先が、刃にまとわれた赤炎とともに、異様な獣人へと突きつけられる。武人のごとき、隙のない構えだ。
幼少の頃からリンカは、たしなみとして刀術を習わされた。刀の作り手は、刀の振るい方も覚えねばならない──至極、合理的な理由だった。
「ブオォーッ!」
野牛の大男は、けたたましい咆哮をあげると、女鍛冶に対して頭頂を向ける。大槍のごとき二本の角と、鉄球のような石頭が、リンカを威圧する。
「来るのよな……」
「──ォォォオオッ!!」
吠えたける獣人は、女鍛冶に向かって突進する。リンカは己が身の正中線を守るように、刃を傾ける。
地面を踏みならし、風を切りながら、二本の角を前に突き出した大男が迫り来る。
「チィ……ッ!」
女鍛冶は、炎をまとう刀身を閃かせながら、巧みな体さばきで、突進を真横に回避する。勢い余って通り抜けた異様な獣人が、少し離れて、ゆっくりと振り返る。
「……オヴッ!?」
野牛の角の大男は、小さくうめき声をあげる。獣人の下腹部から胸部にかけて、焼け焦げた剣筋が残っている。
リンカは、ふたたび刀を構えなおす。白熱した刃がかすめて、白い灰と化した足下の草が、風に舞って消えていく。
交錯の瞬間、相手の胴体を逆袈裟に斬り裂いた。大男が一歩、踏みだそうとする。傷口が開き、黒くよどんだ血があふれ出す。
「さもありなん……」
女鍛冶は、ふたつの理由でわずかに動揺する。
ひとつは、胴体に大きく刀傷を負いながらも、野牛の獣人はわずかにのけぞっただけで、まったく動じる様子を見せないことだ。
確かに、リンカの踏みこみは甘かった。致命傷には、至らなかったのだろう。
だが、それは動かなければ、の話だ。重傷であることに、かわりはない。相手の足下に、血だまりができている。暴れ続ければ、斬り口も開く。
(痛みを、感じていないのか?)
女鍛冶は、内唇をかむ。もうひとつの理由は、単純な、獣人たちとの親交だった。
野牛の部族は、リンカの住処から地理的に近いこともあって、なにかと頼り頼られる間柄だ。洞窟を整える土木工事を率先しておこなったのも、彼らだ。
友なる獣人たちに対して覚える義理の感情が、刃のきらめきを鈍らせたのだろう。女鍛冶は、冷静に分析する。
(生粋の武人なら、はじめの一刀でしとめたんだろうが……これだから女は、などと言われるのも、しゃくなのよな)
野牛の獣人は、自ら作った血だまりを踏みこえながら、よろめき、近づいてくる。ななめ方向の傷が大きく開き、臓物がぼとぼとと草原のうえにこぼれ落ちる。
「……ぬうッ」
リンカは、刃の切っ先を相手に向ける。己を叱咤し、この場から退きたくなる衝動を抑えこむ。
一歩退けば、相手が踏みこむ隙になる──刀術を習わされたときに、イヤと言うほど身体に叩きこまれた。
「ん……?」
女鍛冶は、目を細める。濁った唾液と淀んだ血糊をこぼし続ける獣人のわき腹に、見慣れぬ傷がついている。
リンカが負わせたものではない。刃の傷でも、殴り合いの跡でもない。強いて言えば、矢傷に近い。なにか小石のような、小さなものに穿たれたような──
「──ヴオオォォォ!」
野牛の獣人が、天を仰いで、咆哮をあげる。刀傷から血がほとばしるが、お構いなしだ。こぼれた自分の臓物を、己の足で踏みつぶす。
「どのみち、助けることは無理そうなのよな……」
女鍛冶は、かみ殺すようにつぶやく。間合いの外から、刀を大振りで一閃する。野牛の獣人は、自慢の角を前に倒し、突進の体勢をとる。
「オオオォォ──ォヴッ!?」
野牛の咆哮が、唐突に途切れる。大男の頭が、どさり、と地面に落下する。首の切断面は焼き切られ、黒く焦げている。
大柄な体躯が、バランスを崩し、仰向けに草原へと倒れこむ。血と肉と臓物が、鮮やかな緑色の大地にまき散らされる。
「ナムアミダブツ……アタシは、坊主じゃない。ちゃんとした経文もあげられなくて、すまないのよな」
リンカは、自ら手にかけた獣人にわびると、首なしの死体に背を向ける。背丈の長い草をかきわけ、投げ捨てた鞘を探し、拾う。
平原まで降りてきて、はっきりとわかる。黒煙は、背後で倒れている男も住んでいた、野牛の部族の集落から伸びている。煙の筋も、さっきより増えている。
「早く、行かにゃあ……んグッ!?」
突然、女鍛冶の細いのどが、背後よりからめとられる。土気色の肌をした、丸太のように太い二本の腕が、リンカの首をしめあげる。
「ま、さか……ッ!」
苦しげにうめきながら、女鍛冶は背後に視線を向ける。先ほどの野牛の獣人だ。
正確には、頭を失った胴体の部分だけだ。生ける屍が立ち上がり、リンカの首をへし折ろうと豪腕に力をこめてくる。
「やはり……死ねないのよな。かわいそうに……」
みしみしと万力に締めあげられるような苦痛に耐えながら、女鍛冶は静かに瞼を閉じる。息ができず、意識がもうろうとする。
それでも、震える右手に握った刀を、祈るように天へと掲げ、『気』をこめる。
──ゴオオウッ。
次の瞬間、リンカの背に赤焔の渦が巻きあがる。『龍剣』より産み出された超常の炎は、首なしと化した野牛の獣人を呑みこむ。
やがて、大男の胴体は、二本の腕を残して消し炭と化す。
「うぅ……げほっ、げぼおっ! う、うぅ……ッ」
拘束から解放された女鍛冶は、その場でひざを突き、激しくせきこむ。同時に、少しのあいだ、むせび泣く。
わずかな時を経て、リンカはふたたび立ちあがる。草原を吹き抜ける風を、正面から受け止める。『戦場』の臭いが、近い。
「無事でいてくれ……というのも、もはや、かないそうにないのよな」
女鍛冶は、一刻も早く、野牛の部族の集落へたどりつこうと走り出す。呪詛、奇病、悪霊──考えつくかぎりの不吉な予想が、リンカの脳裏を駆け抜けていった。
→【憤怒】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
